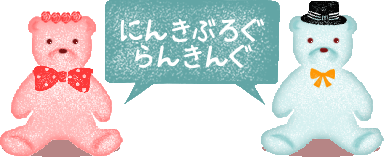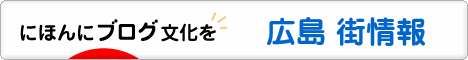◎
◎ お早う御座います。!先日、旅行より帰り久々のウオーキングです。今日は先日の続きで、団地内の植物を紹介いたします。
お早う御座います。!先日、旅行より帰り久々のウオーキングです。今日は先日の続きで、団地内の植物を紹介いたします。
◎宮島上空の動画>朝日の出も大分遅くなり、まだ日も出ていませんが朝焼けがあり、今日は秋日和になりそうです。
◎センニチコウ(千日紅)の動画>花言葉:「終わりのない友情」
◎PHOTO・千日紅(センニチコウ)
●ひゆ科の植物で、熱帯アメリカ地方が原産です。
●日本には17世紀に渡来しました。
●開花時期は夏から秋までと長く紅色があせない事からこの名前が付きました。
●別名を「千日草」と言い、乾燥させても3年以上色あせない事で、ドライフラワーに良く用いられるそうです。
②デュランタの動画>花の後に、面白い形の実が成ります。
③デュランタPHOTO>
●熊葛(くまつずら)科の植物で、メキシコ地方が原産です。
●日本には明治中期頃に渡来しました。
●色はちょっと藤の花に似ています。
④コリウスPHOTO>
●しそ科の植物で、インドネシアのジャワ島が原産です。
●別名を「錦紫蘇」・金襴紫蘇」・と呼ばれます。
⑤南天の木PHOTO>
●目木(めぎ)科の植物で花は、6・15~7・10頃に咲き比較的地味な白い花です。
●秋に赤い実をつけます。鳥が食べない限り冬中見る事が出来ます。
●実を乾燥させたものには「咳止め」の効き目があり、南天のど飴・と言うのがありますね。
●葉には「ナンジニン」と言う成分を含み、殺菌効果があります。
●正月には、福寿草の花と南天の実とセットで、「難を転じて福となす」という縁起物の飾り付けをしますね。
●京都・金閣寺の床柱は、南天の材を使っている事で知られています。
⑥白い彼岸花PHOTO>
●ひがんばな科の植物で開花時期は9・15頃~9月末頃までと短い。
●原産地は中国で赤が主流で有るが、上のように花の白いものもあります。
●別名:白花まんじゅしゃげと言います。
●根のところにはリコリンという毒があるが、水で何回もさらせば取れるので昔の人はねの部分からデンプンを取って飢饉の際の食料としたそうです。
⑦ニラPHOTO> 団地内の空き地に自然自生していました。
●ゆり科の植物で開花時期は8・20~10・25ごろです。
●アジアが原産で、かなり昔に渡来しています。
●ねぎの一種で、ビタミンAとカロチンを多く含み、消化を助け、風の予防効果もあります。
●漢方では種子を乾燥させたものを「韮子(きゅうし)」と言い、胃腸薬などに用います。
⑧風船唐綿(フウセントウワタ)PHOTO>
●ががいも科の植物で、南アフリカが原産地です。
●とげを持つ丸い実の形がなんともユニークですね。とげ部分は触っても痛くないです。
●晩秋になると実がパッと割れて、中から綿毛と種が出てきます。
 おまけ・その1>まりあさんより写真を拝借し、旭川の一枚稲田の春~秋までの移り代わりを動画にしました。
おまけ・その1>まりあさんより写真を拝借し、旭川の一枚稲田の春~秋までの移り代わりを動画にしました。

 ☆お早う御座います。!本日はウオーキングに出かける前に、爺の住む岡の上の団地内にある、花や植物をご紹介しましょう!
☆お早う御座います。!本日はウオーキングに出かける前に、爺の住む岡の上の団地内にある、花や植物をご紹介しましょう!
 10月6日の瀬戸内の風景です。
10月6日の瀬戸内の風景です。
この場所はメイン道路を下った突き当たり何時もの撮影場所で、小生の背中側が今日紹介する団地になります。
☆団地の入り口の土手の坂に咲く=つゆ草=です。
②=つゆ草=
●つゆ草科の植物で開花時期は、6~10月末頃まで咲きます。
●別名を「蛍草」と、言います。そのほか「藍花」・「青花」・「移し草」・「月草」・「はなだ草」・「帽子花」と、いっぱいあります。
③アサガオPHOTO>●昼顔科の植物で、7月~10月中旬頃まで開花します。
④アサガオの動画>●「朝顔=朝の美女」の意味だそうです。
⑤朝顔PHOTO>
●加賀千代女の詠んだ 「朝顔に つるべとられて もらひ水」 は、有名な句ですね。
☆おまけ・その1>広島植物公園のベゴニア花壇に、バラの花を生けて見ました。↓の赤いバラは、団地内の空き地に咲いていた秋のバラです。(10月5日・撮影)
③=バラ=
●ばら科の植物で、開花時期は5月~11月末頃まで咲きます。
●とげのある木の総称である「うばら」または「いばら(茨)」が、「ばら」に略された。
●次々に咲きますが、春と秋に咲くのが最も多いそうです。
●薔薇は古代から「繁栄」と「愛」の象徴とされました。
☆花壇にニ咲く=ブーゲンビリア=の花>別名:「筏葛(いかだかずら)」と言います。
④=ブーゲンビリア=
●白粉花科。
●南アメリカ地方が原産。
●熱帯花木の代表で、開花時期は夏~10月ごろまで咲きます。
●花言葉は「あなたは魅力に満ちている」
⑤花壇に咲いている=ヤブラン=
●ゆり科の植物で開花時期は、7・25~10月末頃まで咲きます。
●別名を「山菅」(やますげ)と言います。
●日陰に生え、葉が斑入りのものもあり実は黒い丸形をしています。
⑥団地内の家庭菜園に出来ていた=唐辛子=
 本日の紹介は之までとし、残りは後日にアップさせて頂きます。又のお越しをお待ちしております。
本日の紹介は之までとし、残りは後日にアップさせて頂きます。又のお越しをお待ちしております。
 様こそ御越し下さいました。! 昨日に続き小生が見かけた、菊科の花をご紹介致します。
様こそ御越し下さいました。! 昨日に続き小生が見かけた、菊科の花をご紹介致します。
①天人菊のPOTO>
●学名で、Gaillardia と書き、18世紀のフランスの植物学者「Gaillardさん」の名前にちなんでつけられました。
●北アメリカ原産で、夏から秋に掛けて開花します。
●別名を「ガイラルディア」と言います。
②天人菊の動画>とてもくっきりとした感じの花です!
③ひまわりの動画>FUJIさんの写真を拝借しひまわりを添えてみました。!
●開花時期は、7・10~9・10頃です
④ひまわり(向日葵)のPHOTO>
●北アメリカ原産で、16世紀にイギリスに伝わり、「太陽の花」と呼ばれ始めました。
●名前は花が太陽の動きに連れて回る事から、”日まわり”と付いたそうです。
⑤コスモスのPHOTO>
●原産地はメキシコで、開花時期は7・25~12・10頃までと長い。
●秋の代表花であるが、早いものは夏から咲き始め、早咲きと遅咲きとがあります。
●メキシコからは、1876年頃にイタリアの芸術家が日本に持ち込んだのが最初、との説があるそうです。また、渡来当時は、花が桜に似ている事から「秋桜」と呼ばれたそうです。
⑤コスモスの動画>台風などで倒されても、茎の途中から根を出し、また立ち上がって花を付けると言うほど強い花です。弱弱しい見た目とは、大分違うようです。
⑥紫苑(しおん)のPHOTO>
●原産地は中国で、開花時期は6月ごろから咲き、栽培歴史は古く平安時代の「今昔物語」にもこの名が出てくるそうです。
●根は咳止めの薬になるそうです。
●別名を「鬼のしこ草」と言います。
⑦麦藁(むぎわら)菊のPHOTO>
●開花時期は、6~8月頃迄
●別名を、・ヘリクリサム・又は、・帝王の貝細工・と言います。
⑧ユリオプステージのPHOTO>
●9月~翌5月まで開花します
。●比較的寒さに強い花です。
⑧ユリオプステージーのPHOTO>10・4に撮影
⑨百日草のPHOTO>
●メキシコ原産で、日本には1862年頃渡来しました。
●強い日照と高温多湿を好みます。
●花持ちがよく、初夏から晩秋まで長い間咲くのでこの名前が付いたそうです。
●別名を、「ジニア」・「浦島草」と言います。

 今回は、朝のウオーキングで4~9月の間に近所の庭や沿道で見かけた「菊科の花」を2回に分けてお伝えします。
今回は、朝のウオーキングで4~9月の間に近所の庭や沿道で見かけた「菊科の花」を2回に分けてお伝えします。
①マリーゴールドの動画>春から秋まで絶え間なく咲き続ける花!
②マリーゴールドのPHOTO>「マリーゴールドとは、「聖母マリアの黄金の花」と言う意味だそうです。
●メキシコ原産で、水が無い状態でもなかなかしおれまさん。
●独特の臭気により除虫の働きをします。
●花には小型種の「フレンチマリーゴールド」と大形種の「アフリカンマリーゴールド」とありますが、一般的にはフレンチマリーゴールドを良く見かけます。
③ガザニアのPHOTO>5月の始めに図書館の花壇で撮影したガザにアですが、ご覧のようにまだ開花していません。
③ガザニアのPHOTO>5~6月が開花時期で、花の形が勲章に似ているので、別名を「勲章菊」といいます。
③ガザニアのPHOTO>開いたところは、昔良く見た勲章に似ていますね。上手い名前を付けたものです。
④浜菊のPHOTO>●日本原産の菊で、主に太平洋側の海岸沿いに生えているそうです。
●葉っぱが段々になっているのが特徴です。
●開花時期は10月上旬~12月上旬(ウオーキング小田島コースの海辺で撮影)
⑤ヒメジョオン(姫女苑)PHOTO>●北アメリカ原産の帰化植物で道端でよく見かけます。
●開花時期は6月~9月頃ですが今年は、ウオークの時まだみかけます。(JR山陽線線路沿いで撮影)
★本来「紫苑(しおん)」の漢字が使われるべきなのですが、日本産で、「姫紫苑」と言う別の植物があり、それと区別するために、「姫女苑」の漢字を当てたらしいです。●花は「春紫苑」にそっくりですが、花期が春紫苑のほうが早いです。(4~5月頃)
⑥特別参加::たんぽぽのPHOTO>開花時期は3~4月頃に咲き、別名を鼓草(つずみぐさ)と言います。
⑥薊(アザミ)のPHOTO>●沖縄の八重山では、とげを「あざ」と呼ぶ事から「あざぎ」(とげの多い木)と呼ばれ次第に「あざみ」になったと言う説と「アザム」の言葉に由来すると言う説があります。
「アザム」には「驚きあきれる」とか「興ざめする」の意味があり、花が美しいので手で折ろうとするとトゲにさされて痛いので、「驚きあきれ、興ざめする」と言うところからこの名前がついたらしいです。(図鑑資料より)
⑦松葉菊(まつば)のPHOTO>☆小田島の団地下の石垣の下で撮影した花ですが前のお宅の奥さんに名前を教わりました。帰宅後インターネットで、調べましたが「松葉菊」を発見出来ませんでした。正式な学名は違うのかも知れません!
◎10月1日より牡蠣漁解禁です。!
◎10月3日・塩屋入り江の朝の風景です。
 今から今朝のウオーキングに出発します。
今から今朝のウオーキングに出発します。
◎本州と宮島の間にある、牡蠣の養殖場です。!光学ズームで撮影。(10月3日の朝)
◎丸石漁港より漁船が漁場に向けて出航です。!
◎牡蠣を満載した漁船が帰ってて来ました。今、朝の6時過ぎです。!
◎漁港の荷揚げ桟橋に到着です。!
◎リフトによる牡蠣の荷揚げ作業!
◎ご夫婦で、牡蠣の荷揚げ作業をされている牡蠣漁船の風景です。!
◎どの牡蠣漁船にはリフトが付いていて、シーズンに成るとこの様な、網を取り付けています。どの様に養殖場で使うのか不明です。
今は忙しく働いておられるので、今度チャンスがあれば伺う事にします。
◎牡蠣を此処で、仮洗浄し右のホッパーに移します。!
◎牡蠣を綺麗に洗うドラムです。!牡蠣の洗濯機の様なものでしょうか!!
 牡蠣養殖漁場から、牡蠣を満載し帰港している船のMVを放映中
牡蠣養殖漁場から、牡蠣を満載し帰港している船のMVを放映中
★ おまけ・その1
◎キバナ・コスモス> ○キク科の植物で、学名を・Cosmos Sulphuresuと言う。
○メキシコ原産で、6~10月頃まで開花します。
○コスモスの仲間で、花色が黄色かオレンジなので、この名前になったそうです。
○似ている花に金鶏菊があります。
◎丸石漁港に平行して、国道2号線と山陽本線が走っています。
ウオーキングは此処の陸橋を渡り山の手に入ります。
線路側にキバナコスモスが沢山咲いています。

★9・30塩屋入り江の朝>朝の夜明けも大分遅くなり、日の出も6時半頃になってきました。
★秋の七草>すすき・キキョウ・ナデシコ・フジバカマ
★秋の七草>オミナエシ・クズ
★9・30コンビナートの朝>爽やかな朝で霞みも無く、工場群がはっきり見えます。このコンビナートの一企業で働いていたので、見るたびに懐かしさを感じます。
★秋の七草★
★秋の七草の覚え方!! ●「お す き な 服 は ?」
①お・・・・・おみなえし(女郎花)
②す・・・・・すすき(薄)(芒)
③き・・・・・ききょう(桔梗)
④な・・・・・なでしこ(撫子)
⑤ふ・・・・・ふじばかま(藤袴)
⑥く・・・・・くず(葛)
⑦は・・・・・はぎ(萩)
①女郎花(おみなえし)>
オミナエシ科の多年草。高さ約1m位になり山野に自生します。
漢方では、根を乾かして利尿剤とします。
別名:アワバナ・オミナメシ
②薄(ススキ)>
イネ科の多年草で、土手・荒地などにしばしば大群落を作ります。
毎年、宿根から新芽を出し、高さ2mぐらいになります。茎葉は屋根を葺くのに使います。
別名:振袖草。
③桔梗(ききょう)>
キキョウ科の多年草で、山地・草原に自生します。
根を乾かして生薬の桔梗根とし、鎮咳薬に使われます、。
古名をおかととき、きちこう。
④撫子(なでしこ)>
ナデシコ科の一群の草木の総称。
日当たりのよい草地・川原などに自生します。高さ数10cm。
種子は黒い色で小さく利尿に有効です。
別名:カワラナデシコ・ヤマトナデシコ。とこなつ。
⑤藤袴(ふじばかま)>
キク科の多年草多年草で、やや湿気のある所に自生する。
高さ約1mぐらいになり、全体に佳香があります。
⑥葛(くず)>
マメ科の大形慢性の多年草で、山野に多く、蔓の長さは10m以上にも達するといいます。
根は肥大し、生薬の渇根として解熱薬に用い、また、葛粉を採ります。
奈良県国栖(くず)の地名に因むといいます。
⑦萩(はぎ)>
マメ科ハギ属の小低木の総称で、高さ約1.5mに達します。
家畜の飼料になります。
普通にはヤマハギ・ミヤギノハギを指します。
⑧ウオーキングの時、JR山陽本線・宮浜陸橋下に書かれていた、壁画?・落書き?・どんな心境で、書くのであろう????











 と
と のMVでお楽しみ下さい。↑ ↓
のMVでお楽しみ下さい。↑ ↓


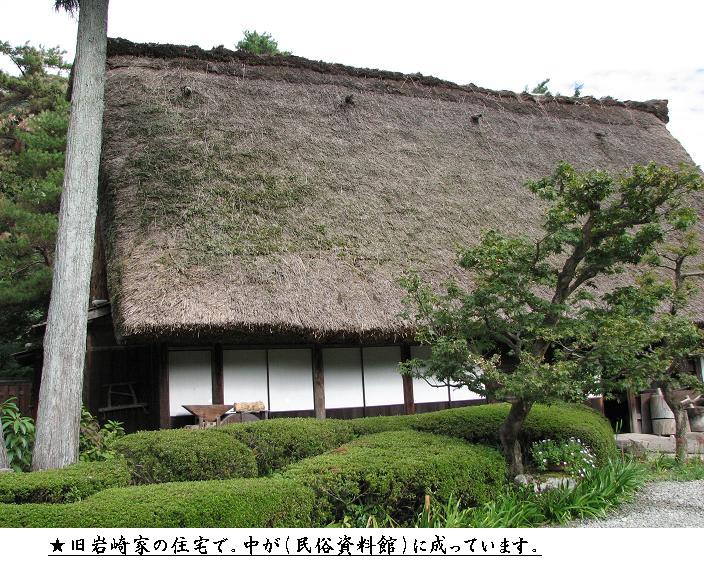
















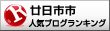

 本日は、広島城と護国神社周辺で行われました「ひろしま・フードフェスティバル」の会場より皆様をご案内致します。
本日は、広島城と護国神社周辺で行われました「ひろしま・フードフェスティバル」の会場より皆様をご案内致します。 






















 琴の演奏MV ↓↓
琴の演奏MV ↓↓ 


 千の風にのっての曲など演奏MV ↓ ↓
千の風にのっての曲など演奏MV ↓ ↓ 

 ↓>予告編<↓明日より又、下呂温泉の旅に復帰いたします。!又のお越しをお待ちいたしております
↓>予告編<↓明日より又、下呂温泉の旅に復帰いたします。!又のお越しをお待ちいたしております 
 街角コンサートの司会者
街角コンサートの司会者 




 お砂焼きの由来
お砂焼きの由来 

 巫女さん姿のお嬢さん
巫女さん姿のお嬢さん