スターバックス、太っ腹です。ちょっと古いニュースですが、記録しておきましょう。
**********
米スタバ、店員13万人の学費を肩代わり 大学側と提携(朝日新聞) - goo ニュース
2014年6月17日(火)19:45
コーヒーチェーン大手の米スターバックスは16日、従業員の大学の学費を肩代わりする計画を今秋から実施すると発表した。オンライン講座を展開するアリ ゾナ州立大学との提携で実現させる予定。米メディアによると、最大で約13万5千人が対象になる見通しで、企業として過去にない規模の取り組みになるとい う。
米国では大学の学費が高騰しており、卒業までに多額の借金を背負ったり、中退を余儀なくされたりする学生が多い。計画の発表に合わ せてニューヨークでのイベントに参加した同社最高経営責任者(CEO)のハワード・シュルツ氏は「すべての人が希望と期待を得られるようにしたい」と導入 の理由を語った。
スターバックスによると、直営店で週に20時間以上働き、大学入学の基準を満たす従業員が対象。既に大学の単位を取得 し、3~4年生としてアリゾナ州立大学に編入できる場合は学費の全額を会社側が負担し、1~2年生として入る場合も奨学金などを通じて支援する。制度を利 用して学位を取得しても、同社に残る義務はないという。(ニューヨーク=中井大助)
スタバ、米従業員の大学授業料を一部負担(ウォール・ストリート・ジャーナル日本版) - goo ニュース
2014年6月16日(月)17:26
米コーヒーチェーン大手スターバックスは、週20時間以上勤務する国内従業員に対し、オンラインでの大学の学位取得を支援するプログラムを立ち上げる。
アリゾナ州立大学(ASU)と提携し、同大の学士号コースに入学する従業員に対する授業料負担や財政支援を行う。従業員は、小売り経営や電子エンジニアリングなど40の分野から選択ができる。
スターバックスは、どうすれば大学教育を受けられるのかという従業員の悩みに応えることで、人材を維持するとともに、採用や研修の費用を節減したいとしている。従業員の定着率については、競争上の理由を挙げ、明らかにすることを控えた。
従業員はこのプログラムに参加しても、勤務を続ける義務は生じない。米国・米州・ティーバナ事業を担当するグループ社長のクリフ・バローズ氏は「従業員にはスターバックスにとどまってキャリアを伸ばしてほしいが、卒業後どうするかは自由だ」と話す。
ASUのマイケル・クロウ学長は、年間1万5000~2万人のスターバックス従業員がプログ ラムに参加するとみている。ASUは新コースのために、50人の教師やカウンセラーを増員した。ASUのオンライン・コースの年間授業料は3000~1万 ドル(約30万6000~102万円)で、支援を受ける従業員の負担は授業料の半額弱になると、同社は予想している。
スターバックスの米国内従業員は正規、非正規を合わせ13万5000人で、同社によると、学士号を持っているのはそのうち約4分の1。また、現在大学に通っているか大学への入学を希望している者は推定70%に達するという。
多くの企業が、授業料の支援を削減している。人材マネジメント協会(SHRM)による2014年の調査では、大学の学生に対する支援を提供する企業の割合は54%と、10年の62%から低下した。
スターバックスは、プログラムへの支出がどの程度になるかは明らかにしていないが、20年以上前に医療保険とストックオプションを導入して以来の大掛かりな従業員向けプログラムだとしている。
プログラムでは、1年生や2年生として入学した者はASUから授業料一部免除の奨学金や、必要に応じた財政支援を受ける資格を持つ。3年生や4年生として 入学した場合には、学士号取得に向けた正規コースの授業料全額について、学期ごとにスターバックスから払い戻しを受ける。他の大学に在学中の従業員は ASUに単位を移せる。ただ、入学に当たってはASUの入学基準を満たさなくてはならない。
スターバックスはこれまで、資格のある従業員に対し年間約1000ドルの払い戻しを行っている。企業が提供する授業料の一部負担プログラムは、業務と関連 するコースの授業料補助が一般的。ウェルズ・ファーゴのアナリストであるトレース・アーダン氏によれば、スターバックスの今回のプログラムは「企業の授業 料支援プログラムとしては利他的なようだ。従業員はマキアートの作り方を勉強するわけではない。このことは、従業員がスターバックスを退社して他社に行く ことを促すだろう」という。
**********
大学を自由に選べないのはマイナスに思えますが、それでも大学に通えるだけでも、アメリカではうれしいことです。何せ私立大学だと年間3万ドルから4万ドルの学費が当たり前ですから、普通の家庭では払えません。
日本でも、こういう企業支援が増えるべきだと思うのですが、なかなか。ハワード・シュルツCEOに触発された経営者が出てきてくれることを願わずにはいられません。













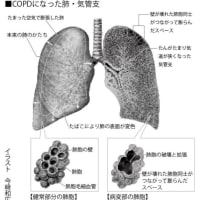
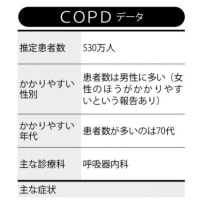




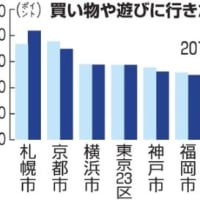





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます