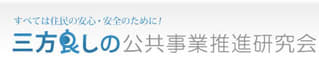朝いちばんのインスタグラム投稿がほぼ日課になってきたわたしが、どれどれ今日はとスマートフォンのライブラリをのぞいていると、一枚の画像に目が止まった。
ひと皿に乗った一匹だけの干物。
丸干しだ。
もちろん、いつ食したのかまでを忘れていたわけではない。その一部始終をくっきりはっきり鮮明に覚えている。
先日、お城下の夜、連れが頼んだ「メヒカリの丸干し」の品書きのその横に書いてあったその干物を、思わず注文したのはなぜだったか。酒を呑むと胃がバカになってしまい、食べだすと止まらなくなるのを警戒自重して、飲酒の端(はな)を除いては、食べ物を口にすることがほとんどなくなってしまうわたしだ。ふだんならアルコールだけがあればよかったはずだ。
が、たまらなくそそられた。
そして、目の前に出された干物を見るとどうにも箸が止まらなくなった。
食う。
そしてぐびり。
また食う。
そしてまたぐびり。
干物になった魚の名は「やけど」。
「やけど」の丸干しだ。
ハダカイワシのことを、ここ高知では「やけど」と呼ぶ。
外見とは異なり上品な身が、ほろほろと口のでほぐれ、口中に広がった脂を酒で胃の腑に流し込む。
「そそられた」直感はまちがいではなかった。
じつにうまい。
食味もさることながら、その見た目がまたよい。
ウロコが取れてツルツルな風貌が、他人ごとのような感じがしない。
心して食えよ、と独りごちながら、
またまた食う。
そしてまたまたぐびり。
気がつけば、となりにあったメヒカリもほとんどわたしが食っていた。
それから何日かが経ち、ひと皿に盛られた一匹の裸鰯の画像を見て、
「さて今宵は・・・」
と早くも晩餉に想いを馳せる辺境の土木屋。
「その前にしごとやろが!し・ご・と!!」
別のわたしにそう叱られて首をすくめる、セントバレンタインデーの次の朝。
↓↓ こんなのもやってます。
↑↑ 土木のしごと~(有)礒部組現場情報
↓↓ そしてこんなのもやってます。
↑↑ インスタグラム ーisobegumiー