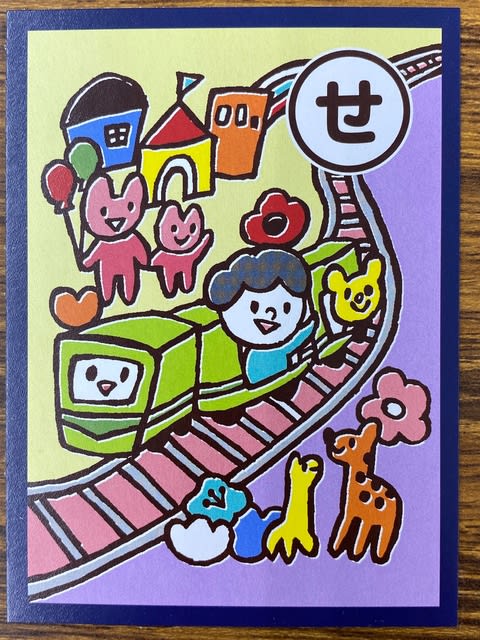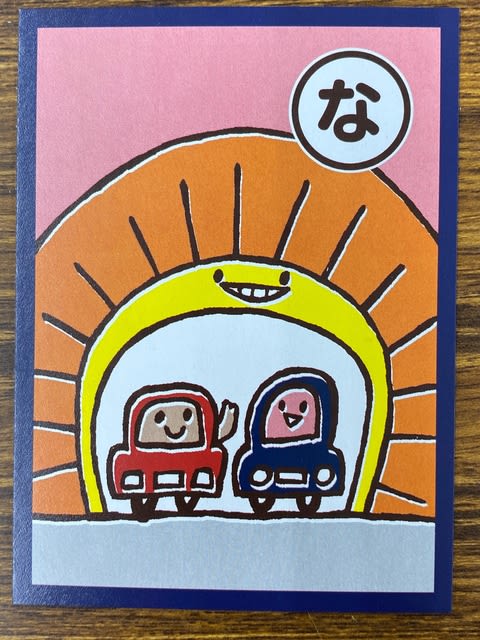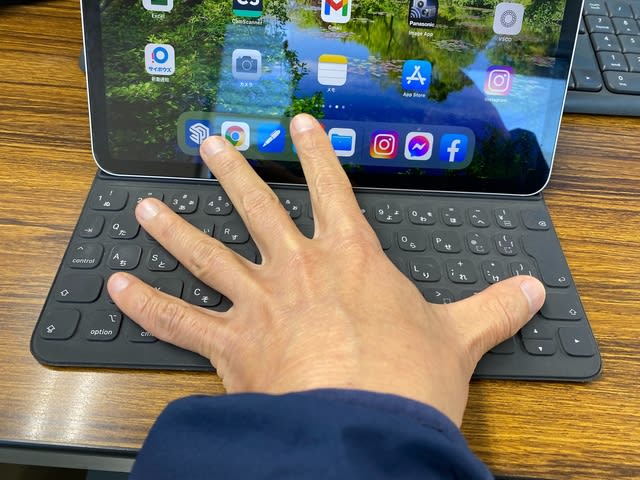しゅんせつ。
ローマ字表記にすると”Shunsetsu"。
音だけを聴いて、また、平仮名の字面だけを見て、どのような漢字を想像するのだろうか。
土木屋であることを、できるだけ差っ引いて考えてみるとそれは、「春節」だろうか。春雪ではあるまい。それほど多くの漢字は当てはまりそうにない語句である。
土木的には言わずと知れた「浚渫」だ。
浚渫という土木専門用語をめぐって平成29年に話題となったTwitter記事のことは、このブログでも書いた。のみならず、ある時期においては、中小建設業の情報発信というテーマでわたしが語るときに欠かせないネタとしていた。
2017年2月16日の拙稿を全文再掲してみよう。
******

地域を守る建設産業というフェイスブックページで教えてもらった、”grape-『心』に響く動画メディア”というサイトに載っていた工事看板の画像。ツイッターに投稿され、ちょっとばかり話題になっているらしい。
話題になっているのは「濠を浚渫しています」という言葉。「皆さんは読めますか?」という問いかけから始まっている。
正解は「ほりをしゅんせつしています」。
わたしはなんなく読める。読者の皆さんはどうだっただろうか。文中、「土木関係の仕事をしている人にとっては読めて当たり前」という解説がある。たしかに「濠」という構造物は土木そのものといって差しつかえないが、「濠」という漢字は読めて当たり前の部類には入らないだろう。土木工事の工種としてはポピュラーな「浚渫」も、同業とはいえその手の仕事に関わりがない人たちにとっては難解なのではないだろうか。
同業のよしみ、「いくらなんでもそこまで晒すのはネ」と思い、わたしは画像から削ったが、元ネタには下の端に発注者と工事名がはっきりと写りこんでいる。一見してわかるとおり、舞台は北国。城下町たる市が発注したその名前には「濠浚渫工事」という文字が見える。
「ああネ」と得心するわたし。
よくやるのである。
陥りがちなのだ。
意識が工事名に拘泥してしまい、そこから抜けだせない。つまりこの場合は「濠」と「浚渫」である。ちょっとがんばれば何ということはないのだが、ついつい安易なところで手を打ってしまう。ではどうすればいいのか。
よく採用される方法として、
1.漢字はそのままでルビを振る。
2.平仮名にする。
3.言い換えをする。
1と2もまたてっとり早いが、本質的な解決にはならない。つまり「伝える」という目的のもとでは、「どうもイマイチだネ」ということだ。だからわたしは、極力3の線でいこうと努めている。この場合でいうと、「浚渫する」は「土砂を取り除く」に言い換えることで工事の概念がストレートに伝わる。では「濠」をどうするか。これはルビを振ることで一目瞭然だ。
「濠(ほり)の土砂を取り除いています」
意味は伝わるが、ルビだと平仮名が小さく目につきにくい。広報紙ならそれでもいいが、看板にはできるだけ大きな文字を使いたい。
平仮名を採用してみる。
「ほりの土砂を取り除いています」
これだと、習ってない漢字が平仮名になっている小学校低学年の国語教科書のようで(ちなみにわたしはアレがキライ)、なんだかバカにされているような気がしないでもない。
同じ意味の違う漢字に変えてみる。
「堀の土砂を取り除いています」
なぜ取り除かなければならないのだろうか、という方向から、もうひとひねりしてみる。
「堀にたまった土砂を取り除いています」
城は多くの人から「おしろ」と呼ばれる。濠もまた、「おほり」と呼ぶのが一般的だろう。ということで、わたしならこうする。
「お堀にたまった土砂を取り除いています」
浚渫を「さらえる」と言い換えるのもアリかもしれない。
とかナントカえらそうなことを書いたが、あくまで他人さまがつくったものに結果論でイチャモンをつけたに過ぎない。そういうわたしとて、いつもいつでも同様のことをやらかす可能性を持っているし、実際に思いあたるフシがいくつもある。
この場合、最悪なのは「濠浚渫工事をしています」という書き方だろう。がっかりである。しかしわたしは笑えない。たしかにがっかりではあるが、そんな「がっかりさん」になったことがないかと問われれば、「ない」と断言できる自信がないからだ。「わたしとわたしの環境」からその類が発信されてないかといえば、「ない」と即答できる自信がないからだ。
「◯◯をつくっています」あるいは「◯◯をしています」。
日本全国にあふれている、あの工事看板をあだやおろそかに考えてはならない。ささやかではあるけれど、あれもまた重要な情報発信なのだ。「情報を発信する」ということは「伝える」ということである。伝わらない情報は、情報を発信していないと同義である。誤解を恐れず言う。「伝える」ためには「相手はバカかもしれない」ぐらいの心持ちでいることが必要だ。伝わらないのは「相手がバカ」だからではなく、バカにも伝わる伝え方ができない自分が悪かったのかも、という省み方をすることが肝要だ。
「じゃあ全部平仮名にしてしまえばいいじゃないか」というそこのアナタ、ことはそれほど簡単ではない。
世の中すべからく、落としどころというものがある。そこが難しいところである。
悩んだあげく、面倒くさくなる。
そしてついつい安易なほうへ・・・
気をつけようっと ^^;
******
さて、それから4年後のわたしはというと、当時とは異なる感想を抱いている。
「濠を浚渫しています」でもわるくないのではないか。また、当時最悪だと断定した「濠浚渫工事をしています」も、それほどわるくない選択肢ではないのではないかと思えるようになってきたのだ。
とはいえそれは、「ただし」という括弧つきである。
説明しよう。
まず、「濠」にも「浚渫」にもルビをふる。
そのうえで、「浚渫」とはどういったものか、そして、その浚渫工事をここで行うのはどのような理由があってなのか、その工事の目的はなんであるかを、たとえば横に併記する。
浚渫工事の歴史は古い。港の底をさらえる。あるいは、川底をさらえる。そして、川や港を深くする。港浚えや川浚えは、古くから、土木工事として代表的なものだったはずだ。
「浚(さら)う」と「渫(さら)う」をドッキングさせた浚渫という文字が、その工事をあらわす言葉として使われだしたのはいつのころからか。少し調べてみたが、はっきりとはしない。しかし、少なくともきのう今日ではないことは確かだ。
そのような専門用語に対して、「言い換え」という手法を採用し、「使わない」という選択をすることが、必ずしも正しいとは言えないのではないか。「言い換え」が、相手に伝えることを第一義に考えた場合に採用する方法としてもっとも有効なもののひとつであるのは疑いようがないにしても、専門用語を安易に使ってはいけないのと同様に、安易な「言い換え」もまた戒めるべきだろう。
ではどうしたらよいのか。
使う言葉と使わない言葉を決めておく、というのはひとつの手である。
たとえば切羽は使う。
たとえば高欄は使う。
たとえば釜場は使う。
たとえば客土は使わない。
たとえば暗渠は使わない。
たとえば防舷材は使わない。
以上は思いつくまま列挙したので少し乱暴だが、たとえば、「語句自体に意味があっておもしろい表現」であるか、「ただ漢字を羅列しただけのつまらない表現」という仕分け方を採用するのもよいのかもしれない。
いずれにしても、道はひとつではない。そして、そういった思考や試みが土木関係者以外の人たちに「伝える」という行為をするうえにおいて役に立たないはずはない。
以上、某日某夜、テレビ画面から流れてきた「しゅんせつ」という言葉に反応し、考えたことである。