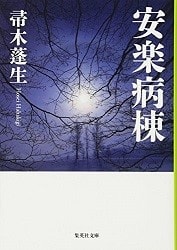
〈来栖の独白2019.4.1 Mon〉
帚木蓬生さんの著作は、『閉鎖病棟』に感動した。次いで『安楽病棟』を読んだ。途中、他のものも読んだということもあるが、『安楽病棟』は読了するまでにひと月以上を要した。老人ゆえに現れる様々な病気、そして尊厳死などについて考えさせられる。重い内容。精神科医でなくては書けない。ほんの僅か、下に引用・書き写すが、「先生」は本書の終末で、何人もの患者を薬で死なせる。そして、そのことに気づいた看護師を隠蔽のため殺害しようとする。
-----------------------------------------------------
p336~
次に立ち上がったのは中年の女性でした。(中略)
オランダでなくても現在の日本でも、とそのお母さんはマイクをしっかり握って続けました。「あんな子供がよく生きているわね」「よくもあんな子供を可愛がれるわね」「あんな子、社会のお荷物ね」といった声が、親子で街を歩いていると、どこからか浴びせられるというのです。日本でさえその有様ですから、オランダであれば、障害児を眼にした一般市民が、「あんなの、早いとこ注射で眠らせたらいい」と排斥するに決まっています-----。そのお母さんはそこで少し涙声になり、そんな社会が来るなんて、悲しくてなりません、と訴えたあと、深呼吸をして続けたのです。
障害をもつ人や病人が健常者からサービスをうけるばかりで、健常者の足を引っ張るのだと考えるのは間違いです。わたしも、初めて生んだ子供が先天性の障害児だと判ったときには、一緒に死のうかと考えました。育児の過程でも、この子がいなかったら(p337~)どんなに楽かと思ったものです。しかし、この子が不自由な言葉でわたしを呼び、曇りひとつない笑いを向けるようになったとき、ケアされているのは自分だと気づきました。夫もそう言いました。そしてこの気持は、この子の妹や弟にも引き継がれています。弱い立場の人たちに優しい目を向ける長女や次男を眺めて、長男のおかげだとしみじみ思うのです。わたしたちが障害者や病人に対して施しているだけのものを、わたしたちもその人たちから施されているのです----。
お母さんのそんな発言を、先生は全身で聞き入り、時々小さく頷いていました。
『守教』帚木蓬生さん(新潮社・上下各1728円)

西日本新聞 2017年12月10日 15時08分
■信仰守った人々の心に迫る
福岡県大刀洗町の田園地帯に赤れんが造の教会が立っている。「何でこげな立派な教会があるとじゃろう」。隣の小郡市で生まれ育った帚木さんは中学時代、この今村天主堂の近くを自転車で通り、不思議に思ったという。半世紀余りを経て、天主堂建設につながるこの地のキリスト教信仰史を大河小説『守教』で描き出した。
今村は戦国期のキリシタン大名、大友宗麟(そうりん)の領地だった。『守教』の中で宗麟は、今村など約20カ村を統(す)べる大庄屋に家臣の右馬助を任じ、「小さなイエズス教の王国を打ち立てよ」との願いを託す。
しかし、豊臣秀吉の時代からキリスト教排斥が始まり、天草の乱以降は完全に禁教となる。苛烈な信徒弾圧、ペドロ岐部や中浦ジュリアンら聖職者のひそかな訪問、棄教、密告、そして殉教…。右馬助の子孫の大庄屋や庄屋、あるいは領民の目を通して、信仰を守り続けた「小さな王国」の300年間が描かれる。「(キリシタンの小説は)普通は天草の乱で終わりですが、最後まで書かないといけません。信仰がどうやって始まり、どうやって守られたのか」
隠れキリシタンは証拠を残さないようにしたため、ほとんど史料がない。帚木さんはフィクションを織り交ぜ、彼らの心に迫った。
「たとえば踏み絵は、どこの何者が作ったのかわからん銅板を踏むのに、なぜびびらんといかんのですか。私は(登場人物に)土足でがちゃがちゃと踏ませました」。久留米藩で今村だけが信仰を守れたのは、人々の勤勉さや檀那(だんな)寺の暗黙の了解があったと考え、場面を丁寧に組み立てた。
『守教』は、筑後川の水利事業に命をかけた五庄屋の物語『水神』、圧政にあえぐ農村と医師の姿を描いた『天に星 地に花』に続く「久留米藩3部作」の3作目にあたる。「方言を書くのはこんなにいいものかって思いました。標準語はぎくしゃくするのに、方言だと会話が進みます」
1947年生まれ。精神科医でもあり、医療小説が多いが、ほぼ無名の人々の目で描く独自の歴史小説の世界も開拓した。「有名人には感情移入できない。診察している患者さんが普通の人たちだからですかね」
年1作のペースを維持する。ほぼ毎日午前4時から2時間、机に向かい、原稿用紙4枚を埋める。現在は日蓮宗の開祖、日蓮を描く小説に取り組んでいる。 この作品にも、フィクションをいろいろと仕掛けているという。
「『守教』では宗麟の書状まで捏造(ねつぞう)しました。今度も…。作家は人をだます楽しみがないと」 =2017/12/10付 西日本新聞朝刊=
◎上記事は[西日本新聞]からの転載・引用です
――――――――――――――――――――――――
産経新聞 2017.12.17 12:26更新
【書評】寛容さ喪う私たちの世界への警鐘 『守教(上・下)』帚木蓬生著
本書を読みながら改めて思い知らされたことは、作品にはそれにふさわしい文体がいるということであった。本書の場合、それは静謐(せいひつ)極まりない筆致である。
物語は戦国期、大友宗麟(そうりん)麾下(きか)の一万田右馬助(いちまだうまのすけ)が、宗麟から、二つのこと--領内の高橋村の大庄屋になることと、小さくともよいから、イエズス教の国をつくること、を頼まれ、これを実行しようとするところから幕があく。
上巻では、存在すら知らなかった神の教えを聞いた人々--武士から農民まで--の歓喜とおののき、そして秀吉の禁教令によって、宗徒の間に広がる不安と動揺が活写されている。
さらに下巻では、苛烈を極めるキリシタン弾圧の中で行われる、殉教、追放、密告などから、幾星霜を経て、明治6(1873)年、外圧によって、開教が成されるまでが描かれていく。
本書は、一貫して、右馬助とその子孫たちの視点で物語が進行し、詳述はしないが、特に、下巻で描かれる、信徒を守るための最大の殉教の場面では、読者は落涙を禁じ得ないであろう。
それを可能たらしめたのは、前述の静謐な筆致によるものであり、映画でいえば、本書はドキュメンタリーに近く、私たちは、この凄惨(せいさん)な事実(もはやそうとしか思えない)から目を離すことはできなくなる。
それだけではない。作中には、イエズス教を一言でいえば「慈愛」である、とする箇所がある。作品が訴えているのは過去のキリシタン受難史だけではないのではあるまいか。
本書は、日々、寛容さを喪(うしな)いつつある、私たちの世界、すなわち〈現在〉に対する警鐘の一巻であり、いま、どこかで、何かに耐えながら生きているすべての人々のためのものだ。
目に見えない神の教えを守り続けた高橋村の奇蹟(きせき)--これは、作家が生涯に何度、書けるかどうか、という高みに手が届いた作品であろう。
本書との出合いは私にとって、まさに大いなる歓(よろこ)びとしかいいようがない。(新潮社・各1600円+税)
評・縄田一男(文芸評論家)
◎上記事は[産経新聞]からの転載・引用です
------------------
◇ 死刑執行された しかし絶命せずに息を吹き返した 『閉鎖病棟』 …〈来栖の独白2019.2.17〉
.................










