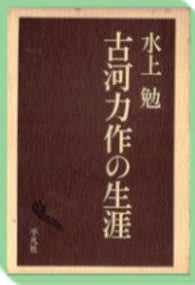
水上勉著 『古河力作の生涯』 平凡社
(ふるかわ りきさく)
あ と が き
つけたりを一つ二つ書いてみると、私と同じ故郷をもつ古河力作の境遇に、私がひとなみならぬ愛惜をもってきたこと、福井県の片隅に生まれた身丈尋常でない少年が、草花栽培というのどかな職業に従事していながら、なぜに大逆事件の死刑者の仲間に入ってしまったのか、その不思議ともいえる運命を私なりにさぐりあててみたかったのである。読んでもらえばわかるはずだが、何といっても、当時の世情が、花つくりの人にさえも、大きな翳を落として、政治のありかた、人生の幸福の求め方に、ひとつの工夫を与えてしまったということにほかならない。人間も花樹と一しょで、土壌があって稔るものである。力作は力作なりに自分の土を耕して一生懸命に生き、二十八歳で、刑死した。しかし、私は当時を見たわけではなかった。それで力作の生まれた国をふりだしに、神戸、東京と、彼の住んだ町々を歩いた。事件のことや、力作のひととなりについては、それを知る存命の方々に会い、苦心の著作をなした人びとの書物を読んで、私なりの知恵とした。(略)
私は天下国家について大きく発言するのは嫌いである。しかし、天下国家の片隅にあって、天下国家の運命に踏みたたかれてゆく小さな人生についての関心はふかくある。今日もその関心はつよい方だ。力作の人生を掘りおこすことで、この国のありようというものに、自然とつきあたり、ひとことでいうなら、明治も今もかわっていない国柄というものについて、ずいぶん考えさせられていった。このことも、「古河力作」から与えられたものというしかないだろう。たくさんの資料、書物を読んだ。(略)
一九七三年十月二十五日 水上 勉
p3~
歓喜山妙徳寺、あるいは文殊峯と町の人々がよぶ曹洞宗永平寺派の古寺へゆく道である。この寺の墓場に古河力作さんは眠っている。私が、岬の端から、力作さんが西を眺めて描いたであろう十三歳頃のスケッチを思いだすのも、じつはこの山に眠っている力作さんの霊に深い感慨をおぼえるからである。力作さんは少年時代に写生したけしきのうしろ山で眠っている。
古河力作さんのことは、世に「大逆事件」といわれる天皇暗殺謀議の罪で明治四十四年一月二十四日に、東京市ヶ谷で死刑を執行され、三日後二十七日下落合の火葬場で焼かれたので知る人も多い。
p15~
小学校時代は、成人の背丈ではないから、小躯は目立ったと思われる。誰にいわれなくても、誰かから、その小躯に生まれねばならなかった暗い家系について、力作は耳打ちされた日があったかもしれない。なぜに自分はこんな小さい躯に生まれねばならなかったか。慈悲深い父母への恨みも感じられた日もあったはずである。しかし、そうは思っても、学校は卒業しなければならない掟であるから、いやいやながらでも、作園場から、小学校まで毎日通学した。
p16~
西津橋の近くに、「古川」とあって、それに架かった橋があり、土提の下方に「小浜監獄署」と記されてある。ここは昭和初期まで活用されていた若狭地方唯一の監獄で、作園場の古河家からは歩いて十分とかからない所にあったようだ。いまは、この建物は失せているけれども、昔はここに罪人を投げ入れる矯正施設があったとみてよい。力作は授業が終われば、級友とあそぶことはあまりなくて、家に帰ると、すぐ人眼を避けて、好きな絵道具をもってスケッチに歩いたとみてよい。(略)
私はこの豆手帖に、力作の奔放敏感な感受性を察すると同時にある、運命さえ感じて考えこまされるのである。作園場古河家をとりまいていた明治の春秋が、「小人」とさげすまれたこの少年をどのようにはぐくんだか。「城址」と「監獄」に興味をもたねばならなかった少年の、行く手はかすかに暗示されているからである。
p70~
利発で敏感だった少年は、背丈こそ一人前ではなったが、もはや青年期に入ろうとしていた。その年まわりに、足尾銅山の悲劇だった。天皇はなぜ田中正造の訴えをお聞きにならなかったのだろう・・・被害民を代表して直訴した田中を、狂人と偽って逮捕処断した政府にどのような気持を抱いたか。その資料もいまはない。
だが、この年から九年後「西津の主義者」とよばれねばならぬ運命を背負う力作の心に、たしかに人間不平等社会への不信の芽は育まれていたと思う。
p129~
花づくりの小躯の人が、なぜに、天皇暗殺謀議という大それた事件に足を踏み入れたかの根拠は、花を愛するという感傷にまぎらわせていては掴めない。園丁生活にそのタネは確在していたとみるのが私の卑見である。土ごしらえがなくては草花は生きぬ。溝口大尉が「馬ひけいツ」と声を発し、大勢の女中に、「行ってらっしゃいませ」と見送られながら、近衛連隊へ帰ってゆくうしろ姿を見送った力作には、クツワを取ってゆく一兵卒が哀れに思われたろう。ここにも人間不平等の思いの根を育てる培養土はある。うちひしがれた兵に、差別される者の悲しみをみた。いや、その大尉のまたがった馬に、遠い在所の馬糞の匂いを嗅ぎ、西津へ無言の帰還をなしたであろう百姓の次男三男の骨の声をきいたかもしれぬ。西洋ダリアをつくる園だけ、格別の温風が吹いていたなど、私は信じられない。
p291~
いずれを「真」とうけとるにしても、古河力作が、死の直前まで、その小躯にかかわらず豪胆な態度で、ゆったりと刑場にひかれていった光景がよみがえるわけだが、三樹松氏の記憶にある面会の思い出は今日も私の瞼をぬらすのである。
何日であったか、その日の記憶ははっきりしないそうである。いよいよ死刑ときまってからのことだから、十八日から処刑の二十四日までのすなわち一週間のうちの何日かだろう。(略)弟妹を監獄の裏門につれてくれば、本人には知らさぬうちに遠くから見せることくらいは許してやる、というしらせがきて、三樹松、つなは出かけてゆく。
裏門の看守詰所で待たされていると、やがて、看守がきて、二人を庭の方へつれてゆく。二人は、手をつないで寄りそってゆく。と建物と建物のあいだに腰板を張っただけの屋根ふき廊下があり、その廊下を動く編み笠がみえた。さあ、兄さんを早くみなさい、と看守は指さした。三樹松とつなは、背のびしてみようとするが、兄の姿はみえず、ただ、編笠が、腰板の上をうごくだけで、やがて、それは建物に吸われてみえなくなった。
力作は背がひくかったので、ふつうの人と同じように歩いても、廊下の腰板にかくれてみえなかったのである。看守のせっかくの親切も、小さな弟妹の瞼に、編笠がうごいてゆく姿をとどめただけだった。
古河力作は、あれほど会いたかった弟妹が、庭の隅から背のびしてみていた一日のことを知らず、刑場に向かった。
p308~
力作研究のバイブルは、この獄中遺品「新約聖書」であった。私の心に残る一章節がある。路加伝第十九章、「ザアカイの章」だ。
p309~
しかし私がザアカイの章に、力作が眼をとられている事実をみて、ある感動をかくし得ない。ザアカイがたとえ、みつぎとりの頭という地位にあったにせよ、その躯が人より小さくて、道ゆくイエスの姿がみえないほどだった。人からあなどられる短躯の人だったことにひかれるからである。ザアカイは大ぜいの人が、われもわれもと、イエスの宿に供させてほしい所望しているのに、背が低いので、人の通らない道へ廻りこんで、多分そこをイエスが通りかかるであろう地点と信じて、桑の樹にのぼった。すると、イエスはみえた。ザアカイは生まれてはじめて救世主をみた。----イエスは、桑の樹上のザアカイに呼びかけるのだ。
ザアカイよ降りて来い、私はこよい、お前の家を宿に選ぼう・・・と。(略)
力作が、この章に眼をとめた心奥に、おのれをザアカイに重ねてみた一瞬がなかったであろうか。私の卑見ならば致し方あるまい。しかし、思うのだ。力作がのぼった桑の樹は、ひよっとしたら、川田倉吉の愛人社であり、千駄ヶ谷の平民社ではなかったかと。力作はこの世に貧しい者が泣き、弱い者がいためつけられることを憎んだ。人間に差別のない万人平等の平和国家が来ることを願って桑の樹へよじのぼった。ザアカイはイエスに祝福されたが、力作は「逆徒」として絞殺された。どうして、力作のような、平和を求めて、桑の樹にのぼった男が殺されねばならなかったか。そこのところを、私はながながと書いてきたのである。読者はどう思われるだろう。
時の行動派文学者徳富蘆花は、処刑当日はまだ委細を知らされていなかったので粕谷村の家で天皇への上奏文を思いたっていた。しかし新聞を見て驚愕した。蘆花夫人の日記にその時の模様がかく書かれている。
『おーい、もう殺しちまったよ、みんな死んだよ。と呼びたまふに、驚き怪しみ書斎にかけ入れば、巳に既に昨二十四日の午前八時より死刑執行!何たるいそぎやうぞ。きのふの新聞に本月末か来月上旬とありしにあらずや(略)
p311~
力作たちの死は、高名な作家や、無数の無告の市民の慟哭を誘ったのである。
p325~
墓を立てる余裕があるなら、弟妹に甘いものでも買って下さいと言いのこし、非墳墓主義を通した力作の墓は、郷里若狭青井山の妙徳寺にあると冒頭で書いておいた。
p326~
青井山は文殊峯ともよばれているが、前記したように、若狭の海を一望にみわたせる風光明媚の中腹台地で、力作が眠る場所としては、最適の地といえる。なぜならば、力作が少年時に大切に所持していた豆手帖のスケッチの場所だ。骨は東京の地に失われたとしても、力作の霊魂は還って眠った。「還源院」。人は在所へ帰って眠るのである。
(2006,6,16up)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
◇ 天下国家の片隅にあって、天下国家の運命に踏みたたかれてゆく小さな人生 大逆事件 古河力作 2010-01-31
◇ 大逆事件:管野スガの書簡見つかる (毎日新聞 2010/1/29)
..........









