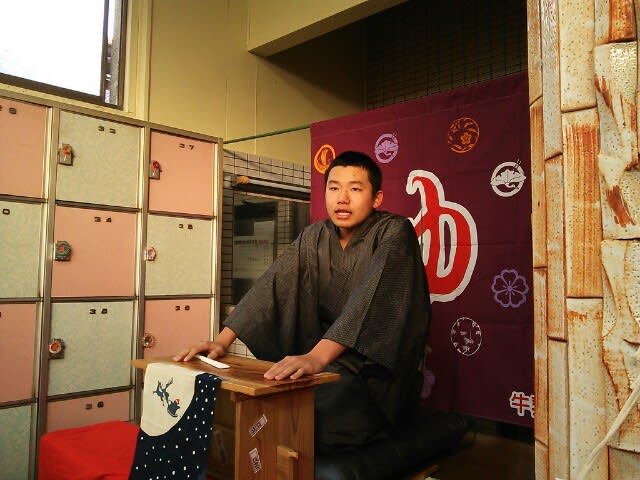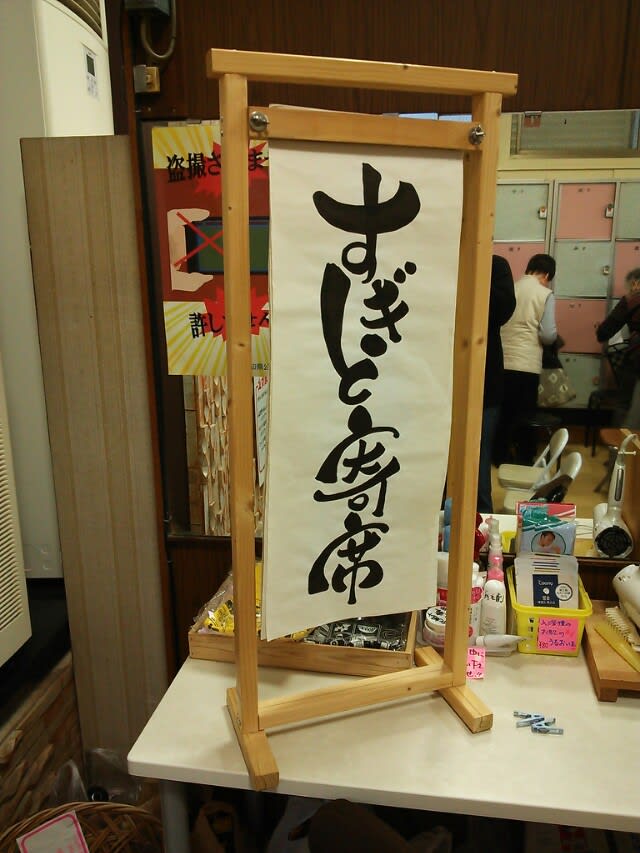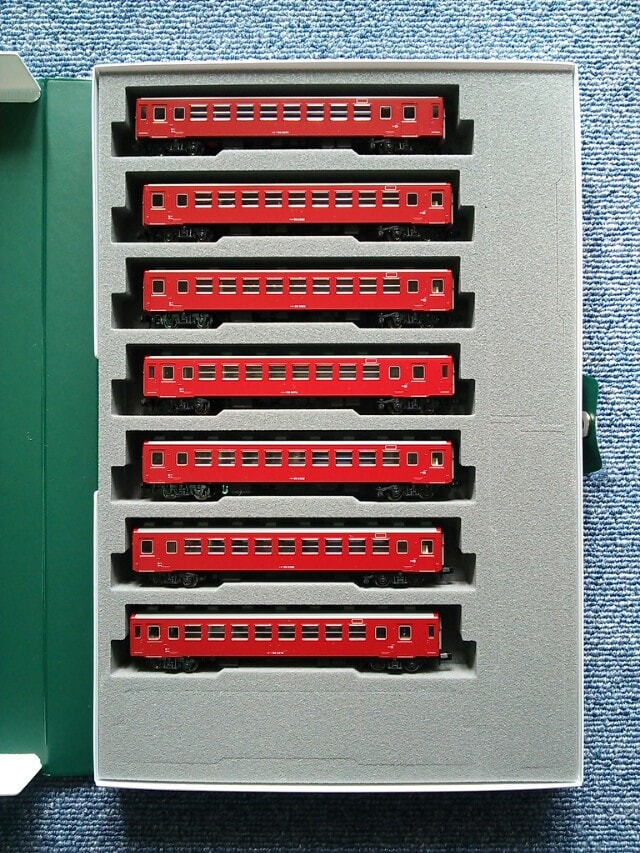皆様、こんばんは。
事務局です。
26日の一宮市内は、曇ったり、晴れたりを繰り返す天気になりました。
本日の寺西は、現場作業でした。
23日午後、杉戸浴場様で開催されました、地域寄席「すぎと寄席」の観覧に訪れました。
引き続き、観覧した感想を書いていきます。
KOHARU亭兄弟のお二人でお話をつなぐ「講談」が始まりました。
先ずは、お兄さんのKOHARU亭たいちろう様が、お話をします。
演目は、鼠小僧外伝「ネズミ小僧とサンタクロース」です。
この演目は、講談師の神田山陽様の持ちネタです。
お話は、検索サイトで「神田山陽」で検索しますと、YouTubeで聞くことができます。
ところで鼠小僧について、皆様、詳しく知っていますか?
寺西が知っていることは、
(1)三河国蒲郡出身
(2)大名屋敷専門の盗人
(3)義賊
ぐらいです。
そこで調べてみました。
生まれた年は、1797(寛政9)年でした。
出生地は二ヵ所ありました。
(1)三河国蒲郡出身説
(2)江戸日本橋(元吉原)説
生い立ちは、10歳前後で木具職人の家に奉公に入り、16歳で親元に戻っています。
戻ったのち、鳶人足になったものの、不行跡(ふぎょせき)のため、25歳の時、父親に勘当されています。
勘当後は、賭博(とばく)三昧の生活を送り、結果として、身持ちを崩してしまい、賭博の資金稼ぎのために、盗人稼業に手を染めたそうです。
鼠小僧は、約5尺(151.515cm)に満たない小男で、動作が敏捷(びんしょう)、という記録が残っています。
鼠小僧は、武家屋敷の奥向(おくむき)専門で盗みに入っていました。
皆様、ご存じかと思いますが、武家屋敷は、男性が住んでいる「表」と、女性が住んでいる「奥」が、はっきりと別れていました。
表は、当主を中心に、家政処理や対外的応接などおこなう場所、奥は、当主の妻を中心に、子女たち家族が生活する場所になっていました。
奥であれば、女性ばかりで、発見されても逃げやすいことを知って、鼠小僧は、奥専門で盗みに入っていたようです。
鼠小僧は2回、捕まっていました。
1回目は1825(文政8)年。
2回目は1832(天保3)年。
1回目で捕まった時までの忍び込み数は28箇所32回(※)。
2回目で捕まった時までの忍び込み数は71箇所90回(※)。
北町奉行所の尋問で、鼠小僧は、荒らした屋敷95箇所839回、盗んだ金額は三千両あまり、と供述したそうです(※)。
※数字については諸説あります。
近年、盗んだお金の大半は、博打、女性、飲酒に消えた、と言われています。
次回に続きます。
■■あしあと■■
2017年12月26日に追記しました。
tropaeolum様、あしあと、ありがとうございました。
ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。
事務局です。
26日の一宮市内は、曇ったり、晴れたりを繰り返す天気になりました。
本日の寺西は、現場作業でした。
23日午後、杉戸浴場様で開催されました、地域寄席「すぎと寄席」の観覧に訪れました。
引き続き、観覧した感想を書いていきます。
KOHARU亭兄弟のお二人でお話をつなぐ「講談」が始まりました。
先ずは、お兄さんのKOHARU亭たいちろう様が、お話をします。
演目は、鼠小僧外伝「ネズミ小僧とサンタクロース」です。
この演目は、講談師の神田山陽様の持ちネタです。
お話は、検索サイトで「神田山陽」で検索しますと、YouTubeで聞くことができます。
ところで鼠小僧について、皆様、詳しく知っていますか?
寺西が知っていることは、
(1)三河国蒲郡出身
(2)大名屋敷専門の盗人
(3)義賊
ぐらいです。
そこで調べてみました。
生まれた年は、1797(寛政9)年でした。
出生地は二ヵ所ありました。
(1)三河国蒲郡出身説
(2)江戸日本橋(元吉原)説
生い立ちは、10歳前後で木具職人の家に奉公に入り、16歳で親元に戻っています。
戻ったのち、鳶人足になったものの、不行跡(ふぎょせき)のため、25歳の時、父親に勘当されています。
勘当後は、賭博(とばく)三昧の生活を送り、結果として、身持ちを崩してしまい、賭博の資金稼ぎのために、盗人稼業に手を染めたそうです。
鼠小僧は、約5尺(151.515cm)に満たない小男で、動作が敏捷(びんしょう)、という記録が残っています。
鼠小僧は、武家屋敷の奥向(おくむき)専門で盗みに入っていました。
皆様、ご存じかと思いますが、武家屋敷は、男性が住んでいる「表」と、女性が住んでいる「奥」が、はっきりと別れていました。
表は、当主を中心に、家政処理や対外的応接などおこなう場所、奥は、当主の妻を中心に、子女たち家族が生活する場所になっていました。
奥であれば、女性ばかりで、発見されても逃げやすいことを知って、鼠小僧は、奥専門で盗みに入っていたようです。
鼠小僧は2回、捕まっていました。
1回目は1825(文政8)年。
2回目は1832(天保3)年。
1回目で捕まった時までの忍び込み数は28箇所32回(※)。
2回目で捕まった時までの忍び込み数は71箇所90回(※)。
北町奉行所の尋問で、鼠小僧は、荒らした屋敷95箇所839回、盗んだ金額は三千両あまり、と供述したそうです(※)。
※数字については諸説あります。
近年、盗んだお金の大半は、博打、女性、飲酒に消えた、と言われています。
次回に続きます。
■■あしあと■■
2017年12月26日に追記しました。
tropaeolum様、あしあと、ありがとうございました。
ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。