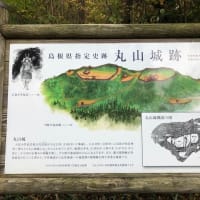32.2.後醍醐天皇と足利高氏

次の絵は永らく、足利尊氏像であるといわれてきたが、近年の研究でこの像は尊氏の側近の高師直とされている。
頭髪がざんばらである理由はつぎのとおりである。
鎌倉にいた足利尊氏に討伐の勅命がでたときに、尊氏は赦免を求めて隠居した。
そして出家しようとして、頭を丸めようと髻を切った。
その時に討伐軍の新田軍と戦っていた、弟の直義が敗戦して尊氏のもとにやってきた。
直義は足利家存続のために立ち上がってくれと要求した。
尊氏は一門の行く末を案じ、立ち上がる決心をした。
このとき尊氏はすでに髻を切っていたので変な髪形となった。
これを見た取り巻きは、同じように髻を切って出陣した。
そのため、次の絵のような頭髪になった、といわれている。

足利高氏はその履歴を見ると得体のしれないリアリストの風雲児である。
後醍醐天皇もまた、その対極にある強烈な個性を持った理想を追求する風雲児であった。
案外この二人はケミストリーが合ったが、結局融合しないままに終わることになるのである。
後醍醐天皇は現実はさておいて、過去の権威を理想としてそれを再興させようとした。
しかし後醍醐天皇の施政についてくるのは、貴族と一部の武士たちだけであった。
一方、足利高氏は、政治的理想や具体的な目標を持っていなかった。
ただ、不満を持つ武士たちをなんとかしてやりたい、という気持を持っていた。
できるという自信がないときでも「よっしゃ、分かった、任せておけ」という。
いわゆる安請け合いである。
これが、武士たちの人気を呼んだ。
もともと、この戦に参加した大部分の武士たちは、北条の下ではうだつも上がらと考え、土地欲、子孫繁栄欲、身一代の名聞欲などにより、この戦乱に賭けたのであった。
だから、朝廷とは何であるか、なぜ天皇は尊く、敬うべきであるのか、分かっていなかった。
勤王などという意味もわかっていなかったのである。
極端に言うと、その頃の武士は、朝廷であろうと幕府であろうが、自分の利益に反するものに対しては敵とみなしていたのである。
また、領地は財産であり、一族の命をかけて守るべきものであった。
32.2.1.親政の論功行賞
新政による論功行賞が始まった。
新政の中心は論功行賞と土地関係の訴訟の処理におかれ、その結果、貴族階級の利益擁護の線の強いことに武士階級は不満を抱いた。
また皇居造営などによる課税の増大は農民の不満もまねいた。
その様子を「私本太平記」では次のように書いている。
足利高氏を従三位、左兵衛ノ督に任じ、武蔵、常陸、下総の三ヵ国を賜る。
同苗、直義には左馬ノ頭をさずけられ、三河の一部と遠江一国を。
新田義貞を正四位ノ下、右衛門佐に叙し、越後守とし、あわせて上野、播磨を下さる。
同、脇屋義助を駿河守に。
また、楠木正成には、摂津、和泉の一部と、河内守への叙任がみられ、また船上山いらい忠勤の名和長年には、因幡、伯耆の両国があたえられた。
それ以下、幾多の武門に、それぞれな恩賞下附が沙汰されたが、ここにたれの目にも、
「これは、何かの間違いか」とすら怪しまれた例外中の例外があった。
播磨の赤松円心則村にたいする授賞だった。
彼の軍功は、顕著である。
――おそらくは円心自身も、名和長年や千種忠顕には劣らぬものと自負していたにちがいない。
ところが、発表になってみると、佐用ノ庄一所を賜う、とあるだけだった。――
のみならず前から所領していた播磨の守護は取り上げて、これを新田義貞の新知行の方へ組み入れ、人の物で他人ひとの恩賞を行っている。
「怒ったろう」
「おれでも怒る」
「ましてや円心入道だ」
「あの戦下手な公卿大将の千種殿さえ大国三ヵ所も受領したというのに、その人を扶けて、早くから中国の勢せいを狩り催し、六波羅攻めにも、獅子奮迅ふんじんのはたらきをした赤松勢がよ」
「このあつかいでは、恩賞の不平よりは、武士として顔が立つまい」
「勇猛をほこる円心だけに、一族や部下を死なせた数も、赤松が一番だろうといわれておる」
「ばかばかしさよ、とあの円心が、おもてに朱をそそいで、沙汰書を引き裂いて捨てたというが、目に見えるようだ」
と、衆口は、みな円心に、同情的だった。
果たして、それからまもなく、赤松円心の一勢は、朝廷へも届け出ず、ただ一書を六波羅の高氏へ投じたのみで、憤然、京をひきはらって国元へ帰ってしまった。
それを見た日も、武士大衆は、「むりはない」と、みな言った。
みな円心の後ろ姿を思って気のどくがった。
けれど、かえりみて自分たちが必死を賭かけて、いま、掌てに乗せ得たところの恩賞を見ると、
「……何と、これは」
と、一抹の不満と淋しみを噛む顔でない者はない。
内々たれもが、自己の功には過大な期待を持ちすぎるものではあったが、やがて彼らの間に起ったやり場なき不平の色は、ただ単にそれだけのものでもなかった。
国家の名で戦った勝者と勝者との、分けまえ争いも、ひとりの女を捕えて身の皮を剥ぎ、その分け前で、仲間争いを演じ出す野盗山賊のつかみ合いも、何と大した違いはないものか。
後醍醐のご理想も。新政府の新政第一歩も。
まずはこのおなじ轍を踏みはずさない人間通有の欲の目に迎えられ、武士大衆は公然、ごうごうと不平を鳴らしだした。
「これが、ご新政というものか」
「いやもうガッカリだわえ」
「日本全土は、おれどもの力で取ったものじゃないか」
「何で公卿だけの力で、北条の世が仆せたろうぞ。おれどもの取った土地ゆえ、おれどもへまず充分に分けるべきを」
「さはなくて、恩賞の、やれ綸旨のと、事々しく、端クレばかりくれくさる」
「いや、過小でも、貰ったほうは、まだいい方だ。いまだに、沙汰なしの者すら多いぞ」
野性の言いかたは露骨で、わざと堂上へもとどけとばかり、声を大にして言いつのる。――
この論功行賞に対する、不満や非難の状況を公卿の北畠親房(「神皇正統記」の筆者)は批判する。
北畠親房は村上源氏の流れを汲む名門の出である。
後の南北朝では南朝方の主勢力として、足利尊氏と戦う。
このころ「神皇正統記」を執筆したものといわれている。
「神皇正統記」は神武天皇から後村上天皇に至る歴代の略譜を記すとともに、神代から皇位が正当な理由のもとに正統な皇位継承者に伝えられてきたことを証明し、後村上天皇(南朝)の正統性を論じたものである。

北畠親房は、神皇正統記の「第95代後醍醐天皇」の項で
たいした功績もないのに報奨を要求する武士どもは、なんとも不忠で浅はかな輩である、と批判している。
いわゆる上から目線であり、武士に対する嫌悪感が伺える。
さしたる大功もなくてかくやは抽賞せらるべきとあやしみ申輩(ともがら)もありけりとぞ。
関東の(北条)高時天命すでに極て、君の御運をひらきしことは、更に人力といひがたし。
武士たる輩、いへば数代の朝敵也。
御方にまゐりて其家をうしなはぬこそあまさへある皇恩なれ。
さらに忠をいたし、労をつみてぞ理運の望をも企はべるべき。
しかるを、天の功をぬすみておのれが功とおもへり。
介子推(かいしすい)がいましめも習しるものなきにこそ。
かくて高氏が一族ならぬ輩もあまた昇進し、昇殿をゆるさるゝもありき。
されば或人の申されしは、「公家の御世にかへりぬるかとおもひしに中々猶武士の世に成ぬる。」とぞ有し。
<意訳>
鎌倉幕府が倒れたのは、北条高時が天命が極まり、後醍醐天皇の武運が開けたからであって、武士の力などによるものではない。
その運を開いたのは、まさに朝威である。
そもそも武士というものは、いわば数代に渡る朝敵なのであって、お味方することで領地を保つことができたことを皇室のご恩と感じ、更なる忠義に励むことで分相応の望みを叶えようとするべきなのである。
春秋時代の介子推(かいしすい:中国春秋時代の晋・文公(重耳)の臣)のような行いをする者はいない。
介子推は、晋の公子である重耳が国の内紛を避け諸国を放浪していたときの従者の一人である。
19年後に帰国した重耳は君主(文公)にとなるが、介子推は身を引いた。
そして、論功報償が行われたが、子推に俸禄は与えられず、子推もまた何も要求しようとしなかった。
なぜなら、重耳が晋公の位につくのは天命であり、天の功績を盗むことはできない、という考えであったからである。
それなのに、高氏一門が、天の功を盗み、己の功と思って、昇進を望むのを認めてしまったので、「公家の御代に戻ったはずなのに、いっそう武士の世になってしまった」と言われている。
さらに、北畠義親は続ける。
君は万姓の主にてましませば、かぎりある地をもて、かぎりなき人にわかたせ給はんことは、おしてもはかりたてまつるべし。
もし一国づつをのぞまば、六十六人にてふさがりなむ。
一郡づつといふとも、日本は五百九十四郡こそあれ、五百九十四人はよろこぶとも千万の人は不悦。
<意訳>
日本は六十余州で限りがある。
一人に一国づつ与えると、60余人で終わる。
一郡づつ与えても日本は594郡なので、594人はこれでよいかもしれぬが、残り大勢の人の不満はのこる。
どうやってみんなの希望通りに土地を分け与えることができるのか。
公卿は公卿で、天皇の威光に帰した天下であるとし、それはわが世の春だと思っている。
得意絶頂にある朝廷は、これからは、頼朝や北条幕府のごときものは絶対につくらず、万機、天皇の直裁とし、遠い延喜、天暦の制に復古するとした。
しかし、つい昨日までは、式部官とか神祇官であった公卿が、一朝、天皇親政の謳歌にのって、俄か政務官となったのだから、なんら行政的手腕があるわけでもない。
事務の渋滞はもちろん、裁決のまちがいなどもたびたびで、ただもう、てんやわんやの新政だった。
不平不満の武士たちは考え出す。
自分たちが目指したのは、こんな世の中ではない、まだ目的は達成していない。
そのため、再度乱が勃発するのを期待するようになっていった。
32.2.2.尊氏なし
足利尊氏は高い官位は与えられても重要な役職には就いていない。
これは護良親王の進言を後醍醐天皇が気にして尊氏を敬遠したのか、尊氏が政権と距離を置いたのか、分からない。
世間は、この状況を指して「尊氏なし」と不思議がった。
ただし弟の足利直義や執事の高師直などは要職に就いており、また尊氏自身が倒幕第一の功労者であるから、政府に対する大きな影響力は保っていた。
もともと、尊氏は世俗の栄達などには淡白だったので、自らが要職に就かないことで周りの人間を栄達させようとしたのかもしれない。
新政府は「公家一統」の政治を標榜し、武家が統治する幕府を否定した。
尊氏は新政府と衝突する気はないが、公家との交流にも嫌気がさしていた。
武士の中に恩賞への不公平感が渦巻き、その反動は尊氏の台頭を待望するようになり、それは急速に強まっていった。
<続く>