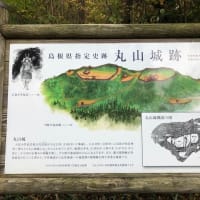34. 足利尊氏叛乱
尊氏は、反乱軍を鎮圧すると、そのまま鎌倉に留まった。
「太平記」や「鎌倉大日記」には、この時に
尊氏ノ鎌倉ニ入ルヤ、自ラ征夷大将軍ト称ス
とあるが、これは事実ではない。
ただし、尊氏が都を出発し、矢作の宿についたころ、朝廷から
征東将軍ニ補ス
との沙汰が届いており、征東将軍になっていた。
だが、この征東将軍には、征夷大将軍のような武士の棟梁であるという、意味は持っていない。
尊氏は今回の合戦の時に忠義な功績のある者たちに、独自で恩賞を行った。
これが、動乱の火種となる。
積もり積もっていた鬱憤・怨念・遺恨・私怨に火をつけた。
34.1. 足利尊氏と新田義貞
尊氏は、尻尾を振ってよろこぶ者を見るのが好きで、余りに気前がよすぎるほどだった。
また、尊氏は降伏者に寛大であり、たいていの旧怨は気にかけず許し、助けるのであった。
それが過ぎて、すでに朝廷で没収していた旧北条遺領や、新田義貞が受領した土地までを、麾下きかの将につい頒てやってしまったほどである。
新田の一族たちが先に拝領した東国の所領を、ことごとく空いている荘園と見なして、褒賞を受ける者たちに割り当てられた。
新田義貞はこれを聞いて、憤慨する。
そして、尊氏に対抗して自分の所領の越後、上野、駿河、播磨などにある足利の一族たちの支配する荘園を取り上げて家来たちに与えた。
新田と足利と武家の主導権をめぐっての対立は益々激しくなっていく。
こうした状況下で、新田を味方する側から、「足利尊氏に謀反の動きがある」と後醍醐天皇に伝える者が出てきた。
後醍醐天皇は、尊氏が勝手に褒賞を授けていることに不満をもっていたので、尊氏を討とうとするが、周りのものから事実を確かめる必要があると、言われ思いをとどませた。
そこで、鎌倉に使者を送り、尊氏に上洛を命じた。
しかし、尊氏は上洛を拒否する。
弟の直義は「いま上洛するのは、危険だ。なにか罠がある」と頑強に、尊氏の上洛を止めたからである。
尊氏と義貞は「後醍醐天皇に反逆の意がある」と互いを非難しあうようになり、相手を成敗するよう訴える。
尊氏は京都に使者を送って、「新田義貞は、都合よく立ち回っているだけで、君側の奸である」と避難し、義貞を誅伐するように、進言した。
これを知った義貞は「足利こそ非がある」と具体例を挙げて主張し、足利兄弟を逆賊として誅伐する許可を求めた。
そんな時に、鎌倉からある人物が京都に到着する。
護良親王のお世話役をしていた「南御方」という女性である。
南御方は護良親王が殺害された現場を見ており、「護良親王は足利直義の刺客によって殺害された」と証言する。

後醍醐天皇は「それなら、尊氏、直義の反逆は間違いない」と思うようになった。
また、その思いを後押しするように、四国や西国に領地を持つ在京の武士達が、足利から届いたと言って書状を見せた。
書状の数は数十に上っていた。
書状には「新田右衛門佐義貞誅伐セズンバ有ル可カラズ一族相催シ急ギ馳セ参ジラレヨ」とすべて同文で、差出人は足利直義であった。
「こうなった以上疑うことはない。すぐに討手を下されなければならない」となった。
新田軍と足利軍の衝突
11月8日に義貞に足利尊氏・直義成敗の綸旨が下り、義貞は天皇側の軍勢の総大将となった。
<新田義貞>

討伐隊が来ると知った直義たちは、尊氏を迎え撃つ準備を急ぐように進言した。
しかし、尊氏は帝に恭順の意を示すと言い、次第によっては出家さえもすると、宣言して隠居した。
というのも、護良親王を殺害したのも、西国の武士に書状を送ったのも、直義が行ったことであり、尊氏は関与していない。
だから、謹んでをもし上げれば、後醍醐天皇はきっと分かってくれると思ったからである。
しかたなく、足利軍は尊氏抜きで直義が、新田義貞軍を迎え撃つが、足利軍は敗退を重ねる。
破れた直義は鎌倉に戻り尊氏に、このままでは足利一門は滅びてしまう、と尊氏の参戦を説得する。
説得するために、直義たちは偽綸旨を作成し、それを敵方のものから奪ったと尊氏に見せた。
その偽綸旨には
足利宰相尊氏、左馬頭直義以下一類等、誇武威軽朝憲之間、所被征罰也。
彼輩縦雖為隠遁身、不可寛刑伐。深尋彼在所、不日可令誅戮。於有戦功者可被抽賞、者綸旨如此。悉之以状。
建武二年十一月二十三日右中弁光守武田一族中小笠原一族中
「足利宰相尊氏、左馬頭直義以下の一党は、武力を誇って朝廷の定めた掟を軽んじたので、征伐しようとするものである。
あの一党は、たとえ世を捨てた身であっても処罰を許すことはできない。
厳しくその所在を尋ねて速やかに討伐せよ。
戦功のある者は恩賞が与えられるだろう。
以上、綸旨はこのようである。これを書面にして明らかにする。
建武二年十一月二十三日 右中弁光守
武田一族御中
小笠原一御族中 」
と書かれてあった。
つまり、隠居していても処罰する、と暗に尊氏を処罰することを指していた。
致し方ないと、ようやく尊氏は翻意して出撃することになる。
足利尊氏が前線に戻り指揮をとると、足利軍の士気が高揚する。
形勢は一気に足利軍が有利となり、12月13日新田軍は総崩れとなった(箱根・竹ノ下の戦い)。
敗退した新田軍は西へ逃れて行った。
新田義貞は尾張で陣を張り敵の進軍を防ごうとする。
しかし、この戦いの情勢を見ていた、朝廷に敵対する勢力が各地で一斉に挙兵しはじめていた。
朝廷は大慌てとなり、新田義貞に帰京の命令を出した。
足利尊氏京に攻め上る
義貞は12月30日に帰京する。
尊氏は義貞を追撃して、京都まで攻め上がっていった。
また、西国から足利の援軍も近づいて来ていた。
朝廷は兵を募るため「今度の戦で忠功のあった者には、即日恩賞が行われる」といった張り紙を決断所(建武新政府の訴訟機関)に貼った。
これを見て、市中の人はいつものようにその言葉の後ろに落書きをする。
かくばかりたらさせたまふ綸言の汗の如くになどなかるらん
「これほどまでに申される綸言なれば、汗の如くの言葉通り取り消されることはないであろうが、汗とともに流れてしまうかも知れないなぁ。」
『綸言汗の如し』は、皇帝が一旦発した言葉(綸言)は取り消したり訂正することができないという中国歴史上の格言である
北畠顕家
後醍醐天皇は、陸奥将軍府の北畠顕家にも、尊氏討伐の綸旨を出していた。
もともと、北畠顕家は新田軍が鎌倉を攻撃している時に南下して足利軍を挟み撃ちにする計画であったのである。
しかし、顕家は兵を集めるのに手間取って出発が遅れていた。
軍勢が整った顕家は鎌倉を目指して南下し、さらに尊氏を追って西へ進んでいた。
つまり、新田義貞を追って足利尊氏が西へ向かい、さらにその尊氏を追って顕家が西進しているのである。
<北畠顕家>

鎌倉末期の激動期に若くして散った「花将軍」である。
北畠顕家は、『神皇正統記』を著した北畠親房の長男として、文保2年(1318)に生まれた。
長じて顕家は、武芸はもとより舞にもたけ、元弘元年(1331)に後醍醐天皇と北山に行幸した際、顕家は「陵王」を舞ったが、その凛々しく艶やかな姿に「花将軍」と称賛されたといわれている。
元弘3年(1333年)顕家は義良親王(後の後村上天皇)を奉じて陸奥へと下った。
建武2年(1335)に足利尊氏が後醍醐天皇に反旗を翻すと、後醍醐天皇は直ちに顕家を鎮守府将軍に任じた。
<続く>