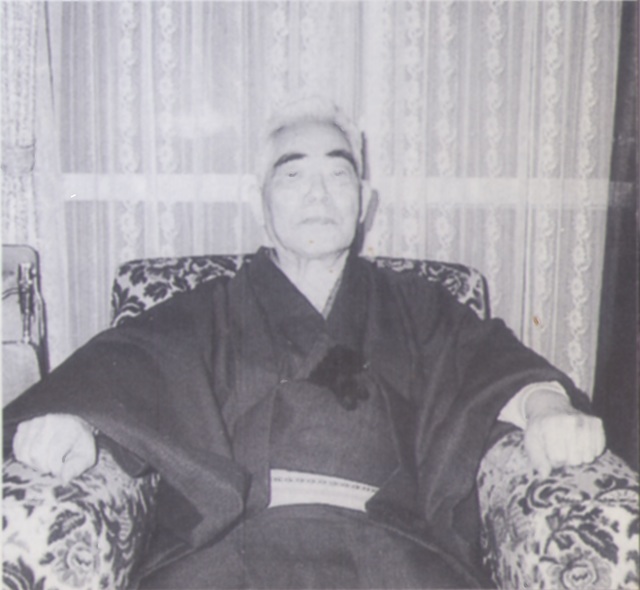2025年2月14日、Reutersは「トランプ米大統領、「相互関税」を表明 日本やEUも調査対象」を配信した。
『……
[ワシントン 13日 ロイター] - トランプ米大統領は13日、米国の輸入品に関税を課している全ての国に「相互関税」を課すと発表した。同盟国と敵対国の双方を標的とした新たな貿易措置となる。
トランプ氏は相互関税の導入を公言してきたが、この日の指示は具体的な導入に至るものではなく、代わりに貿易相手国が米国製品に課している関税の調査開始を指示するもの。対応策の策定まで数週間から数カ月かかるとみられている。
対象には日本のほか、中国、韓国、欧州連合(EU)が含まれる。
トランプ氏は大統領執務室で記者団に対し「公平性の観点から相互関税を課すと決定した。各国が米国に課している関税と同額を課す。それ以上でもそれ以下でもない」と述べた。ホワイトハウスは、こうした関税措置は米国の経済、国家安全保障の強化につながるとの見方を示している。
トランプ氏は、他国が課している関税に対応する相互関税の算出開始と、非関税障壁への対抗措置を指示する覚書に署名。商務長官が国別に対応していくと述べた。
……』
トランプ大統領の真意を知る意味で、少々古いが次の記事が参考になる。
『……
米韓FTA、カナダ、メキシコとのNAFTA再交渉でアメリカに有利な条件を引き出したトランプ大統領が、日本の消費税を「非関税障壁」と見なすアメリカが日本にも厳しい条件を突きつけてくるのは必至?
短期集中シリーズ「消費税を疑え!!」2回目では消費税引き上げをめぐる、思わぬ「外圧」の正体に迫る! 来年10月からの2%消費増税を進める安倍政権に立ちはだかる最大の壁は国内の増税反対勢力ではなく......、アメリカのトランプ大統領だった?
なぜアメリカが日本の消費税に口を挟むのか? その背景を徹底解説する!
■消費増税に反対する「巨大な外圧」の存在
来年10月に8%から10%への引き上げが予定されている消費税。「深刻な財政難のなか、少子高齢化に伴い増え続ける社会保障費の財源を確保するには消費増税しかない」というのが、財務省や政府の一貫した主張だ。
一方、立憲民主党など野党の一部は「日本経済がいまだにデフレ脱却を果たせていない状態で消費税を引き上げれば経済に深刻な悪影響を与えかねない」と、増税に反対の姿勢を見せている。
ところが消費税の引き上げにおいて、こうした国内での議論とは別に日本が無視することのできない「巨大な外圧」があるという。それは消費税という制度そのものに否定的で、消費税を「非関税障壁」と見なすアメリカの存在だ。
「来年以降、『アメリカ・ファースト』(アメリカ第一主義)を掲げるトランプ政権との貿易交渉が本格的にスタートするこのタイミングで、日本が消費税10%引き上げへ向かえば、アメリカの強い反発を招くことは避けられません」
と語るのは、金融コンサルトで『アメリカは日本の消費税を許さない』(文春新書)の著書がある岩本沙弓(さゆみ)氏だ。
「日本やヨーロッパなど、約140の国と地域で採用されている消費税(日本以外では付加価値税と呼ばれる)ですが、実はそこに連邦国家アメリカは含まれていません」
ヘー、これだけ多くの国で採用されているのに、アメリカは国税として採用してないんだ。
「ただ、アメリカには商品の小売り段階でのみ消費者に課税する『小売売上税』という州税があります。しかしこれは、原材料の仕入れから、製造、流通、卸売り、小売りに至るまで、すべての商取引の段階で課税される『消費税』や『付加価値税』とは根本的に異なるものです。
アメリカでも過去何度も消費税導入が議論されたことがありますが、そのたびに退けられてきました。その背景には、消費税や付加価値税を『不合理で不公正な税制』ととらえるアメリカの考え方があります。そのため、この税制に関して、アメリカは一貫して否定的なスタンスを取り続けてきたのです。
もちろん、消費税を採用している国から見れば、アメリカは『少数派』ということになりますが、多くの政策で独自路線を突き進み、公平な市場環境を訴えるトランプ政権が『こちらに歩調を合わせるべきだ』と言いだしても不思議はないのです」(岩本氏)
■輸出企業への還付は不正なリベートか?
なるほど。すでに消費税や付加価値税を導入している日本やヨーロッパが常識だと思っていることが、アメリカにとってそうとは限らないということがよくわかった。
だが、アメリカが消費税導入に否定的だとしても、彼らが他国の税制に「不公正だ」「非関税障壁だ」と不満を訴えているのはなぜなのか?
その最大の理由は、日本も含めた消費税導入国が自国の輸出企業に対して行なっている「輸出還付制度」の存在だ。アメリカはこれを「自由競争の原則を歪(ゆが)める制度」だとして問題視しているという。岩本氏が解説する。
「先ほど説明したように消費税は仕入れから小売りまで、すべての段階で課税されます。そして事業主は基本的に、最終的な売り上げにかかる消費税(購入者から預かった消費税)から、その前の段階の仕入れなどにかかる消費税を差し引いた額を税務署に申告することになります。ただし、インボイス制度未採用(*)の日本で正確に計算ができるのかという問題がまずあります。
仕入れから製造までを国内で行なう企業がその製品を海外に輸出する場合、消費税は実際に消費が発生する輸出相手国の税制に沿って課されることになります。
仕入れの段階でも日本の消費税を払っているので、このままでは輸出相手国と国内とで2度消費税が課されることになる。そうした『二重課税』が起きないよう、輸出製品については仕入れなどにかかる消費税が国から還付されることになっています。これが『輸出還付制度』です」
(*)日本の消費税は、ヨーロッパの付加価値税のように取引に関する個々の請求書、領収書ベースで消費税額を計算するインボイス制度を採用していない。
例えば、日本の自動車メーカーが国内から部品を調達していれば、そのメーカーは国内の下請け企業に「部品代+消費税」を支払っていると見なされ、そのクルマを輸出して海外で販売した場合は、国内で払った消費税分が全額還付されるのだ。これは消費税制度のないアメリカに輸出する場合も例外ではない。
「そのアメリカはこの還付金を、政府が輸出企業に与える『実質的なリベート』だと見なしていて、強い不満を訴えています。消費税制度のある国からアメリカに輸出する企業は消費税免除により『輸出還付金』の形でリベートを受け取るのに対し、アメリカ国内の企業にそうした制度はなく、輸出先の相手国の消費税を課税されている。これがアメリカからすると『不公正だ』という主張です」(岩本氏)
ではアメリカにとって日本の消費税引き上げはどんな意味を持つのだろう?
「もちろん、こうしたアメリカ側の主張については、さまざまな異論もあると思います。しかし、あくまでアメリカ側の立場で見れば、日本の消費税の8%から10%への引き上げは、『日本の輸出企業へのリベートの引き上げ』と『日本向けアメリカ輸出企業への実質的な課税強化』ととらえることになる。当然、アメリカが強く反発するのは避けられないでしょう。
アメリカは日本だけ目の敵にしているわけではありません。欧州の付加価値税や日本の消費税のような間接税については還付制度を認め、直接税では認めないWTO(世界貿易機関)のルール自体を変えるべきだと主張しているのです」(岩本氏)
■自工会が増税支持から懸念表明に転じた理由
実は、そうしたアメリカ側の空気に最も敏感に反応しているのが、日本の自動車メーカーによる業界団体で、トヨタ社長の豊田章男氏が会長を務める「日本自動車工業会」(自工会)だ。
これまで基本的に政府の「消費税引き上げ」という方針を支持してきた自工会が、今年9月20日に発表した「平成31年度税制改正に関する要望書」では増税反対という明確な表現は避けながらも、消費税10%への引き上げについて国内市場縮小への懸念を強く訴えている。
岩本氏は、こうした自工会の消費税に対する姿勢の変化に、彼らの日米関係に対する「シビアな現状認識」が表れているとみている。
「韓国とのFTA(2国間貿易協定)の見直しに続いて、10月にはメキシコとカナダとのNAFTA(北米自由貿易協定)に代わる新たな協定(USMCA)の合意にこぎ着けたトランプ政権が、『次のターゲット』として日本を視野に入れるのは当然でしょう。
日本はこれから、自動車関税25%への引き上げをチラつかせるトランプ政権と、2国間貿易協定の交渉に臨みます。しかし、前述したようにアメリカは日本の消費税に対して、強い不満や不信感を抱いている。
そんな状況で日本が消費税の引き上げを強行すれば、日米交渉のテーブルではアメリカ側が態度をさらに硬化させ、場合によっては自動車関税25%発動という、自工会にとって最悪のシナリオを招きかねません」
なるほど。アメリカはどこまで本気なのか?
「今年9月25日、国連総会出席のため訪米した安倍首相に同行した茂木敏充経済再生担当大臣がUSTR(アメリカ通商代表部)のライトハイザー代表と会談しましたが、このライトハイザー氏は消費税の『輸出還付制度』を一貫して不当なリベートだと訴え続けてきた人物として知られています。
安倍首相の訪米直前のタイミングで、自工会があえて『消費増税への懸念』を表明したのも、アメリカ側に配慮した自工会のメッセージではないかとみています。
また、先ほど述べたUSMCAでは、アメリカへの関税が免除される製品に関して『部品の現地調達率』などの条件が大幅に強化されており、これまでメキシコでの現地生産でNAFTAの恩恵を受けていた日本企業にとって、かなり厳しい内容になっています。
日本の自動車メーカーにとってはトランプ大統領の言う『メキシコ国境の壁』がつくられたも同然で、今後アメリカ市場での拡大があまり期待できないことを考えれば、『消費税引き上げで国内市場まで縮小されてはたまらない』というのが自工会の本音ではないでしょうか」(岩本氏)
もちろん、税制は日本の重要な「内政問題」だ。それに消費税を採用せず、輸出還付制度を不公正なリベートと見なすアメリカの考え方が必ずしも正しいとは限らない。
だが、世界にはアメリカのように消費税に対して否定的な超大国もあるということ。そして、そのアメリカの姿勢がさまざまな形で日米関係に大きな影響を与えかねないという現実があることは理解する必要があるだろう。
何しろ相手は「アメリカがルールだ」と公言してはばからないトランプ政権である。日本の税制をめぐる大切な議論が、日米貿易交渉の「取引材料」に使われる可能性もないとはいえないのだ。
……』
それから7年が経過した。日本の消費税還付制度の実態は変わらず、アメリカの現大統領も「アメリカ・ファースト」を標榜している。このため、7年前にアメリカが主張した「自由競争の原則を歪める制度」という見解は、現在も有効であると考えられる。
したがって、トランプ大統領のいう相互関税の対象には、日本からの輸入車に対する「自動車関税25%」の適用が含まれる可能性がある。今後の展開によっては、日米貿易交渉がさらに緊迫することが予想される。
トランプ大統領の真意は、今後徐々に明らかになっていくだろう。以上(寄稿:近藤雄三)
「図1.輸出企業に対する還付金」
出所:国商工新聞:https://www.zenshoren.or.jp/2023/11/27/post-29301」