堅苦しいことは抜きにして、春の息吹が肩を流れていくこのころに心に移りゆくうたかたをちょっとだけ書きたいと思います。
私が高校を卒業して上京し、しばらくして住み始めた西荻窪の駅近くに古い映画館がありました。18歳の私はなけなしのおこずかいの中からでも映画だけは時たま覗かないと禁断症状が出てきかねないくらい、映画を見るのが好きでした。そこでたまたまやっていたのが鶴田浩二主演の「総長賭博」でした。あの小柄で静かな山下耕作監督の作品です。その一シーン、鶴田の後ろ姿に深く魅了されたのをはっきり覚えています。親分を手にかけたドスを右手にだらっと下げるように持ち、肩は心なしか震えるようでした。白いものでも親分が黒と言えば黒と言わざる得ない博徒の世界です。「義」と「理」の葛藤と言えばそれまでですが、このアンビバレントな心情に私はいかれていました。兄弟の杯を交わした若山富三郎演ずる博徒との心のやり取りは、涙なしには見ることができません出した。
それからすでに50年以上が経過しました。私が知った本・小日向白朗を小説スタイルで活写した馬賊戦記のほぼ終わりの頃のお話です。10代で大陸に渡り、総覧把にまで上り詰めた馬賊の王者です。葛月譚老子のもとで道教をベースとしている武道を習得、その後、昭和の初期には奉天城襲撃を計画したり、天津では阿片ビジネスに手を染めたり、憲兵隊ともギブアンドテイクの密なやり取りを続けながら農民さえも匪賊と断じて討伐(殺戮)を繰り返す関東軍ともタフな交渉を繰り広げてき白朗です。確か、昭和14年のころ、某憲兵幹部に請われて「上海」をどうにかしてほしいと。確か最初は嫌だと断ったのですが、どうしてもと頼まれたようです。蒋介石一派の組織、関東軍の息のかかった組織、それも一つではなく幾つか作って力関係を拮抗させようとしていた政策が行き詰っていたのでしょう。やりたい放題で中国の民を暴行、搾取するほぼ今でいうところの「反社会的集団」と化してしまったようでした。・・・白朗はそこで、「青幇」として動きはじめるのです。この「青幇」については、酒井忠夫氏の「中国幇会史の研究 青幇篇」、一橋大学三谷孝教授による「現代中国秘密結社研究の課題」(一橋大学機関リポジトリ)などに詳しく論じられています。その精神が、「任」と「侠」だと私は思っています。これは、馬賊の精神と重なってきます。この精神を理解しないと、ほぼ絶対に中国を理解することは不可能とも思っています。話は飛びましたが、上海で力をふるっていたいわば戦友のような人物、杜月笙とのやり取りがありました。どうしても上海を出ていかせなければと、ドスで脅しながら『殺す』と言わざるを得ない状況になるのでした。そのときの、阿吽の呼吸で通じていた杜月笙と白朗の心情が、私にはあの映画「総長賭博」のシーンと重なってくるのです。マっ、ちょっと違うとは思いますが。
ちなみに任侠の「任」は人のために尽くすこと、「侠」は人のために命を捨てることです。(文責吉田)
私が高校を卒業して上京し、しばらくして住み始めた西荻窪の駅近くに古い映画館がありました。18歳の私はなけなしのおこずかいの中からでも映画だけは時たま覗かないと禁断症状が出てきかねないくらい、映画を見るのが好きでした。そこでたまたまやっていたのが鶴田浩二主演の「総長賭博」でした。あの小柄で静かな山下耕作監督の作品です。その一シーン、鶴田の後ろ姿に深く魅了されたのをはっきり覚えています。親分を手にかけたドスを右手にだらっと下げるように持ち、肩は心なしか震えるようでした。白いものでも親分が黒と言えば黒と言わざる得ない博徒の世界です。「義」と「理」の葛藤と言えばそれまでですが、このアンビバレントな心情に私はいかれていました。兄弟の杯を交わした若山富三郎演ずる博徒との心のやり取りは、涙なしには見ることができません出した。
それからすでに50年以上が経過しました。私が知った本・小日向白朗を小説スタイルで活写した馬賊戦記のほぼ終わりの頃のお話です。10代で大陸に渡り、総覧把にまで上り詰めた馬賊の王者です。葛月譚老子のもとで道教をベースとしている武道を習得、その後、昭和の初期には奉天城襲撃を計画したり、天津では阿片ビジネスに手を染めたり、憲兵隊ともギブアンドテイクの密なやり取りを続けながら農民さえも匪賊と断じて討伐(殺戮)を繰り返す関東軍ともタフな交渉を繰り広げてき白朗です。確か、昭和14年のころ、某憲兵幹部に請われて「上海」をどうにかしてほしいと。確か最初は嫌だと断ったのですが、どうしてもと頼まれたようです。蒋介石一派の組織、関東軍の息のかかった組織、それも一つではなく幾つか作って力関係を拮抗させようとしていた政策が行き詰っていたのでしょう。やりたい放題で中国の民を暴行、搾取するほぼ今でいうところの「反社会的集団」と化してしまったようでした。・・・白朗はそこで、「青幇」として動きはじめるのです。この「青幇」については、酒井忠夫氏の「中国幇会史の研究 青幇篇」、一橋大学三谷孝教授による「現代中国秘密結社研究の課題」(一橋大学機関リポジトリ)などに詳しく論じられています。その精神が、「任」と「侠」だと私は思っています。これは、馬賊の精神と重なってきます。この精神を理解しないと、ほぼ絶対に中国を理解することは不可能とも思っています。話は飛びましたが、上海で力をふるっていたいわば戦友のような人物、杜月笙とのやり取りがありました。どうしても上海を出ていかせなければと、ドスで脅しながら『殺す』と言わざるを得ない状況になるのでした。そのときの、阿吽の呼吸で通じていた杜月笙と白朗の心情が、私にはあの映画「総長賭博」のシーンと重なってくるのです。マっ、ちょっと違うとは思いますが。
ちなみに任侠の「任」は人のために尽くすこと、「侠」は人のために命を捨てることです。(文責吉田)












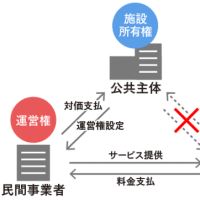
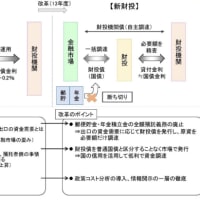

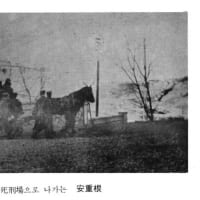






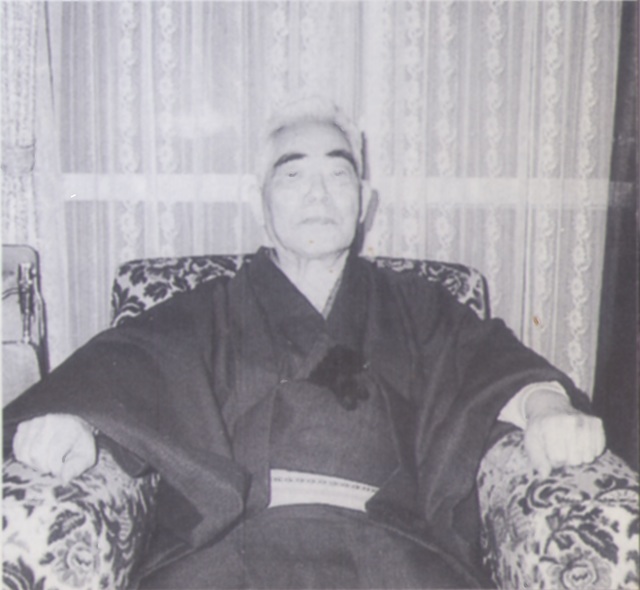





この映画は、三島由紀夫が絶賛したことで、一躍有名になったことでも知られています。