●国家の役割を知らない哀れな日本人
今の日本のかなりまずい状況は、主に公民教育がもたらしてきた。今、多くの日本人は、「国家の役割とはなにか」と聞かれてもまともに答えることができないだろう。
これは、きわめて異常なことである。上記の質問に答えられるかどうかは、歴史教育は関係ない。歴史教育がしっかりしていても、国家に対する認識がこの程度であれば、日本がまともな主権国家として国際社会を生き抜くことは不可能である。
●国家の役割とは←中学生にも読んでほしい。
国家には、決まった範囲の領土(りょうど)があって、その周りに領海(りょうかい)を持ち、それらの上に領空(りょうくう)を持つ。これが国家の領域(りょういき)である。
領域の中にはそこで生活する人々がおり、この人々が国家を運営する主体となる。これが国民(こくみん)である。
国家が、領域や国民を支配する権利を、統治権(とうちけん)といい、これが対外的に独立し、どの国の干渉も受けないようになると、国家主権(こっかしゅけん)となり、主権を持つ主権国家(独立国)となる。
この主権、領域、国民が国家の三要素(こっかのさんようそ)である。領域や国民がなければ、国家が成立しないのは分かるだろう。では、主権はどうだろうか。
主権を持たない国家は、どこかの国に属するか、他国の影響を強く受ける傀儡国家(かいらいこっか)になるしか、選択肢がない。このような場合、当然、現地の国民の意思や利益が尊重されるわけがなく、現代の国家は、この主権を持ち、かつ独立し、主権と独立を守ることが重要である。
このような現代の国家は、対外的には軍事力を使用した防衛(ぼうえい)により、その主権と独立を保ち、対内的には公共の秩序を維持し、国民の安全を守るとともに、インフラの整備や教育など公共事業への投資(こうきょうじぎょうへのとうし)により、国民の生活の向上を図り、国民の自由と権利(こくみんのじゆうとけんり)を守ることが重要な役割だと考えられている。
これらの役割を担うのが、国会や、内閣、裁判所などの国の機関である。例えば、防衛省や自衛隊は、このうちの防衛を担っている。警察は国内の秩序の維持を担っている。裁判所は、国内の秩序の維持と国民の自由と権利を守る役割を担っている。
国家は、これらの役割を限られた時間で果たすために、できるかぎり合意に努める。これが政治である。ただし、限られた時間で対立を解消しきれず、合意に達しない場合は、権力による強制も避けられない。この権力が、政治権力である。
政治権力は、一見すると、国家による一方的な強制力のようにも見えるが、実は国民がその政治権力を承認しているから成立しているのである。国民の承認がない政治権力は、歴史上いくつか存在してきたが、例外なく、その国家は消滅している。国民の承認がなければ、政治権力を維持することは不可能なのである。
このような国家の役割や政治権力の必要性に対する理解がなければ、なぜ国家があるのか、なぜ政治があるのか、なぜ政治権力があるのか、なぜ民主主義があるのかということが分からない。
民主主義は、政治権力の調整のために生まれた思想であるが、国家がどのような役割を持つものか知らなければ、そもそも政治権力や国家自体がなければ良いという結論に達するであろう。
ゆえに、公民教科書は、政治編の冒頭部で国家論について記し、最低でも国家の役割と政治権力の必要性ぐらいは記す必要がある。
●国家の役割を記さない公民教科書
しかし、中学校の普通の公民教科書では、国際社会編で、国家の三要素(主権、領域、国民)やそれらに関する原則が展開されるだけであり、その中でも「国益」という視点はない。そして、決して国内政治編で国家論が展開されることはない。おまけに、領土不可侵の原則さえも書かない教科書が一定数存在する始末である。
占領期は、国家に関する教育が否定され、公民教育では国家論も、国家の三要素も全く展開されなかった。「ナショナリズムや国家主義の宣伝」を禁じた検閲基準や、教科書検閲基準の影響と見られる。
その後、占領解除と同時に、徐々に公民教育にも国家論が返り咲き、国家の三要素などが書かれるようになり、国内政治編で国家の役割を書く教科書も増えた。しかし、そのような流れの中でも、防衛が国家の役割であると書く教科書はなかった。
昭和47年以降に入ると、再び国家の役割を記す教科書が減っていく。一方、国際社会編ではかろうじて対外主権国家の説明が残った。小山常実氏は、この一連の流れを「国際社会編では対外主権国家の教育を行うけれども、国内編では対内的な国家の目的・役割を教えないという風に、検閲指針との間で折り合いが付けられるようになったのである」と評価している。
それでも平成18年度と平成24年度の教科書では清水書院が「国は、対外的には独立を保ち、国内では秩序を維持し、国民の安全を守るとともに、経済、福祉、教育などさまざまの分野で国民が健康で快適な生活をおくることができるように支援することが重要な役割と考えられている。」と記していた。
個人的には、清水書院のこの記述は「防衛」という視点がないことを除ければ、かなりしっくり来るものである。
平成24年度版以降は、自由社も、国家の役割についてかなり詳しく記すようになったし、全社で唯一国家の成立について記している。すなわち、国家とは、農業の発達に伴う食糧生産(しょくりょうせいさん)の増大で食料収奪(しょくりょうしゅうだつ)からの防衛の必要性が生まれて、さらに農業仕事の共同作業の必要性から、共同体(きょうどうたい)がつくられて成立したものであるということを記している。
育鵬社も、平成24年度版では正面からは記さないものの、多少なりとも国家の役割について触れていた。
平成28年度版以降は、清水書院が国家の役割を記さなくなったし、現行版ではそもそも中学公民教科書事業から撤退した。育鵬社も、国内政治編で国家の役割について記していたものを国際社会編に移動し、内容もより簡素なものとした。もはや、国家論とは言えないものとなった。
自由社は、現行版でも、国家の成立と役割について全社で唯一正面から記している。
●領土不可侵の原則すらまともに記さない公民教科書
このように、国内政治編の国家論は絶望的な状況であるが、国際社会編で国家の三要素などがまともに記述されているかというと、そういうわけでもない。
先ほども言った通り、領土不可侵の原則さえも書かない東京書籍と日本文教出版があるし、教育出版は「領土不可侵の原則」を明言しない。単に「領海侵犯あるいは領空侵犯になります」と記すのみである。
帝国書院も、「国家の支配する領域は,領土,領海,領空の三つから構成され,不法に立ち入ることは認められていません(領土不可侵の原則)。」とはするものの、国家主権の侵害であるとは明記しない。
さらに平成28年度版までは、三要素説さえ書かない教科書が存在した。現行版では、いわゆる「つくる会効果」で三要素説が全社で展開されている。
●領土問題は充実するも...拉致問題は壊滅的
外交問題・主権問題に関する記述に目を向けると、領土問題については、「つくる会効果」と安倍政権による学習指導要領の改訂の影響により、記述が充実してきているものの、拉致問題については、本文で書かない教科書が一定数存在する有様である。
ひとまず、領土不可侵の原則の明記と拉致問題の記述充実からはじめて、さらに国内政治編で国家論を展開し、国家の役割ぐらいは記すようにする必要がある。
この記事を読んで問題意識を感じた皆様には、ぜひ教科書会社に対し、教科書記述を充実させるよう意見を送って欲しい。下にもリンクを貼っておくので、ぜひ意見を送ってもらいたい。
【東京書籍】 お問い合わせ 内容についてのご質問・ご意見箱:個人情報の取扱いについて
※東京書籍と日本文教出版は、全社で唯一領土不可侵の原則さえ記さない。拉致問題については、一応本文で記述されている(ただしかなり不十分)。一方、東京書籍は拉致問題を「主権問題」であると明言せず(写真説明で「人権問題」とするだけ)、日本文教出版も写真説明で「主権問題」「人権問題」とするも単語だけである。
※教育出版は、「領土不可侵の原則」と明記しないし、それが「国家主権の侵害」であると明言しない。拉致問題については、本文では全く触れていない。一方、コラムではそれなり触れているが、「主権問題」とせず、「人権問題」とさえしない。なお、利用規約に同意すればお問い合わせできる。
教科書の内容や指導書・Webサポート・QRコンテンツについて|株式会社帝国書院
※帝国書院は、領土不可侵の原則について「国家主権の侵害」と明言しない。拉致問題については、本文では全く触れていない。一方、写真説明では、「主権問題」「人権問題」とはしている。
※上記の出版社と同様、育鵬社は、国内政治編で国家論を展開しない。一方、拉致問題については一応本文で記述されている(ただし不十分)。また、拉致問題についてコラムもあり、そこでは「主権問題」「人権問題」であると明言している(ただし授業で全く使われないのが現実)。
※自由社のホームページにお問い合わせホームが見つからなかった。自由社は、全社で唯一政治編の冒頭部で国家論として国家の成立と役割に触れている。領土不可侵の原則も明言する。一方、拉致問題については本文ではほとんど記述せず、授業で全く使われないのが現実のコラムで記しているのみである。ただし、コラム自体は育鵬社より詳しいし、コラムの中では、「主権問題」「人権問題」と明言しており、さらに、全社で唯一「安全保障問題」的な扱いをしている(明言はしない)。













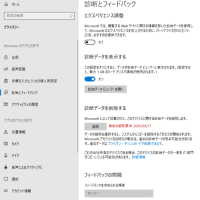


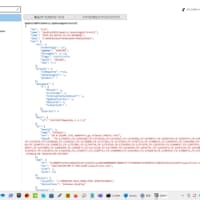


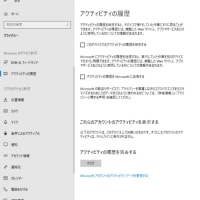
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます