
クロヒカゲ。
ヒカゲチョウを暗色にしたようなチョウ。

前翅の裏面に、上から3つ目の目玉模様が、かすかに見られる個体。
冒頭の個体のように、この3つ目は消失傾向にあります。
ヒカゲチョウとの違いは、
①全体に黒味がかること
②クロヒカゲの方がより高い標高に分布し、同じ林内でもより暗い場所にいる
③後翅の裏面の暗色のラインが、目玉模様の列に向かって、深く鋭く湾入すること
ただし、③は個体差があるようで。

冒頭の個体では、それほど鋭くはありません。
①~③を総合的に判断した方が良さそうです。

比較のため、ヒカゲチョウ。
図鑑では「直線的」と書かれますが、あくまでクロヒカゲとの比較で言えることで、クロヒカゲが富士山なら、緩やかな丘、と言ったところ。

こちらは、「鋭く」はないですが、結構、深く湾入する個体。
こうなるとやはり、①~③の総合的な比較が必要でしょう。

クロヒカゲ
分類:チョウ目タテハチョウ科ジャノメチョウ亜科
前翅の長さ:約23~33mm
翅を広げた長さ:45~55mm
分布:北海道、本州、四国、九州
丘陵~山地
成虫の見られる時期:5~10月(年1~4化)
2~4齢幼虫で冬越し(非休眠)
エサ:成虫・・・樹液・腐果・獣糞(花に来ることもある)
幼虫・・・メダケ、ゴキダケ、ネザサ、クマザサ、チシマザサなど
その他:ササが下草の少し薄暗い雑木林などの周辺で見られる。
ヒカゲチョウを暗色にしたようなチョウ。
前翅裏面の翅頂付近と後翅裏面の外縁に沿って眼状紋がある。
前翅長の紋は小さく、一番下の眼状紋は消失傾向。
後翅裏面の黒色線は、眼状紋に沿うように鋭く湾入する。
(ヒカゲチョウでは湾入が緩やか)
♂は地色が黒褐色、♀は茶褐色。
♂は前翅裏面の後縁に黒色の毛束があり、後翅表の前縁下に性斑を持つ。
♂は午後、林内や林縁で縄張りを作る。
地上で吸水もする。
クロヒカゲは樹液における順位が低く、こうした蝶では訪花性も見られる傾向があるという。
♀は地上近くの食草の葉表に基部に頭を向けて止まり、斜めに向きを変えてから、腹端を葉裏に回して、一卵ずつ産卵する。
幼虫は秋から夏に見られる。
終齢まで葉裏に糸を吐いて台座を作り、葉表には出ない。
体色は3齢までは緑色、4齢以降は褐色型も見られる。
褐色型は茎に止まる習性が強い。
緑色の幼虫は越冬中も褐色にならない。
終齢幼虫の体長は約35mm。
越冬幼虫は、少しずつ摂食しながら越冬する。
主に食草の葉裏で蛹化する。
蛹は緑色型と褐色型があるが、緑色型はまれ。

ヒカゲチョウ
分類:チョウ目タテハチョウ科ジャノメチョウ亜科
前翅の長さ:約25~34mm
翅を広げた長さ:50~60mm
分布:本州、四国、九州(東北地方、九州では分布が限られる)
平地~標高400m位まで
成虫の見られる時期:6~10月(年1~3化、茨城県では年2化)
3~4齢幼虫で冬越し
エサ:成虫・・・樹液、獣糞、動物の死体、腐果で吸汁(ノリウツギに来た例がある)
幼虫・・・ゴキダケ、メダケ、マダケ、クマザサ、ナンブネマガリ、イワテザサ、アズマネザサなど
その他:平地の雑木林周辺などで見られる。
山地では出現が遅れる。
夕方~日没頃、最も活発。
地色は黄褐色で、♀は色彩が淡い。
♂は後翅表に黒褐色の毛束がある。
前翅裏面の翅頂付近と後翅裏面の外縁に沿って眼状紋がある。
前翅長の眼状紋は小さく、消失傾向。
後翅裏面の黒色線の湾入は緩やか。
(クロヒカゲでは眼状紋列に沿うように、鋭く湾入する。)
食草の葉裏に産卵する。
幼虫は秋~夏に見られる。
主として葉裏に糸を吐き台座を作って生活するが、時に茎に止まる。
静止時、頭部を強く前屈する。
地色は緑色で、無紋型と、背中に黄色で囲まれた褐色の点が並ぶ型とがある。
越冬中も褐色にならない。
終齢幼虫の体長は約37~40mm。
蛹は緑色型のみで、葉裏に垂下する(垂蛹)。
参考:茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)
ポケット図鑑日本の昆虫1400①(文一総合出版)
検索入門チョウ①(保育社)
原色日本昆虫生態図鑑Ⅲチョウ編(保育社)
ヒカゲチョウを暗色にしたようなチョウ。

前翅の裏面に、上から3つ目の目玉模様が、かすかに見られる個体。
冒頭の個体のように、この3つ目は消失傾向にあります。
ヒカゲチョウとの違いは、
①全体に黒味がかること
②クロヒカゲの方がより高い標高に分布し、同じ林内でもより暗い場所にいる
③後翅の裏面の暗色のラインが、目玉模様の列に向かって、深く鋭く湾入すること
ただし、③は個体差があるようで。

冒頭の個体では、それほど鋭くはありません。
①~③を総合的に判断した方が良さそうです。

比較のため、ヒカゲチョウ。
図鑑では「直線的」と書かれますが、あくまでクロヒカゲとの比較で言えることで、クロヒカゲが富士山なら、緩やかな丘、と言ったところ。

こちらは、「鋭く」はないですが、結構、深く湾入する個体。
こうなるとやはり、①~③の総合的な比較が必要でしょう。

クロヒカゲ
分類:チョウ目タテハチョウ科ジャノメチョウ亜科
前翅の長さ:約23~33mm
翅を広げた長さ:45~55mm
分布:北海道、本州、四国、九州
丘陵~山地
成虫の見られる時期:5~10月(年1~4化)
2~4齢幼虫で冬越し(非休眠)
エサ:成虫・・・樹液・腐果・獣糞(花に来ることもある)
幼虫・・・メダケ、ゴキダケ、ネザサ、クマザサ、チシマザサなど
その他:ササが下草の少し薄暗い雑木林などの周辺で見られる。
ヒカゲチョウを暗色にしたようなチョウ。
前翅裏面の翅頂付近と後翅裏面の外縁に沿って眼状紋がある。
前翅長の紋は小さく、一番下の眼状紋は消失傾向。
後翅裏面の黒色線は、眼状紋に沿うように鋭く湾入する。
(ヒカゲチョウでは湾入が緩やか)
♂は地色が黒褐色、♀は茶褐色。
♂は前翅裏面の後縁に黒色の毛束があり、後翅表の前縁下に性斑を持つ。
♂は午後、林内や林縁で縄張りを作る。
地上で吸水もする。
クロヒカゲは樹液における順位が低く、こうした蝶では訪花性も見られる傾向があるという。
♀は地上近くの食草の葉表に基部に頭を向けて止まり、斜めに向きを変えてから、腹端を葉裏に回して、一卵ずつ産卵する。
幼虫は秋から夏に見られる。
終齢まで葉裏に糸を吐いて台座を作り、葉表には出ない。
体色は3齢までは緑色、4齢以降は褐色型も見られる。
褐色型は茎に止まる習性が強い。
緑色の幼虫は越冬中も褐色にならない。
終齢幼虫の体長は約35mm。
越冬幼虫は、少しずつ摂食しながら越冬する。
主に食草の葉裏で蛹化する。
蛹は緑色型と褐色型があるが、緑色型はまれ。

ヒカゲチョウ
分類:チョウ目タテハチョウ科ジャノメチョウ亜科
前翅の長さ:約25~34mm
翅を広げた長さ:50~60mm
分布:本州、四国、九州(東北地方、九州では分布が限られる)
平地~標高400m位まで
成虫の見られる時期:6~10月(年1~3化、茨城県では年2化)
3~4齢幼虫で冬越し
エサ:成虫・・・樹液、獣糞、動物の死体、腐果で吸汁(ノリウツギに来た例がある)
幼虫・・・ゴキダケ、メダケ、マダケ、クマザサ、ナンブネマガリ、イワテザサ、アズマネザサなど
その他:平地の雑木林周辺などで見られる。
山地では出現が遅れる。
夕方~日没頃、最も活発。
地色は黄褐色で、♀は色彩が淡い。
♂は後翅表に黒褐色の毛束がある。
前翅裏面の翅頂付近と後翅裏面の外縁に沿って眼状紋がある。
前翅長の眼状紋は小さく、消失傾向。
後翅裏面の黒色線の湾入は緩やか。
(クロヒカゲでは眼状紋列に沿うように、鋭く湾入する。)
食草の葉裏に産卵する。
幼虫は秋~夏に見られる。
主として葉裏に糸を吐き台座を作って生活するが、時に茎に止まる。
静止時、頭部を強く前屈する。
地色は緑色で、無紋型と、背中に黄色で囲まれた褐色の点が並ぶ型とがある。
越冬中も褐色にならない。
終齢幼虫の体長は約37~40mm。
蛹は緑色型のみで、葉裏に垂下する(垂蛹)。
参考:茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)
ポケット図鑑日本の昆虫1400①(文一総合出版)
検索入門チョウ①(保育社)
原色日本昆虫生態図鑑Ⅲチョウ編(保育社)










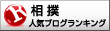


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます