
酔って笑う これぞ狂言
狂言発祥の地 向日神社「鎮守の森」で開催された、昔ながらの
「向日明神篝狂言」を観に行ってきました。
神社の境内の中で、かっぽ酒をふるまわれながら、狂言を楽しむという、なんとも粋狂なイベントがあるというので、2007年5月26日、京都府向日市にある向日神社「鎮守の森」に行ってきました。

狂言発祥の地
今年で2回目を迎える「向日明神篝狂言」は、狂言発祥の地といわれる鎮守の森を整備し、住民自治の再生と、向日市の誇りとなるような行事にしようということから、狂言師 茂山千乃丞さん(重要無形文化財総合指定保持者 京都能楽会相談役・狂言協議会幹事)の協力を仰ぎ、去年の8月23日、400人満員の観客を集めて催されました。
室町時代から
狂言はもともと、室町時代、農民のバイタリティを糧として生まれた芸能で、社寺の境内などで酒を飲み、やんやと声をかける観客に合わせて演じるアドリブの多いものだったそうです。
実際に観るのは初めてで、よくわからないんじゃないかと心配していましたが、当日は始まる前に狂言の「笑い方」など、初心者にも分かりやすく、おもしろおかしく解説してくださったので、一緒に連れてきた小学生の息子たちも興味津々。

飲んで笑って楽しんで
「狂言は、何も難しいものではありません。好き放題笑ってください。今日はおおいに飲んで、楽しんでください。」
ごあいさつのお言葉どおり、かっぽ酒をいただきながら、かがり火と月明かりの下で繰り広げられる非日常の世界に、観客一同、気持ちよく酔いしれていました。

舞台真横、ござ席の一番前を陣取って、かぶりつき。
「宇治田楽」に「祇園獅子舞」
日本一の狂言会を目指して、今年は狂言の他に、「宇治田楽」や「八坂神社の祇園獅子舞」、「煎茶方円流」のお茶席も設けられるなど、いろいろ趣向が凝らされていました。

おいしいお茶にほっこり
田楽の踊りを真似ていた息子
気取りない手づくりの良さ
前売り券は完売御礼。東京や九州など、わざわざ県外から観にこられた方や、残り少ない当日券を求めて早朝から神社に訪れる方もいるほどの盛況ぶり。80名のボランティアスタッフによって実施された、手づくりの、気取りのない昔ながらの狂言会は、友達・家族・親族一同、おばあちゃんから子供まで、みなで楽しませていただきました。

準備から後片付けまで全てボランティアスタッフの方たちの協力で。
素晴らしい日本の芸能と、住民自治の再生から起こった「向日明神篝狂言」が、向日市の初夏の風物詩となり、この先もずっと毎年行われることを、心から願っています。

感動を絵と文でお届けする イラストライター こゆり
狂言発祥の地 向日神社「鎮守の森」で開催された、昔ながらの
「向日明神篝狂言」を観に行ってきました。
神社の境内の中で、かっぽ酒をふるまわれながら、狂言を楽しむという、なんとも粋狂なイベントがあるというので、2007年5月26日、京都府向日市にある向日神社「鎮守の森」に行ってきました。

狂言発祥の地
今年で2回目を迎える「向日明神篝狂言」は、狂言発祥の地といわれる鎮守の森を整備し、住民自治の再生と、向日市の誇りとなるような行事にしようということから、狂言師 茂山千乃丞さん(重要無形文化財総合指定保持者 京都能楽会相談役・狂言協議会幹事)の協力を仰ぎ、去年の8月23日、400人満員の観客を集めて催されました。
室町時代から
狂言はもともと、室町時代、農民のバイタリティを糧として生まれた芸能で、社寺の境内などで酒を飲み、やんやと声をかける観客に合わせて演じるアドリブの多いものだったそうです。
実際に観るのは初めてで、よくわからないんじゃないかと心配していましたが、当日は始まる前に狂言の「笑い方」など、初心者にも分かりやすく、おもしろおかしく解説してくださったので、一緒に連れてきた小学生の息子たちも興味津々。

飲んで笑って楽しんで
「狂言は、何も難しいものではありません。好き放題笑ってください。今日はおおいに飲んで、楽しんでください。」
ごあいさつのお言葉どおり、かっぽ酒をいただきながら、かがり火と月明かりの下で繰り広げられる非日常の世界に、観客一同、気持ちよく酔いしれていました。

舞台真横、ござ席の一番前を陣取って、かぶりつき。
「宇治田楽」に「祇園獅子舞」
日本一の狂言会を目指して、今年は狂言の他に、「宇治田楽」や「八坂神社の祇園獅子舞」、「煎茶方円流」のお茶席も設けられるなど、いろいろ趣向が凝らされていました。

おいしいお茶にほっこり
田楽の踊りを真似ていた息子
気取りない手づくりの良さ
前売り券は完売御礼。東京や九州など、わざわざ県外から観にこられた方や、残り少ない当日券を求めて早朝から神社に訪れる方もいるほどの盛況ぶり。80名のボランティアスタッフによって実施された、手づくりの、気取りのない昔ながらの狂言会は、友達・家族・親族一同、おばあちゃんから子供まで、みなで楽しませていただきました。

準備から後片付けまで全てボランティアスタッフの方たちの協力で。
素晴らしい日本の芸能と、住民自治の再生から起こった「向日明神篝狂言」が、向日市の初夏の風物詩となり、この先もずっと毎年行われることを、心から願っています。

感動を絵と文でお届けする イラストライター こゆり















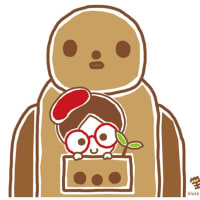




一度行ってみたいわ。
向日市行く途中、阪急長岡天神で普通に乗り換え
なつかし~ ん年前のこと(^ー^)
向日神社も本当にきれいで素敵なところでした。
子供が笑えるなんてスゴイ!
ウチの住んでいる地域の神社も能舞台があって、毎年、ウチの小学校6年の生徒が狂言の「ぶず」(字が解らなくてメンゴ!)を舞います。手作りのハカマとか着てやるみたい。
ウチの子が舞うのもあと2年後。密かに楽しみにしてるねん。
私も観にいきたいわ~
「附子(ぶず)」
気になったので調べてみました。
簡単なあらすじは、「附子という猛毒が入っている桶には近づくな」と主人に言われて留守番する使用人が、辛抱溜まらなくてひとなめすると、毒ではなくて砂糖だった。おいしくて全部食べてしまった二人は、主人に言い訳するために、大事な掛け軸をわざと破って、「死んでお詫びしようと、「附子(ぶず)」を食べたがまだ死ねません。」と言う、嘘をうそでかえすとんち話みたいなもののようです。
昔話として、聞いたことあるような気がします。
ちなみに「附子(ぶず)」はトリカブトの根を乾かして精製する猛毒のことだそうです。
一休さんのとんち話に似たようなのがあったな~。
ありがとう、調べてくれて。
っていうか、自分で調べろ~ってか!