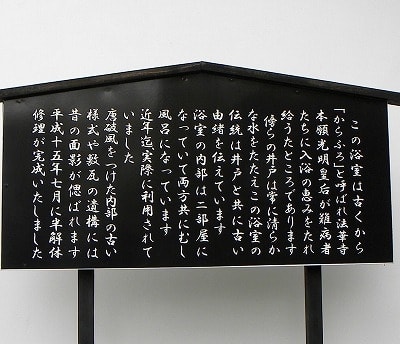2010年5月15日(土)晴
よく晴れましたが、乾燥しているのでしょうか、じっと座っていると寒い感じがします。
奈良へ行ったのは1月以上前ですが、まだ引きずって書いています。
今回の奈良行きは「平城宮を見たい」と、「これから10年間、大修理に入ってしまう薬師寺の塔の写真を境内ではなく勝間田池(大池)からの遠望を撮りたい」でした。そのほかの予定なしで、あとは成り行き次第で出発しました。
往路の新幹線でタヌキが「吉野へ行こう」タヌキは何回か行っているようですが、桜の季節は経験がないようです。コッコーは「そう、いいわよ、、、」 本当のところそれほど乗り気ではありませんでした。「高野山ならNOだけど、吉野なら電車を下りた後、それほど大変ではないからいいわ」桜の季節の高野山の交通渋滞は2度と経験したくなかったので、、、コッコーにとって吉野は数年前に大学時代のサークルの連中と桜の季節に訪問しているので、、、、。2泊3日の真ん中の日に吉野へ行くことにしました。しかし、7日の明け方まで雨だったので、急遽吉野は8日にしました。
2010年4月8日 吉野山その一
ホテルの最寄の駅・近鉄新大宮から吉野は結構遠かったです。電車の本数も少なかったですね。乗り換えの樫原神宮前からは東京のラッシュ並みの超満員でした。
タヌキ「西行庵まで行こう」というので、バスで中千本までのぼり、そこから奥千本行きのバス停まで少し上って、

ピストン輸送のマイクロバスで奥千本へ上りました。

バスを待つ行列です。5~6回待ちでした
吉野山は下から下千本、竹林院辺りの中千本、そして一番上の西行庵辺りを奥千本とよびます。
2004年の桜の季節に吉野へ来たコッコーは雨模様だったので下千本の上に当たる蔵王堂まで行きました。その時は吉野へ行った気分でしたが、蔵王堂は吉野のほんの入口だったようです。
奥千本のバス停を降りると西行庵までの登りは足です。奥千本のバス停から少し上って所に義経の隠塔がありました。


途中の道標で右か左か、どちらも行き着くところは西行庵でした。右の道をとったのですが、これ、失敗でした。ちょっとばかり高所恐怖症のコッコーにとっては必死の思いの連続で西行庵へたどり着きました。




西行庵あたりは山桜のようですね。チラホラでしたが、咲いていました。
正午をとっくに周っていましたが、食べるところはどこにもありません
お弁当を持ってきた人たちは正解だわ。
次回来るなら、お弁当かついで来ましょ。
西行がこの地で詠んだ歌
吉野山こずゑの花を見し日より心は身にもそはずなりにき
吉野山こぞのしをりの道かへてまだ見ぬかたの花をたづねむ
吉野山花のさかりは限りなし青葉の奥もなおほさかりにて
苔清水

とくとくと落つる岩間の苔清水汲みほすまでもなきすみかかな西行
つゆとく試み浮世すすがばや芭蕉
中千本の竹林院付近までマイクロバスで下りました。
竹林院のみごとな庭園




ちょっと一休み 竹林院の中の茶店

コッコーは抹茶と桜餅

タヌキは甘酒
テクテク歩いて下りました。途中の茶屋でやっと昼食
吉野山ならではという写真を並べます。









江戸時代前半、元禄のころ芭蕉は西行の歌心を慕って吉野山を訪れましたが、美しい桜に圧倒されて句はできなかったようです。しかし、弟子の宝井其角は
明星や さくら定めぬ 山かづら
芭蕉はこの幽玄な句をよんだ其角が羨ましい、と、其角に手紙を書いたそうです。
この手紙をもらった其角はそれほどのできばえとは思っていなかったようですが、この句を「満山の花をよめている」と確信したようです。
さて、この「明星や さくら定めぬ 山かづら」の意味は
明け方、其角が外へ出てみると
吉野のさくらさくらと人は言うけど、さくらなんか見えないじゃないか、
定めぬの「ぬ」を否定で読むとこうなりますが、これを表の意味とし、
裏の意味として、「ぬ」を連体形とすると、「雲のむこうに満山さくらがある」と読めます。
たった17文字で2通りの意味を含む面白みのある句のようですね。
続く
よく晴れましたが、乾燥しているのでしょうか、じっと座っていると寒い感じがします。
奈良へ行ったのは1月以上前ですが、まだ引きずって書いています。
今回の奈良行きは「平城宮を見たい」と、「これから10年間、大修理に入ってしまう薬師寺の塔の写真を境内ではなく勝間田池(大池)からの遠望を撮りたい」でした。そのほかの予定なしで、あとは成り行き次第で出発しました。
往路の新幹線でタヌキが「吉野へ行こう」タヌキは何回か行っているようですが、桜の季節は経験がないようです。コッコーは「そう、いいわよ、、、」 本当のところそれほど乗り気ではありませんでした。「高野山ならNOだけど、吉野なら電車を下りた後、それほど大変ではないからいいわ」桜の季節の高野山の交通渋滞は2度と経験したくなかったので、、、コッコーにとって吉野は数年前に大学時代のサークルの連中と桜の季節に訪問しているので、、、、。2泊3日の真ん中の日に吉野へ行くことにしました。しかし、7日の明け方まで雨だったので、急遽吉野は8日にしました。
2010年4月8日 吉野山その一
ホテルの最寄の駅・近鉄新大宮から吉野は結構遠かったです。電車の本数も少なかったですね。乗り換えの樫原神宮前からは東京のラッシュ並みの超満員でした。
タヌキ「西行庵まで行こう」というので、バスで中千本までのぼり、そこから奥千本行きのバス停まで少し上って、

ピストン輸送のマイクロバスで奥千本へ上りました。

バスを待つ行列です。5~6回待ちでした

吉野山は下から下千本、竹林院辺りの中千本、そして一番上の西行庵辺りを奥千本とよびます。
2004年の桜の季節に吉野へ来たコッコーは雨模様だったので下千本の上に当たる蔵王堂まで行きました。その時は吉野へ行った気分でしたが、蔵王堂は吉野のほんの入口だったようです。
奥千本のバス停を降りると西行庵までの登りは足です。奥千本のバス停から少し上って所に義経の隠塔がありました。


途中の道標で右か左か、どちらも行き着くところは西行庵でした。右の道をとったのですが、これ、失敗でした。ちょっとばかり高所恐怖症のコッコーにとっては必死の思いの連続で西行庵へたどり着きました。




西行庵あたりは山桜のようですね。チラホラでしたが、咲いていました。
正午をとっくに周っていましたが、食べるところはどこにもありません

お弁当を持ってきた人たちは正解だわ。
次回来るなら、お弁当かついで来ましょ。
西行がこの地で詠んだ歌
吉野山こずゑの花を見し日より心は身にもそはずなりにき
吉野山こぞのしをりの道かへてまだ見ぬかたの花をたづねむ
吉野山花のさかりは限りなし青葉の奥もなおほさかりにて
苔清水

とくとくと落つる岩間の苔清水汲みほすまでもなきすみかかな西行
つゆとく試み浮世すすがばや芭蕉
中千本の竹林院付近までマイクロバスで下りました。
竹林院のみごとな庭園




ちょっと一休み 竹林院の中の茶店

コッコーは抹茶と桜餅

タヌキは甘酒
テクテク歩いて下りました。途中の茶屋でやっと昼食

吉野山ならではという写真を並べます。









江戸時代前半、元禄のころ芭蕉は西行の歌心を慕って吉野山を訪れましたが、美しい桜に圧倒されて句はできなかったようです。しかし、弟子の宝井其角は
明星や さくら定めぬ 山かづら
芭蕉はこの幽玄な句をよんだ其角が羨ましい、と、其角に手紙を書いたそうです。
この手紙をもらった其角はそれほどのできばえとは思っていなかったようですが、この句を「満山の花をよめている」と確信したようです。
さて、この「明星や さくら定めぬ 山かづら」の意味は
明け方、其角が外へ出てみると
吉野のさくらさくらと人は言うけど、さくらなんか見えないじゃないか、
定めぬの「ぬ」を否定で読むとこうなりますが、これを表の意味とし、
裏の意味として、「ぬ」を連体形とすると、「雲のむこうに満山さくらがある」と読めます。
たった17文字で2通りの意味を含む面白みのある句のようですね。
続く

































 懐かしいので寒さもなんのそののコッコーですが、お付き合いのタヌキはあまりの寒さに
懐かしいので寒さもなんのそののコッコーですが、お付き合いのタヌキはあまりの寒さに




 カレーを食べて、西ノ京を目指しました。
カレーを食べて、西ノ京を目指しました。