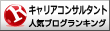卒業後に働く予定の高校生の就職支援の仕事に、田舎の高校に行ってきた。対象は3年生の就職組で、9月中旬の選考開始に向けて様々な準備の仕方やアドバイスを伝える。講義あり、グループワークあり、面接のロールプレイありの盛りだくさんの内容だ。就職を目指す高校生の不安を和らげ、前向きな気持ちにさせ、就職した後も仕事を続けて行く心構えを伝えることも大きな目的となっている。
今日の高校は、いわゆる中堅クラスの県立高校。進学組も多く、全国レベルのスポーツ競技もある学校だ。参加した就職組の生徒たちは、まじめで素直だけど、ややおとなしい生徒が多かった。就職先を迷っている生徒もいるし、この授業への参加に消極的な生徒もいた。
キャリアコンサルタントという仕事柄、時々、このような学生対象の仕事の依頼を受けることもある。学生と言っても、未成年だ。正直なところ、普段の仕事では中高年以上を対象にすることが多いので、接し方に戸惑うこともある。こんな時、自分としては念頭に置いていることがある。「一生懸命働く大人、楽しそうに働く大人、わかろうとする大人として講義やワークを進めよう。」ということだ。
そのように接し進めていると、最初不安そうな顔や硬い表情だった生徒も、だんだんと前向きに参加するようになる。また、グループワークなどではお互いに助け合う様子も見えてきたりする。授業開始前の挨拶の声も大きくなってくる。
面接の練習で、「私の長所はいつも笑顔でいることです!」と屈託のない笑顔で言われたり、「僕は3年間部活でがんばってみんなをまとめてきました!」と目を輝かせて言われたりすると、こちらも眩しくなってくる。自己PRや志望動機をしっかり作ることも大切だが、おそらく採用担当者は眩しいくらいに明るい将来を感じさせてくれる、素直な生徒を採用したいと思うだろう。
今日の高校は、いわゆる中堅クラスの県立高校。進学組も多く、全国レベルのスポーツ競技もある学校だ。参加した就職組の生徒たちは、まじめで素直だけど、ややおとなしい生徒が多かった。就職先を迷っている生徒もいるし、この授業への参加に消極的な生徒もいた。
キャリアコンサルタントという仕事柄、時々、このような学生対象の仕事の依頼を受けることもある。学生と言っても、未成年だ。正直なところ、普段の仕事では中高年以上を対象にすることが多いので、接し方に戸惑うこともある。こんな時、自分としては念頭に置いていることがある。「一生懸命働く大人、楽しそうに働く大人、わかろうとする大人として講義やワークを進めよう。」ということだ。
そのように接し進めていると、最初不安そうな顔や硬い表情だった生徒も、だんだんと前向きに参加するようになる。また、グループワークなどではお互いに助け合う様子も見えてきたりする。授業開始前の挨拶の声も大きくなってくる。
面接の練習で、「私の長所はいつも笑顔でいることです!」と屈託のない笑顔で言われたり、「僕は3年間部活でがんばってみんなをまとめてきました!」と目を輝かせて言われたりすると、こちらも眩しくなってくる。自己PRや志望動機をしっかり作ることも大切だが、おそらく採用担当者は眩しいくらいに明るい将来を感じさせてくれる、素直な生徒を採用したいと思うだろう。