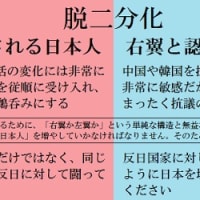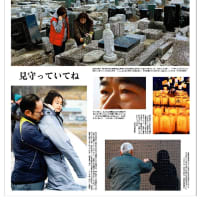▼凶事を嘘に「鷽」作り大詰め (2015.1.1 写真)

あらゆる傷の中で、
心の傷ほどいやし難いものはない。
あらゆる悪意の中で、
女の悪意ほど耐え難いものはない。
シラ書〔集会の書〕/ 25章 13節
(旧約聖書 新共同訳)
すべての宗教は、永遠なるもの、
つまりもうひとつの命を信じています。
この地上の人生は
終わりではありません。
終わりだと信じている人たちは、
死を恐れます。
もしも、死は神の家に帰ることだと、
正しく説明されれば、
死を恐れることなどなくなるのです。
マザーテレサ
(マザーテレサ『日々のことば』より)

★英国国教会、初の女性主教は
「マンU」ファン
◆AFPBB 2015年1月26日 19:23(ロンドン/英国)
【1月26日 AFP】英国国教会で教区の主教に女性として史上初めて指名されたリビー・レーン師が26日、中部の都市マンチェスター郊外のストックポート教区の主教に正式に就任した。
就任式はイングランド北部にあるゴシック様式のヨーク大聖堂で行われた。レーン師はサックスを演奏することや、地元のサッカークラブ、マンチェスター・ユナイテッドのファンだといった普通の女性であることでも知られている。レーン師は1994年、同教会が初めて女性司祭を認めた年に、夫のジョージ氏とともに司祭に任命された。
1534年にイングランド王ヘンリー8世が英国国教会を創設して以来、女性が教区の主教に就任するのは初めて。教会内では今も女性を主教とすることをめぐり賛否が分かれ、深い対立がある。レーン師を知る人々は、レーン師ならではのユーモアや良識で、初の女性主教という特別な立場に対して受けるプレッシャーも乗り越えていくだろうと期待している。
(c)AFP/Katherine HADDON

★教会が同性愛者の葬儀でキスシーン再生を拒否、友人ら抗議 米
◆CNN.co.jp 2015年1月15日
http://www.cnn.co.jp/m/usa/35059015-2.html
(CNN) 米コロラド州の教会で行われた同性愛者の女性の葬儀で、教会側がパートナーとのキスシーンを含む動画の再生を断る出来事があり、遺族や友人が抗議の声を上げている。
遺族らによれば、バネッサ・コリアーさん(享年33)の葬儀は10日午前、同州デンバー郊外の教会で行われる予定だった。コリアーさんの友人で遺族の広報を務めるホセ・シルバさんはCNNの系列局KMGHに、「10時には参列者が集まり始めていた。だが10時15分に牧師が、技術的な問題から葬儀の場所を変更すると言った」と語った。
原因はコリアーさんをしのぶために用意されたビデオだった。別の友人がKMGHに語ったところでは、コリアーさんがパートナーとキスしている場面があったため、教会側が式の直前に削除を依頼。だが「遺族はそれを丁重に断り」、近くの葬儀場に会場を変更して欲しいと述べたという。
だが葬儀場の部屋は狭く、参列者が入りきらない事態に。クリスティーナ・ヒグリーさんは「ロビーにもあふれ出してテレビの画面から葬儀を見る羽目になった」と述べた。
これに対し友人らは13日、教会の周辺で抗議活動を行い、牧師に対し謝罪を求めた。別の友人によれば、教会は前日に渡しておいたビデオを紛失、別のコピーを持ってくるよう遺族に頼んだという。「それをチェックして、ようやくキスの場面があることに気がついた」
シルバさんはCNNに対し、教会はコリアーさんが同性愛者であることを前から知っていたと語った。もしビデオを手直しする必要が事前に分かっていたら、対応する方法もあったと彼は言う。
教会からのコメントは得られなかった。
(CNN.co.jp 2015年1月15日)

▲『不思議なキリスト教』橋爪大三郎✖️大澤真幸(講談社現代新書)
★寺とは何か「教会でもモスクでもありません」と橋爪大三郎氏
◆ガジェット通信 2015年1月4日
http://getnews.jp/archives/752716
戦後、新宗教(一般的に幕末~明治以降、現在までに創設されたもの)が勢力を伸ばした背景には、既存の伝統仏教が人々の「救い」になりえなかったという指摘がある。江戸時代に定められた檀家制度を踏襲し、さらには寺院を世襲運営している日本仏教の現状は、世界から見ても特殊だ。改革の必要はないのか。社会学者の橋爪大三郎氏に聞いた。
* * *
現在の「葬式仏教」をやめて、本来の仏教を日本に復興するには、いまの仏教界をスクラップにする、リセットボタンを押さなければならないのでしょうか。
世襲の寺院はつぶして、葬式もやらない。しかしこれでは、新しい仏教がかわりに生まれて来る保証がない。
仏教寺院は現に、日本の葬儀の大部分を担っています。それなりに社会的サービスを果たしている。また貴重な文化財を多く保存してもいる。それを、有無を言わさずリセットするのは、非現実的です。ではどうすればいいのか。
仏教再生の方向をみつけるためには、仏教の根本に戻る以外に、道は見えないと思います。そういう努力がまだまだ足りない。もっとアイデアを出し、議論することが必要です。
たとえば最近、「寺を開こう」というスローガンを掲げ、活動している僧侶たちがいます。お寺を親しみやすい場所に変えようと、境内で各種のイベントを催すなどしたり、手さぐりで運動している。よいことです。
ただ私は、その前に、「寺とはなにか」を突き詰めて考えてもらいたい。寺は教会でも、モスクでもありません。
寺がなければいけないと、経典のどこにも書いてない。寺は仏教の本質と、関係ないのではないか。そこまでさかのぼらないと、人々の深いところに届く運動にならないと思います。
仏教の本質に関係ないことに、価値を認めないようにすべきです。
葬儀はやってもいいが、仏教の本質と関係ない。戒名は、ますます関係ないから、そのことをはっきりさせる。法を説く、という釈尊の活動に立ち帰って、仏教の活動を再組織していく。瞑想や念仏、座禅は、いつどこででもできます。
仏教に関係ないことを削ぎ落とし、もっとも大事なことがらにふさわしい器を造る。仏教再生は、ここから始まるしかないと思うのです。
●取材・構成/小川寛大
※SAPIO2015年1月号
(NEWSポストセブン)

あらゆる傷の中で、
心の傷ほどいやし難いものはない。
あらゆる悪意の中で、
女の悪意ほど耐え難いものはない。
シラ書〔集会の書〕/ 25章 13節
(旧約聖書 新共同訳)
すべての宗教は、永遠なるもの、
つまりもうひとつの命を信じています。
この地上の人生は
終わりではありません。
終わりだと信じている人たちは、
死を恐れます。
もしも、死は神の家に帰ることだと、
正しく説明されれば、
死を恐れることなどなくなるのです。
マザーテレサ
(マザーテレサ『日々のことば』より)

★英国国教会、初の女性主教は
「マンU」ファン
◆AFPBB 2015年1月26日 19:23(ロンドン/英国)
【1月26日 AFP】英国国教会で教区の主教に女性として史上初めて指名されたリビー・レーン師が26日、中部の都市マンチェスター郊外のストックポート教区の主教に正式に就任した。
就任式はイングランド北部にあるゴシック様式のヨーク大聖堂で行われた。レーン師はサックスを演奏することや、地元のサッカークラブ、マンチェスター・ユナイテッドのファンだといった普通の女性であることでも知られている。レーン師は1994年、同教会が初めて女性司祭を認めた年に、夫のジョージ氏とともに司祭に任命された。
1534年にイングランド王ヘンリー8世が英国国教会を創設して以来、女性が教区の主教に就任するのは初めて。教会内では今も女性を主教とすることをめぐり賛否が分かれ、深い対立がある。レーン師を知る人々は、レーン師ならではのユーモアや良識で、初の女性主教という特別な立場に対して受けるプレッシャーも乗り越えていくだろうと期待している。
(c)AFP/Katherine HADDON

★教会が同性愛者の葬儀でキスシーン再生を拒否、友人ら抗議 米
◆CNN.co.jp 2015年1月15日
http://www.cnn.co.jp/m/usa/35059015-2.html
(CNN) 米コロラド州の教会で行われた同性愛者の女性の葬儀で、教会側がパートナーとのキスシーンを含む動画の再生を断る出来事があり、遺族や友人が抗議の声を上げている。
遺族らによれば、バネッサ・コリアーさん(享年33)の葬儀は10日午前、同州デンバー郊外の教会で行われる予定だった。コリアーさんの友人で遺族の広報を務めるホセ・シルバさんはCNNの系列局KMGHに、「10時には参列者が集まり始めていた。だが10時15分に牧師が、技術的な問題から葬儀の場所を変更すると言った」と語った。
原因はコリアーさんをしのぶために用意されたビデオだった。別の友人がKMGHに語ったところでは、コリアーさんがパートナーとキスしている場面があったため、教会側が式の直前に削除を依頼。だが「遺族はそれを丁重に断り」、近くの葬儀場に会場を変更して欲しいと述べたという。
だが葬儀場の部屋は狭く、参列者が入りきらない事態に。クリスティーナ・ヒグリーさんは「ロビーにもあふれ出してテレビの画面から葬儀を見る羽目になった」と述べた。
これに対し友人らは13日、教会の周辺で抗議活動を行い、牧師に対し謝罪を求めた。別の友人によれば、教会は前日に渡しておいたビデオを紛失、別のコピーを持ってくるよう遺族に頼んだという。「それをチェックして、ようやくキスの場面があることに気がついた」
シルバさんはCNNに対し、教会はコリアーさんが同性愛者であることを前から知っていたと語った。もしビデオを手直しする必要が事前に分かっていたら、対応する方法もあったと彼は言う。
教会からのコメントは得られなかった。
(CNN.co.jp 2015年1月15日)

▲『不思議なキリスト教』橋爪大三郎✖️大澤真幸(講談社現代新書)
★寺とは何か「教会でもモスクでもありません」と橋爪大三郎氏
◆ガジェット通信 2015年1月4日
http://getnews.jp/archives/752716
戦後、新宗教(一般的に幕末~明治以降、現在までに創設されたもの)が勢力を伸ばした背景には、既存の伝統仏教が人々の「救い」になりえなかったという指摘がある。江戸時代に定められた檀家制度を踏襲し、さらには寺院を世襲運営している日本仏教の現状は、世界から見ても特殊だ。改革の必要はないのか。社会学者の橋爪大三郎氏に聞いた。
* * *
現在の「葬式仏教」をやめて、本来の仏教を日本に復興するには、いまの仏教界をスクラップにする、リセットボタンを押さなければならないのでしょうか。
世襲の寺院はつぶして、葬式もやらない。しかしこれでは、新しい仏教がかわりに生まれて来る保証がない。
仏教寺院は現に、日本の葬儀の大部分を担っています。それなりに社会的サービスを果たしている。また貴重な文化財を多く保存してもいる。それを、有無を言わさずリセットするのは、非現実的です。ではどうすればいいのか。
仏教再生の方向をみつけるためには、仏教の根本に戻る以外に、道は見えないと思います。そういう努力がまだまだ足りない。もっとアイデアを出し、議論することが必要です。
たとえば最近、「寺を開こう」というスローガンを掲げ、活動している僧侶たちがいます。お寺を親しみやすい場所に変えようと、境内で各種のイベントを催すなどしたり、手さぐりで運動している。よいことです。
ただ私は、その前に、「寺とはなにか」を突き詰めて考えてもらいたい。寺は教会でも、モスクでもありません。
寺がなければいけないと、経典のどこにも書いてない。寺は仏教の本質と、関係ないのではないか。そこまでさかのぼらないと、人々の深いところに届く運動にならないと思います。
仏教の本質に関係ないことに、価値を認めないようにすべきです。
葬儀はやってもいいが、仏教の本質と関係ない。戒名は、ますます関係ないから、そのことをはっきりさせる。法を説く、という釈尊の活動に立ち帰って、仏教の活動を再組織していく。瞑想や念仏、座禅は、いつどこででもできます。
仏教に関係ないことを削ぎ落とし、もっとも大事なことがらにふさわしい器を造る。仏教再生は、ここから始まるしかないと思うのです。
●取材・構成/小川寛大
※SAPIO2015年1月号
(NEWSポストセブン)