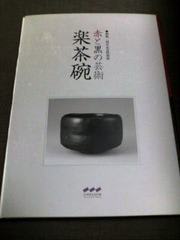
三井記念美術館で開催中の楽茶碗を見にでかけた。11月12日まで。現在、重文の長次郎作“大黒”が展示されている。夜も7時まで(入館は6時半)、会社帰りに立ち寄ることも可能。社会人にはうれしい開館時間です。
楽茶碗は茶人には馴染みのお茶碗。といっても、こんなに一同に、一代から当代までを見たことはなく、説明も充実していて勉強になった。今回もたっぷり2時間弱拝観。まだいらしていない方はこの機会にどうぞ。
楽家系譜は、長次郎→常慶→道入→一入→宗入→左入→長入→得入→了入→旦入→慶入→弘入→惺入→覚入→吉左衛門
楽家では常慶以来、当代が吉左衛門を名乗り、隠居して○入と称す。15代に渡る代々を覚える語呂合わせ。他にも色々あるようですが。
“阿米夜尼 長次① 常慶② そのあとに下に入付く人が十二。
道③ 一つ④ 宗は⑤ 左に⑥ 長く⑦ 得て⑧ 了⑨ と 旦とで⑩ 慶⑪ 弘⑫ 惺⑬ 覚⑭ (けいこせいかく)に “
楽茶碗は千利休様により創意され、その意をうけた長次郎が作り始め、陶法を継承しつつ各代独自の作意を加えて四百数十年、現在に至っている。
特殊な特徴としては、手捏ね成形であること、内釜(家屋内にある小規模な窯)焼成であること。
私が一番驚いたのは、まず天正9年前後に赤茶碗が作られ、やがて天正14年位までの間に黒茶碗が作られるようになったこと。楽といえば黒が代表と思っており、まず最初に黒茶碗が作られたのだと思い込んでいたのだった。
赤楽は赤土に透明釉がかけられて色が出ている、黒楽は鉄釉をかけ、焼成中に釉が溶けたのを見計らって引き出すことによって黒くなるのだそうだ。
また、長次郎の後二代常慶が受け継いだと思われていたが、昭和30年に公開された五代宗入文書が公開されて、二人の間に田中宗慶という人物がいることがわかったそうだ。常慶の父は長次郎ではなく、利休様に常に従っていた天下一の称号をもつ田中宗慶という人物で、長次郎と常慶の間で大きな役割を果たしていた。何故田中宗慶の名が消えたかというと、利休様のあと、少庵が継いだように、徳川の時代に移って楽家でも秀吉色の強い宗慶(秀吉から印を賜っている)を系図から外して存続を図ったのではないかと書かれていた。
代を追って作品と説明が置かれているので、大変判りやすく、養子や娘婿、兄弟など直系に限らず受け継ぐことによって楽家が今まで続いてきたことがよくわかった。
気になった作品について書きとめておく。
七代長入作の赤楽の島台茶碗。お正月用の濃茶茶碗として如心斎に好まれた島台、私もお正月に先生のお宅で使用させて頂くが、とても大きく平たくて、まさに盃の形をしていた。大きさにびっくり。
宗慶の香炉釉菊紋水指。長次郎の頃はまだ水指は作られておらず、これが楽としては一番古い水指だと。貫入の入った白地の肌に赤い菊が描かれてなんともかわいらしい。ちなみに香合が作られるようになったのは道入の頃だとか。
二代常慶の赤楽井戸形茶碗。楽には珍しいすっきりと立ち上がった井戸の姿の茶碗。高台の土がたくさん見えて愛らしい。
了入作の白楽筒茶碗。白といってもクリーム色で優しく、ヘラ目が縦にあり、すっきりした筒で美しい。
旦入作の赤楽印尽し茶碗。長入の頃から印を装飾的に使用するようになり、印尽くし、数印と呼ばれる。
慶入作の白楽貝文茶碗 銘 潮干。茶碗の中にホンモノの貝が貼り付けられている。釉薬が薄くかけられていることで、本当に潮干狩りをしているかのような気分になる。
楽というと黒か赤という乏しいイメージしかなかったので、様々な姿、色のものを拝見して刺激的だった。
(ご参考)楽茶碗の由来
http://blog.goo.ne.jp/m-tamago/e/5aa1d853bf81ff2e5697f945c351846a
楽茶碗は茶人には馴染みのお茶碗。といっても、こんなに一同に、一代から当代までを見たことはなく、説明も充実していて勉強になった。今回もたっぷり2時間弱拝観。まだいらしていない方はこの機会にどうぞ。
楽家系譜は、長次郎→常慶→道入→一入→宗入→左入→長入→得入→了入→旦入→慶入→弘入→惺入→覚入→吉左衛門
楽家では常慶以来、当代が吉左衛門を名乗り、隠居して○入と称す。15代に渡る代々を覚える語呂合わせ。他にも色々あるようですが。
“阿米夜尼 長次① 常慶② そのあとに下に入付く人が十二。
道③ 一つ④ 宗は⑤ 左に⑥ 長く⑦ 得て⑧ 了⑨ と 旦とで⑩ 慶⑪ 弘⑫ 惺⑬ 覚⑭ (けいこせいかく)に “
楽茶碗は千利休様により創意され、その意をうけた長次郎が作り始め、陶法を継承しつつ各代独自の作意を加えて四百数十年、現在に至っている。
特殊な特徴としては、手捏ね成形であること、内釜(家屋内にある小規模な窯)焼成であること。
私が一番驚いたのは、まず天正9年前後に赤茶碗が作られ、やがて天正14年位までの間に黒茶碗が作られるようになったこと。楽といえば黒が代表と思っており、まず最初に黒茶碗が作られたのだと思い込んでいたのだった。
赤楽は赤土に透明釉がかけられて色が出ている、黒楽は鉄釉をかけ、焼成中に釉が溶けたのを見計らって引き出すことによって黒くなるのだそうだ。
また、長次郎の後二代常慶が受け継いだと思われていたが、昭和30年に公開された五代宗入文書が公開されて、二人の間に田中宗慶という人物がいることがわかったそうだ。常慶の父は長次郎ではなく、利休様に常に従っていた天下一の称号をもつ田中宗慶という人物で、長次郎と常慶の間で大きな役割を果たしていた。何故田中宗慶の名が消えたかというと、利休様のあと、少庵が継いだように、徳川の時代に移って楽家でも秀吉色の強い宗慶(秀吉から印を賜っている)を系図から外して存続を図ったのではないかと書かれていた。
代を追って作品と説明が置かれているので、大変判りやすく、養子や娘婿、兄弟など直系に限らず受け継ぐことによって楽家が今まで続いてきたことがよくわかった。
気になった作品について書きとめておく。
七代長入作の赤楽の島台茶碗。お正月用の濃茶茶碗として如心斎に好まれた島台、私もお正月に先生のお宅で使用させて頂くが、とても大きく平たくて、まさに盃の形をしていた。大きさにびっくり。
宗慶の香炉釉菊紋水指。長次郎の頃はまだ水指は作られておらず、これが楽としては一番古い水指だと。貫入の入った白地の肌に赤い菊が描かれてなんともかわいらしい。ちなみに香合が作られるようになったのは道入の頃だとか。
二代常慶の赤楽井戸形茶碗。楽には珍しいすっきりと立ち上がった井戸の姿の茶碗。高台の土がたくさん見えて愛らしい。
了入作の白楽筒茶碗。白といってもクリーム色で優しく、ヘラ目が縦にあり、すっきりした筒で美しい。
旦入作の赤楽印尽し茶碗。長入の頃から印を装飾的に使用するようになり、印尽くし、数印と呼ばれる。
慶入作の白楽貝文茶碗 銘 潮干。茶碗の中にホンモノの貝が貼り付けられている。釉薬が薄くかけられていることで、本当に潮干狩りをしているかのような気分になる。
楽というと黒か赤という乏しいイメージしかなかったので、様々な姿、色のものを拝見して刺激的だった。
(ご参考)楽茶碗の由来
http://blog.goo.ne.jp/m-tamago/e/5aa1d853bf81ff2e5697f945c351846a




























とても興味があり気になっていたこの頃です。
お裏さんでは濃茶の時に楽茶碗には出し服紗(なんというのでしょうか?)を添えないのには理由があるのでしょうか?
表では濃茶の時には出し服紗はどんなお茶碗でも添えますよ。
いつも色々詳しく書いてくださりありがとうございます。
わたしは会期の早いうちに鑑賞いたしました。ひと口に楽と申しましても、四百数十年の系譜には新たな試み、初代への回帰、そして苦悩と停滞もあったのだと感慨深い思いでした。わたしも目にとまった作品がいくつかあるのですけれども、今回はとくに十五代吉左さまの赤楽に感銘をうけました。まさにこれから花開こうとする瞬間の姿、期待に胸をふくらませたみずみずしさ。今後、ひと花もふた花も咲かせんとする当代の気構えがビンビンと伝わってくるようでした。芸術とは前衛的なものであることを、この赤楽に実感いたしました次第です。
よろしければ、参考までにこちらの方の記事もご覧ください。
http://japanesearts.cocolog-nifty.com/silkroad/2006/09/post_6bff.html
見たいものと暦を眺めています。
投稿色々と参考になり有り難うございます。
雪月花さんのブログも見せて貰いました。
もちろん、是非行ってみたい!って思いカレンダーとにらめっこ・・・神戸からだとちょい距離が遠くて断念しました。
でも、お写真の図録は東京の友達が購入してくれて今は手元に・・・♪
11月は2回京都に行くので楽美術館の方に伺ってみますね!
赤い印に墨の黒で、毎日が“赤と黒のブルースや・・・”と云ってられたのを思い出しました。
TBさせていただきました。
白や黄色の樂茶碗はときどきみかけますが、
以前、五島美術館で見た黄色いものも、味わいがあり
お茶をたてたら華やかだろうな、と思いました。
樂代々の方たちは、自分のブランドを打ち立てるのに
熱心に研究をし、そんな中で白や黄のものも生まれてくるのかしら、と考えました。
>田中宗慶さんは?どんな人だったのでしょうか?
楽家においては彼の存在が実は大きかったようです。常慶には宗味という兄弟が存在していたともありました。
また、楽家は江戸時代までは田中姓で(陶芸家としては楽だが)明治初めに戸籍上も楽と変えたとか。これは永楽とも通じますが。
>お裏さんでは濃茶の時に楽茶碗には出し服紗を添えないのには理由があるのでしょうか?
裏では、濃茶で、楽茶碗の場合は添えません。萩や井戸茶碗、高麗茶碗を使う場合だけ添えます。また、表千家は大帛紗ですが、裏千家は基本的には古帛紗で、サイズが違います。
大帛紗の使い方については改めてまた近いうちに書かせて頂きます。先日先生から伺って目からウロコなことがあったので。
ともあれ、表と裏の出し帛紗の使い方の違いは、表が先にありきで、裏が変えていったということなのではないでしょうか。。。。いつそうなったのか、知りたいですね。誰かご存知じゃありませんか??
昔、表の友達に知らずに古帛紗をプレゼントしたら、表は大帛紗なのよ、と言われてびっくりした思い出があります。もちろんその古帛紗は私の手元に戻り、友達には帛紗をプレゼントしなおしました(笑)。
>今回はとくに十五代吉左さまの赤楽に感銘をうけました。
>芸術とは前衛的なものである
そうですね、切磋琢磨してそれぞれの代で作品を残してこられたのでしょうね。今は古いと思われる姿の茶碗も、その時代には前衛的だったのかもしれません。
黄色い楽茶碗は私はまだ見たことがありませんが、衝撃を受けそうだなぁ。
ともあれ、鑑賞としてでなく、お茶を点ててみたらどうだろう、飲むにはどうだろうと必ず使う立場で見てしまう私です。
急に涼しくなりましたし、お大事になさって下さい。
11日までに間に合えば是非いらしてください。
お会いできたら嬉しいかも。
それにしても、図録は手元とはさすがです。きれいに撮れているので私も再び眺めては楽しんでいます。
私はまだ楽美術館にはご縁がないのですよ。
11月は2回も京都に行かれる!羨ましい!!楽美術館は今、楽と光悦ですか?感想お聞かせくださいね。
ご朱印は確かに墨の黒に朱の印ですね。
赤と黒といえば、私はスタンダールを思い出してしまいました。
当代のお話も聞けたなんて羨ましい。私は葉書見事に外れましたよ。でも、当日は空席もあったやに聞いています。残念。
当代と一緒にお話なさった赤沼さんという方はこの道では有名な方らしいです。
何故、次男が二代目となったかは分かりませんが、父親の宗慶、長男の宗味(庄佐衛門)の製作したものも、長次郎焼と称したそうですね。
楽茶碗は、そうそう日頃から扱えませんが、抹茶の色との調和といい、湯の熱さを適度に和らげ、かつ温かさも保ち、手の持った時や飲む時の口当たりの柔らかさ、まさにお茶に相応しい茶碗ですよね。
昔の人々の人間模様は思いがけないところで繋がっていて面白いですね。昔は次男が継ぐことも多かったようですけど、宗慶さんのところはどうしてだったんでしょうね?楽家のこともまだまだ知らないことだらけ。
わが社中では、茶名をとると先生がお祝いに和楽を下さることになっています。精進して、その茶碗で濃茶を点てる日を楽しみにしています。
「光悦と楽道入」の展示でした。
光悦の自由奔放な作風に驚き。のんこうの洗練された作風は光悦の影響を受けながらも自分の追及する茶碗を作り上げたように感じました。
幸運にも「手にふれる楽茶碗鑑賞会」に参加でき慶入のお茶碗をしっかりこの手で触りました♪
楽美術館はまだ一度もご縁がないのですよ~。
茶会や楽茶碗鑑賞会など、当代は皆さんに楽を披露する場を色々設けていらっしゃるようですね。
見るだけでなく手にしたり、お茶を頂いたりするとその茶碗のよさが益々わかりそうですね。羨ましい。
私も機会を見つけて参加したいと思っています。
歴史は未知の部分があるのが魅力でもありますね。
私は楽についてもまだまだ不勉強ですが、未知の部分がありつつもこうして15代まで続いてきたというのはすごいことだと思います。
紫庵さんはお詳しいようですが、茶道を学んでいらっしゃるのでしょうか。
やきものがお好きなんですね。私もお茶をやって焼物にも興味が沸くようになり、一時は陶芸を習っていました。
鎌倉、葉山界隈は海あり、山あり、風光明媚な場所ですね。私も好きです。
確かに鎌倉はよく歩きますが、葉山となると車でないと不便なので、なかなか行きません。
機会あれば訪ねたいと思います。