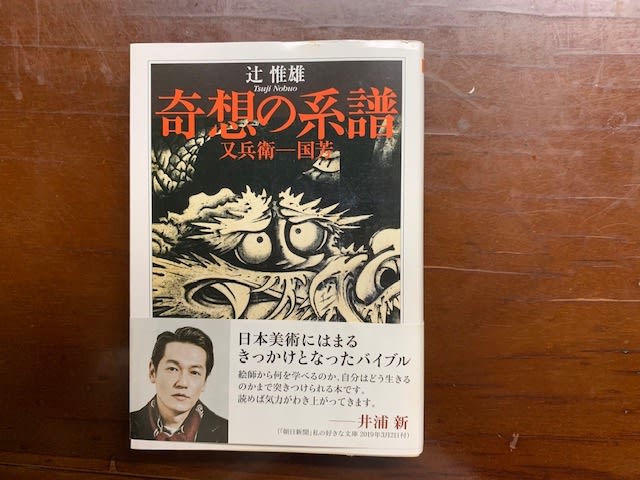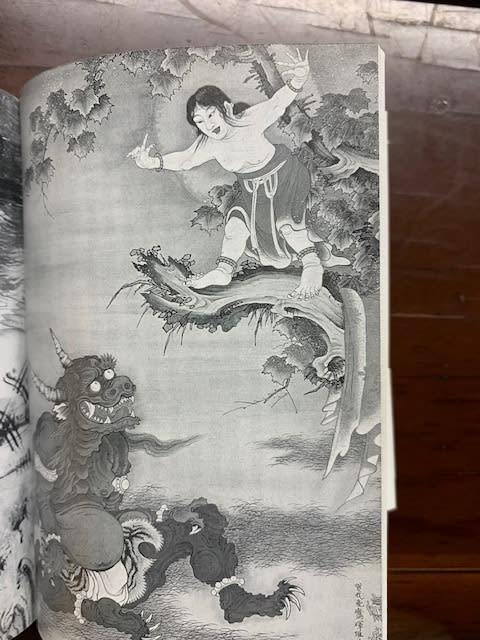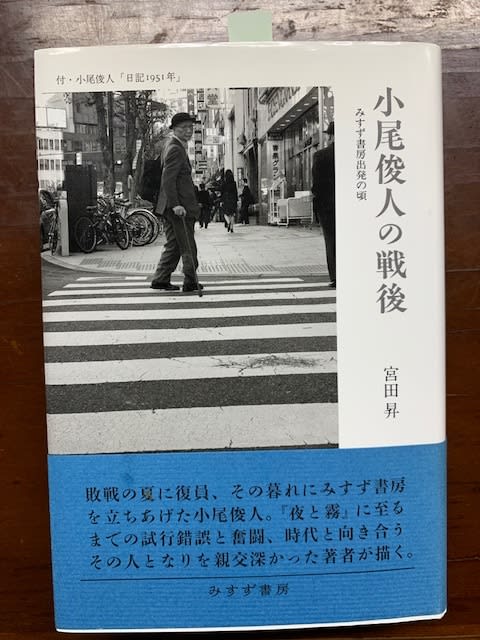第1次世界大戦は今から約100年前の出来事ですが、この3年間ほどのコロナ禍に関しても、100年前のスペイン風邪のことがよく話題になりますが、第1次世界大戦でアメリカの兵士がヨーロッパに持ち込んだとも言われています。その時代は日本では、大正デモクラシーの時代で、思想統制なども行われていた時代であり、米騒動を始め、普通選挙制度要求や、それに続く恐慌から戦争への流れ、そんなことを思い巡らしている。こんな時に、管政権時に行われた日本学術会議任命拒否問題に関する本として

を読んでみました。
学問と政治に関して、今、戦前との比較で考える人が多いのではないか、少なくとも私の世代より上の世代の人では。
年代的には、菅、安倍元首相なども世代的には、学問と政治に関しては高校時代には勉強していたら、つまり、滝川事件等などを日本史で勉強していたら、こんなことはしないだろうと思われることが少なからずある。そう考える人も私より上の世代では多いのではないか。
もっとも、滝川事件当時の文部大臣は鳩山一郎で、鳩山由紀夫の祖父であるし、戦後京大の総長にもなった瀧川幸辰は、意外にも高圧的なというか、管理的な総長らしかったとも言われているが。
私の学生時代は、時計台には白いペンキで、「竹本処分粉砕」と書かれていたのが、日常でした。たまに時計台の前で、学生側と教授とで断交が行われていたし、教養部の1回生2回生の時はストで定期試験がなくなっていたし、授業料値上げ闘争もあったそんな時代でした。ストが可決されるのか心配で、代議員大会に出ていたこともありました。可決された翌日の朝には、綺麗にバリケードストになっていました。いつ椅子など積み上げたのかと思いました。もっとも、「竹本処分粉砕」も大学当局が消すと、翌日にはまたその特徴的は書体で書き上げられているという噂でした。
授業料が値上げされるようになったのは、国会審議をしないで、文部省通達で値上げが可能に法令改正が行われて、その後一気に授業料の値上げが毎年のように行われていったのです。ちなみに私の時の授業料は年間3万6千円でした。月3千円です。一日バイトすれば、1ヶ月の授業料は稼げたものです。自動販売機の缶ジュースなども100円で今と変わらなかったです。授業料はいま国立大学で50万ほどですね。15倍ですね。
70年代から80年代にかけては授業料も上がり、国立大学の医学部が新設され、浜松医科大、旭川医科大、宮崎医科大学が始まりで、南から琉球大学医学部、大分医科大、佐賀医科大学、島根医科大、高知医科大、香川医科大、福井医科大、山梨医科大学などが新設され、その後地元の国立大学の医学部に合併されたりもしました。それと並行するように、90年代にかけて教養部が廃止され、総合人間学部や、情報文化学部などの学祭的な学部へと変わって行きました。さらに、90年代から大学改革が行われ、独立法人化が進み、改正学校教育法や大学院重点化などとともに、国立大学には民間的発想の経営手法や第三者評価による競争原理の導入、資金の選択と集中、運営交付金の毎年1%の削減と競争的資金の拡充、中期目標中期計画の策定などによって、そのあり方を一変させることになる。
最近の30年間の日本の成長率の減衰と上記のような大学を取り巻く環境の変化は同期しているように思えます。ときを同じくして、日本製とか、日本のもの作りとか、日本の技術力とかを賛美することが多くなってきたのもですが、それは現実には日本の技術の進歩の鈍化を逆説的に示してきたのではないかと考えます。大学生の政治意識も低下して、学問を学ぶ真っただ中にある学生から学問の自由を論じることで、学術会議の任命拒否を考えることもなく、我々の世代からすると学生は何してるんだと思えなくもない。歴史を紐解くことで、今からの将来に不安を覚える昨今の日本の状況に情けなさを憶えてしまう自分がある。