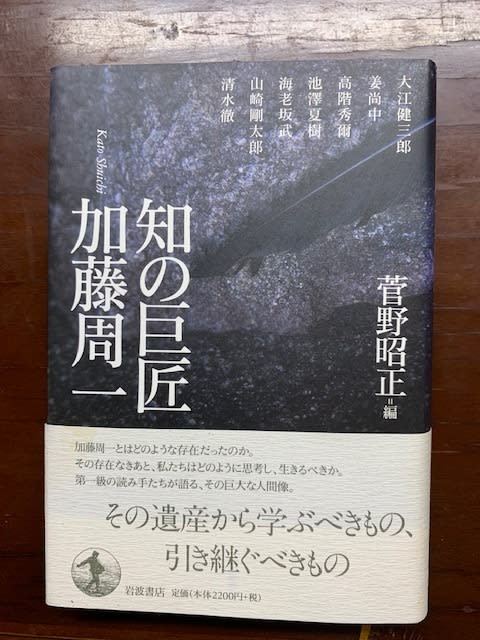朝日新聞の昨日の朝刊にアインシュタイン来日100年の記事が載っていました。100年前というフレーズは、2018年の時、100年前のスペイン風邪のことでよく耳にしたフレーズです。
第1次大戦が終わり、大正時代の日本では、大正ロマンとか言われる時代でもありましたが、学術や文学など知的なものに対する世間の関心も強くなってきた時代ですね。アインシュタインが来日した時の日本の反響は、後にビートルズが来日した時のような騒ぎだったとか。その様子が描かれている本として、本棚にあるのが下の本です。

今から20年ほど前に出版された本ですが、80周年記念で出版されたが、100周年ではこの種の本は出版されないのだろうか。そこには知的なものに対する日本人の感覚が退化しているとさえ思えてしまう。少しページを捲ってみると



こうしてみると、日本各地を訪問していることがわかる。しかも各地ですごい歓迎を受けているのが伺える。
1922年(大正11年)11月17日に神戸に到着して、その後43日間全国を回ったことになっている。当時、アインシュタインは43歳であった。この本はさしずめ、アインシュタインの日本での写真集ともいうべき本で、貴重な手紙や講演録や写真が収められていて、その内容に関しても貴重な本とも思えます。
特に印象的な記事に関しては、アインシュタインが京都大学を訪問した際に、学生代表として、祝辞を述べた学生代表の荒木俊馬(としま)のドイツ語はアインシュタインから完璧なドイツ語と賞賛されたところで、当時の京大生の語学の素晴らしさが伺える。ちなみに、この荒木俊馬は当時物理を専攻する学生でのちに物理学者になり、京都産業大学の創設者になる人物であり、私が学生時代にまだご存命で、当時の京都産業大学の総長でもあった記憶があります。そういえば、当時の京都産業大学には、数学者の岡潔もおられていたようでした。友人の京都産業大学の学生がその講義を受けていたとか。もっとも数学ではなく、随筆に書かれていたような内容の講義だったようです。これを聞いて自然科学系の単位がもらえたそうです。岡潔はアインシュタインが来日した時は、京都帝国大学の理学部の物理学科で学んでいて、上記の荒木との関係がありそうです。岡潔は次の年に数学科へ転科したそうです。

岡潔は私が高校時代にその随筆「春宵十話」を角川文庫で読んだ記憶がありますが、数学者が書いた随筆であることと、厚くない文庫本だからかもしれませんが、今は光文社文庫から出版されています。

実はこのアインシュタインの日本に招待したのは、当時の日本の出版社の改造社でした。改造社は「円本」時代を作り上げ、大正・昭和初期に日本の文人・思想家がこぞって執筆した雑誌「改造」を主宰した山本実彦の創設した出版社であった。当時、岩波と双璧をなすと言われた改造社であり、その文化の担い手としての役割をアインシュタインの来日という形で果たしたと言えよう。
その改造社に関しては、下の本に詳しい。