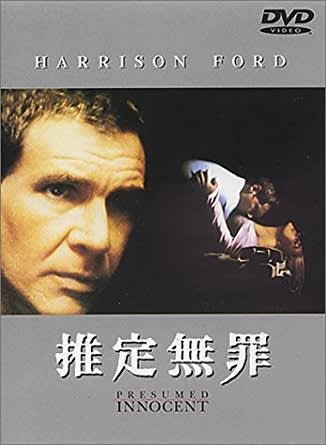「終戦記念日」をググってみると、大体こういった同じような内容の文章がヒットする。曰く、第二次世界大戦「終戦日」の認識は国によって異なっているとして、ロシア、アメリカ、中国などの諸外国の日付が参照されるのだが、これらの文章にはある重要な視点が欠落しているのが、お判りだろうか。
→Wikipedia終戦の日
→日本人だけが8月15日を「終戦日」とする謎
それは、この戦争に勝ったか負けたかと言う視点で、「戦勝記念日」と「終戦記念日」とでは、その意味合いが全く異なると言わなければならない。つまり、こういった文章で書かれている<第二次世界大戦終結の日の認識>という見方は、この「戦争における勝者と敗者=戦勝国と敗戦国と言う本質的な差異」を覆い隠し、「日付の差異」という別の「差異」への論点ずらしになっているということである。
そもそも、「戦勝記念日」というのは、勝利を記念するという意味で、至極当然の記念日であって、多くの国で設けられているのも良くわかる道理だが、恐らく「終戦記念日」なる摩訶不思議な記念日が存在するのは、わが国だけであろう。この摩訶不思議さは、「終戦」という言葉を「敗戦」と言い換えてみればすぐにわかることで、よく自虐史観などと言われるが、さすがに自虐史観であっても「敗戦記念日」はあり得ないだろう。
この私の感ずる「終戦記念日」に対する違和感を、表立って表明した識者や知識人を、残念ながら私は知らないのだが、このように、この”論点ずらし”が、全く意識されていないという点で、それだけ根は深いと思わざるを得ないとも言える訳である。
そしてまた逆に、多くの国にあって、わが国にない記念日がある。それは「独立記念日」で、この二つの相補的な事実ー「終戦記念日」の存在と「独立記念日」の不在・欠落は、戦後における日本人の、表立って意識されてはいない考え方の特異性を先鋭且つ顕著に表しているのではないかと私は考えているのだが、それがこの文章を書いている理由でもある訳である。
日本の「独立記念日」というと、普通に考えれば、1952年(昭和27年)にサンフランシスコ平和条約を締結した4月28日ということになろう。知らない人も多いと思うが、→ようやくにして2013年(平成25年)になって、第2次安倍内閣が4月28日を「主権回復の日」として定めたが、「記念日」ないし「国民の祝日」ではないため、カレンダーには載ってはいない。これら事実としての行動様式から考えると、「主権回復の日」(=「独立記念日」)よりも、「終戦記念日」の方が重要だと我々日本人は考えていることになると言えよう。
では、この「終戦記念日」の体現している思想、見方や考え方とは、一体なんなのであろうか。
そのことは、8月15日という日付に端的に表れていると言えよう。日本の「敗戦」が決まったのは、前日のポツダム宣言受諾の8月14日である事実から考えれば、日本人にとってはポツダム宣言受諾よりも記念日とすべき、重要なある歴史的な事件が8月15日に起こったということである。その重要なある歴史的な事件とは、何を隠そう「玉音放送」で、この8月15日に、我々日本人は「敗戦」を「終戦」として受け入れたということある。
つまり、「終戦記念日」というのは、「敗戦」=戦に敗れた日ではなくて、日本国民が「敗戦」を「終戦」として受け入れ、納得した日として記念する日なのだと言うことが出来る。言い換えると、戦後の我々日本人にとって、記念日として今後未来永劫に渡って記念していく日としては、ポツダム宣言受諾の日でもなく、サンフランシスコ平和条約締結の日でもなく、玉音放送の日こそが、そして玉音放送の日だけが、それに相応しいと考えていると言うことである。
なぜこのような事になっているのか。その背後にある、表立っては意識されてはいない思想、見方や考え方については、日本の歴史的・文化的な深い理解に基づいた洞察が要請されると考えられるが、ここで私見を述べてみたい。
結論を先ず述べれば、この背後にあるものは、「やれやれやっと終わった」という安堵の気持ちではないかと私は考えている。つまり、前にも書いたが、日本は明治・大正と無理をして「軍国主義」へと舵を切ってきたのだが、やっとその無理難題から解放されたということである。制度的に見れば、江戸時代の朝廷・幕府二極体制から、明治になって国際情勢による圧力に対抗するために、相当な無理をして現人神である天皇(=朝廷)一極体制にもっていったのだが、敗戦によってこの無理難題から解放されたと言うことである。この意味で、戦後の象徴天皇・代議制民主主義という二極体制は、江戸時代の朝廷・幕府という二極体制へと、言わば先祖返りしたと見ることが出来る訳である。
このことは、なんせ江戸時代は三百年も続いたのであるから、江戸時代に培われた我々日本人の考え方や見方は、たかだか文明開化による近代化や、その帰結である近代戦争に敗れたぐらいでは変わりはしなかったとも言えよう。この意味では、戦後の昭和・平成の日本は、戦前の明治・大正の日本を飛び越して、文化的・精神史的には、江戸時代に地続きで繋がっているということになる。従って、戦後の日本社会は表向きは近代民主主義国家の体裁をとっているが、実際には江戸時代的秩序としての「世間」として弾力的に運用されているということでもある。「近代社会という建前」と「世間という本音」の矛盾や軋轢を内包しながら。
そして、この安堵はまた、勿論一部には反発もあったが、占領軍に対する日本国民の熱烈な歓迎ぶりに表れていると思われる。その歓迎ぶりは占領軍というよりもまるで解放軍といった有様で、そのことは異様なとも言える当時のマッカーサー人気からも伺える。何とマッカーサーに全国の日本国民から、数十万通の結婚の申し込みや娘の婿にといった手紙が殺到したというから凄まじい。これだけではないだろうが、こういった様々な進駐軍に対する日本人の態度が、マッカーサーの眼にどう映ったのかは、<科学、美術、宗教、文化などの発展の上から見て、アングロ・サクソン民族が45歳の壮年に達しているとすれば、(敗戦国である)ドイツ人はそれとほぼ同年齢である。しかし、日本人は生徒の段階で、まだ12歳の少年である>という後年の発言から窺い知ることが出来る。
ただ、私がこのことを指摘するのは、「玉音放送」の日を境にして、日本人の考え方が、反米から親米へ、「鬼畜英米」から「ギブ・ミー・チョコレート」へと、一変した事実に注目したいからである。
このように日本人は、8月15日に、言わば「心を入れ替えて出直した」訳だが、この変わり身の鮮やかさは、アメリカが予期していたような、亡命政府樹立による地下レジスタンス運動などの動きも全く見られず、アメリカにとってみれば、言わば拍子抜けしたといった格好で、アメリカ進駐軍は歴史上最も寛容な占領軍であったなどと評価する向きもあるが、それはこういった日本側のある意味では卑屈とも言い得る従順な態度を抜きにしては、片手落ちの評価だと言わなければならないだろう。
そして、様々な多くの歴史書をこれまで読んできたが、この日本人の豹変ぶりを指摘し考察した著述家は、私の知る限り山本七平だけである。この点で、現在良く知られている司馬遼太郎史観や半藤一利史観などに対して、歴史に対する洞察力という点で、山本七平史観は一つも二つも頭抜けていると言っても良いと思う。
そして、その山本七平の著作で最も名高く、最も読まれている著作は『空気の研究』であろうが、またこれほど理解されていない著作も珍しいのではないかとも思う。

それはこの本が言及される場合は、殆どと言って良い程前半の部分のみあって、肝心な後半の「研究」の部分は、これまた全くと言って良い程言及されないからである。要は、ほとんどの読者は日常生活に感じている、上手くは言語化出来ない同調圧力の存在を、明確に言語化して説明・指摘されれば、それだけで言わばお腹一杯、それ以後は咀嚼できず、消化不良を起こしてしまうといった事のようなのだ。山本は「空体語」と「実体語」という彼一流の概念を使って説明しているが、山本が「実体語」として「空気」を語っているのにも関わらず、「空体語」として理解・消費されて、多くの読者を引き付けているというのは、逆にそれだけ「空気」の強固さを証明していることになってしまっていると言わなければならない。ここでもまた「名声とは誤解の異名である」というテーゼを証明する結果になっているのは、皮肉な巡りあわせである。やれやれ。
これは、山本独特の語法やプレゼンの流儀、さらには「山本学」の全体像を理解した上でないとなかなかと理解しにくいという点にもあると思われるが、この意味で少し前に「山本学」の全体像のアウトラインを掴むのに格好の著作が復刊されたので、ここで紹介しておくのも良いだろう。小室直樹によって、山本独特の語法やプレゼンの流儀の灰汁が中和されて、すこぶるリーダブルな著作になっているからだ。
『日本教の社会学』

それはともかく、山本はこの同じ日本人の豹変パターンを、尊王攘夷から開国文明開化へと舵を切った明治維新にも見ているが、この『空気の研究』の中で、先の「空体語」と「実体語」の天秤モデルとして説明している。詳しくは同書を参照されたいが、「空体語」と「実体語」でバランスを取っていた天秤が、バランスが取れなくなるとひっくり返ってしまい、一挙に反転してしまうことになるという動的なモデルを提示している。
これまでに述べたようにそれが敗戦時に反米から親米へという形で現れ、戦後が始まった訳だが、最近はまたこのバランスが危うくなってきているように見受けられる。これまで「ギブ・ミー・チョコレート=親米保守」が本流だったのが揺らぎだして、「鬼畜米英=反米保守」の言説が顕在化して来ているのはその表れであろう。
さて、現在「終戦記念日」に広く恒例行事として、靖国神社参拝が行われているのは承知の事実だが、私の眼から見るとこれもまた摩訶不思議な行動に映る。例えば、その趣旨からいえば、「主権回復の日」(=「独立記念日」)である4月28日の方が相応しいのではないかと思うのだが、どうやら参拝者達は「終戦記念日」自体にも、「終戦記念日」に靖国神社参拝をするという点にも、何ら違和感を感じていないように見える。
この靖国神社参拝については。その裏付けとなっている「保守主義思想」ともども、次に考えてみたいと思う。
→Wikipedia終戦の日
→日本人だけが8月15日を「終戦日」とする謎
それは、この戦争に勝ったか負けたかと言う視点で、「戦勝記念日」と「終戦記念日」とでは、その意味合いが全く異なると言わなければならない。つまり、こういった文章で書かれている<第二次世界大戦終結の日の認識>という見方は、この「戦争における勝者と敗者=戦勝国と敗戦国と言う本質的な差異」を覆い隠し、「日付の差異」という別の「差異」への論点ずらしになっているということである。
そもそも、「戦勝記念日」というのは、勝利を記念するという意味で、至極当然の記念日であって、多くの国で設けられているのも良くわかる道理だが、恐らく「終戦記念日」なる摩訶不思議な記念日が存在するのは、わが国だけであろう。この摩訶不思議さは、「終戦」という言葉を「敗戦」と言い換えてみればすぐにわかることで、よく自虐史観などと言われるが、さすがに自虐史観であっても「敗戦記念日」はあり得ないだろう。
この私の感ずる「終戦記念日」に対する違和感を、表立って表明した識者や知識人を、残念ながら私は知らないのだが、このように、この”論点ずらし”が、全く意識されていないという点で、それだけ根は深いと思わざるを得ないとも言える訳である。
そしてまた逆に、多くの国にあって、わが国にない記念日がある。それは「独立記念日」で、この二つの相補的な事実ー「終戦記念日」の存在と「独立記念日」の不在・欠落は、戦後における日本人の、表立って意識されてはいない考え方の特異性を先鋭且つ顕著に表しているのではないかと私は考えているのだが、それがこの文章を書いている理由でもある訳である。
日本の「独立記念日」というと、普通に考えれば、1952年(昭和27年)にサンフランシスコ平和条約を締結した4月28日ということになろう。知らない人も多いと思うが、→ようやくにして2013年(平成25年)になって、第2次安倍内閣が4月28日を「主権回復の日」として定めたが、「記念日」ないし「国民の祝日」ではないため、カレンダーには載ってはいない。これら事実としての行動様式から考えると、「主権回復の日」(=「独立記念日」)よりも、「終戦記念日」の方が重要だと我々日本人は考えていることになると言えよう。
では、この「終戦記念日」の体現している思想、見方や考え方とは、一体なんなのであろうか。
そのことは、8月15日という日付に端的に表れていると言えよう。日本の「敗戦」が決まったのは、前日のポツダム宣言受諾の8月14日である事実から考えれば、日本人にとってはポツダム宣言受諾よりも記念日とすべき、重要なある歴史的な事件が8月15日に起こったということである。その重要なある歴史的な事件とは、何を隠そう「玉音放送」で、この8月15日に、我々日本人は「敗戦」を「終戦」として受け入れたということある。
つまり、「終戦記念日」というのは、「敗戦」=戦に敗れた日ではなくて、日本国民が「敗戦」を「終戦」として受け入れ、納得した日として記念する日なのだと言うことが出来る。言い換えると、戦後の我々日本人にとって、記念日として今後未来永劫に渡って記念していく日としては、ポツダム宣言受諾の日でもなく、サンフランシスコ平和条約締結の日でもなく、玉音放送の日こそが、そして玉音放送の日だけが、それに相応しいと考えていると言うことである。
なぜこのような事になっているのか。その背後にある、表立っては意識されてはいない思想、見方や考え方については、日本の歴史的・文化的な深い理解に基づいた洞察が要請されると考えられるが、ここで私見を述べてみたい。
結論を先ず述べれば、この背後にあるものは、「やれやれやっと終わった」という安堵の気持ちではないかと私は考えている。つまり、前にも書いたが、日本は明治・大正と無理をして「軍国主義」へと舵を切ってきたのだが、やっとその無理難題から解放されたということである。制度的に見れば、江戸時代の朝廷・幕府二極体制から、明治になって国際情勢による圧力に対抗するために、相当な無理をして現人神である天皇(=朝廷)一極体制にもっていったのだが、敗戦によってこの無理難題から解放されたと言うことである。この意味で、戦後の象徴天皇・代議制民主主義という二極体制は、江戸時代の朝廷・幕府という二極体制へと、言わば先祖返りしたと見ることが出来る訳である。
このことは、なんせ江戸時代は三百年も続いたのであるから、江戸時代に培われた我々日本人の考え方や見方は、たかだか文明開化による近代化や、その帰結である近代戦争に敗れたぐらいでは変わりはしなかったとも言えよう。この意味では、戦後の昭和・平成の日本は、戦前の明治・大正の日本を飛び越して、文化的・精神史的には、江戸時代に地続きで繋がっているということになる。従って、戦後の日本社会は表向きは近代民主主義国家の体裁をとっているが、実際には江戸時代的秩序としての「世間」として弾力的に運用されているということでもある。「近代社会という建前」と「世間という本音」の矛盾や軋轢を内包しながら。
そして、この安堵はまた、勿論一部には反発もあったが、占領軍に対する日本国民の熱烈な歓迎ぶりに表れていると思われる。その歓迎ぶりは占領軍というよりもまるで解放軍といった有様で、そのことは異様なとも言える当時のマッカーサー人気からも伺える。何とマッカーサーに全国の日本国民から、数十万通の結婚の申し込みや娘の婿にといった手紙が殺到したというから凄まじい。これだけではないだろうが、こういった様々な進駐軍に対する日本人の態度が、マッカーサーの眼にどう映ったのかは、<科学、美術、宗教、文化などの発展の上から見て、アングロ・サクソン民族が45歳の壮年に達しているとすれば、(敗戦国である)ドイツ人はそれとほぼ同年齢である。しかし、日本人は生徒の段階で、まだ12歳の少年である>という後年の発言から窺い知ることが出来る。
ただ、私がこのことを指摘するのは、「玉音放送」の日を境にして、日本人の考え方が、反米から親米へ、「鬼畜英米」から「ギブ・ミー・チョコレート」へと、一変した事実に注目したいからである。
このように日本人は、8月15日に、言わば「心を入れ替えて出直した」訳だが、この変わり身の鮮やかさは、アメリカが予期していたような、亡命政府樹立による地下レジスタンス運動などの動きも全く見られず、アメリカにとってみれば、言わば拍子抜けしたといった格好で、アメリカ進駐軍は歴史上最も寛容な占領軍であったなどと評価する向きもあるが、それはこういった日本側のある意味では卑屈とも言い得る従順な態度を抜きにしては、片手落ちの評価だと言わなければならないだろう。
そして、様々な多くの歴史書をこれまで読んできたが、この日本人の豹変ぶりを指摘し考察した著述家は、私の知る限り山本七平だけである。この点で、現在良く知られている司馬遼太郎史観や半藤一利史観などに対して、歴史に対する洞察力という点で、山本七平史観は一つも二つも頭抜けていると言っても良いと思う。
そして、その山本七平の著作で最も名高く、最も読まれている著作は『空気の研究』であろうが、またこれほど理解されていない著作も珍しいのではないかとも思う。

それはこの本が言及される場合は、殆どと言って良い程前半の部分のみあって、肝心な後半の「研究」の部分は、これまた全くと言って良い程言及されないからである。要は、ほとんどの読者は日常生活に感じている、上手くは言語化出来ない同調圧力の存在を、明確に言語化して説明・指摘されれば、それだけで言わばお腹一杯、それ以後は咀嚼できず、消化不良を起こしてしまうといった事のようなのだ。山本は「空体語」と「実体語」という彼一流の概念を使って説明しているが、山本が「実体語」として「空気」を語っているのにも関わらず、「空体語」として理解・消費されて、多くの読者を引き付けているというのは、逆にそれだけ「空気」の強固さを証明していることになってしまっていると言わなければならない。ここでもまた「名声とは誤解の異名である」というテーゼを証明する結果になっているのは、皮肉な巡りあわせである。やれやれ。
これは、山本独特の語法やプレゼンの流儀、さらには「山本学」の全体像を理解した上でないとなかなかと理解しにくいという点にもあると思われるが、この意味で少し前に「山本学」の全体像のアウトラインを掴むのに格好の著作が復刊されたので、ここで紹介しておくのも良いだろう。小室直樹によって、山本独特の語法やプレゼンの流儀の灰汁が中和されて、すこぶるリーダブルな著作になっているからだ。
『日本教の社会学』

それはともかく、山本はこの同じ日本人の豹変パターンを、尊王攘夷から開国文明開化へと舵を切った明治維新にも見ているが、この『空気の研究』の中で、先の「空体語」と「実体語」の天秤モデルとして説明している。詳しくは同書を参照されたいが、「空体語」と「実体語」でバランスを取っていた天秤が、バランスが取れなくなるとひっくり返ってしまい、一挙に反転してしまうことになるという動的なモデルを提示している。
これまでに述べたようにそれが敗戦時に反米から親米へという形で現れ、戦後が始まった訳だが、最近はまたこのバランスが危うくなってきているように見受けられる。これまで「ギブ・ミー・チョコレート=親米保守」が本流だったのが揺らぎだして、「鬼畜米英=反米保守」の言説が顕在化して来ているのはその表れであろう。
さて、現在「終戦記念日」に広く恒例行事として、靖国神社参拝が行われているのは承知の事実だが、私の眼から見るとこれもまた摩訶不思議な行動に映る。例えば、その趣旨からいえば、「主権回復の日」(=「独立記念日」)である4月28日の方が相応しいのではないかと思うのだが、どうやら参拝者達は「終戦記念日」自体にも、「終戦記念日」に靖国神社参拝をするという点にも、何ら違和感を感じていないように見える。
この靖国神社参拝については。その裏付けとなっている「保守主義思想」ともども、次に考えてみたいと思う。
















![憲法改正の流儀[アメリカ編]](https://business.nikkei.com/atcl/report/15/120100058/111400009/fb.jpg)