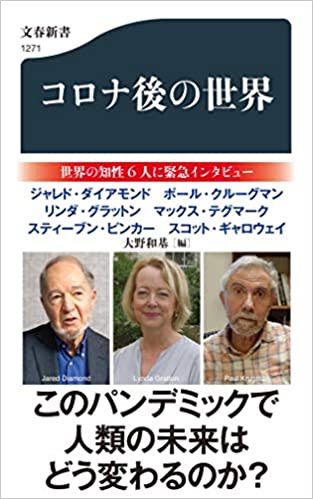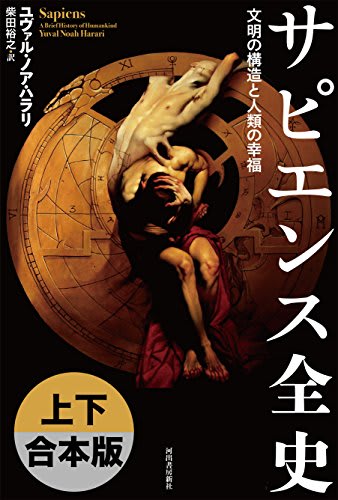いろいろと読書の寄り道をしたため、『サピエンス全史』の上下巻を完読するのに1か月余りかかりました。
概要は中田敦彦のYouTube大学の動画を見て、おおよそ知っていましたが、実際に読むとなるとかなりの量です。興味深い内容であることは確かですが、そのボリュームに相応しく膨大な詳細情報が記載されており、読んで咀嚼するのに時間がかかります。
目次
(上)
第1部 認知革命
第1章 唯一生き延びた人類主
第2章 虚構が協力を可能にした
第3章 狩猟採集民の豊かな暮らし
第4章 史上最も危険な種
第2部 農業革命
第5章 農耕がもたらした繁栄と悲劇
第6章 神話による社会の拡大
第7章 初期体系の発明
第8章 想像上のヒエラルキーと差別
第3部 人類の統一
第9章 統一へ向かう世界
第10章 最強の征服者、貨幣
第11章 グローバル化を進める帝国のビジョン
(下)
第12章 宗教という超人間的秩序
第13章 歴史の必然と謎めいた選択
第4部 科学革命
第14章 無知の発見と近代科学の成立
第15章 科学と帝国の融合
第16章 拡大するパイという資本主義のマジック
第17章 産業の推進力
第18章 国家と市場経済がもたらした世界平和
第19章 文明は人間を幸福にしたのか
第20章 超ホモ・サピエンスの時代へ
あとがき―神になった動物
目次を見ても分かるように、著者は人類史を認知革命・農業革命・科学革命の3つの分岐点で区切って考察します。
「産業革命」は?と疑問に思うかもしれませんが、これは科学革命(プラス資本主義)の結果として起こった変化であり、本質的な革命ではないということです。
人類史において認知革命を取り上げられることは稀だと思いますが、これによってホモサピエンスは、アフリカ大陸の取るに足らない動物から食物連鎖の頂点に立ち得る知能を獲得したので、一番本質的な変化と言えます。
ただ「革命」というと、通常は人間が引き起こす社会的変化を指すので、偶然の生物的な進化と言っていい「認知革命」はその名称に多少語弊があるとは思いますが。
1万5千年前に起こったこの認知能力の変化によってサピエンスはネアンデルタール人よりも大きな集団で協力して計画を立てて実行する能力を勝ち取ったので、他のホモ属を凌駕し、唯一生き残った人類種となりました。
こうして数千年の間狩猟採集民として世界中に拡散していきましたが、およそ7千年前に中東で農業革命が起こります。
この農業革命も「革命」と言うにはあまりふさわしくないと思うのですが、何はともあれ栽培化しやすい穀物に恵まれた土地に定期的に採集していたサピエンスは、そのうち種を蒔き、作物(特に麦)の面倒を見て収穫するようになり、徐々に季節的な移動を止めて、一か所に定住するようになりました。
それは今日的な感覚では非常に緩やかな変化でしたが、人類の歴史を俯瞰するならば、比較的急な変化と解釈できます。
農業革命の結果起きたのは人口増加で、人口増加がまた生産増加につながる性のスパイラルに突入したため、今までにない大きな共同体を形成し、社会を成り立たせる必要が出てきました。
ここで大きな役割を果たすのが「物語」です。
神話や伝説などは言うまでもなく、法律や国家といった概念もサピエンスの想像力の産物であり、そうした虚構を見知らぬ他人と共有することでそれらは集団的に構築された現実となります。
物語の共有とは言うまでもなく価値観・価値体系の共有であり、それに従って社会の階層や主従関係などが構築され、狩猟採集民では想像もつかないような規模の複雑な共同体「国家」の出現に繋がります。
現在、西側諸国を始めとする多くの国で共有されている物語が資本主義・自由主義・個人主義です。思想の土台はヨーロッパで形成されましたが、その価値観の多くは世界中で共有されています。こうした動きが著者の言う「統一に向かう世界」です。中でも最も普遍性がある虚構は、宗教でも思想でもなく「貨幣」です。
「貨幣」が信用に基づく虚構であることは、信用が崩壊して価値がなくなることがある事実からも明白です。これはあくまでも多くの人が紙幣・硬貨またはデジタルの数字を受け入れ、物品やサービスと交換してくれるという相互信用と貨幣発行元の保証によって成立しており、米国と対立しているイスラム教国家でも米ドルを喜んで受け入れるというように、強い通貨は国家ばかりでなく主義主張や宗教を超えて共有されている虚構です。この意味ではサピエンスが作り上げた虚構の中で最強のものと言えるでしょう。
次に訪れる科学革命は、貨幣の力、すなわち資本主義と領土の拡大を求める帝国主義の結び付きによって協力に推進されますが、その出発点は「Ignoramus(私たちは知らない)」という無知の認識です。
知らないからこそ「知りたい」という探求心が湧き、それが調査や研究の推進力になるわけです。
これは全知全能の神が存在する世界観では発展しないと著者は指摘しています。なぜなら、全ては聖書なりコーランなりに記されているはずであり、人間は神の言葉を理解するために努力すれば十分ということになるからです。
ヨーロッパは中世や近世において特別に強力でも豊かでもありませんでしたが、大航海時代に「知りたい」と「富を増やしたい」と「領土を広げたい」が初めて統合され、前代未聞の原動力となり、新しい世界を「発見」して植民地化し、富を搾取強奪することで、それまで強大だった中国やイスラム世界をも凌駕するようになったと著者は言います。
ヨーロッパ人たちはダーウィンの進化論のアイデアを受け入れ、自分たちが優れた人種であるから世界で支配的な地位を築いたという新たな「物語」を語り始め、自分たちの科学や価値観を世界中に拡散しました。
第二次世界大戦後は、特に個人主義と「人権」が新たな物語として語られていると言えます。
何かの宗教やイデオロギーを信じ、唱える人たちは決して認めようとしませんが、どれをとっても「自然の摂理」などではなく、サピエンスの想像力に基づく物語の共有であり、共有主観の虚構に過ぎません。
科学万能主義もその一種です。
「自然の摂理」とは人類が滅亡しても変化しないであろう万有引力などの現象だけであり、それが誰かに認知されるか否かに関わらず存在します。
著者のこの指摘は、宗教や思想的・政治的対立の空しさを的確に示していると思います。
しかし著者は「全ては物語(虚構)」という指摘だけにとどまらず、最後に幸福について考察しているのが興味深いです。
農業革命は、食料余剰と人口増加をもたらした結果、大きな社会と分業化を可能にし、全体的に見れば繁栄をもたらしましたが、個人個人を見ると、一握りの支配階級を除いて皆苦役が増えたり、病気が増えたりして、必ずしも幸せをもたらしたとは見えません。
科学革命も人類に未曽有の物質的豊かさをもたらし、現在のサピエンスの能力を超える超人すら遺伝子工学で作り出せるかもしれないところまで理論と技術双方が発展してきましたが、それで人々はより幸せになったのかと著者は問いかけます。
最後の2章とあとがきは著者の幸福についての考察で、本当はこれを語りたいがために膨大な前置きをホモ属の発生から始めたのではないかと思えるくらい哲学的です。
サピエンスは今また新たな物語を必要としている。