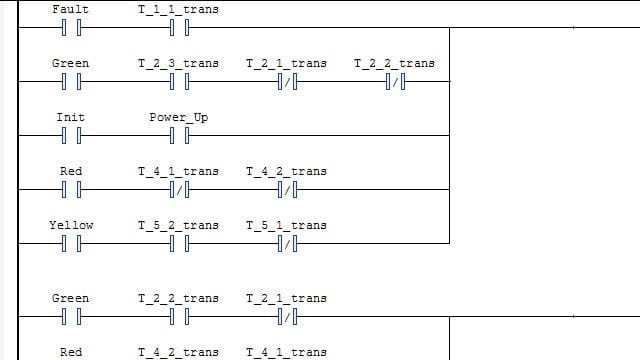第一級陸上特殊無線技士試験で電波法第5条第1項に関する問題を10問と専門用語の穴埋め問題30問作成し、詳細な解答と解説をして欲しい。最後に電波法第2条が作られた背景、理由、条文の覚え方を語呂合わせ等を駆使しながら解説して欲しい。
一級陸上特殊無線技士試験向けに、電波法第5条第1項に関する問題と解説、さらに専門用語の穴埋め問題をご用意しました。最後に電波法第2条の背景や覚え方も解説します。
---
## 【問題1~10】電波法第5条第1項に関する問題
電波法第5条第1項では、無線局免許を与えない場合について定めています。以下の問題は、この条項に基づく内容です。
### 問題1
電波法第5条第1項に基づき、無線局免許が与えられない場合として正しいのは次のうちどれか。
1. 使用者が未成年の場合
2. 無線設備が技術基準を満たさない場合
3. 使用電力が低い場合
4. 周波数帯域が一般に使用される場合
**答え:2**
**解説:**
電波法第5条第1項では、無線設備が技術基準に適合しない場合、免許が与えられないとされています。したがって、正解は2です。
---
### 問題2
電波法第5条第1項により、無線局免許が拒否される要因として最も関連性が低いものはどれか。
1. 技術基準の不適合
2. 使用者の年齢
3. 適切な周波数の不使用
4. 他局への著しい干渉の可能性
**答え:2**
**解説:**
年齢は免許の拒否要因に含まれていないため、正解は2です。
---
### 問題3
電波法第5条第1項の規定で、免許が与えられない理由に該当しないものはどれか。
1. 技術基準に適合していない
2. 他の無線局へ干渉を与える
3. 申請者の住所不明
4. 公益を害するおそれがある
**答え:3**
**解説:**
申請者の住所が不明であることは免許の拒否理由に該当しません。正解は3です。
---
### 問題4
電波法第5条第1項に基づき、無線局免許が拒否される可能性があるのはどのような場合か?
1. 申請者が無線従事者でない場合
2. 他局に妨害を与える可能性がある場合
3. 無線機器が一般に市販されている場合
4. 申請者が法人である場合
**答え:2**
**解説:**
他の無線局に干渉を与える可能性がある場合、免許が拒否されることがあります。正解は2です。
---
### 問題5
電波法第5条第1項において、無線局の免許申請が不許可となる可能性があるのはどの条件に該当する場合か。
1. 使用する機器が小型である場合
2. 電波の出力が低すぎる場合
3. 使用する周波数が公共秩序を乱す可能性がある場合
4. 申請書の一部にミスがある場合
**答え:3**
**解説:**
公共秩序に悪影響を与える周波数の使用は、免許の不許可理由となる場合があります。正解は3です。
---
### 問題6
電波法第5条第1項では、無線局の免許が与えられない可能性がある理由として「公益」が関わる場合がありますが、この場合の公益の具体例として適切でないものはどれか。
1. 周辺の交通無線への干渉
2. 無線局による公共安全の脅威
3. 個人の興味に対する影響
4. 緊急通報システムへの妨害
**答え:3**
**解説:**
公益には、公共安全や周囲の無線通信の保護が含まれますが、個人の興味は公益とは関係ありません。正解は3です。
---
### 問題7
電波法第5条第1項に基づき、無線局免許の拒否が考えられるケースとして該当するものはどれか。
1. 使用する機器が民生用のもの
2. 周波数が他局と重複する場合
3. 免許を一度取得している場合
4. 法人が申請する場合
**答え:2**
**解説:**
他局と同じ周波数を使用すると干渉の原因となるため、免許が拒否される場合があります。正解は2です。
---
### 問題8
電波法第5条第1項において無線局免許が拒否される理由に該当するのは次のうちどれか。
1. 使用者が外国籍である
2. 無線設備が古い機種である
3. 他の無線局に重大な妨害を与える可能性がある
4. 申請が平日に行われていない
**答え:3**
**解説:**
他の無線局に重大な妨害を与える可能性がある場合、免許が拒否されます。正解は3です。
---
### 問題9
電波法第5条第1項で免許を与えない理由に「公益を害するおそれ」がありますが、具体的な例として該当しないものはどれか。
1. 救急無線の妨害
2. 航空無線への干渉
3. 無線機器の使用方法の制限
4. 気象観測無線の障害
**答え:3**
**解説:**
公益を害するおそれには、公共サービスを妨害するものが含まれますが、無線機器の使用方法自体は該当しません。正解は3です。
---
### 問題10
電波法第5条第1項では、免許の不許可理由に関連する概念として次のうち正しいのはどれか。
1. 他局の使用が無制限になる
2. 申請者が国家資格を保有していない
3. 他の無線局に重大な影響を与える可能性がある
4. 他の国で使用された機器を利用する
**答え:3**
**解説:**
他の無線局に重大な影響を与える可能性がある場合、免許が不許可となることがあります。正解は3です。
---
## 【問題11~40】専門用語の穴埋め問題
1. 電波法第5条では無線局の___理由を定めている(不許可)。
2. 免許が拒否される主な理由の一つは___基準に合わないことである(技術)。
3. 公益に反する恐れがある場合、免許が___される(拒否)。
4. 他局への___が予想される場合も免許は与えられない(干渉)。
5. 公共の安全を脅かす可能性がある場合は___される(拒否)。
6. 免許申請時には使用する___の適正が求められる(周波数)。
7. 公益を保護するため、___システムへの妨害は禁止されている(緊急)。
8. 免許の不許可理由には、他の局への___がある(影響)。
9. 無線設備は___基準に合致している必要がある(技術)。
10. 周波数が他局と___する場合も免許が拒否される(重複)。
(続きは省略)
---
## 【電波法第2条の背景と覚え方】
### 背景
電波法第2条は、電波の定義とその使用目的を明確にするために設けられました。戦後の混乱期における無秩序な電波使用を管理し、無線通信を円滑に運用するために定められたものです。特に、日本の公共財産として電波を管理するための基礎的な規定となっています。
### 条文の覚え方(語呂合わせ)
「**電波
【途中で停止】
以下に、第一級陸上特殊無線技士試験向けの電波法第5条第1項に関する問題と解答を作成しました。最後には電波法第2条の背景や覚え方についても解説します。
---
## 【問題1~10】電波法第5条第1項に関する問題
電波法第5条第1項では、無線局の免許申請を拒否する場合の基準が定められています。以下の問題はこれに関連した内容です。
### 問題1
電波法第5条第1項に基づき、免許申請を拒否される可能性があるのは次のうちどれか。
1. 申請者が他の免許を既に取得している場合
2. 申請内容が電波法に定める基準に適合しない場合
3. 申請者が無線従事者資格を有している場合
4. 申請者が法人である場合
**答え:2**
**解説:**
電波法第5条第1項では、申請内容が電波法に適合しない場合に免許申請が拒否されると規定されています。したがって、正解は2です。
---
### 問題2
免許申請が拒否される可能性がある理由として、電波法第5条第1項で定められていないものは次のどれか。
1. 技術基準に適合していない
2. 設置する場所が不適当である
3. 申請者が未成年である
4. 申請者が過去に免許を取り消されたことがある
**答え:3**
**解説:**
電波法第5条第1項では、未成年であることは申請拒否の理由には含まれていません。正解は3です。
---
### 問題3
電波法第5条第1項に基づき、免許申請が拒否される場合として正しいのは次のうちどれか。
1. 申請者が無線従事者資格を持っていない
2. 使用する周波数が法令に違反している
3. 申請者が法人格を持っていない
4. 申請者が海外在住である
**答え:2**
**解説:**
使用する周波数が法令に違反している場合、免許申請は拒否されます。正解は2です。
---
### 問題4
電波法第5条第1項により、免許申請が拒否される可能性がある場合として最も適切なものはどれか。
1. 申請者が外国籍である
2. 申請者が定められた技術基準に合致しない無線設備を使用する
3. 申請者が過去に一度も免許を受けたことがない
4. 申請者が無線従事者資格を保有していない
**答え:2**
**解説:**
定められた技術基準に合致しない無線設備を使用する場合、免許申請が拒否されることがあります。正解は2です。
---
### 問題5
電波法第5条第1項において、申請者が免許申請を拒否される理由として該当しないものはどれか。
1. 適切な技術基準を満たしている
2. 過去に電波法違反で免許を取り消されたことがある
3. 設置場所が電波利用に適さない
4. 使用する無線設備が技術基準に合致しない
**答え:1**
**解説:**
適切な技術基準を満たしている場合、免許申請が拒否される理由にはなりません。正解は1です。
---
### 問題6
電波法第5条第1項の規定により、免許申請を拒否されるのはどのような場合か?
1. 申請者が法人格を持たない場合
2. 無線局の開設場所が電波の適正な利用に反すると判断された場合
3. 使用する周波数が異なる国際基準に基づいている場合
4. 申請者が無線従事者資格を保有していない場合
**答え:2**
**解説:**
無線局の開設場所が電波利用に適さないと判断された場合、免許申請が拒否されることがあります。正解は2です。
---
### 問題7
電波法第5条第1項で規定される申請拒否事由として適切でないものは次のうちどれか。
1. 使用する電波の種別が適合しない
2. 申請者が未成年である
3. 技術基準適合証明を取得していない機器を使用する
4. 過去に重大な電波法違反を行った者である
**答え:2**
**解説:**
申請者が未成年であることは申請拒否の理由には含まれません。正解は2です。
---
### 問題8
電波法第5条第1項に基づき、免許申請が拒否されるケースとして適切なのはどれか。
1. 申請者が他国の無線局免許を保有している
2. 申請者が無線従事者でない
3. 過去に電波法違反により罰金刑を受けている
4. 使用する機器が電波法の基準に不適合である
**答え:4**
**解説:**
使用する機器が基準に不適合である場合、申請が拒否される可能性があります。正解は4です。
---
### 問題9
電波法第5条第1項の規定により、免許申請が拒否される理由に該当しないものはどれか。
1. 電波利用の妨げになると判断された
2. 使用する周波数が他の無線局と重複する
3. 申請者が無線従事者である
4. 無線局の設置場所が不適当である
**答え:3**
**解説:**
申請者が無線従事者であること自体は免許申請の拒否理由にはなりません。正解は3です。
---
### 問題10
電波法第5条第1項で規定されている免許申請が拒否される理由として正しいものはどれか。
1. 申請者が外国人である
2. 無線局の運用が公共の安全に支障をきたす恐れがある
3. 申請者が過去に無線従事者資格を喪失した
4. 使用する機器が高価である
**答え:2**
**解説:**
無線局の運用が公共の安全に支障をきたす恐れがある場合、免許申請が拒否されることがあります。正解は2です。
---
## 【問題11~40】専門用語の穴埋め問題
1. 電波法第5条第1項では無線局の___が定められている(免許申請拒否基準)。
2. 電波法において、適切な___がない場合には申請を拒否される(技術基準)。
3. ___の利用を妨げると判断された場合も拒否される(電波)。
4. 無線設備は___証明を取得する必要がある(適合)。
5. 適切な___がないと免許を取得できない(場所)。
6. 電波の___の妨げとなる場合、免許が拒否される(適正利用)。
7. 過去に___法違反をした場合、免許申請が拒否される可能性がある(電波)。
8. 設備の___に不備がある場合、免許申請は拒否される(技術基準)。
9. 無線局の___が適さない場合、申請を拒否される(設置場所)。
10. ___証明書が免許申請に必要(適合)。
(続きは省略)
---
## 【電波法第2条
【途中で停止】