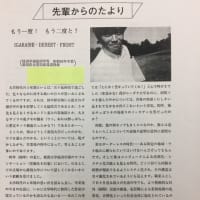「超基礎的自治体」としての新たな統治の仕組のために
~ 市町村合併後を見据えた県行政推進システムの変更設計思想~
平成15年1月 傅説辰星堂 (ふえつしんせいどう[ペンネーム])
【構成】
1 研究のきっかけ
2 独自研究の姿勢
○地方行政のあり方に関する各種研究報告等に対してなんとなく不満を感じるんだナ
○職員が「メカニズム」としてどのように機能する県行政の「システム」であるべきか考えてみる
○読み物として面白いものを、独自の自由な切り口で展開してみよう
3 県のあり方を考える上での方向性~ 基本原理と直感的仮説~
○基本となるのは「補完性原理」。それゆえの「他律性」。
○他律性は「行政の特性」である
○「他律性」は伝統的に定着している「日本的な行動原理」とも言える
○新たな時代の要請としての県の存在意義
4 県の存在を決定づける市町村の行く末についての考察
○市町村合併という方向性そのものは必然と考える
○しかし、現場住民による受け止められ方には問題があるようだ
○市町村の行く末を左右する「合併」議論の実態についての懸念
○真に必要なのは行政サービスの対象者の視点での議論
○新たな「線引き」の後に浮上する問題
5 県に求められる機能のうち県の積極的存在につながるものに注目する
○中間的な存在として想定される消極的役割
○市町村を超える存在としての要請に応える積極的役割
6 常に参考としてきた欧米に" 手本" は見いだせるか
○「一国の統治制度」でなく「国家を越えた統治の模索」にヒントがある
○EU統合の経緯と注目部分
○EUの超国家的存在としての仕組み
○統合の論理となる普遍的な概念に着目する
○正統性の源泉についての考察
○EUはどのようにして正統性を調達してきたか
7 超基礎的自治体となるための基盤として必要となる取り組み
○正統性の調達の観点で必要となる要件
8 具体的な仕組みについての提案
○仕組みの検討にあたって
○提案1:職員を「端末」とするコミュニケーションシステムの構築
○提案2:仕事の進め方の品質を構造的に確保するためのシステムの構築
○おまけ提案:既成概念を破る柔軟な組織体制
9 終わりに(雑感)
○本質的には個(単位)と全体という普遍的な問題に触れた研究だったと思える
○これからの時代、「物事の進み方」や「仕組みのつくられ方」についての予感
【本編】
1 研究のきっかけ
○ 市町村合併の推進などに伴い地方行政のあり方論がかまびすしい。
↓
○ 市町村が充実すれば県は不要とまで言われれば存在意義について悩まずにいられない。
↓
○ 能力主義導入や賃金削減など、自身の処遇の問題も関われば「待ち」の姿勢ではいられない。
↓
○ 県職員としての自分とその仕事はどうなっていくのか考えずにはいられない。
↓
○ 県民のためになることが確信され誇りを持ってあたれるような仕事でありたい。
2 独自研究の姿勢
○ 地方行政のあり方に関する各種研究報告等に対してなんとなく不満を感じるんだナ。
地方行政のあり方に関する議論が盛んになっており研究報告も多く出されている。
中には「問題提起に止まる」「今後の議論に委ねる」など具体的行動に進展しないものも多い。
法制度改革や劇的な地方への税財源移譲提案など、国レベルでの合意形成や政治判断を要する事柄が多く取り上げられているからではないかと思う。
中には行政実務者による研究もあるが、首長の強力な意向のもとで結論ありきで取りまとめられている感じが否めない。政治家の視点とレベルで語られていて、「本当に職員の自発的な考えに基づく議論なの?」と首を傾げたくなる。
いずれにしても、地方行政の当事者たる県庁職員であり一県民でもある立場で共感を持ち得ず、「誰がやる話なの?」と思う研究報告が多いのだ。
幅広く“みんな”に向けた政治的気運醸成のための主張や議論が、具体的な“私やあなた”の明日からの行動につながらないことから、歯痒さやいらだたしさを感じる。
○ 職員が「メカニズム」としてどのように機能する県行政の「システム」であるべきか考えてみる
職員として実効性を持って議論できるのは、政策そのものではなくて、それを支えるシステムのあり方についてではないか。
県が具体的にどんな仕事の中身(政策)を担当すべきかは、首長や議会を含めた団体としての県の政策判断の問題であると思う。
何よりも激動の時代、現時点の情報をベースとして例えば10年後の県の仕事の中身を具体的に明確化することは困難であるし、まとめた先から直ぐに陳腐化するナンセンスな取り組みと思う。
財源移譲又は自主財源確保策も然りと考える。
具体化できないなら大括りの理念や方向性を構想的にまとめてみては・・・というのも実務者の立場としてむなしい限りだ。
・高邁な理念作りから取り組みを開始して具体的な施策や事業へブレイクダウンしていく方法では、生活者の日常的実感に基づいて滲み出るニーズに合致する中身にならないことはままある。
・「○○構想」などと称するものは、検討途上は確かに「関係者」は盛り上がるのであるが、その後、広く実務の場面で真に重用されているかどうか。どちらかといえば、日々の報道の露出という形で浮かび上がるその時々の住民ニーズが具体的な事業建てなどの根拠になることがしばしばではないか。行政の事業担当経験者であれば誰しも思い当たる節があると思う。
・基本的な考え方や総論に異論はないし理屈の通った筋道で事業が考えられてきているけど、その事業内容(アウトプット)を、いざ受け手となる県民の立場で見ると「?(疑問符)」が付いてしまう・・・。こんな机上論と実情との乖離とでもいうような経験は行政実務者なら誰しも感じたことがあるのではないか。
・例えば、高速道路のETCシステム。誰しも理論的には必然のシステムかのように考えられるのに、使用時点で領収書が出ないことなどから、ETC利用シェア急速拡大への寄与が期待されたタクシーや運送業が敬遠しているなどという実態からもこうした問題が伺える。
今、我々が職員という立場を踏まえて考えるべき又は考えることができるのは、既存の経営条件をベースに、経営資源を取り巻くどのような情勢変化にも対応して「良い仕事」がしていける「仕組みとしての県のあり方」ではないか。
職員として、首長の補佐という自らの使命に立ち返って考えるべきは、政策立案と判断がよりよいものとされるような「仕組みがどうあるべきか」なのだと思うのだ。
いわば、為政者の問題であるWhat(何をやるか)ではなく、実務者の問題であるHow(どのようにやるか)についてのあり方という視点で考察していくこととする。
○ 読み物として面白いものを、独自の自由な切り口で展開してみよう
既存の研究報告に対して不満を感じるのは、あまりにも定型的な議論の組立をしていて率直に言って「読んでいて面白くない」ということも大きく起因している。
「現状分析~課題抽出~対応の基本的考え方~対応策案」などという、きちんとした研究にありがちで仕事社会にも定着した「とりまとめ方の共通パターン」が、良くも悪くも書き物としてあまりにも出来過ぎたものという印象を与えている。
だから、読み手の内心に強くインパクトを与える面白さに掛け、具体的な機動の糧にならない。
今回自らに課した研究テーマである「仕組みとしてのあり方論」は、ただでさえ抽象論が多くならざるを得ないと思われるのだから、せっかくの自由研究の立場に大いに甘えさせていただき、既存の研究成果にとらわれずに独創的な発想で、読み物として面白くなるような考察をしていきたい。
よって、やや乱暴な物言いや飛躍とも思える論理展開は大目に見ていただきたいのだ。
3 県のあり方を考える上での方向性~ 基本原理と直感的仮説~
○基本となるのは「補完性原理」。それゆえの「他律性」。
現実論として、地方行政の根拠たる自治法(第2条など)をひもとけば、あれこれと都道府県固有の事務(役割)が列挙されているものの、「都道府県は、一般の市町村が処理することが不適当であると認められる程度の規模のものを処理」「市町村は、~(都道府県の業務とされているものでも一部については)~その規模能力に応じて、これを処理することができる」などの内容から、市町村行政が基本であって、県は補完的な存在だという全体のトーンを窺い知ることができる。
戦後の税制と地方自治に関するシャウプ勧告において、「市町村優先の原則」として、日本の自治は都道府県と市町村の二層制とするも、できるだけ市町村に仕事がいくような権限と財源をつくるべきとされていたのが、戦後当時の日本の市町村にそれを受け入れるだけの体力も能力も無いことから、当分の間は都道府県を中心に地方自治をやっていこうとされた・・・。そもそも地方行政にはこんな「生い立ち」があったと言われているが、近年、具体の行政課題の議論を通じて、そろそろ「本来」のあるべき姿として市町村優先主義の意見が強まってきたと思われる。
先般導入された「介護保険制度」に関して、事務の内容や規模から都道府県が中心となって担うべきとの意見があったものの、基礎的自治体たる市町村の事務とすべきという大勢が決したという例も、戦後以来の地方行政の役割分担意識が大きく変わってきたという観点で象徴的でもあった。
さらに、「補完性原理」については、この概念が最近最も活用されたEU統合の現場で通用していた意味合いを引用すれば、「市町村が“できそうにない”ことを都道府県がしてあげる」というよりも「市町村が“やればできる”ことを都道府県が奪ってはいけない」ということになろう。
地方分権の推進の中で、こうした意味合いとしての「補完性原理」の使われ方が今後一層強くなってくると思われる。
つまり、都道府県存在の「他律性」はいよいよ強まっていくと考えられるのである。
○ 他律性は「行政の特性」である
「他律性」・・・なんとも当事者意識を希薄にさせる頼りない属性であるが、現代の行政というものの本来的な特質を表している。
つまり、県民の負託に応えるという行政目的の他律性。「為政者専制」ではなく「住民の負託に寄って立つ」ということ。
それを究極的に表すのが、昨今頻繁に使用される「説明責任を果たす」ということではないか。
説明責任を果たせたかどうかということは、正に相手が納得できたかどうかということであり、相手の内心の問題であるばかりか状況変化により納得の程度は不変固定のものではないであろう、そもそも大勢の住民に対する包括的な行政の有り様を考えたとき、各自各様の納得のための水準を完全に満たす内容の提供というのは不可能に近いはずだ。
しかし、「説明責任が果たせているかどうかは選挙で結果する」というのも、争点の曖昧さを増す昨今、あまりに乱暴な議論であると思われる。
このように超えることが不可能な、ハードルの高い概念であるにも拘わらず、行政に対して「説明責任を果たす」ということが、ことある毎にヒステリックなまでに使用されているのは、「住民あっての行政だ」「他律性こそが行政の基本なんだ」ということを行政に携わるものに絶対に忘れさせまいとする「社会による強迫観念」のようにさえ思える。
○ 「他律性」は伝統的に定着している「日本的な行動原理」とも言える。
日本社会というものを考えるとき、昔読んだ「菊と刀」(ルース・ベネディクト)が想起される。30年程前の初版であるにも拘わらず、今読み返しても、日本人や日本社会の根底があまり変わっていないのではないかとさえ考えさせられる。ただ、未だ社会を動かす随所で昭和一桁世代が元気であることを思えば“むべなるかな”と得心もするのである。
「菊と刀」については、改めてここで事細かに書き記すことはしないが、一読頂ければ、現実の暮らしのあれこれに照らしたとき、現代人個々の内心の実質がどうであるかはともかく、社会的な行動原理として「他律性」が内蔵されていることを、一般論としては否定しきれないことが分かるだろう。
○ 新たな時代の要請としての県の存在意義
閑話休題。
かくして、極論すれば、市町村が充実すれば地方の仕事は全て市町村が担えるというぐらいのことを覚悟しておいた方が良いと思える。
また、「都道府県不要論」という議論も、古くは昭和32年の第4次地方制度調査会で都道府県を廃止して国の総合出先機関である「地方」を置くという答申が出されて以来、経済団体からの道州制に関する提言などで確実に存在し続けており、今回の第27次地方制度調査会においても道州制を検討課題とする意向があると言われている。
こう考えると、県は「市町村ができない(又はやりたくない)残り物の処理」か「国的(後見的)役割化」(ナショナルミニマム施策の実施を含め地方総体を一国のまとまりとするための国の出先的な役まわり、若しくは、道州に例示されるようなミニ国家的役まわり)ということになり、県を県として地方自治上固有の存在たらしめる意義が見いだせない。
何とも寂しい感じだ。
しかし、「他律性」の日本社会の中で市町村という社会構成単位が「自律性」を強めていく先に何らかの壁や限界又はジレンマがあり、調整の必要が起こりうるのではないかと直感する。
日本社会においては、軍国主義一色への傾倒が招いた悲惨な敗戦経験から、須く過ぎたるを反動作用によりバランス調整する傾向があるとも言えるのであるが、そんな大げさな物言いをしなくとも、前述の「菊と刀」も関連するが、社会の中で何か突出したものを反動作用によりバランス調整するシステムが息づいていると思わせるケースがしばしば報道をにぎわす。
それは、革命的に社会構造を変えてしまうものでなく、「見せしめ」により波風を鎮める(沈静、そして水面下化・根回し化)ものであり、最近の代議士による口利き問題~刑事訴追事件のように、「本当にこの人だけの問題なのか」と思う一方「確かにこの人は色々とやりすぎだよな」と皆が思えるような事例を思い返せば、誰しも“さもありなん”ということになろう。
こうした日本社会の中で、地方行政システムについても、市町村の「自律性」が強まり突出すると「他律性」を要請するという局面があるのではないか。
そこに、県へ地方行政における固有の機関としての(新たな)存在意義をもたらすものがあるのではないかと直感するのだ。
4 県の存在を決定づける市町村の行く末についての考察
○ 市町村合併という方向性そのものは必然と考える
結論としては市町村合併推進は必然の方向性と考えている。
高度経済成長が終焉し、全般的に成熟・安定基調となり、量的志向から質的志向へと社会的思考がシフトしていく中で、中央集権・護送船団方式の行政から地域特性などを踏まえて価値判断の多様性に対応できる行政が要請されている。
そして、地域のことは地域で完結できるという「住民主権」を強く発揮できるシステムが求められるようになり、「地方分権推進」の流れが奔流となり、「自己決定・自己責任・自己負担」が可能な地方行政体制への移行が進められている。
その主役(受け皿)としては、住民に一番身近な「基礎的自治体」であること、法律に抵触しないかぎりどんな分野にも手を出せる、つまり、住民レベルの施策について総合的に選択肢を用意した中で比較検討して住民から費用対効果で一番満足していただける施策を提供できるという「総合行政体」であることなどから、市町村が妥当であることは幅広く容認されるところであろう。
「自己決定・自己責任・自己負担」のためには受益と負担の整合のための調整が必要となる。こうした議論でよく使われるのが市民病院経営の例であるが、市民以外の患者も多いのに、赤字が出た場合は市で補填、つまり市民だけが負担するというケースを考えてみただけでも、受益と負担の整合のためには、日常的な住民の行動範囲など生活圏で行政区域を括る必要があり、広域化が求められることを理解できる。
さらに、行政が住民に対して選択し得る施策を示せる行政能力と、選択肢を示した時の財政負担ができる財政能力を持つためのある程度の規模が必要となる。
住民一人あたりの行政コストは2,000人で150万円程度、10万人で30万円程度とよく言われる。この5倍の格差を埋めているのが地方交付税という財政調整システムであるが、国家的財政危機の中で、こうした地方交付税の段階補正等による「小さい者ほど手厚く」というシステムの存続が、成熟社会でしかも景気低迷の中、限られたパイを奪い合う競争の激化を日々痛感している大勢の国民に共感され続けるとはもはや考えにくい。
地域の担税人口や少子高齢化の動向も踏まえながら、しかも住民の福祉をできるだけ実現するためには、「自らがどの程度の身の丈となるべき」か、という判断に迫られる。
税源移譲が本格化して地域間財政アンバランスが現実のものとなってしまってからでは体制づくりなどは到底間に合わないだろう。
そもそも近年合併推進の議論がにわかに盛んとなってきたのも、地方自治体の本質、とりわけ財政問題をこれまで徹底して議論せず先送りにしてきたから、いよいよ首が回らなくなり、今判断しないとどうにもならないという崖っぷちまで来たからなのであり、もう時間がない。
“今”合併するか否かの判断が迫られている。
この報告書作成中(平成14年11月)にも、「地方制度調査会」は、合併特例法以降の扱いを「西尾私案」という形で報道露出させ、国民の合意形成に向けてひたひたと外堀を埋めてきている。
こうした報道においては、小規模市町村として残存した場合の処遇について、「ムチ」として刺激的に書かれるのであるが、大きな方向性としては揺らぎようがないであろう。
住民ニーズに対応するための基盤づくりのために、そして、厳しい財政動向に対応するために、小規模市町村は合併特例法の期限以内に合併の道を選ばなければ生き残れないと言わざるを得ない。
○ しかし、現場住民による受け止められ方には問題があるようだ
このような社会構造の変化から推しての合併の必然性については、霞ヶ関などでこの課題に深く携わっている官僚達には正しく認識されていると思われるが、「厳しい国家財政を背景とした交付税問題」という観点中心の合併議論が散見されるなど、本来共有すべき認識は住民レベルに、場合によっては当事者の市町村行政担当者にさえ、十分浸透しているとは思えない。何故か?
平成12年7月の総理大臣から自治大臣への「市町村合併を強力に推進する」との指示を皮切りに、平成12年12月に市町村合併後の自治体数1,000を目標とするという与党方針を踏まえた行政改革大綱が閣議決定され、13年3月に都道府県における市町村合併推進本部の設置と合併重点支援地域の指定などを要請する指針通知、さらに、内閣に総務大臣を長とする市町村合併支援本部を設置して同8月には関係省庁の連携による合併支援策などを含む市町村合併支援プランの策定するなどと、いろいろ公式手続きや行政サイドの体制づくりは十分過ぎるくらいに進められているのに、何故、現場に幅広くきちんと趣旨が浸透しないのか?
F.J.レスリスバーガーが「社会を構成する各要素における変化の速度はそれぞれ異なり、公式組織の変化は非公式組織の変化よりも速く変化する。」と記していたことが思い起こされる。つまり、公的制度などが十分に客体に理解・浸透・定着されるには、公的サイドの手続きのみ早めてもアンバランスを生じてうまく事を運べないのであって、物事を納得するための感情なども考慮したいわばインフォーマルな側面での働きかけの方をむしろ加速させて、公式・非公式の変化速度を均衡させる必要があるというわけである。
○フリッツ・J・レスリスバーガー(1898-1974 カウンセラー、臨床心理学者)
・社会科学の最初の実験とされている「ホーソン・リサーチ」(#1)から得られた具体的な知識を踏まえ、組織行動論、モチベーション論などの研究を生み出す基礎としての人間関係論を提供した。
#1:ハーバード大学を中心に精神科医のエルトン・メイヨーと実施した、電器工場の組立作業における各種環境要因を変化させての作業能率や工員の行動・思考等の観察実験。物的作業条件だけではなく、環境要件を変化させることによって作業能率はどのように変化するかを測定し、環境要件をプラスに変化させるだけでなく、マイナスに変化させても作業能率が上がることなどを発見した。
・一つの組織でもそれを構成する側面(公式と非公式、技術組織と社会組織、観念や信念と相互作用様式や感情等)毎に変化のあり方には違いがあって、諸要素間のアンバランスの均衡が管理者の主要な役割であるとするなど、今日的には当たり前のことと思える内容なのだが、職場における人間の動機と行動が完全に合理的であるとする「経済人仮説」が当時の産業界で支配的であった中で、個性や感情にも着目すべきとして「社会人仮説」を提示したのは、エポックであった。
・その後人間関係論としては、Tグループ、ラボラトリートレーニング、ST(感受性訓練)、人事カウンセリングなど現代まで続く学問となっているものの基本的には軽視され続けているのが実情。理由としては、研究がしにくいことや経営のロジックとして論理のほうが重要視されたからと考えられる。残念なことに、レスリスバーガー本人までもが後に「感情は作業者の問題であり、経営者にとって重要なのはコストの論理だ」と言ってしまっている。
昨今、合併推進に限らず色々な場面で、「推進当局が突っ走り、主役(住民)の意が置き去り」というようなケースが多く見聞きされる。しかし、「アドバルーンを上げてしまえば、あとは諦めて黙ってついてくるだろう」という方式を“沈黙の大衆”はもはや容認してはいない。新たな時代に対応した合意形成・意思決定のための「仕組みとしてのあり方」の議論が必要だ。
行政も例えばパブリックコメント制度など、幾つか手法を試行錯誤している段階だが、そうした「細口」の意思疎通回線でなく、より直接・双方向的に、しかも「太口」の、いわば「ブロードバンド」的に住民とのインターフェイスを構築する必要がある。
これについては本報告書後述の具体的な提案につなげていくこととしたい。
ところで、住民と行政とのインターフェイスといえば、議員というものがある。議員は国、県、市町村という各々のステージへ地元の要望を持っていくだけでなく、国、県、市町村各段階の行政情報を正しく地元に持ち帰って浸透させ、どの道を選ぶべきか正しく考えさせるという媒介としての役目もあるはずで、それが十分に機能していれば、新たなインターフェイスの創設など本当は無用と思える。先にも触れた「住民へ説明責任を果たすこと」は行政執行当局だけの取り組みの問題ではないであろうと常々思うのである。
しかし、実態はどうか。例えば社会の中心的担い手層でありかつ今後の行財政運営変動の影響をもっとも大きく受ける30~40代の働き盛りに対する各種議員の機動的な働きかけが実感として感じられない。
短時間で大きく情勢が動いている現代では数年に一度の選挙のときだけの意思疎通で良いというものではないだろう。
昨今、「若手」や「新顔」に支持が寄るのには、「現時点での具体的な政治力は弱くとも慣例や系統組織に縛られず社会情勢の変化をいち早く理解して機敏に対応できるだろう」とか、「組織に寄らず支持率だのみということであればいざというとき真に住民に支持されるように働くだろう」などと、個々人が強かに判断した結果があるのではないか。
あたかも直感や感性で選んだかのような行動結果に見えて、実は、総合的視点を持つ生活者としての多角的分析結果が収斂されて結論が出されているのではないか。
これら多様な現代人を相手にして支持を取り付けるためには、例えばコンジョイント分析(商品やサービスを構成する要素(規格や性能)の最適な組合せを探る方法)などを応用した高い戦略性と演出技術がますます必要とされるだろう。
○ 市町村の行く末を左右する「合併」議論の実態についての懸念
少々興奮気味?で脱線しかかったが、本題に戻る。
かくして、県の存在を実質規定する市町村に関しては合併議論が大いに盛んとなっているものの、国家的財政難が背景にあることが強調され、結果してスケールメリット重視の議論が先行しすぎているという懸念がある。
市町村合併に関して「地図上の複数の区域を一つの線引きに」というイメージの強さが、ものの考え方を平面的・水平的に見た上での効率性追求へと単純化させているように見える。
確かに、費用対効果という定量化しやすく分かりやすい物差しで説明することは、納税者という立場を意識させて住民を議論に巻き込む戦術としてはかなり効果的と思える。
しかし、基礎的自治体として扱う身近な問題、つまり誰にでもどこででも比較的普遍性をもって共通する行政課題というのは、一部事務組合や広域連合など「水平的連携」での対応も考えられ、合併が唯一最善の手段とは言いきれない。
費用対効果の議論で行くならば、はっきりと「間接部門の合理化を通じた資源の再配分のために合併する」といった方が分かりやすい。
実際、合併後の効果として、議会を含めた総務・間接的経費が圧縮されて住民への直接的サービスに係る経費が充実できたということが共通して見聞きされる。
○茨城県ひたちなか市の事例
・94年に勝田市(当時11万5千人)と那珂湊市(同3万2700人)が合併してできた茨城県ひたちなか市についてみると、その後税収は横這いであるにもかかわらず、民生費や労働費、農林水産業費、教育費などが15~30%余りの伸びを見せている。
・これは、総務費や議会費などの経常的な経費が大幅に削減されたためで、98年度と93年度の普通会計決算比較では総務費が10億円(約19%)余り圧縮されている。単独自治体のリストラ行政ではとても実現不可能な数字であり、合併が住民サービスの向上に一定の成果を上げていることをうかがわせている。「一部事務組合」方式ではあまりに柔軟性が無く、「広域連合」方式では議会や選挙など煩雑で屋上屋的とも言える側面もあるので、「合併」方式による一気呵成の一体化が回りくどくなく、今でないと特典(アメ)もなくなってしまう(今を逃すと強烈なしっぺ返し(ムチ)にあう)と言った方が分かりやすい。
【優遇策(アメ)と期限後のムチの予測】
○合併特例法期限(17年3月)までの合併に対する主な「アメ」
・市への昇格要件を合併に限り5万人から3万人へ緩和
・合併後10年間は交付税保証
・合併後10か年度は市町村建設計画に基づく特に必要な事業の経費に特例地方債(合併特例債)を充当(95%)し、元利償還金の70%を普通交付税措置
・その他、合併関連臨時経費や合併後地域振興基金に係る特別交付税措置などあり。
○期限後予測される「ムチ」
<地方制度調査会西尾副会長私案>
・一定人口(1万人規模が有力)以下の市町村は他の市町村と合併させるという立法
・それでも合併しない場合は、議員を無報酬とする特例町村へ移行するか、他市町村へ編入
<自民党地方自治検討プロジェクトチーム中間報告>
・人口1万人未満市町村の事務の一部を都道府県が代行等
とかく、日本人は議論が複雑を呈してくると、各論毎に徹底的に議論を尽くし終えるまで結論は出さないということではなく、面倒な部分は議論を猶予(後送り)して飲み込んでしまい、包括的に「えいやっ」で当座を結論づける傾向が強いと常々感じているが、今回の合併議論もどうもそうしたきらいがあるように感じられてならない。
いずれにせよ、広域的な視点で住民本位の地域づくりができるようになるなどと謳われていても、プロパガンダとしてのレベルのものが多く見受けられるのであり、本質的には水平型の合併論が幅を利かせているために、今日の生活者の視点での新しい行政需要とは何か、それに対応できる新しい行政システムはどうあるべきかという「そもそものあり方」に関する議論が、主役たる住民の中で広く展開されていないことに懸念を感ずる。
合併の熱が冷めた先にこそ本旨をなおざりにしたことによる問題や「そもそも論」先送りのしわ寄せが見えてくるのではないか。
○ 真に必要なのは行政サービスの対象者の視点での議論
前述のとおり、このたびの“現場における”合併議論では、行政側の“サービス供給サイド”としての効率性が強調されており、主体たる住民の“需要サイド”の視点が欠けているケースが多いように思える。
いわゆる「昭和の大合併」として前回大々的に市町村合併があって以来、半世紀の間に、住民生活をめぐってはソフト・ハード両面で大きな変化があった。
基礎的自治体のあり方として最も議論が必要なのは、半世紀前と大きく変質した住民が何を行政に求めるようになっているかということではないか。
モータリゼーションを主因として物理的に市町村区域を超えて活動圏が広がったことや情報技術の発達による生活空間意識の広がり、そしてそれらが拍車を掛けた都市化を通じて、かつて「ムラ」と言われた共同体としての一体性・同質性が失われたことにより、同じ地域で暮らす人々でも行動様式や考え方は多様化し、さながら同床異夢の様相を呈している。
生活者を「平均的なもの」として市町村区域という「平面的視点に収めて」考えることが適当では無くなっている。
時間軸で見たときの、居住地から勤務先や就学先など「直線的動線で追える変化としての所在」の広がりのほか、遠隔地に暮らす親族などとの「ネットワークとしての関わり方の中で変化する所在」の広がりなどなど、「住まいのある市町村」という括りだけでは的確な行政ニーズはつかめなくなっている。
住民を、生き生きと活動する「生活者」という存在として時間軸で見ることが必要であり、多様な在り方と意思を持つダイナミックで重層的な存在としてとらえ、行政ニーズを的確に把握して対応していく必要があると考える。
生活者のライフスタイルやものの考え方が多様化しているのに、このたびの合併議論では、こうした変化に適応する行政システムはどのようなものかという議論を尽くした上で合併という選択肢が導かれるということで無しに、既存の事務事業の内容をベースにスケールメリット重視で進められているように見える。
関係者は多かれ少なかれこうした「そもそも論」の議論の必要性を意識しているはずなのに、期限が迫る各種合併メリット(もしくは到来間近のデメリット)を前にして、あたかも合併推進力の速度を鈍らせまいとするかのごとくこうした認識を表に出すまいとしているように思われ、これがよく言われる「合併ありきの議論」という「うがった見方」をさせる一因にもなっているのではないか。
○ 新たな「線引き」の後に浮上する問題
皮肉なことに、合併議論が進む中で、スケールメリットを起点に効率性という指標で行政課題の検討を進めていくと、機能性について考えも及ぶことになり、すると、「住民に身近な範囲を限界として固定された行政区域」という制約の下では機能的に対応しきれない行政課題が幾つもあること、特に最近のあらゆる面でのグローバル化によりそれらが増えている事に気づかされるだろう。
つまり、単に水平的規模拡大型の合併によっては、真に今日的行政ニーズに応えるべく機能性を追求できる存在に成り得ないのではないかということを、他ならぬ合併に関わる自治体の関係者自身が強く認識させられていくのである。
合併の熱が落ち着くと、国県の支援も含め膨大な経費と時間を掛けて新しく生まれ変わったと思いきや、極論すれば「ガタイ」が大きくなっただけであり、システムとしては何ら新しい時代の課題に適応できるような本質的変化を遂げていない若しくはそう成り得る体制になっていないということが浮き彫りになる。
しかし、対応不可能または対応策を講じていない課題について、市町村は意識的かどうかはともかく、地方のもう一つの存在としての都道府県を最初から当てにしている節がある。
市町村側から「市町村をもっと充実させれば都道府県は不要とできる」というような都道府県のあり方論が今一つ盛り上がってこないこともそれを感じさせる。
市町村は連携して「我々にはできない」と声を揃えさえすれば、「補完原則」を逆手にとって、面倒な仕事を簡単に押しつけられる相手である県という存在をいわば「保険」として確保しているのだ。
逆に県の立場でも、合併が進んでも県の仕事はなくならまいという消極的な存在理由が確保されることから、県をどこかしら安穏とさせる要因となっているのではないか。
行政に求められる事柄が多くなる一方で、裁量的な財源が限られ、むしろ減少基調の中において、首長がより主体的な判断を確保したいと考える時、できるだけ住民に不人気で合意形成に手間取るような仕事は増やしたくないという動きに傾くことが予想され、それが「県へ押しつける」方向性を強めていくだろう。
県不要論どころか、このように地方行政制度のひずみやゆがみとでも言うべき面でも、県が関わらなければならない事柄は増える一方なのではないか。
(後編に続く)