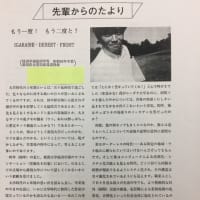▼昭和の修学旅行は京都と奈良(その3)
~法隆寺、春日大社、若草山、二月堂、三月堂、大仏殿、奈良公園、二条城~
昭和54年5月9日は柏崎市立第二中学校三年生の修学旅行の二日目。初日は10時間近くに及ぶ列車移動であり、宿舎居室も狭く二段ベッドで4人の相部屋とキツかったが、十代の我々は非日常感に高揚していたので、全体として元気な雰囲気だった。
この日の日程は奈良方面ということで京都駅前の宿所からは遠い。その距離感を今でこそ分かるのであるが、旅行で遠出することなどなかった私は日程表で記されたとおりに集団の中で言われるがままの行動だった。
それにしても、ホテルで朝食を終えると早朝から1時間近くかけて近鉄デパート前にぞろぞろと歩き、そこで待ち構えたバスに乗り込んで2時間かけて「法隆寺」に向かうという3時間に及ぶ移動は、前日の旅程による疲労と夜の大騒ぎでの寝不足による意識を更にぼんやりとさせていたようだ。
そんな心身状況だったから心に焼き付けられなかったのか「法隆寺」の印象が中々思い出せない。日本最古の木造建築、教科書参考資料でカラー刷りで見て魅力的だった釈迦三尊像、そして子供心にも日本的な美しさを感じさせる造形の五重塔や金堂など、修学旅行の行程の中でも楽しみにしていたはずなのに、記憶に蘇ってこないのだ。
それは疲れや寝不足だけでなく、やはり参拝の仕方に問題があったのだと思う。
とにかく、行く先々のいずれも早歩きで慌ただしいのだ。移動時間が旅行日程を圧迫して肝心な視察がじっくりとできない。せっかくの京都や奈良への訪問で、しかも二泊三日もかけながら、この地に来ることだけが目的化してしまっていたようだった。
思い返して恨み節を言うのは簡単だが、当時の交通事情や大勢を事故無く引率するリスク、限られた旅行積立金などの制約を考えればむべなることかとも思う。
そんなわけで、まさに駆け足のように通り過ぎた「春日大社」や「若草山」も、今の私にはその風情すら記憶に残っていない有様だ。
それでもやはり大仏を擁する「東大寺」はさすがに鮮明なイメージとして残っている。思っていたよりも大きくないなという印象ではあったが、仏像として見たことのない大きさには息をのむ思いにさせられたものだ。日本人は狭い島国で慎ましく生きてきているはずなのに、むしろその反動なのか、やたら大きなものを造り崇め奉りたがるものだとも感じていたと思う。
余談だが、大仏殿を支える太い柱の一本の下部に四角い穴が開いていたのが気になった。観光客の一部が通り抜けしていたように思うが、我ら大勢の修学旅行団体では、さすがに人数的に停滞していまうので、体験した生徒は居なかったのでは。どうやら無病息災の願掛けになるようであるが、太目だった私はそもそも引っ掛かって抜けなくなっていたかもしれないのでスルーして正解だったかも。いまも一応健康に過ごせてるので悔いなし。
「東大寺」では大仏殿に続けて「二月堂」「三月堂」という建物を観たのだが、リレー作文を書く担当箇所になっていた「三月堂」は事細かに造形や普請材の新旧などを一生懸命に観察したことを覚えている。しかし、私自身の気持ちとしては「二月堂」に魅かれた。三月堂に比べた雰囲気的な好みに加えて、松明の火の粉を振りまきながら催すという1200年以上続く”お水取り”のことが何故か印象に残ったから。詫び寂びある寺社からは想像できない派手な行事の話が私の琴線に触れたのかもしれない。
「奈良公園」では、野放しの鹿たちを見るとやはり珍しく思え、例のせんべいを買って与えている生徒もいたのでは。お辞儀のように頭を下げて寄ってくる姿は微笑ましくもあったが、せんべいを争う場面などを見ると獣の猛々しさも垣間見えた。公園の広さの割に数が多くて面倒見が大変そうだななどと無責任なお節介を考えていたと思う。
教科書で見て期待を膨らませていた奈良の古刹や名所もまあこんなものかと思いつつ、宿所のある京都市内に戻る途上で二日目の最後に立ち寄ったのが「二条城」。ここでこの度の修学旅行の中で予想外に大きな感銘を受けることになった。
低い木造建物であると知っていたので名ばかりの城なのだろうと軽んじていたのだが、その佇まいと内装の豪華さには圧倒された。あの徳川家康が上洛した際の居城としたと聞けば権勢を誇示するような絢爛さは納得が行くし、何よりも400年を経ても、廊下や広間のスケールや造作、装飾に見劣りが感じられない。城内を見て回る先々で息をのんだ。城といえば山城、櫓、天守閣などと思い込んでいた私の概念を覆す経験だった。
「二条城」での興奮冷めやらぬままホテルに到着。二泊目なので利便も不便も慣れたものだったが、夕食時に前日同様の洋食仕立てだったところに割箸が配給されたので、私を始めてナイフとフォークの不得手派は大いに喜び、楽々と食べられた。ホテルのスタッフから見れば正に田舎育ちの集団のように見えただろうが、恥ずかしくも”てらい”も無い我々だったのだ。
お風呂はどうだったかと思い返すが、大浴場とはいえ広くなく質素な設えで、クラスごとに次々に”投入”されていたので、ため息を吐くようにゆっくり入れたという記憶がない。明るくない照明の下で、まさに芋の子を洗うような、ごった煮のような、そんな雰囲気だけを覚えている。
お喋りだゲームだなどと、なんだかんだで騒いで過ごしていると京都での二晩目も更けて消灯時間になり、疲れもあってバタンと寝入ってしまったように思う。
☆「活かすぜ羽越本線100年」をスピンオフ(?)で連載始めました。
☆「新発田地域ふるわせ座談会」を日記と別建てで連載してます。
☆新潟久紀ブログ版で連載やってます。
①「へたれ県職員の回顧録」の履歴リストはこちら
②「空き家で地元振興」の初回はこちら
③「ほのぼの日記」の一覧はこちら
➃「つぶやき」のアーカイブスはこちら
☆新潟久紀ブログ版で連載やってます。
①「へたれ県職員の回顧録」の履歴リストはこちら
②「空き家で地元振興」の初回はこちら
③「ほのぼの日記」の一覧はこちら
➃「つぶやき」のアーカイブスはこちら
↓柏崎市立第二中学校修学旅行以来40年ぶりに京都を訪れました。