いまだに避難所や親戚宅に避難しているフィリピン人70万人を救援するために何ができるでしょうか?




フィリピン地方自治体が被災者へ提供できるものは少なく、国民の期待度は低い。数日か一週間ほどの飢餓からの一時的な救済?おそらくその程度である。
フィリピンの特定の地域に強い台風(激しい洪水を伴う)が襲来すると、学校、避難所や屋根付き広場が大規模な避難キャンプに変わることは間違いありません。
フィリピンではさまざまな要因により、避難所に取り残された避難者が国や世界中の人々からのわずかな援助に頼っているような絶望的な状況を数多く目撃しました。
大半の人々は洪水で家を失いました。換金作物は台無しになり、これらの人々のほとんどはごく普通の「その日暮らし」の生活で生き延びているため、再び国から支給される救援物資に頼ることになります。
救援パック(フィリピンではこう呼んでいました)には、米 2 kg、缶詰食品 10 個程度、麺類、食用油 1 本、インスタントコーヒー 2 袋 6 個、砂糖、蒸留水 1 リットル、頭痛薬と下痢薬が数個入っています。この救援パックは、家族の人数に関係なく、1 世帯分で1パックです。
フィリピン人は自然災害に対して強い、それは本当です。そして、これらの人々が全面的災害による部分的または全面的な被害を受けた場合、(地方自治体の職員が収集したデータが不十分なため)無視されることがほとんど多く、彼らが期待する支援は一時的な救援パック救済に限られているようです。
毎年同じように被災していながら、インフラは全く改善されることなく、押し寄せた泥水洪水の中で水泳をし、瓦礫の中から衣服を収集、瓦礫を集め臨時的な住居を設置する。そしてその日暮らし、あるいは首都圏へ出稼ぎに出ている家族からの送付金での生活をする。
農業や漁業に従事していても、獲れる収入はフィリピン法律の最低賃金法などは全く無視されたわずかな賃金。
しかし、多少災害から復旧しても、また新たな台風、あるいは大洪水に見舞われる。
その繰り返しを延々と現在に至るまで生活の一部として行なっている。
特に、ビサヤ、ビコール地方には自然災害復興という対策はないのかとも思えます。
フィリピンがこれから発展するには、自然災害に強い住宅、電気水道の確保、河川改良、道路網の充実、鉄道の拡大など上げたらキリがないほどあります。
一面が海のようになった洪水現場をヘリコプターで視察しても、その対策を率先しない限り、国は良くならない。もちろん、いまだに続けられている役人によるコラップも大きな問題点である。
ASEAN(東南アジア諸国連合)諸国でも、スーパー台風の襲来や集中豪雨による大洪水から少雨・干ばつまで、異常気象といわれる自然災害が確実に増加しており、現地企業の事業の継続・発展を脅かしている。とはいえ、アセアン各国ごとにその自然災害の実態は大きく異なる。
災害列島/災害大国と呼ばれる日本と同じように地震・津波、台風が発生しやすいフィリピンやインドネシア、自然災害の発生が比較的少ないとされるシンガポールなど、様々な特徴が見られます。
その中でもフィリピンの災害の弱さは、アセアン10ヶ国中ワースト1位はフィリピンで世界171ヶ国中2位、日本は17位にランキングされます。ちなみに1位はバヌアツ(WRI:36.50)、3位はトンガ(同28.23)と地震・サイクロンに脅かされる南太平洋諸国が占め、最も危険度が低い171位にはカタールがリストアップされています。エクスポージャー(自然災害の危険にさらされている程度)をみるとフィリピン、日本とも高いものの、両国の対処能力と適応能力の大きな差がWRIの数値の差に結びついている。
フィリピン政府は、各地域における自然災害リスクの特徴と実態をしっかり把握した上で、想定される事態に備えることが重要である。大統領はじめ政府官僚、経営者から管理者、現場の従業員に至るまで、それぞれの役割に応じた意識・感性を持ち続け、ソフト・ハードの両面から対策・取り組みを継続して発展させることが必要とされる。
しかし、フィリピンのこの問題解決は非常にハードルが高く、結果はいまだ対策をしていないのだと思える。

























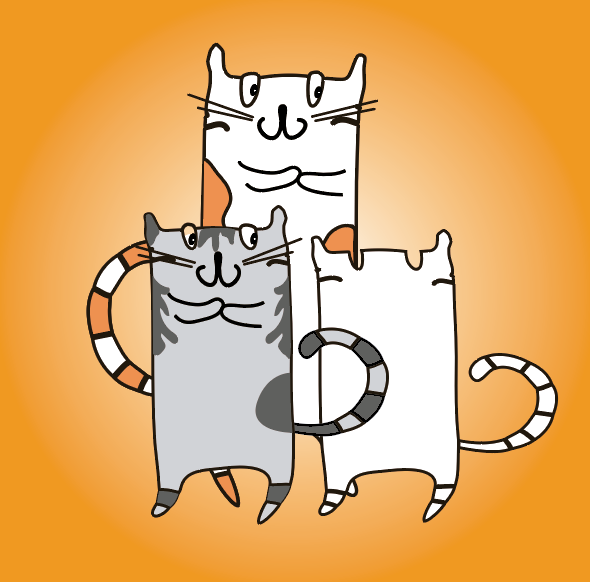

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます