1930 年代に中国人女性に焦点が当てられたのは、中国人女性が奴隷化され人身売買されていると考えられていた約 60 年間の植民地時代の言説を引き継いだものでした。
この研究は性を売る女性に関するものであるが、奴隷制の歴史には家事労働に従事する少女も含まれており、彼女たちの性産業への経路が必要な背景を提供している。

Mui tsai(奴隷制度廃止論者によって「奴隷少女」と訳されている)は、家事使用人としてしばしば海外で契約されている約 7 歳から 13 歳の中国人の少女たちであった。
奴隷少女論争が香港で始まったのは1870年のことで、ジョン・スメール裁判長が売春宿に売られた奴隷少女をめぐる裁判を行った。
歴史家は1930年代後半までこの慣習を追跡し、マリア・ジャショクは1927年に中国から来た10歳の少女の売買証書を引用している。
マリア・ジャショックは、1927年に中国から来た10歳の少女の売買証書を引用し、奴隷少女がいったん売春宿に転売されると、「あるいは女たちに飼われ、
その稼ぎで生活していたため、少女たちがその生活から抜け出すのは困難だった」と結論づけた。
シンガポールに関するジェームズ・ウォーレンの研究でも同様に、「身の処分をする権利のない売られた売春婦」を指すのに、コンチュウ(文字通り「王女」)が使われていたことを指摘している。
多くの歴史家が、中国人女性の奴隷制に関するこうした物語を問題視してきた。
サラ・パドル(Sarah Paddle)によれば、イギリスの奴隷廃止論者たちは、中国の女性は子供のようで、沈黙を守り、受動的であるというイメージを広めようとした。
レイチェル・レオウ(Rachel Leow)は、スメールが「普遍的な道徳に対して中国の風習を投げかけている」と示唆した。
香港では1923年に女性家事サービス条例が制定され、禁止されたにもかかわらず、家事サービスは続けられ、国際連盟の奴隷制度委員会でも取り上げられた。
しかし、マガリー・ロドリゲス・ガルシアによれば、国際連盟は奴隷少女現象を売春を目的とした「女性と子どもの往来」とは別の問題と判断した。
彼女は、1930年代の中国では、「天津の売春宿で働く女性の数は、天津の綿工場で働く女性の数のおよそ2倍だった」と述べている。
しかし、中国人の男性が多い東南アジアに行った女性は、家事や性的奉仕の役割に就く可能性が高かった。

























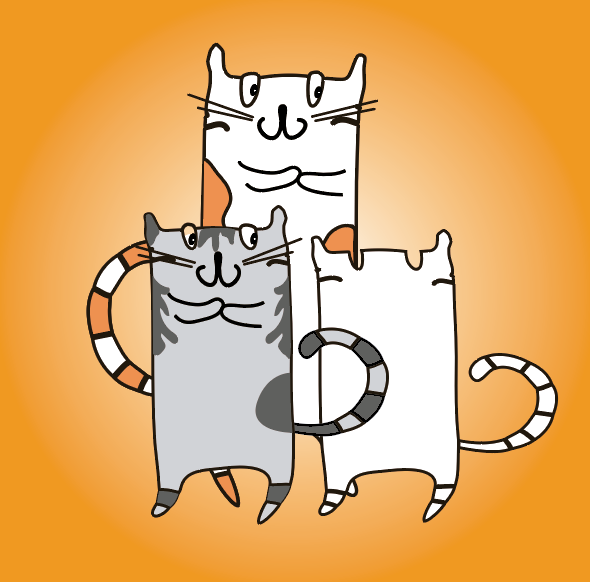

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます