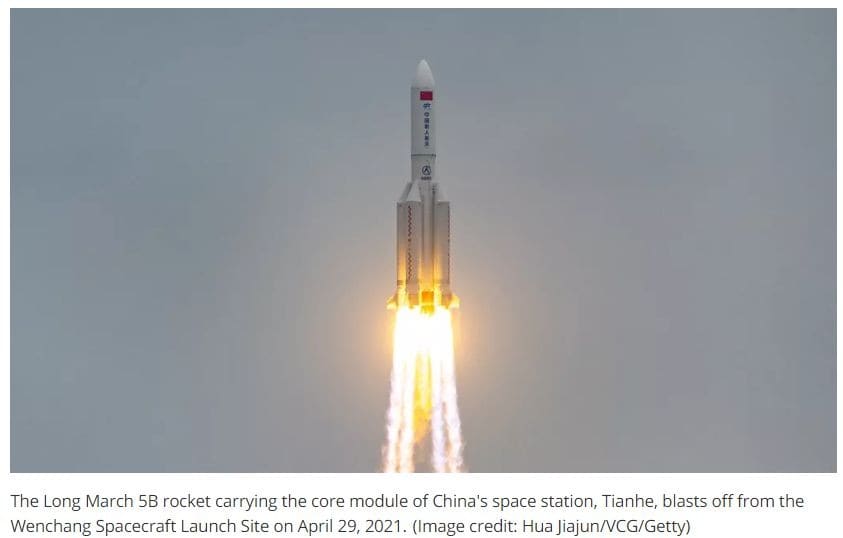22.11.16 NHK News WEBの以下のURLの記事のようにアルテミス計画ロケットの打上げに成功とのことですので,記事を記録しておきます.
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221116/k10013892651000.html
アポロ計画以来の月探査「アルテミス計画」 ロケット打ち上げ
2022年11月16日 15時57分

宇宙飛行士の月への着陸を目指す国際プロジェクト「アルテミス計画」で、月までの試験飛行を行う無人の宇宙船「オリオン」を搭載した大型ロケット「SLS」=「スペース・ローンチ・システム」が日本時間の16日午後3時47分ごろ、アメリカのケネディ宇宙センターから打ち上げられました。
このあと順調に進めば、オリオンはSLSから切り離され、月を周回して地球に戻るおよそ25日間の試験飛行を行う予定です。
◎ケネディ宇宙センター周辺には多くの観光客
半世紀ぶりの宇宙飛行士による月探査の第一歩となるロケットの打ち上げを一目見ようと、ケネディ宇宙センターがあるフロリダ州ケープカナベラルや、その周辺には多くの人が集まっています。
ケネディ宇宙センターが見える公園には、打ち上げ時刻の8時間以上前からキャンピングカーなどで大勢の人がやってきて、双眼鏡やカメラで発射台の方向を見たり、写真を撮ったりして打ち上げを待っていました。
このうち、イギリスから打ち上げを見にきたという男性は「月探査への第一歩が見られるのは一生に一度の機会です。将来、超重量級のロケットや宇宙船が誕生する可能性があり、とても興奮しています」と話していました。
また、中西部オハイオ州から車で20時間かけてやってきたという夫婦は「ここに到着したら、どんどん気分が盛り上がってきました。たびたびカウントダウンの途中で延期されましたが、3度目の正直で成功すると思います」と興奮した様子で話していました。
地元の観光当局によりますと、今回の打ち上げに合わせておよそ10万人の観光客がこの地域を訪れると見込んでいるということです。
◎今回打ち上げ予定の「SLS」とは
今回打ち上げられるNASAのロケット「SLS」は小型衛星を10機搭載する予定でそのうち2機が日本の探査機です。
2機のサイズは1辺がそれぞれおよそ11センチ、24センチ、37センチといういわゆる“超小型”で、いずれも地球の近くで分離されたあと自力で月へ向かいます。
JAXAによりますと、打ち上げが延期になったあと、先月13日に2機ともにバッテリーの充電を行うなど、必要な作業を終えているということです。
◎月面着陸を目指す探査機は「OMOTENASHI(オモテナシ)」
このうち「OMOTENASHI」は今回の打ち上げで唯一、月面着陸を目指す探査機です。
日本はこれまで、月面に着陸した実績がなく、成功すれば、旧ソビエト(1966年)、アメリカ(1966年)、中国(2013年)に続く4番目となります。
「OMOTENASHI」は、ロケットから分離されたあと探査機が持つガスジェットを噴射して、月に向けて軌道を修正。そして、月に降り立つ直前に、着陸態勢に入るため、向きを変えるとともに、探査機そのものを回転させながら姿勢を安定させます。
大気のある地球と異なり、パラシュートを開いて減速することができないので速度を落とすための固体ロケットを進行方向に噴射。時速をおよそ180キロまで落として月に衝突させます。
探査機にはあらかじめ、衝撃を吸収する緩衝材を入れるなど、複数の対策が施されていて、まさに月に「体当たり」で着陸する計画。成功したかどうかは、地球に送られる電波で確認することにしています。
「OMOTENASHI」はミッションとして、月面着陸のほか、月に向かう軌道に入った後、被ばく線量を1分ごとに計測する予定で、有人での月探査活動に備えて、放射線環境に関するデータを集めることにしています。
月面に降り立つことができれば、世界最小の月面着陸機になるということで、注目されます。
◎月の裏側に回り込む探査機は「EQUULEUS(エクレウス)」
もう1つの探査機「EQUULEUS」は、JAXAや東京大学などが共同で開発。地球からは見えない月の裏側に回り込む計画です。
そのエリアには、月と地球の引力に加えて、探査機の遠心力が釣り合う「ラグランジュ点」と呼ばれる場所が5か所あり、この周辺にある軌道に入ると、最小限の燃料でとどまり続けることが可能です。
この特性を生かすことで、将来、月へのアクセスや、火星探査の重要拠点となる「宇宙港」の建設場所になりうることから「ラグランジュ点」は宇宙開発上の重要な場所だと位置づけられています。
「EQUULEUS」は、この場所に効率よく到達することが目的で、ロケットからの分離後は、推進剤に水を使い、1年半ほどかけて月の重力を使うなどして軌道を変えながら月の裏側にある「ラグランジュ点」に向かう計画です。
そして、有人での月や周辺探査に重要な地球周辺の放射線環境や、月にぶつかる隕石の撮影などに挑戦することになっています。
超小型の探査機は開発のコストやハードルが低く、今後も活用の機会が増えると期待されることから、JAXAは月面着陸や航行に必要な技術を実証し、将来の科学探査の可能性を広げるねらいです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221116/k10013892651000.html
アポロ計画以来の月探査「アルテミス計画」 ロケット打ち上げ
2022年11月16日 15時57分

宇宙飛行士の月への着陸を目指す国際プロジェクト「アルテミス計画」で、月までの試験飛行を行う無人の宇宙船「オリオン」を搭載した大型ロケット「SLS」=「スペース・ローンチ・システム」が日本時間の16日午後3時47分ごろ、アメリカのケネディ宇宙センターから打ち上げられました。
このあと順調に進めば、オリオンはSLSから切り離され、月を周回して地球に戻るおよそ25日間の試験飛行を行う予定です。
◎ケネディ宇宙センター周辺には多くの観光客
半世紀ぶりの宇宙飛行士による月探査の第一歩となるロケットの打ち上げを一目見ようと、ケネディ宇宙センターがあるフロリダ州ケープカナベラルや、その周辺には多くの人が集まっています。
ケネディ宇宙センターが見える公園には、打ち上げ時刻の8時間以上前からキャンピングカーなどで大勢の人がやってきて、双眼鏡やカメラで発射台の方向を見たり、写真を撮ったりして打ち上げを待っていました。
このうち、イギリスから打ち上げを見にきたという男性は「月探査への第一歩が見られるのは一生に一度の機会です。将来、超重量級のロケットや宇宙船が誕生する可能性があり、とても興奮しています」と話していました。
また、中西部オハイオ州から車で20時間かけてやってきたという夫婦は「ここに到着したら、どんどん気分が盛り上がってきました。たびたびカウントダウンの途中で延期されましたが、3度目の正直で成功すると思います」と興奮した様子で話していました。
地元の観光当局によりますと、今回の打ち上げに合わせておよそ10万人の観光客がこの地域を訪れると見込んでいるということです。
◎今回打ち上げ予定の「SLS」とは
今回打ち上げられるNASAのロケット「SLS」は小型衛星を10機搭載する予定でそのうち2機が日本の探査機です。
2機のサイズは1辺がそれぞれおよそ11センチ、24センチ、37センチといういわゆる“超小型”で、いずれも地球の近くで分離されたあと自力で月へ向かいます。
JAXAによりますと、打ち上げが延期になったあと、先月13日に2機ともにバッテリーの充電を行うなど、必要な作業を終えているということです。
◎月面着陸を目指す探査機は「OMOTENASHI(オモテナシ)」
このうち「OMOTENASHI」は今回の打ち上げで唯一、月面着陸を目指す探査機です。
日本はこれまで、月面に着陸した実績がなく、成功すれば、旧ソビエト(1966年)、アメリカ(1966年)、中国(2013年)に続く4番目となります。
「OMOTENASHI」は、ロケットから分離されたあと探査機が持つガスジェットを噴射して、月に向けて軌道を修正。そして、月に降り立つ直前に、着陸態勢に入るため、向きを変えるとともに、探査機そのものを回転させながら姿勢を安定させます。
大気のある地球と異なり、パラシュートを開いて減速することができないので速度を落とすための固体ロケットを進行方向に噴射。時速をおよそ180キロまで落として月に衝突させます。
探査機にはあらかじめ、衝撃を吸収する緩衝材を入れるなど、複数の対策が施されていて、まさに月に「体当たり」で着陸する計画。成功したかどうかは、地球に送られる電波で確認することにしています。
「OMOTENASHI」はミッションとして、月面着陸のほか、月に向かう軌道に入った後、被ばく線量を1分ごとに計測する予定で、有人での月探査活動に備えて、放射線環境に関するデータを集めることにしています。
月面に降り立つことができれば、世界最小の月面着陸機になるということで、注目されます。
◎月の裏側に回り込む探査機は「EQUULEUS(エクレウス)」
もう1つの探査機「EQUULEUS」は、JAXAや東京大学などが共同で開発。地球からは見えない月の裏側に回り込む計画です。
そのエリアには、月と地球の引力に加えて、探査機の遠心力が釣り合う「ラグランジュ点」と呼ばれる場所が5か所あり、この周辺にある軌道に入ると、最小限の燃料でとどまり続けることが可能です。
この特性を生かすことで、将来、月へのアクセスや、火星探査の重要拠点となる「宇宙港」の建設場所になりうることから「ラグランジュ点」は宇宙開発上の重要な場所だと位置づけられています。
「EQUULEUS」は、この場所に効率よく到達することが目的で、ロケットからの分離後は、推進剤に水を使い、1年半ほどかけて月の重力を使うなどして軌道を変えながら月の裏側にある「ラグランジュ点」に向かう計画です。
そして、有人での月や周辺探査に重要な地球周辺の放射線環境や、月にぶつかる隕石の撮影などに挑戦することになっています。
超小型の探査機は開発のコストやハードルが低く、今後も活用の機会が増えると期待されることから、JAXAは月面着陸や航行に必要な技術を実証し、将来の科学探査の可能性を広げるねらいです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー