夕方、陽がオレンジ色に染まるそんなとき。
ケイトの幼馴染、ショーンは嫌そうな顔をして父の書斎から出てきました。
厳かに渡されたのは一通の手紙。
――前略 ショーン・ガーティ様
貴方にお目にかかりたいとベラリナ王女様自らの仰せです。
来たる明後日の土曜日、王宮に参られるよう、通知いたします。
追伸
おめかしをしてこられるよう、王女様付き侍女より忠告が届いております。
「いかがなされました、ショーン様」
屋敷のしもべ、もう65歳を超えたアダムがショーンの隣に来て、言いました。
「ああ、アダム。ぼくは庭を散歩するよ、この手紙を部屋に置いてきてくれ」
「かしこまりました。……もしや、これはケイト様からでございますか?」
「違う、なんでそうなるんだ? ベラリナ王女から」
「なんと!」
しかし、ショーンの頭の中に浮かぶのは過去の幼馴染・ケイトの笑顔ばかり。
「ベラリナ王女様は先日の舞踏会では熱烈にショーン様を見つめられておりましたとのこと、噂に聞いております」
アダムはそんなショーンを複雑な瞳で、けれどもあたたかく見つめていました。
「くそ、なんでケイトからは手紙来ないの?」
大理石の壁を拳で叩くショーンは、少し俯いて、顔を前髪で隠します。そして、そのまま歩いて庭へとふらふら出ていきました。手紙をもったアダムもあとに続きます。
「ショーン様。一つ申し上げたいことが爺にはございます」
「言ってみろ。くそ、なんて言うなってか?」
「いいえ。――そんなにケイト様のことをお慕いなさるのであれば、ご自分から手紙を出してはいかがでしょう」
「――バカ。こんな地位になって、ぼくがどうしてジオライ家のオレンジジュース搾り係に手紙が出せるんだよ?!」
「ショーン様。アダムは調べつくしております。ケイト様はジオライ家の令嬢ニーナ・ジオライ様付きの侍女になられたということです」
「え? は? えええっ?」
「ニーナ様ご自身がケイト様のことをお気に召して侍女にとりたてた、とのことです」
ショーンはぽかんとアダムを見つめました。
「はい」
アダムは優しく微笑みます。
その一時ほどあとの頃。
「ショーン元気かなあ?」
ケイトは檸檬形にふくらんだ月を見上げて呟きました。
「誰、ショーンって」
「おひい様、おひい様は恋をしたことがおありですか?」
「恋?!」
「おっとおひい様」
夜の庭で転びそうになった10歳のお姫様を支えて、ケイトは少し顔を紅く染めたのでありました。
そんなケイトを月明かりの中、ちらり見上げたお姫様がムッと頬をふくらませたことには、ケイトは気づきません。
そして、夜が更けていきました。
――――
☆万梨羅さんへ☆
長い間お待たせして申し訳ございませんm(__)m
やっと今日書けました。
もし読んでくださいましたら、感想いただけると嬉しいです。
ケイトの幼馴染、ショーンは嫌そうな顔をして父の書斎から出てきました。
厳かに渡されたのは一通の手紙。
――前略 ショーン・ガーティ様
貴方にお目にかかりたいとベラリナ王女様自らの仰せです。
来たる明後日の土曜日、王宮に参られるよう、通知いたします。
追伸
おめかしをしてこられるよう、王女様付き侍女より忠告が届いております。
「いかがなされました、ショーン様」
屋敷のしもべ、もう65歳を超えたアダムがショーンの隣に来て、言いました。
「ああ、アダム。ぼくは庭を散歩するよ、この手紙を部屋に置いてきてくれ」
「かしこまりました。……もしや、これはケイト様からでございますか?」
「違う、なんでそうなるんだ? ベラリナ王女から」
「なんと!」
しかし、ショーンの頭の中に浮かぶのは過去の幼馴染・ケイトの笑顔ばかり。
「ベラリナ王女様は先日の舞踏会では熱烈にショーン様を見つめられておりましたとのこと、噂に聞いております」
アダムはそんなショーンを複雑な瞳で、けれどもあたたかく見つめていました。
「くそ、なんでケイトからは手紙来ないの?」
大理石の壁を拳で叩くショーンは、少し俯いて、顔を前髪で隠します。そして、そのまま歩いて庭へとふらふら出ていきました。手紙をもったアダムもあとに続きます。
「ショーン様。一つ申し上げたいことが爺にはございます」
「言ってみろ。くそ、なんて言うなってか?」
「いいえ。――そんなにケイト様のことをお慕いなさるのであれば、ご自分から手紙を出してはいかがでしょう」
「――バカ。こんな地位になって、ぼくがどうしてジオライ家のオレンジジュース搾り係に手紙が出せるんだよ?!」
「ショーン様。アダムは調べつくしております。ケイト様はジオライ家の令嬢ニーナ・ジオライ様付きの侍女になられたということです」
「え? は? えええっ?」
「ニーナ様ご自身がケイト様のことをお気に召して侍女にとりたてた、とのことです」
ショーンはぽかんとアダムを見つめました。
「はい」
アダムは優しく微笑みます。
その一時ほどあとの頃。
「ショーン元気かなあ?」
ケイトは檸檬形にふくらんだ月を見上げて呟きました。
「誰、ショーンって」
「おひい様、おひい様は恋をしたことがおありですか?」
「恋?!」
「おっとおひい様」
夜の庭で転びそうになった10歳のお姫様を支えて、ケイトは少し顔を紅く染めたのでありました。
そんなケイトを月明かりの中、ちらり見上げたお姫様がムッと頬をふくらませたことには、ケイトは気づきません。
そして、夜が更けていきました。
――――
☆万梨羅さんへ☆
長い間お待たせして申し訳ございませんm(__)m
やっと今日書けました。
もし読んでくださいましたら、感想いただけると嬉しいです。















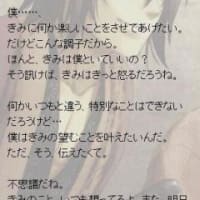

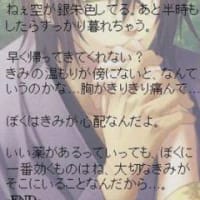

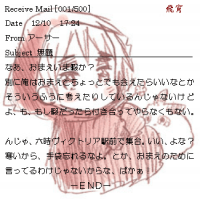

ショーンとケイトちゃん。
なんだかお互いなかなか進まなそうな2人ですねぇf^_^;
HAPPYになりますよーに……