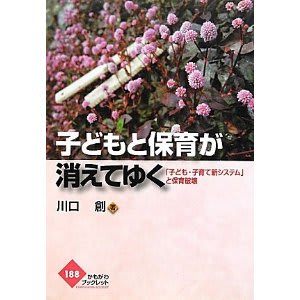
子どもと保育が消えてゆく―「子ども・子育て新システム」と保育破壊 (かもがわブックレット) [単行本] 川口 創 (著)
保育所に入りたくても入れない「待機児童」は全国で2万5千人ほどおり、深刻な問題となっています。安倍総理は、2013年4月19日、待機児童ゼロを実現した横浜市の方式を横展開していく考えを明らかにしました。平成25・26年度の2年間で20万人、平成29年度までに40万人分の保育の受け皿を確保し、待機児童ゼロを目指すとしています。
そして、政府は2013年4月26日、2015年度から始まる新たな子育て支援制度(「子ども・子育て支援新制度」=新システム)の詳細を議論する「子ども・子育て会議」の初会合を開きました。保育サービスの需要見込みや保育施 設の整備の在り方など、市町村の取り組みの参考となる基本指針を、今夏までに策定するとのことです。
この子育て新システムは、野田民主党政権が子育て支援改革関連3法の成立を受けて2012年8月に導入が決定したものですが、保育関係者には非常に評判の悪い代物です。しかし、安倍内閣になっても何も変わりません。
『子どもと保育が消えてゆく』 子どもと親を追いつめ、少子化を促進する野田民主党と橋下維新の会
この新システムは、消費税引き上げとバーターで「消費税増税を飲まなければ待機児童解消なし」とばかりに、消費税増税で生まれる財源の一部1兆円を使い、待機児童の解消などに向けて、 地域の子育て拠点を整備することになっています。消費税増税分を財源とすると決められているのは異様です。つまり、この新制度を安倍自民党も継続するということは、消費税増税をこのまま推進することがすでに織り込み済みということです。
消費税のために「人質」にとられた幼保一体化 「総合こども園」は要らない 子ども未来法律事務所通信16
さて、新システムでは保育所と幼稚園の両方の機能を併せ持つ「認定こども園」を増やすほか、これまで認可の対象外だった小規模保育や事業所内保育などの認可制度を創設するとしています。
この待機児童に関しては、安倍晋三首相が2017年度までに40万人分の保育の受け皿を整備し、解消する方針を示しているのですが、待機児童が50人を超える自治体に対し、全員、資格のある保育士が必要とされている基準を当面、8割から9割程度に緩和するなど質を下げて量を増やす方針です。質より量というわけです。
さらに問題は株式会社の保育所への参入です。認可保育所の設置主体の制限は2000年に緩和され、法律上は株式会社の参入が認められています。しかし、株式会社立の認可保育所は全国で1%程度にとどまっています。株式会社による保育所経営は、突然の撤退や、もうけ優先による質の低下を招きかねないので信用されていないのです。
保育園が差押え!民主党の子ども子育て新システム「総合こども園」は幼児を不幸にする

「便利な」保育園が奪う本当はもっと大切なもの [単行本(ソフトカバー)] 長田 安司 (著)
今、保育が危機的な状況に追い込まれている。規制緩和が進み、駅ナカ保育や延長保育などのサービスを推進する企業保育所の増加で便利になる一方で、肝心であるはずの保育の質は低下している。子を持つ親の「親心」はなくなり、秩序を保つ大人たちも減ってしまった。学級崩壊、いじめ、ひきこもり、学力低下、幼児虐待など、日本が抱えている問題の根底は保育教育と行政の施策にある。保育園は決して「親の労働を支える施設」ではない。待機児童解消を大義名分に、親との関わりを軽視した「保育サービス」では、子供たちが「思いやり」を知らない人間に育っていくのだ。現在、八王子で3つの認可保育園を経営する著者が、日本の将来を救うべく企業保育所と保育施策の問題性に正面から切り込み、あるべき保育の姿を説く。
ところが、各分野の規制改革策について議論している規制改革会議(議長=岡素之・住友商事相談役)は5月2日に会合を開き、認可保育所への株式会社の参入拡大で厚生労働省と合意したと発表しました。
規制改革会議が教育問題を扱うのがおかしいのですが、同会議は、待機児童解消が進まない理由について、自治体が株式会社を排除しているからだと問題をすりかえ、「自治体の裁量で株式会社立保育園を認可しないことは許されない」と厚労省に圧力をかけてきました。
株式会社は営利社団法人であり、黒字を出して株主を儲けさせることが存在目的です。予備校は経営してよくても学校を経営させるべきではありません。だから学校法人というものがあるのですから。保育・教育という経済で語るべきではない部分こそ公が担うべきです。いったい、安倍政権の教育再生とはなんだったのか。
また、この議論は安倍首相が参考にするとしている待機児童を解消した横浜の例からも、おかしいのです。横浜では市が独自に認定した認可外保育所に市が助成し保育料を下げています。また幼稚園の預かり保育などの情報を提供する専門相談員を各区役所に配置しています。駅から離れた定員に空きのある保育所へ、駅近くの保育ステーションからバスで送迎するのです。株式会社を積極的に導入したから待機児童が解消したのではありません(もちろん、この横浜市のやり方も認可外保育所を使うことや市が援助する基準など、いろいろ問題があるのですが)。
さて、2015年4月導入が狙われている新システムでは、設置主体が株式会社であることを理由に自治体が裁量で認可しないことは許されない、と明文化されます。塾なら株式会社立もあり得ますが、保育所でやるのは保育です。人を育てる営みは、営利企業ができるものではありません。
結局、安倍政権の教育再生って、単なる教育利権です。
安倍自民党政権の「教育再生」利権が凄いんです
それが証拠に、厚労省は今回、新システム導入を待たずに各都道府県・市町村に対し、「公平・公正な認可制度の運用」を求めることを、月内にも通知する意向を示し、通知後に株式会社の参入状況を調査し、公表するとしています。これでは公平どころか「株式会社立保育所ゴリ押し」です。
また、細かい話ですが、同会議と厚労省は、事業所内保育施設の避難用屋外階段の設置義務については、保育所増設の「阻害要因」だとし、「(現在と)同等の安全性と代替手段を前提として緩和」する方向で今年度中に結論を得るとしました。もう、質を落として数を増やす新システムの保育所政策が前面に出ているのです。

まとめますと、基準を満たした保育所に対する認可制度がある以上、待機児童の解消も基本は認可保育所でないといけません。40万人分のほとんどが認可保育所であるべきです。まして、認可保育所にも参入すべきでない株式会社が、こども園として安易に認定する制度で認可外施設で誤魔化して参入するべきではありません。
面積や保育士の数など国の基準をクリアした認可保育所には自治体などから補助があり、保育料が抑えられています。認可保育所は国の基準を満たす保育士や一定の居室、庭などが確保され、補助も厚いので、フルタイムで働くある母親の場合、月額5万円程度で入 れるが、認可外に行かざるを得なくなったら10万円にもなるというのです。誰もが認可保育所に入れたいのです。
実は、認可保育園に入れたこどもの比率は自治体によって大きな差があります。東京23区の場合、入所希望者で入れないこ どもの割り合いが最も高いのは杉並の62%、つづいて港区60%、世田谷・江東両区の52%となっています。低かったのは葛飾区の2%、荒川区の6%でした。もちろん、子育て世代の増え方などあるでしょうが、それを差し引いてもこれだけの差が自治体であるのは、自治体が認可保育園を計画的に整備する姿勢をもって きたかどうかが大きいことはいうまでもありません。
杉並では山田前区長(現在、維新の会の衆議院議員)の時代から、民間の認可外保育所で対応する方針を掲げていた時期が長かったことが今日の事態の一番の原因です。さすが維新マインド。
これに対して、先ごろ、認可保育所に子どもが入所できなかった杉並区の60人の母親たちが行政不服審査法に基づき区に異議申し立てを行ないました。杉並区では認可保育所の定員の2倍を超す約3千人が入所を申し込んだため、多くの保護者は選考から漏れ、保育料が高い認可外保育所に入れるか、働きに出ることを諦めるかなどの選択を迫られたからでした。
認可保育所を増やすために、国は国有地を優先利用させる取り組みを始めたものの、時価を基本としているため高すぎて2年半余でわずか24件しか実績がないのです。ここは国が有給国有財産の無償または廉価での提供も検討すべきです。新たに税金がかかる話でもないのですから。
このように認可保育所を短期間に増やし、待機児童を解消して、かつ安全で快適な環境で子どもたち全員を育てる方法は必ずあります。それができれば、日本最大の問題、少子化対策の道も開けるのです。安易な新システムと株式会社参入には絶対反対です。
事は子どもと親御さんの人権問題です。
ご面倒でしょうが、お力を貸していただきたく、
是非是非上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!
待機児童対策 親の悲鳴に耳を傾けたい
子どもを保育所に預けたくても入れない。そんな保護者が集団で自治体に対し、抗議の声を上げ始めている。待機児童は子育て世帯にとって深刻な問題だ。
認可保育所に子どもが入所できなかった東京都杉並区の60人の母親たちが行政不服審査法に基づき区に異議申し立てを行った。同様の動きは、足立区や渋谷区、さいたま市などにも広がっている。
面積や保育士の数など国の基準をクリアした認可保育所には自治体などから補助があり、保育料が抑えられている。異議申し立ては、子どもを入所させたい認可保育所が増えない現実に対する保護者たちの切実な悲鳴であろう。
杉並区では認可保育所の定員の2倍を超す約3千人が入所を申し込んだ。多くの保護者は選考から漏れ、保育料が高い認可外保育所に入れるか、働きに出ることを諦めるか-などの選択を迫られた。
認可外を含む保育所に入所できなかった全国の待機児童は昨年10月時点で約4万6千人に上る。大阪市では1600人を超え、福岡市は1168人だった。都市部を中心とした全国的な問題である。
家計を支えるため、パートなどで働くことを希望する母親は増えている。これに伴い、保育所の需要も高まっている。
施設整備は進んでいるものの、需要にはなかなか追い付かない。都市部の高い地価や用地不足などが要因とされる。
ただ、横浜市のように待機児童ゼロに向けて成果を上げている自治体もある。
市が独自に認定した認可外保育所に市が助成し保育料を下げる。幼稚園の預かり保育などの情報を提供する専門相談員を各区役所に配置する。駅から離れた定員に空きのある保育所へ、駅近くの保育ステーションからバスで送迎する-。
さまざまな工夫の結果、10年間で認可、認可外を含め保育所の定員は2万人増えたという。
福岡市は本年度、認可保育所の増改築などを通じて定員を1900人増やすとともに、各区に専門相談員を配置した。
成功例を参考にしながら、地域の実情に応じた創意と工夫を積み重ね、保育の量と質を充実させてもらいたい。
政府は、子育て世帯の負担軽減を目的に、幼稚園や保育所、両者の機能を併せ持つ「認定こども園」の利用料を無料にする制度設計を始めた。対象は3~5歳児を想定している。
子育てには多額の費用がかかる。無償化で親の負担を軽くすることは少子化対策にもつながる。その方向性は理解できるとしても、まずは待機児童の解消を優先して検討すべきではないか。
親たちは「子どもを安心して預ける場を確保してほしい」と願っている。とりわけ、待機児童の8割強を占める0~2歳児の受け入れ拡充を強く求めている。
子育て世帯が何を望んでいるのか。保護者の生の声を聞き、就労と子育てが両立できる環境づくりをしっかり進めなければならない。
=2013/04/11付 西日本新聞朝刊=
認可保育所に入れない「待機児童」の親たちが、自治体に次々に不服申し立てをして、注目を集めている。認可保育園の整備が追い付かない行 政への母親たちの怒りの反乱だ。政府も対策を打ち出しているが、完全解消は7年後とされており、規制改革会議で前倒しの議論も始まった。
杉並区は2.6倍の競争率
2013年の2月から3月にかけて、東京杉並区、大田区、足立区、目黒区、渋谷区やさいたま市、東大阪市など各地で、親たちの異議申し立てが続いた。例えば杉並区の場合、2968人の入所希望に対し、区の認可保育所の募集枠は1135人。実に2.6倍の競争率だ。
認可保育所は国の基準を満たす保育士や一定の居室、庭などが確保され、補助も厚いので、フルタイムで働くある母親の場合、月額5万円程度で入 れるが、認可外に行かざるを得なくなったら10万円にもなるという。「共稼ぎを前提に住宅ローンを組んでいるので、払いきれない」といった悲鳴が聞こえ る。
認可外でも、東京都などが補助金を出す「認定保育所」はあるが、ビルの一室で庭がないなど、保育環境が認可保育所に劣る場合がほとんどで、自治体の補助があっても、認可保育所に比べれば割高。そんな無認可保育所でも、入れればまだ良い方という実態もある。
待機児童は主に都市部で問題になっており、厚生労働省のまとめでは、2012年10月1日現在、全国で4万6127人と、前年より493人減っただけ。都道府県別では東京1万105人、大阪5488人、神奈川4052人など。
育児休業制度の整備で出産後も働く女性が増えているのに加え、リーマンショック後の景気低迷で共働きが増えたほか、地価下落もあって都心でも 住宅が買いやすくなったことで若い世帯が増えたことなどから、大都市部の保育需要が拡大膨らんだという事情がある。自治体の努力で保育所が増えると、諦め ていた人が応募し、却って待機児童が増えるという悪循環も指摘される。
消費税分から7000億円を投じる
待機児童解消への政策は一応、立てられている。2012年夏の「社会保障と税の一体改革」で、2015年度から保育の新制度が導入され、親の 申請を受けて就労状況などで保育の「必要量」を判定し、これに応じて施設を選ぶことになる。新制度のために消費税増税分から年間7000億円の財源を投じ て保育所整備などを進めることになっている。ただし、政府は、待機児童の解消には5年程度必要と見込んでおり、現在から考えると7年後の2020年ごろと いうことになる。
政府の対応をにらみながら、自治体独自の取り組みも注目される。一番の先進例が横浜市。2010年4月に全国自治体でワーストの1500人超 の待機児童を抱えていたが、昨年春に179人まで減らし、今春でほぼゼロを達成したのだ。認可、無認可含め3年で1万人以上置保育所定員を増やすととも に、個別のニーズをくみ上げ、最適の対応を親と一緒に考える「保育コンシェルジュ」を区役所に置いた。フルタイムで働くのが前提の保育を、パートのひとに はそれに合ったメニューを考えるといったきめ細かい対応の成果だ。
政府目標は「今後2年間で解消」
一連の親の異議申し立てを受け、緊急対策を打ち出す自治体もある。区の施設などを転用して認可保育所の定員を急きょ60人拡大(杉並区)、13年度補正予算で6億円余りを積み増すなど14年度までに定員を420人増やす(豊島区)などの動きが出ている。
政府の規制改革会議でも議論になり、3月21日の会合で「待機児童を今後2年間で解消」との政府目標を提言する素案を打ち出した。ただ、保育 士の数や建物・庭の面積など認可保育所の設置基準について「国の基準は融通が利かない。人口も面積も違う東京と北海道が同じ扱いだ」(猪瀬直樹都知事)と いった不満を背景に、設置基準を緩和するというのが、規制改革会議の議論でも大きな柱だったという。
先進例の横浜市でも、全ての需要を認可保育所で賄ったわけではなく、「駅周辺ビルの1室など便利だけど、まるでコインロッカーに預けるみたい で、子供の成長への影響が心配」(ある母親)との不満・不安もある。保育士が少なくて、保育中の事故も後を絶たない。安心して子育てできる環境への道のり はまだまだ険しそうだ。
保育所待機児童ゼロ実験 45平方メートルに19人 ぶつかる場面も
- 産経新聞
- 2013年04月30日08時05分
■保育士目届かず
保育所に入れない「待機児童」が問題となる中、政府の規制改革会議(議長・岡素之住友商事相談役)が、認可保育所の面積や保育士数の規制緩和を検討している。
「2年間で待機児童をゼロにするための現実策」との見方もあるが、安易な緩和は保育の質低下につながりかねないとの危機感も広がっている。(三宅陽子)
東京都内の保育所の一室に、保護者に連れられた0~2歳の子供たちが続々と集まってきた。保育士5人に見守られる中、ついたてで区切られた45平方メート ルの部屋で19人の子供たちが遊び始めると、狭い空間の中でぶつかり合う場面も。だが、保育士は泣いている別の子供に気を取られ、対応が追いつかない。昼 寝用の布団が敷かれると、歩くスペースは消え、遊びの場は部屋の隅に追いやられた。
これは、全国保育団体連絡会が28日に行った実験だ。 国は現在、0、1歳児1人当たりの面積を3・3平方メートル以上確保するよう認可保育所に求めているが、この基準以下(0、1歳児1人当たり2・5平方 メートル)の場合、保育環境がどう変わるかを調べた。実験に協力した日本保育学会保育政策研究委員会の村山祐一委員長(70)は「基準以下の部屋では子供 たちの命に関わる問題が想像以上に出てくる。安全な食事、昼寝には、それぞれ空間を別に確保することが重要」と指摘する。
安全性の確保な どから、認可保育所に国より厳しい面積基準を独自に定める自治体は多いが、規制改革会議は、待機児童が50人を超える自治体は国の基準まで引き下げて「量 の確保を目指すべきだ」との方針を打ち出した。子供たちを見守る職員全員が保育士であることを求める現在の基準を、保育士は8~9割程度でもよいとして緩 和し、残りは幼稚園教諭などを充てることも提案されている。
こうした規制緩和の流れは、待機児童を減らす効果が見込める一方、保護者らに不安も与えている。
17日には、保育所の拡充を求める保護者グループらが、「規制緩和による待機児童解消より、安全、安心な保育環境の整備を優先すべきだ」などとする意見書 を規制改革会議事務局と厚生労働省に提出。東京都杉並区で活動する「保育園ふやし隊@杉並」の曽山恵理子代表(36)は「規制緩和で子供たちを詰め込もう という動きになっているのはショックだ」と憤り、「私たちはただ子供を預けられればいいのではなく、安心、安全な環境で過ごしてもらいたい」と求めてい る。
保育所 定員超過が深刻化
ベネッセ研調査 幼稚園は定員割れ
保育所の入所待ちをする「待機児童」が問題になる中、全国の保育所で定員超過が深刻化していることなどが、ベネッセ次世代育成研究所の調査でわかった。
調査は昨年10月から12月にかけ、全国の公立と私立の認可保育所、幼稚園などに実施、5221園から回答を得た。
認可保育所に、昨年9月時点の0~2歳児の定員充足率を聞いたところ、私立では定員を超過して受け入れている保育所が全体の61・8%に上り、4年前の前 回調査より3・4ポイント増加した。125%以上の定員超過は24・1%を占め、前回調査より3・6ポイント増加、150%以上の超過施設も7・5%あっ た。
一方、私立幼稚園で定員割れをしている園が79・4%に上り、このうち定員の半数に満たない園も14%あった。公立幼稚園でも94・2%が定員割れをしていた。
子育て関連新法では、2015年度から認定こども園制度が拡充され、幼稚園から認定こども園への移行が期待されている。
今回の調査では、私立幼稚園の36%が「条件によっては移行してもよい」と答える一方、「移行は考えていない」との回答も26・7%。また、「詳しい内容が分からないので判断できない」が22・4%だった。
移行しない理由で多かったのは、「0~2歳は家庭での育ちを大切にしてほしい」「施設整備が対応できない」「地域に待機児童がいない」など。移行するかどうかの判断で重視する点は、「施設整備費の保障」が最も多かった。
同研究所主任研究員の後藤憲子さんは、「保育所への入所希望が増加するなか、幼稚園は定員割れを起こしている。幼稚園の認定こども園への移行を促すには、施設整備費や人件費の充実などを進めることが必要」としている。
(2013年5月4日 読売新聞)
毎日新聞 2013年04月12日 地方版
昭島市初の「幼保連携型」認定こども園建設に伴い、市立堀向(ほりむこう)保育園(美堀町)が廃園となる方針が明らかになり、反発した保護者ら約50人と市側が10日夜、話し合いの場を持った。しかし、議論は平行線で、問題の決着は不透明のままだ。
昭島市内の待機児童は年間130人以上とされ、市が把握していない潜在的な数字も含めると500人以上 に上るという。待機児童の削減を目指し、市はJR昭島駅の北側に約1500平方メートルの土地を借り、建築費約4億5000万円で認定こども園を建設。社 会福祉法人を運営主体に、定員190人で15年4月の開園を計画する。
市は、13年度予算で土地の賃料や建設費の一部など約7800万円を計上、定員80人の堀向保育園(年間運営費約1億3800万円)は、認定こども園に吸収される形で廃園となる。
しかし、保育園の保護者が一部報道で廃園計画を知ったのは今年になってからで、市から直接知らされなかったことに強く反発した保護者ら約40人が「堀向保育園を守る会」(松本和広会長)を結成。廃園撤回を要求し市に説明を求めた。
10日の話し合いには、新藤克明副市長らが出席。「120人規模の保育園の場合、年間運営費は約2億円 に上るのに対し、認定こども園として国や都の補助を受けた場合は4250万円となり、市の負担は5分の1で済むという試算がある。浮いた予算を効果的に使 える」と主張した。
これに対し「守る会」からは「待機児童軽減といいながら廃園にするのはおかしい」「民間主体では保育の質が確保できない」などの意見が出た。今月下旬に改めて話し合いをすることになった。
松本会長は「市側は子供や親のことは考えておらず、お金のことしか考えていない」と批判する。【黒川将光】
その内容は、幼稚園・保育所の現状と課題を浮き彫りにするもので、ポイントは大きく次の4点となる。
(1)必要年齢層での保育所の定員超過と幼稚園の定員割れ
前者では0~2歳児層を受け入れる施設で61.8%が超過受け入れを、一方で後者では私立の79.4%、国公立の94.2%が定員割れをしており、必要な箇所に手が届かないサービスのアンバランスさを露呈した。
(2)現状の認定こども園への移行希望の低さ
深刻な待機児童問題を緩和するための鍵となるのが、私立幼稚園の動向だ。しかし、「条件によっては、認定こども園に移行してもよいと思う」の回答をした私立幼稚園は36.0%と、約3園に1園にとどまった。
(3)保育者の非正規雇用率の高さ
特に国公立の幼稚園・保育所では、前者が47.1%、後者が54.2%とどちらも半数にまでのぼる。背景には、施設運営費が一般財源化されたことにより、人件費の捻出がより難しくなっていることなどがある。
(4)きわめて多くの回答者が「保育者の待遇改善」が必要と回答
私立幼稚園では77.2%、私営保育所では83.4%が、育者の質の向上のためには、「保育者の待遇改善」が必要と回答した。
昨年8月に「子ども・子育て関連3法」が制定された直後に実施され、関連3法を受けて間もなく始まる「子ども・子育て会議」の前に公になった本調査。それぞれの園が現状と今後を鑑みる、まさにベストタイミングでの発表となった。
上記のうちここでは(3)にフォーカス。保育者にも見られる雇用の問題に着目し、さらには広く女性の働き方までを考えていく。
国公立の幼稚園では47.1%、同保育所では54.2%にまで達する、非正規雇用率。この話題について真田氏は、「保育の長時間化などを考えると、非正 規雇用が多くなっていることは一概に悪いとは断定できない」と発言した。たしかに、時間を区切って必要な場面に人員を配置できることは、経営側にとってメ リットがある。しかし氏は「ただし、研修期間がないなどで専門性は(正規の場合より)上がりにくい」とも指摘。(4)で「保育者の質の向上」について触れ ているだけに、理想と現実との間にジレンマがあることが伺える。
個人の問題としてこれを捉えたとき、当人が雇用形態と技術の伸びのバランス、さらには正規に比べて少ない収入などをよしとして選んでいれば、これには何ら問題がない。むしろ、性別に限らず希望に応じた働き方を選択できるのは基本的にはよいと考えることもできる。
しかし、もしそれが「仕方なく」の選択だとしたらどうか? 無藤氏からは「結婚を機に辞める方も多い」との指摘もあり、日々子育てに接する現場にさえ、女性が働くことに壁があるようだ。
2月末、東京都・杉並区の田中良区長が行った緊急記者会見が記憶に新しい。「緊急・臨時的対応として、区立・私立の認可保育所受け入れ枠増、区立施設の 活用などにより、保育所の定員を200人増やす」という内容の報道。ここに至るまでには、“保活”中の母親たちの、涙ぐましい日々がある。妊娠期や出産間 もない時期から、居住地域の保育所を探す保活。激戦の認可保育所入所を勝ち取るため、自治体の保育所事情を調べ上げたり、場合によっては担当課に窮状を手 紙で訴える。それでも子どもを入れられる保育所は見つからず、そのような母親たちが集まって異議申し立てをしたことで、定員増設の運びとなったのだ。
彼女たちの多くは、出産後に復職を希望するからこそ保育所を必要とするが、それが叶わなければ仕事に戻ること自体を諦めるか、雇用の形態を変更せざるを 得ない。ここでもまた、仕方なくの選択を強いられる構図がある。今回増設を勝ち取ったことが大きな一歩として評価される一方で、急に全員の不満が解消され るわけでもなく、苦渋の選択をする母親たちはまだまだ多いのではないだろうか。
先の保育者の非正規雇用の問題と、直接のつながりがあるわけではないが、どちらも「結婚」や「生み育てる」ことが知らず知らずのうちに一種の“足かせ”に変質しているように見える。
ただし、横浜市の待機児童対策のように、難局を打開する行政側の動きも見られるようになってきたのは、一つの光明だろう。林文子市長のもと、2009年 度・2010年度と全国ワースト1、2011年度にはワースト2だった待機児童数を、積極的な保育所整備により2012年度にはほぼ0にまで解消し、各所 で話題となった。たとえばこのような大きな取組みで、全国的に女性の生き方、働き方をもっと開放的に変えられないものか。
昨年8月制定の「子ども・子育て3法」を受け、間もなく始まる「子ども・子育て会議」。保育者の待遇改善に、大きく一歩を踏み出す話合いとなることに期 待する。できるところから少しずつ、女性たちが、結婚するしない、生む生まないに関わらず、生き方の軸を自由に設定できる社会の実現が望まれる。
待機児童の理由は何か 駒崎弘樹さんに伝えたいこと
認可保育園に入れない待機児童の問題がいよいよ深刻になる中で、首都圏各地で父母が認可保育園増設を求めて、勇気をもって立ち上がっています。私の住む渋谷でも認可保育園を求める931筆の署名がよせられ区議会に提出されました。
杉並のお母さん達の行動をきっかけに、メディアも大きく待機児童問題を報道しています。これまでのメディアの報道と違い、父母が求めている認可保育園と、行政が認可外の保育施設で安上がりにすませようとしている両者の溝に焦点をあてての報道が増えています。
ところで、これらのメディアの報道について、保育事業を経営している駒崎弘樹さん(NPO法人フローレンス理事)がブログ上で批判をしています。わたくしのところの新聞も名指しされています。
駒崎さん本人は「データとファクトにもとづいた議論」といっていますが、報道批判の前提となっている事実について大事な点で勘違いされているようです。駒崎さんは、保育関係者に影響力が大きい方だけに、ネット上で、事実について記したいと思います。
一番の勘違いは、認可保育所の基準が「高度成長を経た日本の都市環境には合わず、機動的にニーズに合わせて建設していくことができなかった」という 点です。続く文章には、東京都が「面積基準や園庭基準等を緩和した独自のシステムを2001年に立ち上げ民間参入を呼び込み…認可保育所に入れない子ども たちの受け皿をつくることに成功しました」ともあります。
この議論にかかわって二つ指摘したいことがあります。
第一に、認可保育園の基準というのは、 いわゆる”あしき規制”といったたぐいのものではなく、こどもたちの健やかな成長のために国がもうけた最低限の基準です。都市の地価が高いことを理由に切り下げていいものでは決してありません。
保育園は、人間形成にとってきわめて大事な時期に、起きている時間の大半を過ごす場所です。
国際的に、保育の質を支えるものとされているのは、第一に施設の面積や設備等の物理的環境、第二に保育者の配置と年齢に応じた集団の規模、第三に保育の内容、第四に保育者の専門性です。
国の社会保障審議会がパリやストックホルムなど14都市の保育所の1人あたりの面積を調べたら東京は最下位でした。何十年も国の基準は変えられておらず、 国際的に見たら面積基準等は狭すぎるぐらいです。また、職員の基準でみると認可保育園はすべての職員が保育士でなければならないとなっていますが、認証保 育所は、6割が保育士ならよいとなっています。
2012年の保育施設での死亡事故は認可保育園6件、認可外保育施設12件となっています。認可保育園は200万人以上が預けられており、認可外保育施設 が20万人弱ですから、死亡事故率は20倍もの差があります。認可保育園での死亡事故も詰め込みがはじまってから増えています。
安倍政権はやれ成長戦略だ、やれ規制改革だといいますが、こどもの命と安全にかかわる分野での規制緩和は親の立場からすれば誰もが絶対に認められないのではないでしょうか。
こどもの安全とすこやかな成長のためには、保育の質を支え、保育の質を高めるために、基準を高くすることこそ本来めざすべき方向です。
二番目に指摘したいことは、認可保育園が足りない理由は、認可保育園の基準の厳しさにあるのではなくて、自治体と国の姿勢によるものだということです。
東京新聞の2月26日付けの調査にありましたが、認可保育園に入れたこどもの比率は自治体によって大きな差があります。4月からの入所希望者で入れないこ どもの割り合いが最も高いのは杉並の62%、つづいて港区60%、世田谷・江東両区の52%となっています。低かったのは葛飾区の2%、荒川区の6%。も ちろん、子育て世代の増え方などあるでしょうが、それを差し引いてもこれだけの差が自治体であるのは、自治体が認可保育園を計画的に整備する姿勢をもって きたかどうかが大きいことはいうまでもありません。
杉並では山田前区長(現在、維新の会の衆議院議員)の時代から、民間の認可外保育所で対応する方針を掲げていた時期が長かったことが今日の事態の一番の原 因です。葛飾区も待機児童はまだ解消できていませんが、計画的に認可保育園を整備して来たことが待機児率に反映しています。
国は待機児童が深刻化する中で、認可保育所整備などをすすめるために、平成20年度第二次補正予算で、「安心こども基金」という制度をつくり、保育所の施 設整備に大きな補助がでるようになりました。父母の運動もあり、この「安心こども基金」を使って、東京でもこの3年間で1万7500人分と、この間にない ペースで認可保育園の整備がすすみました。政治がやる気になれば、認可保育園の整備を数十万人おこなうことも難しくありません。
消極的な自治体はいろんな理由をいいますが、それを鵜呑みにしてはならないと思います。政府と自治体の姿勢で財源を手当てすれば、認可保育園の整備は抜本的にすすめることができます。
駒崎弘樹さんはブログ上で、「認可保育園を作らない自治体は悪だ」という政府たたきでは、有効な政策を生み出すことには全くつながりません」と書かれてい ますが、これは逆です。認可保育園を必要な数だけつくるように自治体と国の姿勢を変えることが、待機児童を解消する一番有効な道です。
待機児童問題の一番の大本にあるのは、税金の使い方の優先順位を自治体や国が何におくのかという点です。
いま、アベノミクスの名で、採算のとれない高速道路建設等、不要不急の大型開発に莫大な税金が投入されようとしています。東京都もたくさんの住民を立ち退 かせる道路計画を次々具体化しています。保育という法律で自治体に義務づけられた市民サービスもできていないのに、不要不急のものに優先して税金を投入す るのはどう考えても間違っています。
認可保育園をつくる財源がないという自治体は、税金の優先順位を洗いなおしてほしいと思います。
憲法25条はすべての人に健康で文化的な生活をおくる権利を保障しています。認可保育園に入れず、認可外にこどもを入れたことで経済的な重い負担を背負うことになったり、認可にも認可外にも入れず、仕事をやめざるをえなくなったりというのは、あってはならないことです。
以上2点述べさせていただきました。待機児童問題を考える参考にしていただければと思います。
それからもう1点、駒崎さんのブログにでてくる、こども子育て新システムについては実は保育関係者のほとんどが反対してます。重大な問題がたくさんあるのですが、たくさんの方がこの問題については、文章を書いているのでこの問題については今回はふれません。
ここから先は駒崎さんのブログの議論からはなれます。
実は、日本の経済界は、保育をビジネス=金儲けの対象にせよということを繰り返しいってきています。政府の規制改革会議等で、「(保育所が)株式会 社立となる事例はごくまれ」「株主への配当が制限されるなど、参入の大きな障害となっている」「阻害要因を早急に取り除くべきである」などと露骨に要求し ています。
株式会社など営利を目的にした事業体が保育園の運営にのりだす場合、保育の質を切り下げる危険性があります。実際、企業立のある認証保育所では、食材費を 一日一人数十円に抑えていました。給食には百グラム十円の鶏肉や見切り品の野菜を使い、おやつは卵ボーロ数粒などという実態でした。
保育園の運営の経費の大半は人件費です。人件費をあまりにも安くしたために、保育士がつぎつぎやめて入れ替わる、こどもにとって不幸な事態もうまれています。
もうけのために無理にコストを削ろうとすれば、こどもにしわ寄せがいくのが保育です。
経済界の側から、現在の認可保育園を自治体や社会福祉法人が運営していることについて、「既得権益」という言葉を使うのを目にしたことがあります。保育園の運営を「権益」という角度でみてしまう時点で、こどものためという視点からブレまくっていると思います。
この経済界の動きは政府もまきこんでいます。待機児童解消の問題とならんで、保育をめぐるこれから大きな問題になります。
いろいろ問題はたくさんありますが、こどものためならエンヤコーラでがんばりましょう。
執筆: この記事は宮本徹さんのブログ『宮本徹 いま言いたい』からご寄稿いただきました。
寄稿いただいた記事は2013年04月16日時点のものです。

































と自信があるのかないのかはっきりしない表情で応えるのを見ていると、思い出します。
1回目のあべちゃんのときに、年金未払いへの対応で、
「最後のお1人まで必ずお支払いします!!」と絶叫していたのを。
最後のお1人まで全然払われてないですよねえ~。
(この件はどうしてくれるんでしょう?100年安心とか言っていたことも)
ですので、待機児童なんか解消するつもりはないのでしょう。解消します!と叫んでいれば、自然と解消していくと思っているのではないでしょうか。
「待機児童解消するっていったら解消するんやもん!」