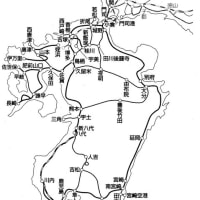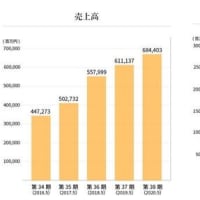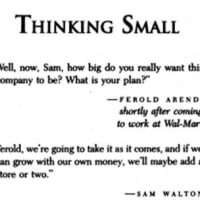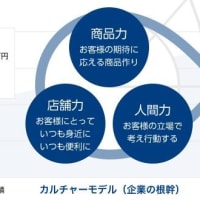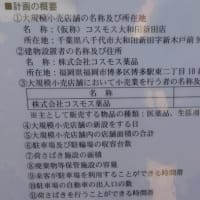2000年代に入り2けた成長が続き,「幻の焼酎」といったブームに沸いた本格焼酎。03年には清酒の出荷量を上回り,国民酒ともいえる存在となった。その本格焼酎は04年をピークに出荷量は横ばいである。
鹿児島県酒造組合が発表の08年7月~09年6月1年間(08焼酎年度)の需給状況によると,鹿児島県内の焼酎全体の出荷量は14万9531キロリットル(前年比1・7%減)と2年連続で前年を下回った。
◇
日本銀行鹿児島支店は,昨年2月に,「焼酎ブームのその先にあるものは?~今回の焼酎ブームの特徴」と題するリポートを発表している。
このリポートでは,焼酎消費について「平成17年度以降はほぼ横ばいの動きで,第3回目となる焼酎ブームも終わった感がある」 としている。 焼酎ならどのような銘柄でも売れるという時代は過ぎ去り,牽引してきた芋焼酎ですら中小メーカーを中心に格差が拡大しており,選別される時代に突入している,とも分析している。
この対策として,①市場調査をしっかり行い,②地元鹿児島の強みを活かしながら,③本格焼酎として,④他のメーカーと明確な差別化を図っていくことが従来にも増して重要,と提言している。
上述の日本銀行鹿児島支店の焼酎業界に対する指摘と対策は,傾聴に値する。なお,焼酎業界より一足先に消費減退に陥っている清酒業界の実態からして,日銀鹿児島銀行の提言する「4つの対策」に,次の2点を補足したい。
▼その一 鹿児島の焼酎メーカーは企業規模が脆弱
いまスーパー,ディスカウントショップにおける清酒の品揃えと売れ行きをみると,①大手メーカーの「紙パック詰めの低価格商品」が6~7割を占めてている,②ブランド力に劣る中小メーカー品は,トップメーカーの価格をを1.5~3割下回る超低価となっている,③新潟,長野,中四国の人気銘柄は,安定した売り上げを維持している。
このような流通の最先端にある大型小売店の清酒の販売動向からして,「価格政策とブランド力」が生き残りの鍵となる。
資本力と全国ネットの販売網,ブランド力の3点からして,鹿児島の焼酎メーカー」は,雲海,いいちこの三和酒類,霧島酒造といったビック3を遥かに下回る。いや,格差は広がるばかりである。
こうした経営環境からすると鹿児島県内の焼酎メーカーは,資本提携,経営統合といった事業統合による経営規模の拡大と,それに続く組織的なマーケティングによるブランド力の向上が必須である。
▼その二 差別化のポイントは低価格販売
清酒メーカー老舗の倒産,あるいは廃業の事例からみて,「よい酒をつくれば,必ず世間は認めてくれる」「老舗ブランドの信用力」「熱狂的なファンを持つ」といった点での差別化は,もはや通じない時代を迎えたといわざるを得ない。
これは何を意味するかというと,全国的なブランド力という裏づけがなければ,「差別化は至難の業」であり,唯一の生き残り策は「低価格販売」となる。
こうした点からすると,鹿児島の焼酎業界が「縮小の時代」を乗り切り,生存領域を確保していくには,「企業間連携による企業規模の拡大」か「大手メーカーの傘下に入り原酒供給(他メーカーからの生産受託による「桶売り」にシフトし,自社ブランド販売から撤退する」,あるいは,「販売エリアを南九州に絞込み地域密着経営に徹する」,の3点が生き残りに向けての「時代対応策」と考える。
◇関連ブログ:酒造メーカーの倒産 二題
焼酎ブームの終焉とその先にあるもの 2

★何でも揃う 楽天市場★
鹿児島県酒造組合が発表の08年7月~09年6月1年間(08焼酎年度)の需給状況によると,鹿児島県内の焼酎全体の出荷量は14万9531キロリットル(前年比1・7%減)と2年連続で前年を下回った。
◇
日本銀行鹿児島支店は,昨年2月に,「焼酎ブームのその先にあるものは?~今回の焼酎ブームの特徴」と題するリポートを発表している。
このリポートでは,焼酎消費について「平成17年度以降はほぼ横ばいの動きで,第3回目となる焼酎ブームも終わった感がある」 としている。 焼酎ならどのような銘柄でも売れるという時代は過ぎ去り,牽引してきた芋焼酎ですら中小メーカーを中心に格差が拡大しており,選別される時代に突入している,とも分析している。
この対策として,①市場調査をしっかり行い,②地元鹿児島の強みを活かしながら,③本格焼酎として,④他のメーカーと明確な差別化を図っていくことが従来にも増して重要,と提言している。
上述の日本銀行鹿児島支店の焼酎業界に対する指摘と対策は,傾聴に値する。なお,焼酎業界より一足先に消費減退に陥っている清酒業界の実態からして,日銀鹿児島銀行の提言する「4つの対策」に,次の2点を補足したい。
▼その一 鹿児島の焼酎メーカーは企業規模が脆弱
いまスーパー,ディスカウントショップにおける清酒の品揃えと売れ行きをみると,①大手メーカーの「紙パック詰めの低価格商品」が6~7割を占めてている,②ブランド力に劣る中小メーカー品は,トップメーカーの価格をを1.5~3割下回る超低価となっている,③新潟,長野,中四国の人気銘柄は,安定した売り上げを維持している。
このような流通の最先端にある大型小売店の清酒の販売動向からして,「価格政策とブランド力」が生き残りの鍵となる。
資本力と全国ネットの販売網,ブランド力の3点からして,鹿児島の焼酎メーカー」は,雲海,いいちこの三和酒類,霧島酒造といったビック3を遥かに下回る。いや,格差は広がるばかりである。
こうした経営環境からすると鹿児島県内の焼酎メーカーは,資本提携,経営統合といった事業統合による経営規模の拡大と,それに続く組織的なマーケティングによるブランド力の向上が必須である。
▼その二 差別化のポイントは低価格販売
清酒メーカー老舗の倒産,あるいは廃業の事例からみて,「よい酒をつくれば,必ず世間は認めてくれる」「老舗ブランドの信用力」「熱狂的なファンを持つ」といった点での差別化は,もはや通じない時代を迎えたといわざるを得ない。
これは何を意味するかというと,全国的なブランド力という裏づけがなければ,「差別化は至難の業」であり,唯一の生き残り策は「低価格販売」となる。
こうした点からすると,鹿児島の焼酎業界が「縮小の時代」を乗り切り,生存領域を確保していくには,「企業間連携による企業規模の拡大」か「大手メーカーの傘下に入り原酒供給(他メーカーからの生産受託による「桶売り」にシフトし,自社ブランド販売から撤退する」,あるいは,「販売エリアを南九州に絞込み地域密着経営に徹する」,の3点が生き残りに向けての「時代対応策」と考える。
◇関連ブログ:酒造メーカーの倒産 二題
焼酎ブームの終焉とその先にあるもの 2
★何でも揃う 楽天市場★
 | ビジュアル 流通の基本 (日経文庫)小林 隆一日本経済新聞出版社このアイテムの詳細を見る |
| 財界九州 2009年 12月号 [雑誌]財界九州社このアイテムの詳細を見る |