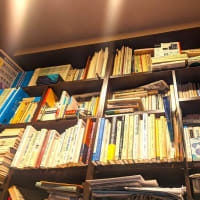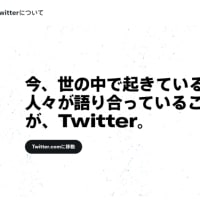コロナ禍で、不要不急の外出の自粛要請が出され続けています。
今もまったくそれがなくなる見込みなし。
オリンピックがそろそろ始まりますが、僕らの生活にはほぼ影響なし。
息詰まる日々だけが続きます。
きっと8月後半には、海外からのコロナが蔓延して、大変なことになっているのでは?、と懸念しています。ワクチンもどこまで効くのかよく分かってませんし、どんなに早くても10月~11月くらいにならないと、当たり前にワクチン接種が打てるようにはならないっぽいです。
…
そうなると、もう「本を読む」ということしか、安全に不安なくできることがない!
というか、こんな時期だからこそ、本をいっぱい読もうよ!って。
で、、、
先週末は、こんな本を読みました🎵
今、話題の本。共感(シンパシー)ではないエンパシーとは何か?という話。相手を真に理解するとはどういうことか。「他者理解」の研究をしている人には、もう何十年も前から議論されてきた話であれですが、この本をきっかけに、共感とは異なる他者理解があるということを知ってもらえたら嬉しいですね。この話は、僕がそれこそ教員になりたてのころから話してきた話であります☝
今、人気絶頂のひろゆき氏の本。とてもストレスなくサクサク読める本。個人的に、ひろゆき氏って好きなんだよなぁ。年齢は一つしか違わないし、話し方も似てるし、忘れっぽいところも似てるし、ADHDっぽいところもそっくり。なんか、子どもがADHDで悩む親御さんに読んでもらいたいかも。そんなにぶっ飛んだことは言ってないけど、「そうだよなぁ」と思うところがいっぱい。「変わり者」の人や変わり者になりたい人は是非読んでほしいですね。
ツイッターでもつぶやきましたが、この本は、政治家の本としては突出して面白かったです。映画「なぜ君は総理大臣になれないのか」の続編?副読本?みたいな新書で、野党でしかもぱっとしない政治家にスポットライトを当てつつ、これまでの(自民党だけに有利な)政治システムを批判的に捉え直す本になっているかと思います。あと、小川さん、大学時代全然学問してなかったんですね。そこがやけに印象に残りました。安倍さんの『美しい国へ』よりはるかに面白いです。
僕の学問的ベースにあるのが、現象学と批判理論なんです(現象学と批判理論のミクスチャー系?)。その批判理論を生み出してきたフランクフルト学派の歴史や歩みを論じながら、第三世代(ホネット等)以降の批判理論を描こうとするアメリカの政治学者Stephen Eric Broonerの訳書。僕的には、エーリッヒ・フロムの話が出ていたので、読もうと思いました。あまりフロムと批判理論って一般的にはつながらない感じですが、深いつながりがあるんです。また、(アメリカの学者の)アドルノやベンヤミンの捉え直しも興味深かったです。
香港は今、どうなっているのか。すごい特集でした。2年前に香港に行く予定でしたが、デモの過激化によって渡航を断念しました。それから2年。香港は、模範的な自由で民主的な国から、監視社会+警察国家になってしまったという衝撃的なレポでした。「国家安全維持法」により一般市民を警察が弾圧するようになり、117人の市民が逮捕された、と。特に教育現場の極端な改革には驚かされた。「通識教育」(リベラルスタディーズ)は潰され、それに代わって順法意識と愛国心を育てる「公民と社会発展」という科目が出された(これはアベ政権が目指した方向とかなり近い)。読んでいて辛かった…。
週間ダイヤモンドの「教師特集号」。一応、教育学者なので読んでおこうか、と。ツイッターで「#教師のバトン」が話題になったことから、この特集が組まれたみたいです。これ、教師になりたい人は(嫌でも)読んでおくといいかも。教育現場がどれだけどれほどブラックかが分かる特集です。ただ、これを読んでも、「教師としての力」は育たないな…。ただ、こういう「外部の目」って大事だとも思いました。
僕のライフワークである「愛することと学ぶこと」。その根本にあるのが、プラトンの「エロス論」やアリストテレスの「フィリア論」。そんなプラトンが友愛や恋について語っているのがこの小さな本。リュシスは推定13歳くらいの少年。その彼やメネクセノスとソクラテスの対話がとても面白い(&難しい)。「愛することの意味」を考えたい人にはとってもいい教材になるなぁと思った。また、親の愛についても語られているので、親や保育士にもおススメかも。コロナ禍の今だからこそ、こういう普段読まないような本に触れてみるのもいいんじゃないかな?!
そして、僕の最高の愛読書「WeRock」。今回は「ガルネリウス特集号」。もう、最高でしたね。ガルネリウスのインタビュー記事は必見。小野さんとSyuの生い立ちに迫るインタビューもすごく面白かったです。あと、44MAGNUMのBANさんのインタビューがすごくよかったです。44MAGNUMは、D'ERLANGERの師匠的バンドですからね。「ジャパメタ時代」の話もとても貴重で読みごたえがありました。
***
コロナ禍じゃなければ、こんな記事は書かなかっただろうなって思います。
あんまり書評とか書いている時間とか余裕とかないし…。
でも、不要不急の外出の自粛が要請されている今、「どのようにして己の生を充実させるか」という問題には向き合わざるをえないんですよね。
この国には、幸い、膨大な本があります。次々に本が出版されています。もちろん国家による規制もほぼほぼありません。僕らは、すごく恵まれた国に生きているんです。それに、Amazonや楽天など、通販もどんどん簡単になっています。図書館だって身近なところにあります。
スマホを置いて、本を読もう。
あえて今、僕はそう訴えたいなぁって思ったんです。
だから、別に「この本を読め!」って言いたいわけじゃないんですよね。そうじゃなくて、「とりあえず自分が読みたいと思った本をかたっぱしから読むと楽しいよ!」って言いたいんです。
今回も、僕がただただ「読みたい!」って思った本を読んだだけです。
本来、本ってそういうもので…。読みたいと思ったものが、読むべき本で、誰かに指図されて読むものもでもないぞ、と。でも、本って、読んでいくうちに、色々つながってくるんです。ある本の中に出てくるある別の本の一文に惹かれて、その別の本を読んでみると、またそこにその別の本とは別の本の一文が出ていて…、みたいな。
それに、読みたいなって思う本を並べると、今の自分の頭ん中がどうなっているのか、何を志向しているのかが分かります。今の僕の頭の中は、今回ご紹介した本の内容でいっぱいです。
まぁ、また来週になれば、全く別の脳みそになっていますけどね。。。
こんな時代だからこそ、もっと本を読もうぜ、Baby!!
ってことで。。。




![ニューズウィーク日本版 7/13号[雑誌]特集 暗黒の香港](https://m.media-amazon.com/images/I/51ch93GkWiS._SL160_.jpg)
![週刊ダイヤモンド 2021年 6/12号 [雑誌] (教師大全 出世・カネ・絶望)](https://m.media-amazon.com/images/I/5132M0UDIIS._SL160_.jpg)