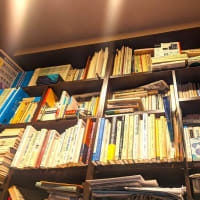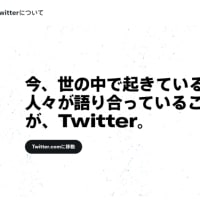昨日、ドイツから帰国したばかりなのだが、今日は早速千葉市内某所で「赤ちゃんポスト」に関する小さな講演をやらせてもらった。
聴きに来てくれる人のほとんどが、社会奉仕や社会貢献に関心のある千葉市の「実力者」(?)の方ばかり。議員さんもおられて。
話した内容は、今回のドイツで学んできたことが中心だった。僕的には、いい「復習の機会」となった。
***
そこで思ったのが、これもこれで「制度内への長征」かな、ということ。
僕は基本的に、研究者だし、政治に介入する気はないけど、でも、政治的に動くこともまた大切なことなのかも、と。政治家だけが「政治」じゃない。政治的な空間は、僕らの生活に関する事柄を決定する場所であるし、緊急下の女性の支援、あるいは母子の支援はまた、政治的問題でもある。
「みんなの声」の中に、僕の声が入ってもいい。というより、僕もその声の一人としての主体性をもっている。政治家にはならずとも、政治家の人に声を届けることはできる。「赤ちゃんポスト研究」を本気でやり始めてから、時折政治家の人たちにこのことを話すこともでてきた。僕の研究は、きわめて「政治的」な問題でもある。
もちろん僕は研究者だから、ある種、ドライに、客観的に、事実に基づいて語る必要がある。けれど、その研究の成果は、政治的な問いかけを含んではいる。赤ちゃんポストは合法なのかどうか。匿名出産を日本で行う場合の政治的制約はどこにあるのか。この問題についての法改正の可能性はどこにあるのか、あるいはないのか。
ドイツでは、実践者や研究者たちの「運動」から、法改正へとつながっていった。僕の仕事は、「赤ちゃんポスト」を風化させないことだとも思う。
今日の講演会で、とある中年男性から、「赤ちゃんポストって、前に話題になったやつですよね。あれ、まだあるのですか?!」、と驚くように言われた。それが、今の日本の実情だとも思う。それが「風化」だとも言える。また、他の人からも、「ああいうところに赤ちゃんを預けるなんてもってのほか。育てられないなら、赤ちゃんを作るな!」という声が聞かれた。それも「ごもっとも」。
でも、それでも、そういう女性はいるし、苦境に立たされる母子はいる。ドイツでは、この12年間で、1000人の赤ちゃんが、赤ちゃんポストないしは匿名出産を通じて、生まれ、そして育っている。日本でも、わずか数年の間に90人の赤ちゃんがこうのとりのゆりかごに預け入れられた。また、年間20万程度の堕胎も行われていることも忘れてはいけない。
こうした問題は、まさに政治的な問題だ。
「赤ちゃんが産めない」、「赤ちゃんを医療機関で産めない」、「誰にも相談できない」… どれも、「子育ての問題」である。子育ての問題は、政治的問題である。子育て問題の中には、妊婦の問題も含まれる。妊婦問題は、これまでずっと私事に関わること、ないしは産婦人科にかかわる内々のこととして済まされてきた部分があるのではないか。
しかも、こうした問題は、日本国内の女性であれば、誰にでも遭遇し得る問題だ。ドイツでも、その利用者(=緊急下の女性)のほとんどが、ドイツ人だという。すべての女性に起こり得る問題であるならば、それは女性の政策にもかかわってくる事柄である。子育て支援というと、「待機児童ゼロ」だとか、「少子化対策」だとかしか、でてこない。これは、女性問題に関する政治的関心の低さ、ともいえなくもない。
それに、僕が一人で学術的にこの問題を研究していても、それで何かが(直接的に)変わるわけでもない。学者の使命として、「制度内への長征」があってもよい。制度内への介入の仕方はいろいろだ。僕は僕なりの仕方で、政治的、あるいは公共的に、長期的にかかわっていきたいとも思う。もちろん、自分の立場を十分に踏まえた上で。(利用されるようなことがなく、かつ、建設的な議論を作る、という意味で)
ドイツでは、学者と政治家の対談や対話が結構あるし、また、学者が世の中に、(評論家としてでなく)学者として、発言する機会も多い。赤ちゃんポストの問題もしかり。
この夏に学んだ「制度内への長征」という言葉は、今後の僕の一つのキーワードになるだろうな、と。
制度内への長征
http://blogs.yahoo.co.jp/urabe_tarou3/32957717.html
この言葉を使った人物について
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%83%89%E3%82%A5%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%B1
ドゥチュケは、赤ちゃんポストを考案したシュテルニパルクの代表のユルゲン・モイズィッヒがかつて本の中で紹介していた人物。当然、ユルゲンも、この「制度内への長征」という言葉を知っていたし、ドゥチュケからも学んでいたはず。
この概念をもってこそ、シュテルニパルクの活動の本質が分かり得るだろうし、この団体の本質に迫るキー概念だと思う。
デモをしたり、政治家になったり活動家になったりすることなく、この「長征」を行うことも可能だと思う。
日本だと、相当長い道のりになると思うけど、すべての母子が安全に、そして平安に出産をすることができる社会づくりのために、僕なりの仕方で制度内への長征をしていきたいと思った。
今回のこの講演もまた、その一つと考えたい。
***
それにしても、緊張したわー、、、汗
基本的に、ひきこもり体質の僕には、なかなかの試練だった…