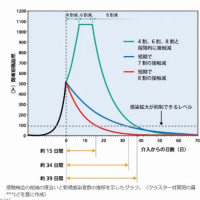地元の映画「標的の村」上映会に参加して
-高江と辺野古の緊迫状況に向き合うために-
地元の小さなカフェでの映画「標的の村」上映会に参加した。
「標的の村」は主に沖縄県東村高江のヘリパッド建設反対闘争の周辺を記録した、琉球朝日放送の報道番組を原型とし、その後を付加した映画だ。特に映画の方は、テレビ番組に使うことができなかった、生々しいシーンが多く挿入されている。報道スタッフを巻き込んだ弾圧の現場、警察と市民に分かれて沖縄県民同士が戦わされることへの悲痛な叫びの姿がある。この映画を観るのは本当につらい。自分がこの間「できない言訳」を繰り返してきたことへの罪責感に苛まれる。
僕は沖縄へそれなりの頻度で行っているが、高江は避けてきた。実際、1泊や2泊程度のスケジュールの中で訪れるにはとても遠いし、戦力として機能できるには1週間位は現地に入るべきで、それができない、ということがある。
ただ、避けてきてのは遠いからだけではない。やはり、東京で集まっている支援者の世代や出自が醸す雰囲気が、僕が経験している、いわゆる伝統派の活動家の作風と少し違うので、自分がうまくなじめない感じがして、遠慮してきたところはある。もちろんそれは僕の勝手な感覚で、実際、「沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック」の運営委員で、高江への派遣実績がないのは僕だけではないかと思う。
今日の上映会にはゲストトークがあり、状況がひっ迫する中で、現地の高江住民の会の方ではなく、東京で支援活動を担う「ゆんたく高江」の方が来ていた。その話の中野体験や知見はとても説得的で、運動の中によくありがちな「熱い思い」だけの人や、知識を鼻にかける人ではなく、多角的な観察力や冷静さや思考の深さやコミュニケーションの力などが総合的にある優れた人だと感じた。そんな人が、映画のシーンの説明で、「眼鏡をかけたおじさんが」と言いかけたところで、僕がつい懐かしさから「大西さんですよね、去年亡くなった」と口を挟んでしまい、そのきっかけで言葉を詰まらせ絶句してしまった。
彼は、その時泣き崩れる寸前だった。
彼が例えば大西照雄さんというひとりの人についても、どれだけの経験を共有してきたのか、それだけでわかったように思う。今まで勝手な苦手意識で高江の支援運動に距離を置いてきたことを本当に申訳なく思った。
上映会参加者は女性が9割近かったと思う。質問や意見が積極的にあったのは年配の女性が多かった。その中でかみ合ってない、と思うことがいくつかあった。否定的ではないにしろ、映画を見て、たくさんの説明を聞いて、でも結局は「アベシンゾウが悪い」「秘密保護法の問題と一緒」と言う。関係があるのは当たり前だが、そういう自分の既知の結論に結び付くものしか受け入れられないのだろうか。「政府が悪い、自分が正しい」を言い訳にしては何も進まないだろうと思ってしまう。また、自分たちの足元で何かを、という発言があった直後に、「反原発でそれどころじゃないわ」という発言もあった。
確認すべきことは2点ある。
まず第1に、「ゆんたく高江」のスピーカーが繰り返しているように、重要なのは「東京で私たちが抑圧の元栓を止める」ということだ。沖縄への基地集中と圧倒的な抑圧と暴力の背景は、沖縄へ犠牲を強いることを暗黙の了解事項とする私たちの差別性であり、抑圧と暴力を止めるためには、加害者としてのあなたと私が今ここで状況を変えようとする具体性が問われているのだと考える。心折れ、無力感に苛まれることが繰り返されても、責任の一端が私たちにあり、状況の根が自分たちにつながっている限り、逆に私たちがそれを覆し変えていくことも可能だと信じてよいのだと思う。
第2に、毎週官邸前で抗議行動を持続するのも大変なのは知っている。だからと言ってそれをアリバイにしていいことではないだろう。何万人が声をあげても政府はそれを無視することが可能で、官邸前の抗議行動だけで状況を止められないのはわかっているはずだ。あえて言えば、群衆の中で「自分のできること」だけを繰り返す中で自分をごまかしていることがあるのではないか。身近な地域でリスクを冒して声をあげることで、今「すごく大変なことを一生懸命やっている」と自己評価している自分の、本当の実力が試されるように思う。その営為を背景にしてこそ、官邸や国会や霞が関への行動も生きてくるのだと思う。
しかし、その苛立ちは、すべて自分自身にも跳ね返ってくることなのだ。そのことができていないこと。足りないこと。届かないこと。日々、何かにかこつけてその言い訳をしていること。僕自身の罪責感の正体はそこにあるのだと思う。僕の場合は、障害福祉に関わる仕事をしていること、とりわけ相談支援の業務をしていて、それが思うように進んでいないことを、日々「やれないこと」の言い訳にしてきている。
僕は、自分の経験を通して、さまざまな課題のある中で、障害者の権利こそが最優先であり鍵であると考えている。自分にとって、そこを通してしか学べないことはたくさんあったからだ。それでも、他の差別が二の次でよいという話ではない。唐突に30年前の話に飛んでしまうが、大学で悶々としながら障害者の自立生活支援に携わっていた1983年に、僕はなぜ信原孝子さんのレバノンからのレポートに魅かれたのか。パレスチナの人々が、日々命を奪われるような絶大な暴力と抑圧の中で、なお、より弱きものへの抑圧の転嫁に向かわなかったことが希望として、具体的にレポートに書かれていたからだと思う。信原さんの希望は、そのレポートを受け取る僕の希望でもあった。
------------------
爆弾が病院の玄関口で爆発したり、夜道で不発弾やクラスター爆弾を踏んでしまうことを恐れて、懐中電灯を照らしながら、恐る恐る歩いたこともあった。病院の隣の10階建のビルが、イスラエル軍の真空爆弾で音もなく崩れたこともあった。いつその病院が砲撃されてもおかしくない状況だった。そんな砲撃が数日続くと、正気を失いそうになる。
しかし、そんな状況の中でも、パレスチナ人の少女たちは、重い救急袋を抱えて走り回っている。小児マヒや眼の不自由な子が、一生懸命に看護婦の仕事を手伝っている。負傷した住民や動けない老人を必至に救出しようとしている。負傷し、松葉杖をついている青年が、我を忘れて自分の杖を放り出し、負傷した老婆を抱きかかえて救う。その後で、ふと我に返り、自分の傷の痛みに気づく。その困難な状況の中で、打ちひしがれて号泣しても、また立ち上がって闘っていく。また自分は貧困で苦しんでいるのに、利己を超えて救援活動を続けていく。そんなパレスチナ人たちの姿を目の当たりにすると、信原さんも『これは逃げるわけにはいかない。自分もここで殺されてもしょうがないなぁ』という気になってしまう。」
「爆弾が落ちて柱が崩れそうになると、パレスチナ人は、まず他人をその柱からどけようとする。そんな行為がとっさにできる。だから、浮き袋が一つあろうが、二つあろうが、どうでもいいのです。みんな一緒に泳げばいいのだから。日本では考えても、考えても、判らなかったことが、あそこへ行けば即座に解答が出てくるんです」
パレスチナに生きた17年─医師信原孝子さんが見たもの─
土井敏邦 月刊誌『世界』(1991年2月号/岩波書店)掲載記事
http://www.doi-toshikuni.net/j/column/20140615.html
------------------
障害当事者もまた、自分の既得権だけを主張し続け、他の場面で相対的には自分もまた他者への抑圧者であったりすることを省みなければ、その営みは衰退する。そのことを福祉工場の職場と労働組合の中でとても強く感じた。障害福祉の課題は他の差別を容認する中では解決を見いだせないことを、障害福祉や支援に関わるすべての人に伝えたいと思う。
7月になって、高江と辺野古へは同時に工事強行の攻撃がかけられる事態になり、両方の闘争を一体のものとして取り組んできた現地は、支援者を二分せざるを得ない苦しい状況になっている。ここで支援が辺野古派と高江派になったら敵の思う壺なのだ。抑圧の根は沖縄ではなく、この東京にこそある。だから東京で闘うのが本旨だが、今は現地を支える人も足りない。24時間の監視体制が必要な中、現地の人は疲弊しているのに、組織的な運動の動員が幅を利かせる時代は終わって、仕事を休んで現地に滞在できる人は現実的に限られているからだ。今、個人的な努力で現地に向かえる人が、とりあえず現地の手足となり、他の人々にその背中を示していくしかない状況は確かにある。
そういうわけで、「仕事が進まないから、できない」を僕も言わないようにしようと思う。
そうでなくては、あの福祉工場での去った20年間と変わらないのだから。