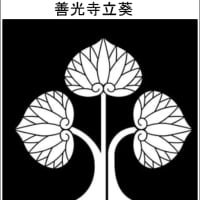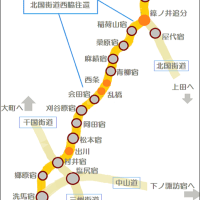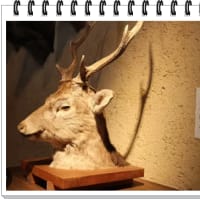大圓寺あたり・
東武野田線・七里駅近く(約200m)に大圓寺という寺はある。
案外威風堂々であるが・、建築は古くないようなので、改築されたのだろう。

さて、どんな由来の寺だろうか、と興味がわく。境内に「縁起由来」の碑が建っている。御影石に文字を彫りこんだ、かなり立派なもの・・これも最近のものと見ゆる。


内容は、以下による・
「縁起」によれば、正保年間(1644~)に災い(=火災)にあったのだろう。それで、詳しい記録は焼失したのだという。
開基が「太田資高」で、「陽光院殿」が目立つ建物だから、陽光院(=太田康資の室)の院所だったのだろう。
「大円寺古天明霰釜(市指定文化財工芸品)」という茶釜があるようだが、道灌の供養に参詣した人に、もてなしたもののようでもあるが、道灌は、伊勢原で謀殺されており、ここには慰霊のための「位牌」のみがあったのだろうか。

「鷲嶽山」とあるのは、七里駅周辺は、むかし「鷲神社」の神領で「鷲」という小字名で呼ばれた地名からであろうか?
どちらにしても、風渡野、門前、宮下などの郷村は、戦国期には、岩付・大田家の知行地・領土として存在していたらしい。
太田康資が、河越・扇谷上杉が小田原北条に敗戦した後の武将のようだから、彼の側室・陽光院は、小田原北条ゆかりの人と思える。
大田家が小田原北条に屈した後の物語上の寺なのであろう。