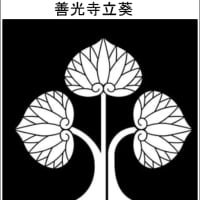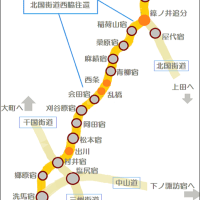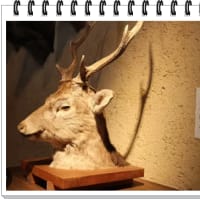道祖土神明社
神社分類で特にややこしいのは「神明」と「明神」の分類である。自身の出自の田舎に、一族の氏神様「おしめんさま」があり、神明神社を管理していたからだろう。「おしめんさま」の存在がなければ、「おしめんさま」が「神明社」のことであることも関心も持たずに過ごしたのだろうと思う。
「おしめんさま」の、間違いなく「お(御)・神明・さま」に他ならないからであり、「アマテラスオオミカミ=天照大神」のことを祀った神社だからである。
従って、明神よりやや神が具体的なのであり、狭義でもある。鳥居の形にも、違いが表れるが、まず内容の違いを理解することから始めた方がいい。
せっかくだから、分類を以下に示す。
------------------------------------------------------------------------------
1:明神(みょうじん)―神社一般
2:神明(しんめい) ― 伊勢信仰系 ― 天照大神
3:天神(てんじん) ― 天神信仰系 ― 菅原道真
4:天王(てんのう) ― 祇園・八坂信仰系 ― 牛頭天王(スサノオノミコト)
5:山王(さんのう) ― 日枝・日吉神社系 ― 比叡山 ― 天台宗
------------------------------------------------------------------------------
「道祖土神明社」というのがある。あまり大きくない・
・
道祖土神明社の道祖土は「さいど」と読む。たまたま、以前に学習していなければ、ほぼ正確に読むことは出来ない。難しい読み方である。
道祖土は、さいたま市緑区のうち・一時は「三室」の一部でもあったし、三室の隣村でもあった。

何故この地名が付いたのかは不詳であり、中世に、岩付城・大田氏の家臣に「道祖土氏」があり、この三室の「道祖土」に住んでいたのも事実である。
この場合、「道祖土」という土地名に住んだので「道祖土氏」と呼ばれたのか、「道祖土氏」という豪族がいて、たまたま住居を構えた土地を「道祖土」と呼ぶようになったのか・これも詳しからず・・


次回は、岩槻城・大田家臣の道祖土氏が、何故川島・八林にに移住したのかを探る?