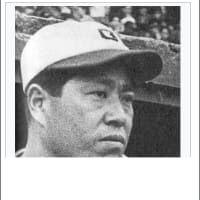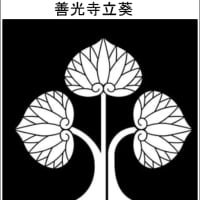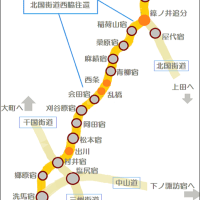11:むかしの「松本」?
「松本」学、あるいは「松本」考:9
11:むかしの「松本」?
:11-1:茶屋明延? ・・・
没年:天正19.5.25(1591.7.15) 生年:生年不詳

戦国時代の武士,豪商。信濃守護小笠原長時の家臣中島宗延の子。通称は四郎左衛門尉。明延もはじめ武士で小笠原長時に仕えていたが負傷して武士をやめ,天文(1532~55)末年ごろから京都に住んで商人になった。茶屋は屋号。ただし茶を商っていたわけではなく,呉服商であった。茶屋を称するようになった由来は,旧主小笠原長時が武田信玄に信濃を逐われ,一時,上杉謙信の保護を受けたあと,三好長慶を頼って京都に逃れ,将軍足利義輝の弓馬の師範となったことと密接に関係する。そのころ,明延は自分の屋敷に茶屋を作り,茶の湯三昧の生活を楽しんでいたが,長時に伴われた義輝がしばしば茶を飲みに立ち寄ったところから,いつしか「茶屋」と呼ばれるようになったという。明延の子清延が四郎次郎を名乗って,徳川家康の御用商人(呉服商,朱印船貿易家)となり,以後代々四郎次郎を称して発展する。
(小和田哲男)・・ 出典 朝日日本歴史人物事典
・・ カラー文字(アンダーライン)の部分は、間違いである。小笠原長時が、父・小笠原長棟から家督を継いだのが、天文10年(1541年)のことであり、長棟が退役した時に、同時に、臣下を辞した」とする方が合理的である。また、明延は、豪商ではなく、子息・清延以降から、呉服屋を営み、「茶屋四郎次郎」を屋号としたようである。明延が京へ上る際、三河の「伴野小笠原」を出自とする小笠原家に世話になり、その頃既に、家康の家臣になっていたも三河・小笠原家の関係で、茶屋四郎家は、「徳川家」の御用商人となったのだろう。茶屋家」から時々「家康」への武家家臣が出ているし、茶屋家」が、後継ぎ問題が発生した時、家康から、「中島某」が武士から商人へ戻ることを要請された」とある。
さて、「中島明延」は松本・松本周辺に出自の爪痕はあるのか?
といっても、調べる術を知らない。術を知らないまま、「中島」姓の旧家・豪農辺りがあるのかどうか調べる。
ここからは、多分に、推論が入る。
歴史、とりわけ日本史の場合、実証的検証の積み重ねの歴史事実確認が、つまりーー帰納的論理方法が主流であり、そのため、時間経過が過ぎればすぎるほど、古くなるほど、資料は散逸し、時には焼失し、時には流失し、時には盗難し、辿ることが不可能になる。こんな時に「有効」な方法が、推論が先にあり、あとで証左を探るという方法・・歴史のダイナミズムな「ストーリー性」は、こちらの方の方法論からのようで、司馬遼太郎の史学は、これに近い。
松本で、中島」という姓には、「中島 治康(なかじま はるやす)」を思いつく。
・・・ <写真>
<写真>
中島 治康(なかじま はるやす、1909年〈明治42年〉6月28日 - 1987年〈昭和62年〉4月21日)は、長野県東筑摩郡中山村(現:松本市)出身のプロ野球選手(外野手)・監督、スポーツライター。
来歴 ・・松本商業(現:松商学園高)でエース・4番、1928年の夏の甲子園で優勝]。早稲田大学で野手に転向。藤倉電線を経て1934年に大日本東京野球倶楽部に入団。そのまま巨人軍結成に参加。 1935年に一度退団するが、翌1936年より春季リーグから右翼手のレギュラーとしてクリーンナップを打ち、7月15日には球団第1号の本塁打を放っている。秋季リーグからは主に4番打者を務め、この年の春・夏・秋通算でチームトップの打率.267を記録。1937年春は本塁打王(4本)、秋は打点王(37打点)[5]、1938年春は首位打者(打率.345)と次々と打撃タイトルを獲得。NPB史上初の三冠王となり、最高殊勲選手にも選ばれた。その後も、1940年まで四番打者を1941年以降は川上哲治に続く五番打者を務める傍ら、1940年(67打点)・1942年(60打点)と二度の打点王を獲得するなど、1939年から1943年までの巨人の第一次黄金時代に主軸打者として大きく貢献。(1943年)に監督を辞任した藤本定義に替わって、1943年には選手兼任監督を務めて54勝27敗(勝率.667)で五連覇を達成。1963年に野球殿堂入り。
中島」姓を名乗る家が、「中島 治康」出生地近辺に、複数あることが確認できた。そのうち数軒は、旧家でそこそこ古いことも確認できたが・・・
こんな記事も見つけました。・・・内田のカキ 今もたわわに実をつける老木 内田地区中村の中島家の庭に成育しています。市内最大のカキで、幹囲は根元で2.9m、目通り2.3m、太さは70cm程度で、高さは15mを測ります。富山という品種の渋柿の老木で、現在も実をつけています。-----なお、中島家の母屋は安永7年(1778年)に火災のため焼失し、・・・・・
それが・・どうした! ともいえます。
馬場家住宅 <写真>
<写真>
馬場家住宅は、松本市郊外内田の鉢伏山の西麓にある本棟造り(ほんむねづくり)の住宅です。馬場家の伝承によれば、先祖は武田信玄の家臣・馬場美濃守信春の縁者とされ、天正10年(1582年)頃、武田氏の滅亡を機に、内田のこの地を開発し、この住宅の原初を築造したとされています。
馬場美濃守信春 ・・・馬場 信春 / 馬場 信房(ばば のぶはる / ばば のぶふさ)は、戦国時代の武将。後代には武田四天王の一人に数えられる。文献によっては房信とも。武田信虎、信玄、勝頼の三代に渡り仕えた歴戦の重臣だったが、長篠の戦いで討ち死にした。
・・・
馬場美濃守信春」と松本との関係は、信玄が小笠原長時を信濃府中から追放して、深志・信濃府中を武田家の支配下に置いた時の「深志城」城代で、築城と河川工事を行ったと知られる。さらに嫡子・民部少輔は、織田の軍勢が武田攻めで侵攻した時に、織田方へ深志城を明け渡した」と文献にある。
ここからが、想像・構想であるが・・・
まず、内田・中山の関係は・・・謂わば、隣接又は大字小字の関係で、ほぼ同地区と思ってよい。かって古代は、この地区の近くに「植原牧」という官制牧場があった。また付近には、馬具や土器の産出する古墳も複数存在する歴史に深い地帯である。
もし、中島明延が、この地の出身で、「小笠原家」を辞して京に上るとき、明居館・住居と領地が空いていたとすれば、その後どうなったのであろうか?・・・
ここに、甲斐・教来石(北杜市)から「馬場家」が移り住んだという経緯が詳らかになれば、・・・
信濃府中・小笠原時代は植原城が置かれてこの城の管轄内で、小笠原の臣・村井氏が治めていたようだ。小笠原長時追放後は、この地の領土、内田・中山は、松本藩から分割されて、諏訪・高島藩に譲られて、馬場家」が、松本藩とトラブルルを避けるために「諏訪・高島藩」をひたすら頼ったとすれば、・・・
「小笠原貞慶」が松本城に復帰した時も、報復の危機を回避できたのではないか!・・・
この移住の経緯を暗示させるのは、馬場家と内田の大柿(中島家)は道を挟んだ隣という位置。
中島家の痕跡が頼れるとしたら、近在の寺にある「過去帳」か、係累の「中島家」に残っている(かもしれない)系図か、墓が残って居れば、墓石の刻印の生没年と戒名・本名か」、あるいは、馬場家に、移住の経緯を記した古文書がないのか?
・・だが、手足が多少不自由になった自分には、調査は無理かもしれない。