2003年春、和束町の砂防堰堤型堰き止め湖に放流ニジマス釣り場が開場した。
オープンの3年前(2000年)に試験放流した魚が野生化して釣れたことは信楽の奥でニジマスが夏を超すことができた事を示す。2003年はルアーでしかも手巻きのフェザージグで楽しんでいた。2004年からフライフィッシングの世界に足を踏み入れ、その迷宮を彷徨い続けているが、最近水質悪化が気になるのでちょっと記す。
確か2006年頃にサイホン型の底水抜き取りを設置し、数年後には水車(これは凍結防止)も設置。とはいうものの毎年水質が悪くなっていると思うのは気のせいじゃないだろう。
まず、放流されたニジマスとダムの水量とを考えてみよう。
ダムの水量、簡単に考える為上流部から堰堤迄300m、川幅50m最深部12mとする。
つまり二万トンになる。
この100ton(倍で200ton)の死魚からなる有機物を分解する生物を飼えば、水はきれいになるはず。
ただ、雑魚はフライにもアタックするので痛し痒しってところです。
一方、ブルックトラウトのヒレをモチーフにしたフライがある事を考えると、マスは死魚を底で食らっているかもしれません。となると、死魚を食らう生物よりもそれらの糞を分解する貝類の放流がよりいい結果を導きそうです。あとは、納豆菌と乳酸菌で水質改善に頑張ってもらいたいですね。
というか、調べたら、屍肉系の腐敗よりも二次三次の分解とデトリタスの低減につとめれば良い様な気になりました。となると上述の納豆菌や乳酸菌が有効かもしれません。
いずれ、もう少しきれいな水に戻ってほしいな。と。
オープンの3年前(2000年)に試験放流した魚が野生化して釣れたことは信楽の奥でニジマスが夏を超すことができた事を示す。2003年はルアーでしかも手巻きのフェザージグで楽しんでいた。2004年からフライフィッシングの世界に足を踏み入れ、その迷宮を彷徨い続けているが、最近水質悪化が気になるのでちょっと記す。
確か2006年頃にサイホン型の底水抜き取りを設置し、数年後には水車(これは凍結防止)も設置。とはいうものの毎年水質が悪くなっていると思うのは気のせいじゃないだろう。
まず、放流されたニジマスとダムの水量とを考えてみよう。
ダムの水量、簡単に考える為上流部から堰堤迄300m、川幅50m最深部12mとする。
すると堰堤部が幅50m深さ12mの三角形で、そこから高さ200mの三角錐が存在する事となり、体積は1/3*1/2*50*12*200=20,000[m3]となる。
つまり二万トンになる。
放流魚のトン数を考えてみよう。月一回の放流量が1t程度として2003年から2011年迄8年(96ヶ月)で96ton。100tonとして全体の0.5%か。
この100ton(倍で200ton)の死魚からなる有機物を分解する生物を飼えば、水はきれいになるはず。
どんな生物が考えられるだろう。
死魚はカワムツに食べられているので、雑魚を入れる事は良い事かもしれませんね。
・水性昆虫で圧倒的なスカベンジャといえば、ゲンゴロウ系(これは希少すぎるな)。
・アメリカザリガニ:これはニジマスの餌にもなるが、あまり良くない気がする。
・スッポン類(何匹か棲んでいる)
・貝類(タニシにカワニナにバカガイ)
・各種水生昆虫(これは結構棲んでいる)
・鯉類のさかな(鯉はいるのでニゴイも)
・アメリカザリガニ:これはニジマスの餌にもなるが、あまり良くない気がする。
・スッポン類(何匹か棲んでいる)
・貝類(タニシにカワニナにバカガイ)
・各種水生昆虫(これは結構棲んでいる)
・鯉類のさかな(鯉はいるのでニゴイも)
死魚はカワムツに食べられているので、雑魚を入れる事は良い事かもしれませんね。
ただ、雑魚はフライにもアタックするので痛し痒しってところです。
一方、ブルックトラウトのヒレをモチーフにしたフライがある事を考えると、マスは死魚を底で食らっているかもしれません。となると、死魚を食らう生物よりもそれらの糞を分解する貝類の放流がよりいい結果を導きそうです。あとは、納豆菌と乳酸菌で水質改善に頑張ってもらいたいですね。
というか、調べたら、屍肉系の腐敗よりも二次三次の分解とデトリタスの低減につとめれば良い様な気になりました。となると上述の納豆菌や乳酸菌が有効かもしれません。
いずれ、もう少しきれいな水に戻ってほしいな。と。














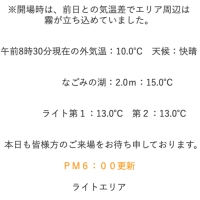





・リンや窒素などのミネラルを吸収して水の富栄養化防止
・光合成による溶存酸素量の増加
・水草を食べたり住みかにする昆虫や小魚の増加
・それを食料にするトラウトの野生化
とると良いのですが...
問題はなごみの水深でしょうか。
かなり深いので底のほうには日光が届かないかもしれません。
魚が藻の中に逃げて大変というのも又一興かと思います。
調べたら藻は水質浄化に有効の様ですが、枯れたり切れるとこれまた大変なようで、なかなか難しい様です。