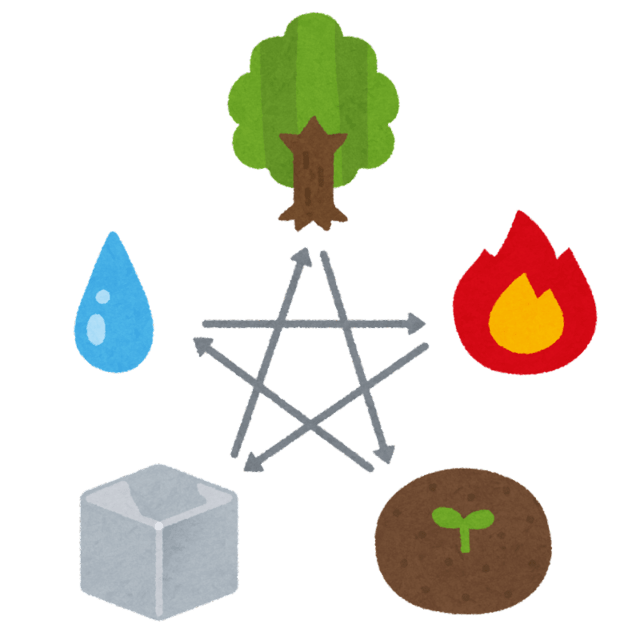春は「肝」に影響を与えやすい季節です。
東洋医学では「肝」は、
※「気」「血」の流れをコントロールする。
※「血」を蓄え、全身の「血」の量を調整する。
という働きをすると考えられています。
春は、「肝の気」が高ぶりやすくなります。
この時期に怒りすぎる。強い風に当たる。などするとさらに「肝」を傷つけてしまいます。
のぼせる。イライラする。目が充血する、目が見えにくくなる。涙が多くなる。
爪がもろくなる。声が大きくなる。強い口調でよくしゃべる。足や手がつる。
口が苦い。脇が重い、痛い。
これらは「肝」が病んでいるサインです。
これらのサインに気づいたら、春の養生法『ゆったりのびのび』を思い出して、
一日のうちに少しでも緩める時間を見つけてください。
(詳しくは 漢方コラム 漢方小噺~春の過ごし方~をご覧ください)
「肝」を元気にする食材は、酸っぱい味の物。にら。鶏肉などです。
木の芽の酢味噌和え。鶏肉とニラの炒め物、鶏肉入りの酸辣湯もよさそうですね。
不調が強くてつらい方は、
「肝の熱」を鎮める。「気」をめぐらす。「血」を補う。
など。おひとりおひとりの状態に合わせた漢方薬がお勧めです。
最近、なんだか調子が悪い。
「どこも悪くないですよ。」「様子を見ましょう。」と言われたけれど…
そんなモヤモヤ解消に漢方を試してみませんか?
あなたの体質に合った漢方薬をご紹介します。
何日分からでもお試しいただけます。相談は無料。お気軽にご相談ください。
詳しくはホームページから ⇒ https://hiroekanpo.co.jp/