混沌のコントロール、そしてカタストロフィー…現代、音楽作品を書く時、聴き手の心を惹きつけようとするなら、成否を分ける鍵となるのがこの2つだろう。
埴谷雄高氏の「死霊」に、それがある。
わが国初の形而上文学…と言われる「死霊」の作者、埴谷氏は愉快そうに言う―小説は論文じゃない。事実一つだけじゃ成り立たない。どう見てもこう見ても、虚構の世界をまるで実際にあるかのように信じ込ませるのが作家の力量。その意味では、夏目漱石など私小説の作家は一段下!と。
生前収録されたNHKのその番組('96年)では、「死霊」に懸ける氏の文学論が、分かり易く、熱く、格調高く紹介されていた。
構想を裏付ける独自の緻密なセオリー、文学作品として立体的にするための登場人物の設定…Mad・Sad・Bad・Gladの4兄弟、そして虚体…それらを駆使しながら、「宇宙の責任を問うのが新しい形而上学」とのコンセプトの下で、ストーリーは時間を超え、空間を超え、奇想天外に、しかし極めてリアルに発展する―これが「混沌のコントロール」。
そして山場(第7章)、食われたものが、食ったものを弾劾する…魚がイエスを、豆が釈迦を、わらが牛を…。
御伽噺に堕してしまい兼ねないスリルを孕みつつ、カタストロフィーとして、これ以上無い厳粛な空気をかもし出す。
氏の発言からは、ニーチェと共通するものを読み取ることが出来る。
「ツァラトゥストラ」の嫌悪―近代社会の集団化と平等化に対する嘔吐―さらに、時間に抗えない人間存在そのものへの嫌悪。道徳の否定、秩序の否定、教育の否定…。
ニーチェは、「なぜわたしはこんなに賢明なのか」「なぜわたしはこんなに良い本を書くのか」などを著した後、44歳で発狂してしまったが、埴谷氏は36歳で「死霊」に着手し、1997年に87歳で没するまで遂に完成することは出来なかった。「死者からの精神のリレー」(氏曰く)を受け継ぐことは、容易では無い。![]()













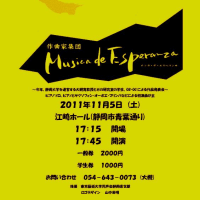



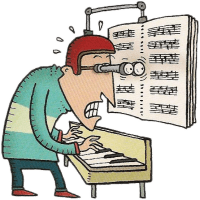

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます