8月31日
雨が続きます。
由緒書をあらためました。
杉森神社の御由緒
当神社の創立年月日不詳ですが、『日本三代実録』によりますと度重なる自然災害を鎮めるため、清和(せいわ)天皇(てんのう)が各地の神様に神階を授けられました。その貞観九年(八六七年)十月十三日条に、正六位上「榲樌神」に従五位下を授けられたのが当神社のことと伝えられています。
御祭神は、天(あま)照(てらす)大御神(おおみかみ)と須佐之(すさの)男(おの)命(みこと)による誓約(うけひ)(真心を表すこと)によりお生まれになった五男三女の神様
天(あめの)忍(おし)穂(ほ)耳(みみ)命(のみこと)、天(あめの)穂(ほ)日(ひの)命(みこと)、天津(あまつ)日子(ひこ)根(ねの)命(みこと)、活津(いくつ)日子(ひこ)根(ねの)命(みこと)、熊野久須毘(くまのくすびの)命(みこと)、多紀理毘賣(たきりびめの)命(みこと)、狭依毘賣(さよりびめの)命(みこと)、多岐都比賣(たぎつひめの)命(みこと)と、
相殿に品陀(ほんだ)和気(わけの)命(みこと)(応神天皇・八幡様)、須佐之男(すさのおの)命(みこと)(天照大御神の弟神)、厳(いつく)島(しまの)大神(おおかみ)をお祀りしております(「神社明細書」による)。
八幡様は、もと入野村の二ツ宮に祀られていましたが、祭礼の時に神輿が洪水で川に落ち、この里に流れ着き、岸に近い石上(推測ですが、鳥居前の延長上、線路の向側の田の中に大きな石があります)に留まっていたそうです。住民により古筵を折りかけ当社の相殿として祀られ、「筵屋八幡宮」と崇められました。
須佐之男命は、風呂本の八坂神社に祀られていましたが、明治四年十月に当社に合祀されました。
『芸藩通志』には当社は「八幡厳島神社」と記されています。
御本殿は、一間社入母屋(いりもや)造りで天保九年(一八三八年)に再建された建物です。
境内は、山林を含め約三〇〇〇坪。杉森という称名の通り杉と檜の約五〇〇本に囲まれた、癒しのお社です。
当社所有地である深山峡の夫婦岩と境内の夫婦杉は、「清く、正しく、睦まじく、お互いを助け合い、伸ばし合い、育て合う」神様の御心の象徴であります。

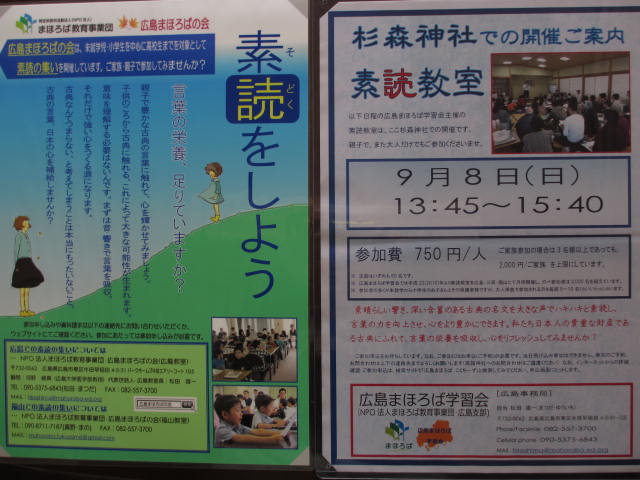
今日もご覧くださり 有り難うございます。
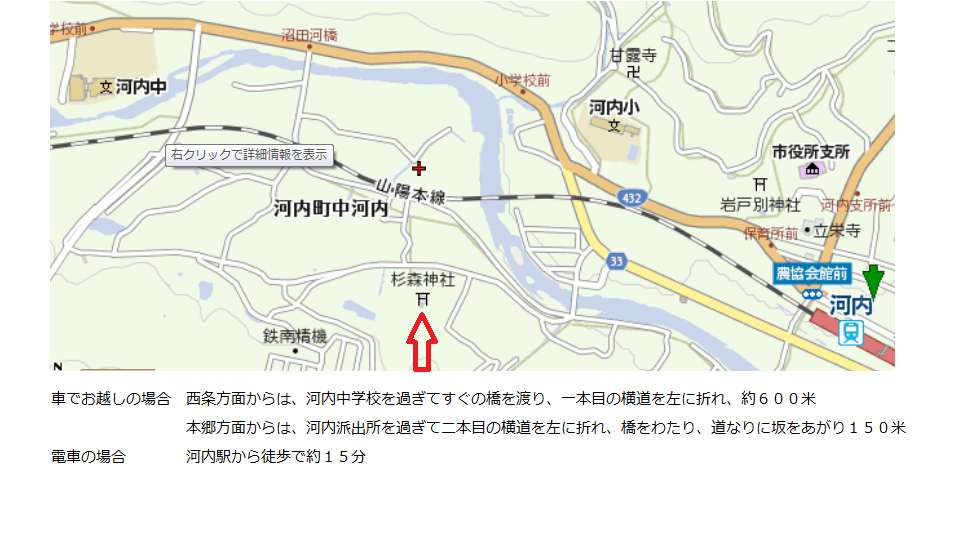













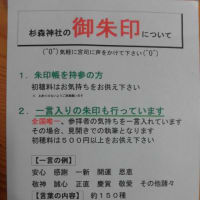






由緒書も現存しているのですね~驚き!~