緒方林太郎氏は、集団的自衛権の議論として、 「持っているのに行使できない」、さらに「持っているのに行使できない」(続)
として、論じられた。
なかなか理解しがたい「持っているのに行使できない」と言う論理である。
自衛権を国連憲章で形態に従って分離して考えただけとすれば、個別と集団的と分離する不都合にいたる。
誰も、国内法と国際法を区分してはいない。緒方林太郎 氏の意見は飛躍しすぎていると感じる。
コメントのtaketakemikamika 氏の考えには不同意である。
自衛権を憲法が禁止していないとする意見に合理性があると考える。
国連加入、日米安全保障条約締結、などの各種の条約批准の過程には、自衛権の禁止は無い筈である。
緒方林太郎
2014年03月09日 10:00
「持っているのに行使できない」
http://blogos.com/article/81948/
集団的自衛権の議論でよく言われるのは、「権利を保有しているにも関わらず、行使できないのは『おかしい』」ということです。「持っているのに行使でき ない」と言われると、感情的には「それはおかしいな」と思う方が多いでしょうが、これは、半分間違っていて、半分は理解できる議論です。
まず、何が間違っているかというと、集団的自衛権の権利が国連憲章第51条で定められており、国際法上保有しているからと言って、それを国内法制上どう いう形で行使し、しないかを決めるのは、あくまでも日本の自発的な判断です。国連憲章や慣習国際法で認められている権利は、当然にして日本は行使できなく てはならないというのは、実は日本国憲法よりも国際法を上位に置く考え方です。
一般的に、集団的自衛権を認めたいと思っておられる方は主権意識の強い方が多いと思います。しかし、その一方で「日本国憲法よりも国際法が上位規範だ」 という主権の一部を国際法に差し出すようなところからしか導かれない理屈を、無意識の内に持ち出しているのです。ちょっと知恵がついてくると、そういう主 張をして如何にも「オレは分かっているのだ」という顔をしますが、正直なところ歪んでいるのです。
では、何が理解できるかというと、「持っているのに行使できないのはおかしい」の意味合いが「(政治的に)おかしい」ということであれば、それは別に理 屈としては間違っていませんし、理解できます。つまり、「国際法で認められている集団的自衛権が、日本国憲法で制約を受けていることはおかしいから改正す べきだ。」という意味合いであれば、理屈の上では筋が通っています(そういう主張を是とするかどうかはともかくとして)。
「法規範上は」完全に間違っていて、「政治的主張としては」何ら問題がない、これが「持っているのに行使できないのは『おかしい』」についての正確な理解だと思います。
しかし、この辺りをきちんと分けて議論している政治家はとても少ないと思います。「持っているのに行使できないのはおかしい」と主張する方の発言を、上 記の「法規範上」「政治的主張として」の区別を念頭に置いて聞いてみてください。私は頭の中が「???」という感じになることが多いです。
緒方林太郎
2014年03月10日 10:00
「持っているのに行使できない」(続)
http://blogos.com/article/81997/
先のエントリー に対して、色々なご指摘を頂きました。どうも上手く意図が伝わっていないような印象があります。
私が言いたいのは、「集団的自衛権を容認するかどうかは、日本国の意思として大いに議論すればいい。ただ、それが国際法上権利として認められているから 『当然にして』日本の国内でも認められなくてはならないという論の立て方は間違っている。あくまでも判断するのは日本国である。」ということです。私の集 団的自衛権についての考え方の一部はこのエントリー に書いている通りです。
国際法上認められているから、当然にして日本国内でも認められるべきだ、というのは、国際法を憲法よりも上位に置く考え方です。そんな事を考えている人 はいないでしょうが、実は「持っているのに行使できないのはおかしい」と主張している方の話をよく聞いていると、そういう論理構成をしている人がいます (少なくとも混同している。)。
この事自体は、集団的自衛権が、自然権であろうと、国連憲章第51条に起因するものであろうと、あまり関係ないのです。実際には、国連憲章制定時に国連 による集団安全保障が常任理事国の掣肘で機能しない時のために、第51条が設けられたわけでして、その過程で「固有の(inherent)」という言葉が 入ってきました。それ以前に集団的自衛権という考え方が広く国際慣習法化していたとは思いませんが、とにもかくにもそういうことになったわけです。
ただ、国際法がどうであろうとも、それをどう国内で行使し、しないかというのは、偏に日本国としての判断です。そして、その最高法規は日本国憲法です。 「国際法上、保有することが出来るけど、それが国内で使えないという状態はおかしいから、『日本国の意思として』憲法改正、あるいは解釈を変更しよう。」 というのは当たり前の事です。
ここは単なる法的な瑣末な解釈論ではありません。むしろ、ここがスタートラインでして、ここで「国際法で認められるものは、当然にして国内でも認められる」論が罷り通ると、今、起こっているプロセスでもとても議論が混乱するのです。
日本は、国際法の直接適用を基本的にはやらない国です(例外は結構ありますけども)。国際法は常に国内法制度で担保していくようにしています。国際法を 日本が締結する際、国内法改正が必要なものは関係法令について国会審議をしますし、国内法改正が必要でないものについては行政取極として閣議決定で通しま す。例えば、今交渉しているTPPなんてのは締結に際して、条約本体と関係法令をそれぞれ外務委員会、関係法令を所管する委員会で審議します。
それが、集団的自衛権については、国内法改正ではなく憲法改正あるいは解釈変更になっているだけです。集団的自衛権は「権利」であって、「義務」ではあ りませんから、それを行使するかどうかは偏に日本国としての自立的な判断が必要、という当たり前の事を言っているだけです。
こうやって説明すると「当たり前だろ」と思うかもしれませんが、論者によっては「国際法の直接適用を憲法にも及ぼすべき。」と言っているように聞こえる方が結構います。その辺りの論理的な整理について書いているだけです。
そんなに大々的なことを書いているわけではありません。
退会者
原則論はそうだが、じゃあ個別的自衛権はどうなるのか?という話になる。
あれだって、国内で憲法改正を行うことなく、そして国民的議論を行うことなく認めた。
また、行使するかどうかは国民の選択によるとしても、その行使を禁ずる文言が無いということも問題だ。
基本的に、それが明確に禁じられていないなら、特に問題なく行使できると考えるのが当たり前の論理だ。
国際法が上か下かということではなく、「明確に禁じていないのに、なぜ禁じられていると言えるのだろう?」という背景が有るからこそ、国際法が持ち出されるのだ。
以前に、それを持ち出して個別的自衛権の行使を認めたように。
退会者
集団的自衛権の議論は、良し悪しは別にして、覇権主義的大国が当面の間存在することを前提した上で、①自然法的立場、②国連憲章的立場、③現憲法9条を是認する立場、④憲法改正を推進する立場、で議論するべきでしょう。自らの立場を正当化した教条的議論はかみ合わないのは当然です。特に、集団的自衛権の憲法解釈変更による行使容認と、憲法改正した上での集団的自衛権行使は、結果として同じ法的効果であっても、理論的には別のものです。
石田 力
フォローする
「集団的自衛権」とは、同盟関係にあるA国がB国から明確な軍事的攻撃を受けたことに対して、A国からの要請に基づいてA国を武力で支援する行為である。まずこの規定が正しいことを確認しましょう。
であれば、これはA国とB国の武力衝突にまで発展した国際紛争を、武力を行使することで解決しようという行為であります。これは憲法九条が明確に禁じている行為ですね。変な解釈の余地はありません。
68式
フォローする
軍事同盟とは、同盟相手が攻撃を受けた場合に、自分自身が攻撃を受けているものとして、反撃を開始します。 これは「攻撃を受けた事に対する、防衛発動」です。
よって、9条によっては束縛を受けません。
アメリカが日本が攻撃された時に、防衛出動するのは、これが理由となっています。
石田 力
フォローする
日米安保条約は双務協定ではなく片務協定という解釈だったと思いますが。
まぁ、そもそも軍事同盟を結ぶこと自体が憲法違反だろうと思いますがね。
68式
フォローする
>片務で良いという解釈
第5条
両国の日本における、(日米)いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動することを宣言している。
このように明記されていますので、(片務で良いという解釈)は間違っています。
・むしろアメリカから見て日本への防衛義務を明記したものではない。 等の議論もあり片務ですらないという意見もあります。
ここでは、米軍が攻撃された場合の日本の解釈なのでここでは議論の遡上には上げません。
まずは、この点について、ご自分の認識の誤りを認めてください。
では、次のご意見
>そもそも軍事同盟を結ぶこと自体が憲法違反だろうと思いますがね。
どこの憲法に違反しているのですか?
taketakemikamika
フォローする
「持っているのに行使できない」というのは、憲法さえ変えれば集団的自衛権の行使ができるということ。
「憲法を変えても集団的自衛権を行使できない」というわけではないということ。
将来的に集団的自衛権を行使する際に妨げにならないような布石だったのでしょう。











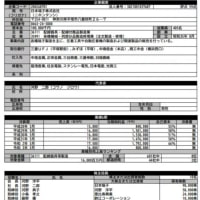
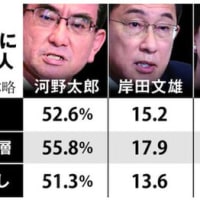
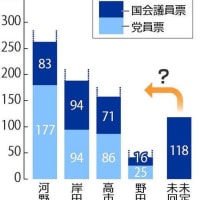



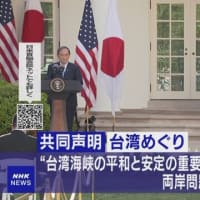
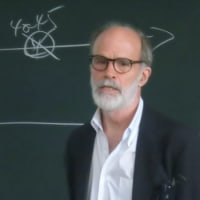

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます