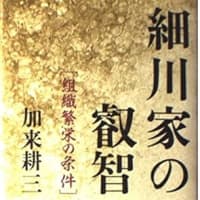ロシアのクリミア侵攻を見て思う、国が戦争に向かう時、為政者がその決断を下したのはどの時点だろうかと。引き返せる時点、というものがあったとしたら、それはどこだったのか。エリツイン政権を引き継いだプーチンは20年かけて今の独裁的地位を築いてきた。見かけ上だけなのかもしれないが、民主的選挙制度を通して、大統領、首相、大統領というポジションに座り続けた結果のはず。支持率は日本やアメリカのトップより遥かに高い。つまり、国民の支持があったから決断できたはず、なのに、ロシアの世論のマジョリティは侵攻に反対している。今のロシア政府内では独裁者だから、一人で決めたことを誰も止められなかった、という分析があるが、その地位を許してきたのはこの20年があったから。プーチンはこの日が来るのを虎視眈々と待ち続けていたのかもしれない。
戦前日本はどうだったのか。日清・日露戦争を経て第一次大戦を戦勝五大国の一国として戦った日本は、日清戦争以降、澎湖島、台湾を手に入れ、その後、満州の権益と朝鮮半島の実質的な支配を手に入れ、第一次大戦の敗戦国ドイツからは中国の権益と太平洋諸島の統括権を手に入れていった。米国による対日警戒感は高まってはいたが、シベリア出兵までの日本の動きは欧米諸国からも容認されていた。ここから1931年柳条湖事件を受けたリットン調査団報告書までの間に、国家としての「戻れない時点」があるはず。
リットン調査団報告書を受けて、日本政府は次のような見解を示す。「日本は満州をはじめとして多くの権益を手に入れるために数知れないほどの犠牲を払ってきた。日本にとっての満州は生命線である」。このとき日本の指導者たちは、欧米諸国にも植民地があり生命線であるはずだ、とも思いがあり、多くの植民地を持つ英国人にも理解されるはずとの期待もあったがそれは言下に否定された。「日本にも守りたいものがあるかもしれないが、欧米諸国も民主主義と自由・平等という価値観を守るために、日本以上の犠牲を払ってきたことを日本は知る必要がある」と日本の立場を否定した。
本書では、10の論点(天皇、女性、メディア、経済、格差、政党、官僚、外交、日米開戦、アジア)を示し、日本が戦争に向かった道筋を検証する。多面的論点整理は読者のためだろうが、「戻らざる時点」を知るために論点となるのはやはり外交と政治である。昭和が始まる頃、その後は幣原外交とも呼ばれた国際連盟における協調外交は、日本の国際的地位向上に寄与していた。1919年パリ講和条約での少数民族問題、1922年ワシントン海軍軍縮条約、1928年パリ不戦条約と積極関与を継続した。しかし、外交官たちはその時点ですでに、日中問題が俎上に上ったときのことを考えていたという。大正デモクラシー以降、厭戦の気運が広がる時期でさえ軍部による政治圧力を外交官たちが感じていたためであろう。1930年ロンドン軍縮会議での若槻礼次郎全権代表は、日本の対米英海軍補助艦保有比率交渉において、米国主張6割、日本主張が7割のところ、6.975というギリギリの線で外交決着を実現する。7割を実現できなかったことに反発した海軍は「統帥権干犯」を持ち出して、この後は浜口首相狙撃からテロが相次ぎ、クーデター未遂とも言える五・一五事件へと続く。統帥権干犯問題に拘泥することのない国会での批准決着は不可能だったのか。それよりも問題だったのは、軍部と政治・政党間の信頼感消失だった。国際協調主義は軍部との信頼関係破綻により、一気に消滅した。満州事変が起きたのはその時1931年だった。
広田弘毅を主人公にした城山三郎の「落日燃ゆ」では、広田が次のように側近に漏らしたとされる。「長州の作った憲法が、日本を滅ぼすことになる」これはワイマール憲法を学び統帥権の独立を認めた明治憲法を指してのこと。しかし幣原喜重郎は敗戦直後、第一次大戦後の大正デモクラシーの時期に、「軍隊なんて余計なもんだ」という風潮が広がって、逆に軍部に反発感が広がり、不穏の情勢を生み出した、と反省したという。大正から昭和はじめのこの時期の日本に、近代的デモクラシー推進と明確な戦争反対の世論が湧き上がっていれば、この後に起きる軍部暴走を止められたかもしれない。「帰れない時点」の濫觴はこのあたりにありそうである。世論は世界恐慌による不況とメディアの好戦的論調に煽られて、政党政治を選択せず軍部主導の権益拡大路線へと進んでしまう。
真珠湾攻撃は事前にルーズベルトにより察知されており、わざと一撃を受けておいて一気に反日の機運を高めた、とする陰謀論がある。筆者によれば、そんなはずはなく、外務省暗号はその時点で解読されていたとしても海軍暗号が解読されたのはその翌年春。そもそも3000人を超えるような犠牲を大統領が受容できるはずがないと。外交的技術論で考える「帰れない時点」は、開戦直前まで存在した。11月26日の最後のハル・ノートにおける「中国からの全面撤退」でも、中国に満州は含まれるのかどうか、という交渉ポイントはあった。1941年4月時点の日米国交調整提案を、近衛首相は受ける気を示す。しかしその直後、日ソ中立条約を締結し帰国して意気上がる松岡洋右外相は、日本の外交ポジションが強化されたと確信。提示されていた調整案を拒絶し交渉可能性が潰える。ひょっとして夏に提案されていた近衛ールーズベルト頂上会談で本調整案が議論されれば、対英蘭と違い、植民地の係争がない日米間の戦争だけでも避けられた、もしくは先延ばしは可能だった。
先延ばしには大きな意味もあった。冬季になれば東南アジアは雨季となり、陸軍の作戦行動が取りにくい時期となる。そこへドイツへのソ連反攻が始まる。そうなると、陸軍が主張する欧州戦線におけるドイツ優勢が危うくなり、開戦の決断にも陰りが出る。そもそも、開戦決断の根拠となる陸軍省経済研究班による国力調査において、日米国力差20分の1と報告されている。分析は圧倒的な敗北であるが、万が一の僥倖、という理論も示されていた。開戦を遅らせると、米による資産凍結、石油禁輸などの経済制裁で日本はジリ貧。しかし、独ソ戦でのドイツ勝利があれば、ドイツがソ連の資源を活用しイギリスを追い詰める。そうなればアメリカも戦争に積極的に離れない、という可能性にかけるという「万が一の僥倖」である。もし、この報告書に第三の案「臥薪嘗胆の3年」論が併記されていたとしたら、ひょっとして軍部首脳がその第三案に乗った可能性はなかったのか。1年でも待てばドイツの敗北は明白になっていたはず。しかし、日本の軍部首脳はこの「万が一の僥倖」に賭けるしかない、という決断をしたのである。陸軍教科書で、戦国時代の「桶狭間の戦い」など3千の兵力が2万5千を打ちのめす奇襲戦を学んで、初戦でかき回す、などという夢を見たのだろうか。
阿川弘之の三部作「山本五十六、米内光政、井上茂美」では海軍善玉論が示された。たしかに、米内海相ー山本次官ー井上軍務局長は日独伊防共協定強化に反対した。しかし海軍の中枢からこの3人は外された。それ以降、海軍上層部は中堅の強硬論に引きずられるように対米開戦を決めていく。慎重論を凌駕する強硬論による「万が一の僥倖」選択は海軍でも組織利益を優先させた判断であった。本書内容は以上。
ロシアのプーチンの侵攻決断は、万が一の僥倖に期待するわけではなく勝利を確信しているかに見える。また欧米による資産凍結や経済制裁は織り込み済みである。独裁者の強硬論を抑止する賢者による慎重論やその他オプションの出番は今のロシアにはないのだろうか。それとも皆で偉大なるソ連時代の国家復活を本当に妄想しているのだろうか。「Make America Great Again」「偉大な中華大国の復権」と通底するのが不気味である。