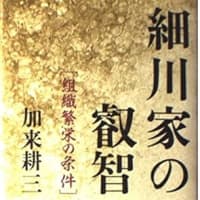平安末期の12世紀前半に成立したとされるのが今昔物語と呼ばれる説話集。全31巻で、天竺(インド)と震旦(中国)が第1巻から10巻、11巻-31巻が本朝(日本)における主題を扱う説話集であり、当時考えられる全世界の説話が収集された。本書では本朝の説話を収蔵する。
印象に残る説話は以下の通り。
1.真言宗の開祖、弘法大師が、天皇の御前で同僚の高僧の面目を潰すなどをして仲違い、お互いに「死ね死ね」と罵り合いの末、空海が一計を案じ嘘の噂を流して相手を騙し油断したところを呪い殺した、というもの。
2.日本国中咳き病が流行するとき、化けて出てきたのは應天門の変で殺された伴善男だった。その化け物が言うには、騙されたうえで殺されてはしまったが、この世には世話になったので、人々が死んでしまう病ではなく、咳き病で苦しむ程度で収めてもらえるように自分が頼んだのでこの程度で済んでいるのだ、というもの。
3.近衛の舎人が稲荷詣でで美人の女性に出会う。舎人は「自分の妻は老いて見苦しく、そなたのような若い女性とともに暮らしたい」とと告白する。若いと思った女性は舎人の妻であり、とんでもない目に遭う、というお話。
芥川龍之介は鼻、羅城門、芋粥などの作品を本今昔物語から着想を得て書いたとされている。芥川は今昔物語について次のように評価している。「今昔物語は野性の美しさに充ち満ちている。その美しさに輝いた世界は宮廷の中にばかりあるわけではなく、この世界に出没する人物は上は貴族から下は土民だの盗人だの乞食だのに及び、觀世音菩薩や大天狗や妖怪変化にも及んでいる。僕は今昔物語をひろげるたびに当時の人々の泣き声や笑い声の立ち昇るのを感じ、彼らの憎悪や武士に対する公卿の軽蔑の声の中に交っているのを感じた。王朝時代の京都さえ、牛車の往来する朱雀大路は華やかだったであらうが、小路へ曲れば、道ばたの死骸に肉を争う野良犬の群れはあったのである。夜になったら、あらゆる超自然的存在は、地蔵菩薩だの女童になった狐だのは春の星の下にも歩いていたのである。修羅、餓鬼、地獄、畜生等の世界はいつも現世の外にあったのではない」。
まさに芥川の評価する通りの世界が展開されているのが本書、今昔物語。本書内容は以上。