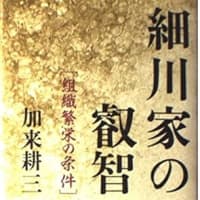黒潮の流れに沿って日本に存在する地名、潮の流れを小高い山に登って見たという「日和山」、全国に八十箇所も存在する。火の国から常陸に進出した多氏、地名にもその名を残している。尾生、御生、邑生、於保、飯宝、飫宝、大生などであるが、多神社の神主であった多氏の子孫達が肥の国から海を伝って北と南に流れていった。地名に多、飫富などを含むのは多氏の子孫たちに縁が深い可能性があるという。沖縄には奥武と名がつく地名が7箇所あるが、久米島の奥武、慶良間島にも奥武、名護や南城市の奥武島もその一つである。これらは「アフ、アウ、アホ」などから由来しているらしく青島という説がある。奥武島とは昔死体を運んで葬った島だった。日本本土にも「青」がつく海岸や湖沼があるが、埋葬地と関係があると考えられるという。宮崎の青島、丹後半島の伊根町にある青島、隠岐の大波加島、美濃の青墓、佐渡の粟島も昔は「オウシマ」と呼ばれていた。
西から東に移動した一族にアヅミ族がいた。安積、安曇、阿曇、安津見、渥美、温海、熱海、厚見などの地名に足跡を残す。アヅミ族は古代海人族であり、穂高見神を祖神とする。長野の安曇郡にある式内社の穂高神社はこの穂高見神を祀る。アヅミ族の他にも宗像大神、墨江大神を祀る海人達も九州には広がっていった。
フォッサマグナに沿った地方には地すべりを示す地名が多々見られる。飛山、崩、青抜、蛇崩、水窪、押田などである。小谷も深い谷の地形を表す。滝がつく地名も災害を暗示する。断崖や岩が屹立した場所を示すのがタキ、タビ、タル、タルミなどである。
筆者によれば、山の民と平地の民は弥生時代以降ずっと戦ってきていて、その結末は南北朝時代の戦いまで続いたという。当然山の民が狩猟民族、平地の民が稲作民族であり、山の民はフォッサマグナや中央構造線の山にそって生き延び南北朝以降は東北から蝦夷地と九州から沖縄地方に逃げ延びた。宮城から山形以北に残るアイヌ由来の地名や沖縄方面に残る独特の地名はそうした名残である可能性が高いとのこと。
中央構造線沿いには水銀を産出した場所があり、丹生、丹波などに痕跡を残す。南朝方を助けたのは古来自然の道を行き来した歩き筋と呼ばれた猟師、サンカ、生地屋、鉱山師、鍛冶屋、鋳物屋などの漂白の民であり、それに山伏や修験者も加わった。猟師がもたらす毛皮や肉、生地屋の盆や椀、サンカの箕細工、鉱山師による水銀は南朝方の生活を支え軍資金となった。南朝方が山にこもった理由は山の民の伝統的戦法であり、黒潮に沿って海人が展開したように中央構造線は陸における山の民の大動脈であった。
川の氾濫から厭い川と言われた糸魚川、元は能生町と青海町であったが合併で糸魚川市になった。新潟の由緒ある直江津が高田が犠牲となり一緒になって上越市となり、新田開発で税が免除されたため御免町と呼ばれた町は合併で南国市となった。このような例は全国に数知れずある。安易な地名改変はこのような長く深い歴史の流れを切断するような行為であり、どんな小さな地名にも歴史や文化、災害や環境を表していると考え、大切に扱うことが重要だ、という筆者の主張に大いに賛同する。