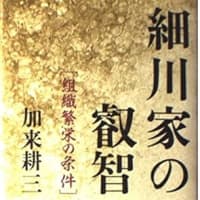ことわざには中国より書物で伝えられたり、日本で江戸時代以前より言い伝えられているものもあるようですが、江戸末期以降、明治維新を期に主に西洋から輸入されてものが意外に多いもの。「一石二鳥」「天は自らを助くるものを助く」「艱難汝を玉にす」「大山鳴動して鼠一匹」「鉄は熱いうちに打て」「時は金なり」「二兎を追うものは一兎をも得ず」「捕らぬ狸の皮算用」「溺れる者は藁をも掴む」、これらの中では日本固有のものはたった一つ。
ことわざ、格言、箴言、故事成語、慣用句など類似のものがあるが、本書はことわざの由来。しかしこれらのことわざが記された一番古い書物を探し当てるのは困難。見つけたとしても、それが一番古いとは証明できないので、歴史的由来や社会環境などの傍証を得るしかない。国会図書館には古書などもマイクロフィッシュとして納められているが、ポジで確認できるのは一回に二点まで。とにかく時間がかかることを筆者は丁寧に行っていて、熱意にリスペクトを感じる。
「鉄は熱いうちに打て」は明治維新より70年あまり早くにオランダ語書物から。オランダ由来の「鉄は赤いうちに打て」が英語フランス語ドイツ語のバリアントとして存在するから。「大山鳴動して鼠一匹」は関ヶ原の戦い前後で、ラテン語、ポルトガル語の可能性もある。「艱難汝を玉にす」はフランス語もしくは英語由来。
日本社会に定着する最大のきっかけは、明治維新以降の国定教科書に記載されたケース。修身の教科書に、教訓を引き出す逸話とともに紹介された。「天は自ら助くる者を助く」は明治初期のベストセラー「西国立志編」に紹介されたのが最初。「鉄は熱いうちに打て」は乃木大将の少年時代のエピソードとともに紹介されて定着、問題対応は手早く、という本来の意味に加え、若いうちに経験したことは後々役立つ、という日本独自の意味を持った。
「艱難汝を玉にす」は「Adversity makes a man wise」からの翻訳と考えられるが、この意訳は明治時代の日本人の向上心と臥薪嘗胆の意識にピッタリ合致したものとも感じられる表現。「大山鳴動して鼠一匹」はイソップ童話由来かと考えられたが、「山から不思議な音がするので人が集まってきたら、出てきたのはネズミが一匹」というお話から「大山、鳴動」という表現には少し距離がある。さらに調べるとイエズス会宣教師たちによる日本語辞典に「タイザン」「メイドウ」という表現があり、あくまで推測の域を出ないが、戦国時代に入って、江戸時代のキリシタン弾圧をも生き抜いたことまで考えられるという。
日本古来ではなく西洋由来という条件は次の通り。
1.西洋文化への接触以前の用例、俚諺辞典やことわざ集への収録例がない。
2.西洋に同一の表現がある。
3.西洋から輸入され定着の足跡がたどれる。
調査方法は次の通り。
1の接触以前という区切りとして幕末を第一候補と考え、確認の後に江戸時代の蘭学、南蛮文化由来をたどる。
2の代表例を調べる。
3具体的な証拠がない場合には社会的背景を考察する。具体的な用例は、「日本国語大辞典」「俚諺大成」から確認した。
「捕らぬ狸の皮算用」は日本古来である、というのも「Catch the bear before you sell its skin.」といい英語があるから、証明はなかなか難しいと思う。