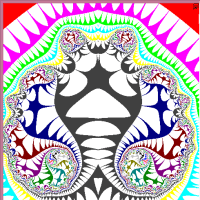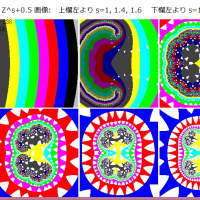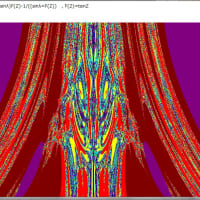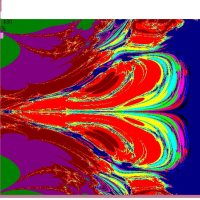以下は以前書いた雑談である。漱石と鴎外の死生観の一端を私なりに見た、言わば私の独断である。其の反芻も兼ねて追記、再掲する。
***
夏目漱石の『硝子戸の中』を漱石の内面的な自伝とするならば、森鴎外の『妄想』は鴎外の内面的自伝と言えるかも知れない。
自伝というのが大げさなら、彼らの内面の一部の告白だと言い換えてもよい。いずれにせよ、それらのエッセーには彼らの死についての思いが語られている。
ここで語られている彼らの死についての思いも、真正面に論じられているものではなく、言わば余談として語られている。
***
余談であるにせよ、漱石や鴎外という巨人の言葉であるから、我々にとって彼らの思いには重みはある。
そして、この巨人たたちの死についての感想に或る共通点があるのは私には興味ぶかい。彼らの死の感想は恐らく日本人の死生観の本質を代弁しているように私には思える。
***
先ず漱石は『硝子戸の中』の8章で以下のように書いている。
『不愉快に充ちた人生をとぼとぼ辿りつゝある私は、自分の何時か一度到着しなければならない死といふ境地に就いて考えている。さうして其の死といふものを生よりも楽なものだとばかり信じてゐる。ある時はそれを人間として達し得る最高至高の状態だと思ふこともある。「死は生よりも尊い」』 と書き出している。
そして、その最高至高と思われる死へと踏み切れぬ理由として挙げていることは、この世で何千年と続いている『如何に苦しくとも生きるべきだ』という慣習だと言うのだ。
(正確には本書の該当章を読んで欲しい)
漱石の願望する死に抵触するものは、いわゆる宗教教義ではなく、単なる『生きることが先決だ』という慣習に過ぎないというのだ。
私流に漱石の死生観を言い換えると、我々は生に意義があるから生きているのでなく、単に慣習として、本能として生きているに過ぎない、ということになる。
そもそも、人間以外の他の生物は自身の生に意義をみつけて生きているのだろうか。そうではあるまい。無意識の本能に従って生きているに相違ない。
極論を云えば、地上に投げられた石が地面へと落下していくように。
人間もその例にもれない。漱石の死生観を突き詰めればそうなる。生きている、ということに対する漱石の苦悶は恐らく其処にあったのだろう。漱石の正直さは其処にあるように私は思う。
そのような漱石の苦悶があればこそ則天去私という境地へ行ったのかもしれない。
***
一方、鴎外は、西洋の『自我』というモノの自身の不在に、痛切に心の空虚を感じ、いわれもない寂しさを覚えると語り、『妄想』で自身の死について以下のように書いている。
『自分には単に我(われ)がなくなるというだけなら、(死は)苦痛とは思われない。ただ刃物で死んだら、その刹那に肉体の痛みを覚えるだろうと思い、病や薬で死んだら、それぞれの病症薬性に相応して、窒息するとか痙攣するとかいう苦しみを覚えるだろうと思うのである。自我がなくなるための苦痛はない。』
又こうも書いている。
『(自分が死んだら)二親がどんなに嘆くだろう。それから身近種々の人のことも思う。どんなにか嘆くだろうと思う』
鴎外は自分の死に対して懸念しているのは『自我の喪失』ではなく、自分の係累の嘆きであり、更に言えば死に伴う肉体的苦痛だけなのだ。そして
『自分は人生の下り坂を下っていく。そしてその下り果てたところが死だということを知っている』という、言わば乾ききった感想である。これはニヒリズムでもなければペシニズムでもない。冷徹な科学者の眼である。鴎外は以下のようにも言っている。
『私の心持をなんという言葉でいいあらわしたらよいかというと、resignationがよろしいようです。私は文芸ばかりではない。世の中のどの方面にもおいてもこの心持でいる。それでよその人が、私のことをさぞ苦痛しているだろうと思っているときに、私は存外平気なのです。もちろんresignationの状態というものは意気地のないものかも知れない。その辺は私のほうで別に弁解しようとは思いません。』
鴎外という人は、『人生の下り坂の果ての自身の死』についてもresignationという心持の乾いた眼で見つめていたようだ。
***
以上は私が鴎外と漱石の残した文章から見た彼らの死生観の一端だが、恐らく其の死生観には私自身のバイアスがかかっているだろうと思う。
つまり私の独断による偏見があることは承知の上で、私は
私なりに彼らの苦悩を読み取ることができる。
その苦悩は、彼らほど明晰でなくとも、私を含めて全ての日本人の底にある苦悩と通底していると思われる。
日本人が、それを明確に意識する、しないに関らず。
***
夏目漱石の『硝子戸の中』を漱石の内面的な自伝とするならば、森鴎外の『妄想』は鴎外の内面的自伝と言えるかも知れない。
自伝というのが大げさなら、彼らの内面の一部の告白だと言い換えてもよい。いずれにせよ、それらのエッセーには彼らの死についての思いが語られている。
ここで語られている彼らの死についての思いも、真正面に論じられているものではなく、言わば余談として語られている。
***
余談であるにせよ、漱石や鴎外という巨人の言葉であるから、我々にとって彼らの思いには重みはある。
そして、この巨人たたちの死についての感想に或る共通点があるのは私には興味ぶかい。彼らの死の感想は恐らく日本人の死生観の本質を代弁しているように私には思える。
***
先ず漱石は『硝子戸の中』の8章で以下のように書いている。
『不愉快に充ちた人生をとぼとぼ辿りつゝある私は、自分の何時か一度到着しなければならない死といふ境地に就いて考えている。さうして其の死といふものを生よりも楽なものだとばかり信じてゐる。ある時はそれを人間として達し得る最高至高の状態だと思ふこともある。「死は生よりも尊い」』 と書き出している。
そして、その最高至高と思われる死へと踏み切れぬ理由として挙げていることは、この世で何千年と続いている『如何に苦しくとも生きるべきだ』という慣習だと言うのだ。
(正確には本書の該当章を読んで欲しい)
漱石の願望する死に抵触するものは、いわゆる宗教教義ではなく、単なる『生きることが先決だ』という慣習に過ぎないというのだ。
私流に漱石の死生観を言い換えると、我々は生に意義があるから生きているのでなく、単に慣習として、本能として生きているに過ぎない、ということになる。
そもそも、人間以外の他の生物は自身の生に意義をみつけて生きているのだろうか。そうではあるまい。無意識の本能に従って生きているに相違ない。
極論を云えば、地上に投げられた石が地面へと落下していくように。
人間もその例にもれない。漱石の死生観を突き詰めればそうなる。生きている、ということに対する漱石の苦悶は恐らく其処にあったのだろう。漱石の正直さは其処にあるように私は思う。
そのような漱石の苦悶があればこそ則天去私という境地へ行ったのかもしれない。
***
一方、鴎外は、西洋の『自我』というモノの自身の不在に、痛切に心の空虚を感じ、いわれもない寂しさを覚えると語り、『妄想』で自身の死について以下のように書いている。
『自分には単に我(われ)がなくなるというだけなら、(死は)苦痛とは思われない。ただ刃物で死んだら、その刹那に肉体の痛みを覚えるだろうと思い、病や薬で死んだら、それぞれの病症薬性に相応して、窒息するとか痙攣するとかいう苦しみを覚えるだろうと思うのである。自我がなくなるための苦痛はない。』
又こうも書いている。
『(自分が死んだら)二親がどんなに嘆くだろう。それから身近種々の人のことも思う。どんなにか嘆くだろうと思う』
鴎外は自分の死に対して懸念しているのは『自我の喪失』ではなく、自分の係累の嘆きであり、更に言えば死に伴う肉体的苦痛だけなのだ。そして
『自分は人生の下り坂を下っていく。そしてその下り果てたところが死だということを知っている』という、言わば乾ききった感想である。これはニヒリズムでもなければペシニズムでもない。冷徹な科学者の眼である。鴎外は以下のようにも言っている。
『私の心持をなんという言葉でいいあらわしたらよいかというと、resignationがよろしいようです。私は文芸ばかりではない。世の中のどの方面にもおいてもこの心持でいる。それでよその人が、私のことをさぞ苦痛しているだろうと思っているときに、私は存外平気なのです。もちろんresignationの状態というものは意気地のないものかも知れない。その辺は私のほうで別に弁解しようとは思いません。』
鴎外という人は、『人生の下り坂の果ての自身の死』についてもresignationという心持の乾いた眼で見つめていたようだ。
***
以上は私が鴎外と漱石の残した文章から見た彼らの死生観の一端だが、恐らく其の死生観には私自身のバイアスがかかっているだろうと思う。
つまり私の独断による偏見があることは承知の上で、私は
私なりに彼らの苦悩を読み取ることができる。
その苦悩は、彼らほど明晰でなくとも、私を含めて全ての日本人の底にある苦悩と通底していると思われる。
日本人が、それを明確に意識する、しないに関らず。