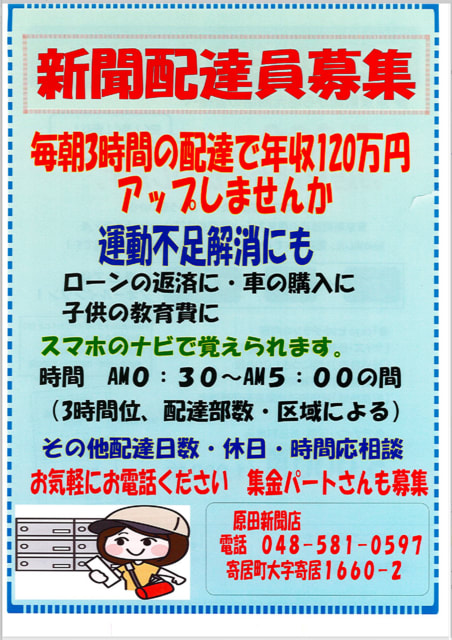懐かしき若者向け雑誌『ホットドッグ・プレス』に作家北方謙三さんの人生相談『試みの地平線』があった。記憶する人は中高年以上の男性か▼いかにもモテそうな北方さんが生き方を説く。「彼女がデートなどの約束を守らなくて困っています」との相談には「張り倒せ」と答えた。掲載当時は昭和。今なら不適切と咎(とが)められそうだ▼「生きるのが限界で自殺のことを考えています」という悩みには、何でもいいから本を50冊読めと助言した。「50冊読むまでは死ぬな。50冊読んでみて、それでも死にたいと思ったら、また手紙をくれ」。本で時をやり過ごせとの趣旨である▼明日は9月。近く学校が始まる子は多い。いじめなどに悩み早まった行動をせぬかと心配する時期、学校が嫌なら逃げていいと唱える活動「#逃げ活」を展開する団体もある▼何から逃げたいかや、逃げたい時のやり過ごし方などを書きだす作業を勧め、必要な台紙なども提供する。ゲーム、昼寝、散歩など手段は多様だろうが、それで命をつなぐ戦略は「本50冊」回答と同じであろう▼北方さんは、読むなら小説もいいと作家の自負をにじませた。「俺は小説が世の中の役に立つなんて考えたことはないが、死にたがっている人間を止めるぐらいの時間を与えることはできると思う」。逃げ込んでくれたら本望だと言う人もいるのだから堂々と逃げていい。
諸説あるが、『怒りの葡萄(ぶどう)』の米作家、スタインベックは大学生のとき、先生にこんなことを言われたそうだ。「ブタが空を飛んだとき、君は作家になれる」▼英語の「flying pigs(空飛ぶブタ)」は現実には起こらないことのたとえ。先生は未来のノーベル賞作家に「君が作家になれることはない」と言ったことになる。ひどい言葉を生涯忘れなかったか、スタインベックは翼の生えたブタを自分のシンボルとし、サインに添えていた▼もう1頭、いや何百、何千の空に浮かぶブタの話を。この方もサインにブタを描いた。子どもたちに人気の『はれときどきぶた』(岩崎書店)などで知られる児童文学作家、矢玉四郎さんが亡くなった。80歳▼『はれぶた』の発表は1980年。子ども時代、矢玉さんの荒唐無稽な物語に夢中になった方は多いだろう。小学3年の則安君が「あしたの日記」に書いたことは全部本当になる。明日の天気は「はれときどきぶた」。次の日、こうなった。「ぶた、ぶた、ぶた、ぶただらけ。ぶたは、いまにもふってきそうだった」-▼『はれぶた』から読書の楽しさを知った方もきっといる。親が読んでと押しつける本ではなく子ども自身が読みたがる本を残した▼発表当初、斬新な内容に評判を心配する声もあったそうだが、ロングセラーとなり、今も読み継がれる。ブタは空を飛んだ。
フランスの海洋探検家、ジャック・クストーが長年の冒険の相棒とした調査船の名は「カリプソ号」である。子どものときに見たドキュメンタリー番組が懐かしい▼クストーにあやかろうと宇宙飛行士たちは宇宙船の愛称に「カリプソ号」を選んだ。宇宙船とは国際宇宙ステーション(ISS)にとどまっているボーイング社のスターライナーである。残念だが、クストーの船ほどには役に立たなかったようだ▼2人の飛行士を乗せ、ISSに到着したまではよかったのだが、エンジン周辺に不具合が見つかり、米航空宇宙局(NASA)は2人を乗せて地球へ帰還させるのは危険と最終判断した▼NASAの判断は当然だろう。2003年、スペースシャトル「コロンビア号」が大気圏再突入時に空中分解する悲劇もあった。安全面の問題を指摘する声があったが、これを軽視した結果、事故を招いた。無理は禁物である▼「詩人と哲学者の宇宙飛行士は地球に帰還できない」-。アポロ11号のマイケル・コリンズ飛行士の言葉で宇宙には地球に帰りたくなくなるほど、不思議な魅力があるという▼今回の決定で2人は来年2月に別の宇宙船で帰還することになる。いくら魅力的な宇宙でも1週間程度で帰還するはずが、約8カ月もステーションで足止めとはつらかろう。詩人でも宇宙飛行士でもない身は考えただけでげんなりする。
男の前に今にも火の消えそうなロウソクがある。これはなにかと尋ねると死に神はおまえの寿命だという。「もうすぐ消えるよ」。三遊亭円朝作の「死に神」▼どうすれば助かるのかとすがる男に死に神が教える。自分の寿命のロウソクの火を別のロウソクに移すことができれば死なないという。男はやってみるが、緊張と恐怖で手が震える。「早くしねえと消えるよ」「消えると命がねえよ」。死に神の言葉にさらに焦る。「ほーら、消えた」…▼重責と緊張は分かるのだが、ロウソクの火をつなぐどころか、パイプを番号通りに並べることもできなかったとはくやしい。福島第1原子力発電所2号機から溶け落ちた核燃料(デブリ)を試験的に採取する作業は初歩的なミスが見つかり延期となった▼釣りざお式の装置を原子炉格納容器に差し込み、デブリを採取する予定だった。いざ採取というところで装置を押し込む5本のパイプの接続順が間違っていることが分かったそうだ▼パイプには順番を示す番号が記入してあったが、当日まで誰も間違いに気づかなかったという。理解しにくい「怪談」だろう▼廃炉に向けた作業が初手でつまずいた。初手で幸いというべきか。ミスは起こるものと再認識し、確認の大切さをかみしめたい。2051年まで続く予定の難作業である。このミスを長い旅を慎重に歩く「お守り」としたい。
高等女学校の生徒が卒業記念にシューベルトを描いた戯曲を書き、自らシューベルトを演じることになった。終戦の翌年である▼舞台は失敗した。肝心の場面でせりふを忘れてしまった。この生徒はやがて詩人となる。戦後を代表する女性詩人、新川和江さんが亡くなった。95歳。忘れたせりふをいつまでも覚えていたという。「わが恋の終わらざるが如(ごと)く、この曲もまた終わることなかるべし」▼故郷、茨城県結城の近くに疎開していた西条八十との出会いが詩人を目指すきっかけという。第1詩集『睡(ねむ)り椅子』に寄せた西条の序が印象に残る。「鬼才の処女詩集」ではないが、「ゆつくりと(略)伸び繁つて、大空に聳(そび)える何ものかのプレリユードであることを、わたしはかたく信じてゐる」。そう書いた▼見立ては正しかった。自然、情愛、女性であること。独特な比喩と吟味した言葉が紡ぐ世界は不思議なきらめきと強さにあふれた▼「わたしを束ねないで/あらせいとうの花のように/白い葱(ねぎ)のように/束ねないでください わたしは稲穂」。自由に生きようとする「わたしを束ねないで」。詩の終わりは「わたしは終わりのない文章/川と同じにはてしなく流れていく 拡(ひろ)がっていく 一行の詩」である▼新川さんが忘れた芝居のせりふを連想する。亡くなろうとも読み継がれ、その詩は「また終わることなかるべし」か。