Skullcrusher - Day of Show (Official Video)
「笑って許して」/ 和田アキ子 Covered by Klang Ruler & 新しい学校のリーダーズ
Come On Eileen Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners
自由への長い旅 岡林信康 // Long Journey to Freedom - Okabayashi Nobuyasu
(ちんちくりんNo,39)
加耶子ちゃんは、サイクリングロードまではいかないところで、両膝をたてて座っていた。僕とは右斜め45度下方先という表現でいいのか、彼女の笑顔が確認出来る程度の距離が離れている。笑顔?加耶子ちゃんはスケッチブックを手にしていた。先程とは打って変わって優しい笑顔を浮かべながら、何かを見て何かの絵を描いているようだ。彼女の視線の先を追った。川岸に男がひとり。見ていると、彼は川原の石を手にしてまるで阪急の山田久志のように、大きく振りかぶり見事な下手投げで石を放っていた。その石は水面を何度か跳ね上がり、最後は川の半ば辺りで力なく沈んでいった。男は、横山先生だった。
横山先生は何度か「石切り」をした後、飽きたのかその場に座り込む。―かと思ったら今度はおもむろに靴を脱ぎ、靴下を脱いでズボンの裾をまくり、川に入って行く。脛の辺りまで水に沈んだところで振り向き、腰を落とすと何度も両手で川の水をすくいあげるような大きな動作を繰り返し、バチャバチャと上にいる加耶子ちゃんに向け無数の水の玉を投げつける。勿論横山先生と加耶子ちゃんの間は相当離れているので、届くはずもないのだが、それを見ている加耶子ちゃんは楽しそうにスケッチブックをたててブロックするようなジェスチャーをする。何なんですか?あなたちは。
そんな中で横山先生は、やっと僕に気づいてくれたようだ。「水遊び」の手を止め川から上がると、そのまま素足に靴を履き、靴下を手に掲げ、こちらに向けて左右に振った。―今、そこに行くから―、横山先生はゆるやかな坂をゆっくりとこちらに向かってくる。加耶子ちゃんは不思議そうな目でこちらを見ていたが、僕が目を遣ると下を向いてしまった。
「いやー、お待たせ」
横山先生が僕の隣に座ったので、僕も腰を下ろした。
「あれは?」
「加耶子が絵を描くのにね、あそこに誰かいた方が"絵になるだろう"ってさ」
「川の風景を描いているんですか?加耶子ちゃん」
「そう」
不思議に思った。何故加耶子ちゃんは一人だけここで絵を描いているのか。何故横山先生が彼女についているのか。僕は思っていることがすぐに顔に出る性質なので、それを察した横山先生は、「一緒にいたよね。君はあの子のことどう思った?」と真摯な顔で僕に訊いてきた。
「最初は彼女の虚ろな目を見て、どんな問題が彼女にあるのだろうかと」
「今は?」
「楽しそうです、一人なのに」
それを聞いて横山先生はすぐには言葉を返さなかった。川が流れ、正面には小高い丘が見えた。丘にはびっしりと隙間なく人間たちの住居が張り付いている。あそこにも「人間の生活」というものがあるのだな、と思ったら妙に物悲しくなった。横山先生はそこで口を開いた。
「分からない」
「え」
「分からないんだ、本当に。ただね、彼女はうちの付属小学校出身なんだけど、いつからか、独りでいることが多くなったそうだ。教室でも独り、昼休みも放課後も校庭に植えてある木の下でなにをするのでもなく、独りでいる。まだね、本でも読んでいるのなら良いのだけど、ただただ空虚な目をしてその場に座っているだけなんだ」
「虐めとか」
「いや、調べたけどそれはなかった。気が付くと独りになっているだけで、集団行動がまったく出来ないという訳ではないからね。熱心な担任は親にも会った。父親は普通の優しい父親という感じで母親も病気がちだが落ち着いた人という感じで、例えば虐待であるとかそういう問題がある家庭とは到底思えなかったそうだ。でも気になるんだ。あの目が・・・」
「空虚だけれど、何らかの危険を孕んだ目、ですか」
「君も感じたか。それで、当時の担任は何かは分からないまま、ともかく放っておいてはいけないと、ボランティアがやっている様々な行事に誘ったんだそうだ。でも彼女は参加はするも、何も興味をもたない。楽しまない。担任はそのたびに悩んだ。そんな中で一つだけ見つかった光明。それが絵を描くことだったんだ。彼女は絵を描くときだけは生き生きとした表情を見せる。たまたま開催した絵画大会でね、彼女の目がガラス玉から輝く星々のような、・・・大げさだけどそういう彼女を初めて見たんだそうだ。きっと彼女もその時初めてだったんだろうな、自分が本心からやりたいことが見つかったということが。それからは、どんなテーマでも風景画でも抽象画でもいいから、描いてみたらと誘って、中学生になり、小学校の担任から僕にバトンタッチ、現在に至るってところかな」
「そうですか」
「それでね。さっきは分からない、と言ったけれど」
横山先生は加耶子ちゃんの方に目を遣り、優しそうに微笑みながらこう続けた。
「これはあくまでも個人的な見解だけれど、彼女は早熟で繊細だったんだろうと思う。同級生の誰よりも早熟だったが故に、内に抱える何かの問題が彼女に自立を要求する。でもまだ心と体がアンバランスな状態ではとてもそれには立ち向かえないはずだ。どうすればいいのか分からないまま、彼女はいつのまにか「絶望」というものを心の中に住まわせてしまった。そんな彼女を救ったのが絵を描くこと。きっと、それが生きていくための「希望」になったんだよね。今、彼女は徐々に成長している。まだまだ彼女の中の「絶望」は追い出せてはいないだろうけれど。それに対して今、僕らはただ見守っているだけなのかもしれない。でもね、いつか彼女が本当の自立の時を迎えた時に、乗り越えなきゃならないものを乗り越えられるようにいつでも手を差し延べて行こうと思っているんだ。・・・これって、思い上がりかな?」
「いえ」
加耶子ちゃんについての話は僕に何らかの啓示のようなものを与えてくれたような気がした。彼女は「絶望」して、その後「希望」を手にしたことで前に進んでいる。僕は、「希望」を手にしたけれど「立ち向かわなかった」ために、その後何年も壁の前に立ちすくんでいた。来てよかった。僕はそう思う。
バーベキューも終わり、その片付けをしている最中にふと気になって横山先生に聞いた。「先生は何故これに僕を誘ってくれたのですか」
「教育実習中君が楽しくなさそうだったからだよ。今日は楽しかっただろう?」
「はい、とっても」
僕は二人でごみ袋を持ちながら、テーブルの上のごみを熱心に袋に詰め込んでいる靖と加耶子ちゃんの姿を見遣り、心底「ありがとう」と呟いたのだった。
「笑って許して」/ 和田アキ子 Covered by Klang Ruler & 新しい学校のリーダーズ
Come On Eileen Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners
自由への長い旅 岡林信康 // Long Journey to Freedom - Okabayashi Nobuyasu
(ちんちくりんNo,39)
加耶子ちゃんは、サイクリングロードまではいかないところで、両膝をたてて座っていた。僕とは右斜め45度下方先という表現でいいのか、彼女の笑顔が確認出来る程度の距離が離れている。笑顔?加耶子ちゃんはスケッチブックを手にしていた。先程とは打って変わって優しい笑顔を浮かべながら、何かを見て何かの絵を描いているようだ。彼女の視線の先を追った。川岸に男がひとり。見ていると、彼は川原の石を手にしてまるで阪急の山田久志のように、大きく振りかぶり見事な下手投げで石を放っていた。その石は水面を何度か跳ね上がり、最後は川の半ば辺りで力なく沈んでいった。男は、横山先生だった。
横山先生は何度か「石切り」をした後、飽きたのかその場に座り込む。―かと思ったら今度はおもむろに靴を脱ぎ、靴下を脱いでズボンの裾をまくり、川に入って行く。脛の辺りまで水に沈んだところで振り向き、腰を落とすと何度も両手で川の水をすくいあげるような大きな動作を繰り返し、バチャバチャと上にいる加耶子ちゃんに向け無数の水の玉を投げつける。勿論横山先生と加耶子ちゃんの間は相当離れているので、届くはずもないのだが、それを見ている加耶子ちゃんは楽しそうにスケッチブックをたててブロックするようなジェスチャーをする。何なんですか?あなたちは。
そんな中で横山先生は、やっと僕に気づいてくれたようだ。「水遊び」の手を止め川から上がると、そのまま素足に靴を履き、靴下を手に掲げ、こちらに向けて左右に振った。―今、そこに行くから―、横山先生はゆるやかな坂をゆっくりとこちらに向かってくる。加耶子ちゃんは不思議そうな目でこちらを見ていたが、僕が目を遣ると下を向いてしまった。
「いやー、お待たせ」
横山先生が僕の隣に座ったので、僕も腰を下ろした。
「あれは?」
「加耶子が絵を描くのにね、あそこに誰かいた方が"絵になるだろう"ってさ」
「川の風景を描いているんですか?加耶子ちゃん」
「そう」
不思議に思った。何故加耶子ちゃんは一人だけここで絵を描いているのか。何故横山先生が彼女についているのか。僕は思っていることがすぐに顔に出る性質なので、それを察した横山先生は、「一緒にいたよね。君はあの子のことどう思った?」と真摯な顔で僕に訊いてきた。
「最初は彼女の虚ろな目を見て、どんな問題が彼女にあるのだろうかと」
「今は?」
「楽しそうです、一人なのに」
それを聞いて横山先生はすぐには言葉を返さなかった。川が流れ、正面には小高い丘が見えた。丘にはびっしりと隙間なく人間たちの住居が張り付いている。あそこにも「人間の生活」というものがあるのだな、と思ったら妙に物悲しくなった。横山先生はそこで口を開いた。
「分からない」
「え」
「分からないんだ、本当に。ただね、彼女はうちの付属小学校出身なんだけど、いつからか、独りでいることが多くなったそうだ。教室でも独り、昼休みも放課後も校庭に植えてある木の下でなにをするのでもなく、独りでいる。まだね、本でも読んでいるのなら良いのだけど、ただただ空虚な目をしてその場に座っているだけなんだ」
「虐めとか」
「いや、調べたけどそれはなかった。気が付くと独りになっているだけで、集団行動がまったく出来ないという訳ではないからね。熱心な担任は親にも会った。父親は普通の優しい父親という感じで母親も病気がちだが落ち着いた人という感じで、例えば虐待であるとかそういう問題がある家庭とは到底思えなかったそうだ。でも気になるんだ。あの目が・・・」
「空虚だけれど、何らかの危険を孕んだ目、ですか」
「君も感じたか。それで、当時の担任は何かは分からないまま、ともかく放っておいてはいけないと、ボランティアがやっている様々な行事に誘ったんだそうだ。でも彼女は参加はするも、何も興味をもたない。楽しまない。担任はそのたびに悩んだ。そんな中で一つだけ見つかった光明。それが絵を描くことだったんだ。彼女は絵を描くときだけは生き生きとした表情を見せる。たまたま開催した絵画大会でね、彼女の目がガラス玉から輝く星々のような、・・・大げさだけどそういう彼女を初めて見たんだそうだ。きっと彼女もその時初めてだったんだろうな、自分が本心からやりたいことが見つかったということが。それからは、どんなテーマでも風景画でも抽象画でもいいから、描いてみたらと誘って、中学生になり、小学校の担任から僕にバトンタッチ、現在に至るってところかな」
「そうですか」
「それでね。さっきは分からない、と言ったけれど」
横山先生は加耶子ちゃんの方に目を遣り、優しそうに微笑みながらこう続けた。
「これはあくまでも個人的な見解だけれど、彼女は早熟で繊細だったんだろうと思う。同級生の誰よりも早熟だったが故に、内に抱える何かの問題が彼女に自立を要求する。でもまだ心と体がアンバランスな状態ではとてもそれには立ち向かえないはずだ。どうすればいいのか分からないまま、彼女はいつのまにか「絶望」というものを心の中に住まわせてしまった。そんな彼女を救ったのが絵を描くこと。きっと、それが生きていくための「希望」になったんだよね。今、彼女は徐々に成長している。まだまだ彼女の中の「絶望」は追い出せてはいないだろうけれど。それに対して今、僕らはただ見守っているだけなのかもしれない。でもね、いつか彼女が本当の自立の時を迎えた時に、乗り越えなきゃならないものを乗り越えられるようにいつでも手を差し延べて行こうと思っているんだ。・・・これって、思い上がりかな?」
「いえ」
加耶子ちゃんについての話は僕に何らかの啓示のようなものを与えてくれたような気がした。彼女は「絶望」して、その後「希望」を手にしたことで前に進んでいる。僕は、「希望」を手にしたけれど「立ち向かわなかった」ために、その後何年も壁の前に立ちすくんでいた。来てよかった。僕はそう思う。
バーベキューも終わり、その片付けをしている最中にふと気になって横山先生に聞いた。「先生は何故これに僕を誘ってくれたのですか」
「教育実習中君が楽しくなさそうだったからだよ。今日は楽しかっただろう?」
「はい、とっても」
僕は二人でごみ袋を持ちながら、テーブルの上のごみを熱心に袋に詰め込んでいる靖と加耶子ちゃんの姿を見遣り、心底「ありがとう」と呟いたのだった。
















![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/77/f5/92393401bdbc0a86905caa6f8f33ec10.jpg)
![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/7c/21f0d773d7635daee13341c7a29e3a9f.jpg)


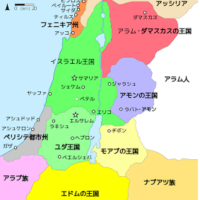







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます