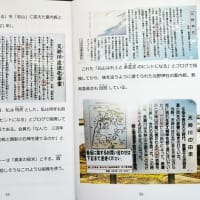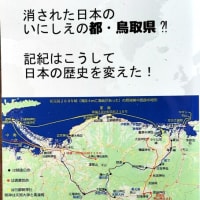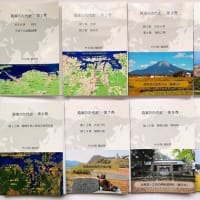1 ある方の記述を引用させてもらいます(抜粋)。
『伊雑宮旧記』『五十宮伝来秘記見聞集』などによると、「伊雑宮こそ天照大神を祀る真の日神の宮であり、外宮は月読を祀る月神の宮、内宮にいたっては邇邇芸命を祀る星神の宮に過ぎない。徳川時代にここの磯部の信仰こそ、本当の原始の天照大神信仰の始まりの地だと熱烈な運動がここで起きたが幕府には認められなかった。偽書を幕府に提出したかどにより、伊雑宮の神人四七人が追放処分を受ける。その熱烈な信仰運動は、いつのまにか内宮のために転用されてしまった。その主張が全面的に認められなかった伊雑宮と、内外両宮、特に内宮との対立は水面下で進行することになる」とする。
(地元の伝承) 「形の上では内宮は格上で伊雑宮は下である。しかし、本当は伊雑宮がもとだった。白い馬の風習も伊雑宮の馬からだった。馬も習慣も内宮に持って行かれてしまった。千田寺周辺は廃仏毀釈でとにかくしこたまやられた。ここらはみんな千田寺の檀家だったんだが、みんな神道に変えられた。千田寺は後に火事にあった。今はただの草むらになっとる。なにも残ってない」とある。
文書よりも人づてによる口伝にこそ真実が残る。文書とは、時の権力の影響を一番に受ける対象であり、廃棄や改ざんが必ず起こる。政権交代が起こると、過去の物は改変される。
文書よりも人づてによる口伝にこそ真実が残る。文書とは、時の権力の影響を一番に受ける対象であり、廃棄や改ざんが必ず起こる。政権交代が起こると、過去の物は改変される。
※ 私見
蒜山の長田神社に、鉾を持った兵を先頭に白い馬に乗った女性を中心にした隊列の絵が描かれている。彼女こそ倭姫命(卑弥呼)であり、その後、倭建命と共に鳥取県中部(倭国)に降りたち倭国を取り返した。倭国平定後、但馬・因幡から来た孝霊天皇たちと合流した。倭建命の伝承は蒜山から降りた関金町に残っている。
倭姫命は崇神天皇と話し合い、全国を巡行し宗教を神道に改めさせて神道の社を創り平定していった。弥生時代後期のことである。崇神天皇は倭国(都)を隠す意味もあり、岡山県津山市の中山神社に常駐した。全国の代表者を集めての祭祀は東国の代表者の便宜を図って、奈良の纒向ですることにした。
白い馬の風習はもともと磯部の伊雑神社にあり、倭姫命(卑弥呼)は伊雑神社の地に留まった。倭姫命は稚日女命に変身して安楽島の伊射波神社を終の棲家とし、ここから奈良の纒向での祭祀に出かけた。奈良にも平定はしたが青銅器文化の一族(銅鐸の主要な製造地であった唐古・鍵遺跡など)は多くいたし、倭姫命(卑弥呼)の安全を考えての居所の選定であった。
2 現在の伊勢神宮の創建年

この看板のとおりだとすると、第一回目の式年遷宮は793年に行われたことになる。その時に20年ごとに改修しなければ、傷みがひどくなるという結論に達した。ということは、少なくとも最初に建てたときよりも20年は経っていたということである。773年より古いと思われるが、それよりも20年も古いとは思われない。いくら古くとも753年くらいではないだろうか。今の規模の伊勢神宮を造ったのは753年よりふるくはないと思われる。今の規模の伊勢神宮は持統が亡くなってから造られたと思われる。持統が勅賜門を千田寺に造ったときに小さな伊勢神宮のもとを造ったかどうかはわからない。倭姫命世紀の伊勢神宮をこの時に造ったという部分は改ざんして後に付け加えたものである。
千田寺は聖徳太子(蘇我入鹿天皇)が建てたが、放火による火事にあった。
千田寺は聖徳太子(蘇我入鹿天皇)が建てたが、放火による火事にあった。
3 「倭姫命世記」は卑弥呼が祭祀場である奈良の纒向から離れた安全な居所を探すための巡行を記したものであった。はじめは、纒向から隠れた宇陀や伊賀も候補地であったが、敵対していた唐古・鍵遺跡(出雲神族である準王一族)などに近すぎて安全ではなく、巡行を続けて最終的な居所は志摩国に定めた。
倭姫命世記は「天照大神が高天原に坐して見し国(伊勢国)に坐せ奉る」ために天照大神を奉戴して巡行した、とする。安全な居所を探すための倭姫命の巡行は宇陀、伊賀から始まるため、先に倭姫命、次に豊鋤入姫命では巡行地が繋がらなくなる。「天照大神が高天原から見た国に行かせる巡行」とするためには、倭姫命の巡行の前に、巡行が三輪神社(本当は鳥取県北栄町の三輪神社)で終わる豊鋤入姫命の巡行が必要であり、そのあと、宇陀から始まる倭姫命の巡行としなければならなかった。伊勢神宮ができた由来を創作するために、目的も時代も違う巡行を整合性を図って順序を逆にして引き継いだとしなければならなかった。
倭姫命は孝霊天皇の皇女であり、豊鋤入姫命は垂仁天皇の皇女であった。国史を改ざんし、倭姫命を垂仁天皇の皇女とし、豊鋤入姫命を崇神天皇の皇女としたのは藤原氏である。全国を平定した倭姫命の居た志摩国(邪馬台国)を封印するために伊勢国・伊勢神宮を創らなければならなかったからである。伊勢国・伊勢神宮を創ったのは藤原氏だから、奈良時代より古くはない。倭姫命は151年に生まれ248年に没している。
「倭姫命世記」に記されている伊勢国・伊勢神宮は藤原氏が創建したものなので、奈良時代後半以降に創建されており、倭姫命(151年~248年)の時代には存在しなかった。「倭姫命世記」に記されている伊勢国・伊勢神宮は中世に京都の藤原氏が改ざん・加筆したものである。
倭姫命世記は「天照大神が高天原に坐して見し国(伊勢国)に坐せ奉る」ために天照大神を奉戴して巡行した、とする。安全な居所を探すための倭姫命の巡行は宇陀、伊賀から始まるため、先に倭姫命、次に豊鋤入姫命では巡行地が繋がらなくなる。「天照大神が高天原から見た国に行かせる巡行」とするためには、倭姫命の巡行の前に、巡行が三輪神社(本当は鳥取県北栄町の三輪神社)で終わる豊鋤入姫命の巡行が必要であり、そのあと、宇陀から始まる倭姫命の巡行としなければならなかった。伊勢神宮ができた由来を創作するために、目的も時代も違う巡行を整合性を図って順序を逆にして引き継いだとしなければならなかった。
倭姫命は孝霊天皇の皇女であり、豊鋤入姫命は垂仁天皇の皇女であった。国史を改ざんし、倭姫命を垂仁天皇の皇女とし、豊鋤入姫命を崇神天皇の皇女としたのは藤原氏である。全国を平定した倭姫命の居た志摩国(邪馬台国)を封印するために伊勢国・伊勢神宮を創らなければならなかったからである。伊勢国・伊勢神宮を創ったのは藤原氏だから、奈良時代より古くはない。倭姫命は151年に生まれ248年に没している。
「倭姫命世記」に記されている伊勢国・伊勢神宮は藤原氏が創建したものなので、奈良時代後半以降に創建されており、倭姫命(151年~248年)の時代には存在しなかった。「倭姫命世記」に記されている伊勢国・伊勢神宮は中世に京都の藤原氏が改ざん・加筆したものである。